【BIMの日 独自取材⑧】BIMから広がる新しい価値とは?BIMの現在、未来をキーワードにパネリストが語る|パネルディスカッション
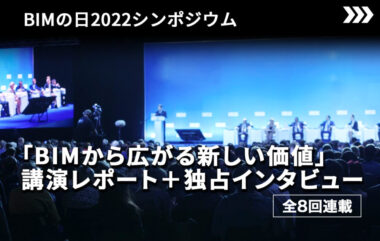
2022年2月22日に行われた「BIMの日」にて独自取材を行いました。
「BIMの日」とは、BIM建築やそれを取り巻く業務に求められる価値を考えることで、BIM の位置付けを改めて見直し、今後の活用のヒントになるようなシンポジウムです。BIM活用の生の声を全8回の連載にてお届けします。
第8回は、BIMの日内に行われた「BIMから広がる新しい価値とは?」と題し、いくつかのキーワードを軸にBIMの現在、未来についてパネリストが語りました。その様子をレポートします。
▼「BIMの日」その他の回の連載記事はこちら▼
第一回連載:BIMの祖型―CAD黎明期の試みに学ぶ | 建築情報学技術研究WG 種田 元晴氏(文化学園大学)
第二回連載: コロナ禍で見えてきたキャンパスBIM-FMのためのIPD | IPDコラボレーション研究WG 飯島 憲一氏(大阪電気通信大学)
第三回連載:BIMと関連するデジタル情報の連携や活用事例の研究|情報連携技術WG 柴田 英昭氏(FMシステム)
第四回連載:建築性能の見える化によるSDGs 達成への貢献|林 立也氏(千葉大学)
第五回連載:デジタルツインが切り拓く近未来の世界~映画の世界が現実に~ |及川 洋光氏(清水建設)
第六回連載:from Room to Planet Mixed Reality ~空間デジタル技術の拡がり~ |伊藤 武仙様(ホロラボ)
第七回連載:BIMはいかに民主化されるのか?~設計・製造・施工の外の人、ConTechスタートアップが考えるBIMの価値|今井 亮介様(アンドパッド)
第八回:BIMから広がる新しい価値とは?BIMの現在、未来をキーワードにパネリストが語る|パネルディスカッション ※本記事です
目次
はじめに
コーディネーター 安井 謙介氏(日建設計)
パネリスト(前掲)林 立也氏/及川 洋光氏/伊藤 武仙氏/今井 亮介氏
シンポジウムの最後は前段プレゼンされた4名の専門家を中心にパネルディスカッションが行われました。コーディネーターは日建設計の安井氏が務めました。
冒頭、コーディネーター安井氏がディスカッションの趣旨説明をしました。4名のプレゼンがBIM単体のみならず、BIM関連のテクノロジーに及んでいたことへの指摘がありました。そこでディスカッションは数テーマを軸にBIMおよび周辺テクノロジーについて自由に語る形式となりました。
vertical(垂直/業界特化)とhorizontal(水平/業界横断)
今井氏(ANDPAD):
SaaSの世界ではサービスを大きく2タイプに分けられると言われています。ADNPADのような業界特化型はvertical(バーチカル:垂直)、Google、Microsoft、box、LINEのような業界横断型はhorizontal(ホリゾンタル:水平)となります。
その考えに則ると、現状BIMは建築業界特化のverticalな存在だと感じます。建物を建てるまでの目的感が強いからです。お台場の商空間でホロレンズを使うイベント(ホロラボのMR事例)は建物を建てた後に生み出され付加価値です。BIMがこのような建てた後の建築価値と結びつくとhorizontalになると思います。
林氏(千葉大学):
発表にあった都道府県別健康寿命は分析データが非常に多岐にわたります。健康診断データから、気候風土、食生活など。突き詰めると人種の違いなどもあり、どこまでデータを広く取るかという意味で研究範囲はhorizontalだといえます。同時に広範囲な情報から重要な数値情報を抜き出す作業も必要となります。何が重要な情報になるかはPCでは処理が難しくAIで膨大な分析を進め判断しています。
BIMも建物の環境性能評価に必要な情報となると、表面データだけでなく、断熱情報を踏まえた熱シミュレーションなどが必要になる、など目的に応じて水平的にデータを集める必要があると感じています。
安井氏(日建設計):
建築設計事務所として、BIMは設計→施工に向けてverticalに使っているのが現状です。施工に近くなるとBIMレベル、データの細かさが上がっていきます。そこにプラスし、最近は発注者にとってのBIMメリットも検討を重ねています。ある時、その流れに自分がワクワクしていないことに気づきました。理由のひとつは、BIMの捉え方が発注者と設計者というverticalな視野になっている点です。発注者も業界も飛び越えたhorizontalな視点が抜けていると思いました。4人のプレゼンはとてもhorizontalな印象でワクワクした気持ちにさせられました。MRや点群のようにワクワクする見せ方でBIM含めた建築情報を捉え直すことが必要だと感じています。
及川氏(清水建設):
清水建設もBIM推進の中で、部署の縦割り(設計、施工など)をどう乗り越えるかが大切だと思っています。業界特化、横断という意味ではなく、会社組織内でのvertical(縦割り部署)とhorizontal(部署間の横串)の関係性です。その際重要なものは、ビジョンを言葉だけでなく、動画などで可視化することだと思います。台湾のスマートダム事例など目に見える形で提示すると人は想像が膨らみ、アイデアを生み出します。また見る人により異なる視点のアイデアになるのです。ラフのコンセプト段階であってもありたい姿を見せることに意味があります。ものを見ると実現に向けて発注者、利用者、テナントさんなどが一緒に進みだし、ワクワク感が生まれます。
伊藤氏(ホロラボ):
MR、ホロレンズは「頭に被るパソコン」として、スマートフォンに次ぐ第4のパーソナルコンピューティングと位置付けられています。当社もサービス展開は業界の垣根なく、horizontalになっています。様々な業界を見る中で、建築業界はデータ開示に対してオープンなイメージがあります。ゼネコンさん含め、図面を関係会社と共有することがスタンダートとなっているためかと思います。そういう意味でMRはHorizontalなテクノロジーです。建築業界への浸透にはデバイスのポータビリティ(携帯性)と関係者のワクワク感醸成が一つキーポイントと感じています。
今井氏(ANDPAD):
伊藤さんの言うポータビリティというのは大切な概念だと思います。デバイスの進化はPC→スマホ・タブレット→ホロレンズというようにポータビリティとともに歩んできました。ソフトウェアも同じように、ローカル→クラウドというようにポータビリティを上げる方向で進化しています。
その観点でBIMを見ると、データ量が重すぎてクラウドで扱うにはうまくいかないというのが現状です。また、操作に専門性が必要とされます。一方、点群はiPhoneのLiDARスキャナがあれば建築知らない人でも簡単にデータ作成できてしまいます。点群データがBIMや建築業界にもたらす可能性は高いと思います。今はその過渡期だと感じます。
及川氏(清水建設):
清水建設でも土木を中心に、LiDARスキャナを活用しています。現場から要望が多く、大量にiPhone、iPadを発注している状況です。身近な製品で試せるというのが非常にいい点だと思います。iPhone、iPadの場合、点群やMRデータを他のアプリやテクノロジーと連動しようと発想しやすいデバイスです。その点でも点群やMRといったテクノロジーはもっと普及すると思います。
今井氏(ANDPAD):
当社ではLiDARスキャナを使って、帰省中に実家の点群データをとった社員がいました。点群はそれほど気軽に試してみたい気にさせるのです。新しいテクノロジーに皆がワクワクするというのはデジカメが世に普及し始めた時と似た状況ではないでしょうか。
安井氏(日建設計):
発注者と話していると、建物が出来た瞬間にBIMデータに対しての熱い想いが冷めていくことを感じることがあります。なぜなら現物の建物が目の前に存在し、BIMの価値が現物よりも下がってしまうからです。BIMに関わる人が一度は感じるショックな場面ではないでしょうか。
ただし、そこに点群の価値を付加すれば、点群データ(現状のスキャニングデータ)とBIMデータのセットで新しい価値が生み出せます。今は点群データのスキャンし楽しみながら、BIMや建築情報への展開を検討する段階ではないかと思います。
林氏(千葉大学):
前職の設備設計の仕事を思い出すと、設計図と施工図は違い、実際の施工はさらに違うものになることがよくありました。完成後に天井設備の補修で、設計図面通りに穴をあけても何も出てこなかった、というのはよくある話でした。
そういう意味では最終的な現場の竣工状況を点群で取得できれば価値があると思います。
安井氏(日建設計):
国土交通省の主導するPLATEAU [プラトー]は都市の3Dモデル化です。大雨時の建物浸水予測情報も含まれていますが、より高度なシミュレーションには正確な建物情報が正確が求められます。そのため、現在、いかに正しい建物情報をPLATEAU [プラトー]に上げるかが議論・検証されています。建築や都市の3Dモデリングは楽しみながら、かつ正確なデータをしっかり集め、マネタイズできることを考え続ける必要があります。
今井氏(ANDPAD):
BIMや3D都市データの可能性として、リアルタイムなデータとの紐づけも一つカギになると思っています。5Gなど通信回線が進むと、建物内の人流も把握できます。例えば、テナントの賃料も人流データを元に定量的な説明性を持たせられます。これは事業者にとってかなりメリットになります。BIMもリアルタイムデータやPLATEAU [プラトー]とクラウド上でサクサクと連動することで、魅力が上がると思います。
林氏(千葉大学):
事業者側の価値という点では、不動産協会、不動産証券化協会の方の意見が参考になります。
不動産の方にとってのワクワクは見た目の面白さではなく、建物の商品流通価値です。建物の性能が〇%アップしたので、投資価値がある建物だ、といった具合です。現場に建物を見に行ったことがない人も多くいます。逆に投資家の建物評価基準を非常に気にしています。最近では、環境性能の高い建物が流通しやすい潮流があり、関連認証制度を利用しようと動いています。
このように不動産、建築、利用者など立場の違いで価値が異なります。BIMや3Dデータも立場に応じた情報の見せ方が必要だと感じます。情報の連携は国土交通省のような国主導では難しい部分もあります。お集まりの方のように業界横断できる方がビジョンやアイデアを出し合っていくのがよいと思います。
伊藤氏(ホロラボ):
業界横断する人材という意味では、当社は多業種から人が集まっています。皆、「ホロレンジャー」としてやっています。前職は大手SIer、外資系企業などさまざまです。印象的だったのは、元建築士の社員でした。その人はRevitを使えるが、設計事務所では下働きなどが多く、物件を担当するチャンスがなかったそうです。そこで建築のノウハウが生き、3Dで新しい世界を構築したいと当社に応募してきました。そういう人はホロレンズというhorizontalなテクノロジーを建築業界というverticalに刺さるためのアイデアを考えられるので、とても助かっています。
BIMは誰のためのもの?
会社のDX化解決策
及川氏(清水建設):
清水建設のデジタル施工事例は増えています。守秘義務上、話できる範囲に限りはありますが、iPad、ホロレンズの活用現場はいくつもあります。使用者は職人さんではなく清水建設社員レベルになります。具体的には、LiDARスキャナを使った配筋検査、本社と遠隔地の現場をつないだ遠隔検査などです。
一方、現場レベルにDXを浸透させる難しさも感じます。現場は忙しいので、新しいテクノロジーを試す余裕が十分ではありません。なぜそれを使わなければならないか、匠な心でやればデジタルよりもアナログの方が効率いい、と反対意見が出るのです。DX成功事例をいかに他現場に横展開するかが直近の課題です。2024年問題の働き方改革関連法による現場の労働時間改正も迫っていて切実です。
今井氏(ANDPAD):
及川さんの課題を「会社をいかにDX化するか」という問いにかえると、ANDPADはまさにその課題解決を目指すサービスです。先述のANDPAD HOUSEでは職人さん含め35社が全てで電子受発注を導入しました。職人さんも請書や請求書をスマホから送るという形です。取引上、紙がゼロになるという衝撃は皆さん感じているようでした。工数も従来に比べ削減され、今では全社継続契約となっています。
先進的な人は率先してテクノロジーを駆使します。課題はその成功事例を、それ以外の人に伝え、動いてもらうことです。経営層の後押しも必要ですが、最後はアナログに面と向かって監督や職人さんに丁寧に説明して回っています。全くデジタルではないコミュニケーションですが、そういった取り組みがDX化を下支えすると感じています。
及川氏(清水建設):
社内DX化は清水建設も似た解決策を用いています。社内では「DXアベンジャーズ」と勝手に名付けてDXに興味のある人を集め、チームを作りました。DXアベンジャーズは通常業務とDXを兼務する形です。デジタルをやりたい、DXの壁を打ち破りたい気持ちを各支店、現場に波及させようという狙いです。チームで楽しみながらやっています。
伊藤氏(ホロラボ):
DXはデジタルにトランスフォーメーションすること。つまり、既存のやり方の抜本的変更で、怖さが先立つ方も多いです。率先して示す姿勢はもちろんのこと、各立場に応じたメリット説明も大切だと思います。変化には時間もコストもかかります。やるからには各立場(現場マネジメント層、現場、経営層など)に合わせて費用対効果の説明が必要です。当社では同時多発的に各職能職種(レイヤー)に説明して回る形をとっています。
ゼネコン同士、業界全体での共創と競争
及川氏(清水建設):
DXアベンジャーズはゼネコン横断でもやりたいと思っています。現在は天井施工ロボットなどを大手ゼネコンが共同で開発しています。1社でロボット開発するよりも、コストや時間を抑えつつ、どのゼネコンでも使える汎用性が確保されるからです。
今後はゼネコン同士がテクノロジー開発や業界課題では共創し、個々の物件受注では競争する姿が理想だと思います。そうしなければ共倒れの可能性もゼロではないという危機感があります。
林氏(千葉大学):
DXやゼネコン共創は危機感が醸成されないと進みづらいのでは感じます。自動車業界がテスラの参入でEV化に動き始めたように、建築業界もいつGoogleのような巨大プラットフォーマーが参入するかわかりません。Googleが基盤情報を持ち、その下請け産業になる危機感がゼネコンで共有されると話が進むのでは思います。
及川氏(清水建設):
危機感という意味では、直近では2024年の働き方改革関連法があります。現場での労働時間改正に向けて、各ゼネコンが単独で考えるレベルではなく、ゼネコンアベンジャーズとして共同で解決していかなければならないと感じます。
点群はBIMなのか?
安井氏(日建設計):
ここまでの議論のように点群は非常にワクワクするテクロノジーだと思います。ただ、点群は属性情報を持っていないので、BIMではないという意見もあります。私は点群とシンプルにしたBIMデータが結びつけば新しい価値を生み出すと考えています。たとえば、確認申請用のそぎ落としたBIMと点群を結び付けて、デジタル都市を構築するというような考えです。皆さんはいかがでしょうか。
今井氏(ANDPAD):
私は「点群はBIM」派です。広義のBIMだと思っています。ビルディングインフォメーションという意味では、点群は建物をスキャンし、情報をタグ付けできる状態になっています。その意味でBIMに活用できるデータだと理解しています。
特に既設建物については、有効性が高いと思います。既設建物のデータは設計図面から変容しています。設計時BIMデータと現状の差分から図面を作り直すには、膨大な時間とコストがかかります。その点、点群は既設の現状をスキャンするだけで、現状をある程度データ化できます。点群データありきで既設の建物情報を再構築する方が汎用性と拡張性が高いと思っています。
伊藤氏(ホロラボ):
大塚駅周辺の飲み屋街を点群データ化した事例があります。飲み屋街のBIMデータは当然ありません。しかし、点群データから作ることはできます。そういう意味では、点群にはXYZ座標軸(形状)データとRGB(色)データがあるので、立派なデータと言えると思います。そこに画像解析を加えれば、平面形状がつづく場所は床。円柱が連なる物体は配管、などと建築的な意味を付加できます。点群はBIMの元となるRAWデータ的な役割を担えると感じました。
及川氏(清水建設):
時代に合わせてBIMの定義を変化させることがいいのではと思います。政府は目指す社会像をsociety3.0→5.0といようにバージョンアップさせます。そのようにBIMも社会やテクノロジー変化に合わせて、バージョンアップさせると考えれば、点群はBIM〇.〇に含まれるよという理解ができます。
安井氏(日建設計):
BIMを使わないシニア設計者に若手が作ったBIMを見せると、設計上の鋭い指摘がいくつも入ることがあります。モデルを介して異なる経験を持つ設計者がコミュニケーションをしている事例と言えます。おそらく点群3Dデータを見ても同様の気づきが入ると思います。これはBIMや点群により建築情報を3D化する大きな効果だと思います。
林氏(千葉大学):
世の中の90%以上は既存物件です。BIMの一般化を考えると、既存物件に対するBIMの有効性検証が必要だと思います。その意味で点群データを起点として、データに建物情報を意味付けしていく方が圧倒的には早い気がしました。
実際、流動している不動産はオーナーが図面すら持っていないケースは多いです。オーナーが数回変わり、データが手元にないのです。そうした場合は点群から入った方がやはり早いと思います。
大塚の飲み屋街の点群データ
伊藤氏(ホロラボ):
BIMが建物を作っている人だけの利用にとどまる限り、点群の可能性は限定的だと思います。BIMが建物を利用する人にも活用された瞬間から点群とBIMの可能性が広がると理解しました。
今井氏(ANDPAD):
確かに、現状BIMは特殊能力のある人しか触れないものになっています。
安井氏(日建設計):
自分の子供にLiDARスキャナを渡したら、いろいろ面白いものをスキャンして、モデリングしそうですが・・・
今井氏(ANDPAD):
お子様にRevitいきなり渡してもなにも作れない。そこにBIMと点群の気軽さの違いが現れていると思います。
Q&A
パネラーが今ワクワクしていること
及川氏(清水建設):
今のワクワクだけでなく、3~5年先を見据えた新しいテクノロジーで何ができるかを考えたいと思っています。DXアベンジャーズとして楽しみながら提案していきたいです。面白いけど、まだ粗があるけど、いいね。と言ってもらえるようなチャレンジをしていきたいです。幸い、清水建設は実際の現場がいくつもあり、実践できる環境にいるのはとてもワクワクします。
林氏(千葉大学):
最近、不動産、金融など別業界と話す機会が増えてきました。異業種に対していい建築の価値をいかに伝えるかの活動が非常に楽しいです。一方メタバースが今後どうなるか、人類がどう対応するかにも興味があります。
伊藤氏(ホロラボ):
MRという3次元コンピューティングにワクワクして会社を立ち上げました。今日の話を通じて、そのテクノロジーが建築業界にも大いに居場所がありそうだとわかり、ワクワクしています。
今井氏(ANDPAD):
ANDPADとしては今後アプリ上で点群が見えるようになる予定です。その可能性が見えてきている前夜という気持ちでワクワクしています。
もう一つは点群の数年後の進化に興味があります。写真のように誰もが気軽に3D化する時代が訪れ、世界観が変わり、多様なメタバースと連携している未来も多いにあります。以前、H&Mがメタバース上にバーチャルショップを試したことがあります。実際に訪れてみて、ヴァーチャル空間でのショッピング体験のリアリティが上がり、あらたな可能性を感じました。そういった変化がどのように起こるかを考えるとワクワクします。
安井氏(日建設計):
最近は発注者とBIMの価値を考える機会があります。verticalな視点にとらわれ時もあるので、もうすこしワクワク感を伝えるような幅のある仕事ができればと思いました。手始めに子供がLiDARスキャナとホロレンズを使ったらどういった行動をとるか観察してみたいと思います。
【この記事を読んだ方におすすめの記事はこちら】





