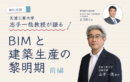芝浦工業大学 志手一哉教授が語るBIMと建築生産の黎明期【後編】
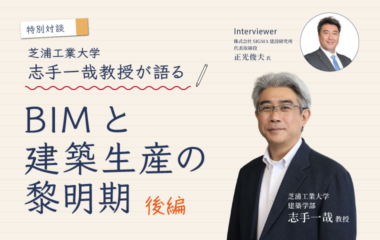
芝浦工業大学 建築学部建築学科にて、BIMに関する指導および建設生産分野の研究を進める志手教授のインタビュー。前編では、志手教授の略歴とBIM元年から15年間の動向について振り返りました。後編では、志手先生が関わる建築BIM推進会議と日本の建設業の未来についてお聞きします。
目次
建築業界の共通言語をつくった「建築BIM推進会議」
ー【正光】前回の記事では、志手教授のユニークなキャリアと直近15年のBIMの動向について伺いました。志手教授は2019年、国土交通省主導で立ち上がった「建築BIM推進会議」の委員としても活動なさっていますね。この推進会議の発足はとても大きな出来事だったのではと思います。
【志手】これまでは建設会社ごとや個人レベルで深掘りしていたBIMについて、国土交通省が主体となり国としてBIMに取り組む姿勢を示したという点で、建築BIM推進会議は大きな意味を持っています。現在は5つのワーキンググループで様々な検討が重ねられています。
中でも「建築分野におけるBIMの標準ワークフローとその活用方策に関するガイドライン(以下、ワークフローガイドライン)」の公表は、全員で同じ言葉を使うきっかけとなりました。建築精査のプロセスをS0からS7のステージに分け、それが建築業界の共通言語となったことは意義のある取り組みです。
加えて、職能ごとにワークフローガイドラインを詳細化したガイドラインが出たことも注目すべきです。これまでは各業界団体でバラバラだったものを、ワークフローガイドラインを大元とし、そこから付随する形で職能ガイドラインがある形となりました。すべて同じ言葉を使って書かれ、体系化されているのはこれまでになかったことです。
ー議論する際の共通言語や、共通理解の土台を作ることができたのは大きな成果ですよね。
また国では建築BIM推進会議のロードマップを検証するため、「BIMモデル事業」を実施しました。50件以上のモデル事業を国主導で行ったのは、世界を見ても珍しい取り組みです。このモデル事業の結果を受けて2023年にロードマップが改正され、2025年までに「BIM-Level2」を目指すことが定められました。その内容もしっかりと定義したうえで発信できたことは、日本のBIMを推し進めるうえで重要なキーポイントになったと思います。
ー「BIM-Level2」はこれまで知っている人だけが使う言葉でしたが、国土交通省の資料に載ったことで、幅広い人に周知され「何を目指すのか」が明確化されたのは非常に大きなマイルストーンでしたね。2023年からは、原則としてすべての新営設計業務および新営工事の発注段階でEIRの提示が義務化されましたが、これはどのような変化をもたらすとお考えですか。
EIRの原則適用により、国土交通省管轄の直轄工事ではBIM化が始まっています。これは建築BIM推進会議の定める「BIM-Level2」を2025年度中に実現するための一つの取り組みです。
海外では国主導で段階的にBIMを義務化した事例もあります。しかし、日本ではBIMの原則適用ではなく「EIRの原則適用」として進めています。表立ってBIMを中心に据えず、中小企業や個人事務所に配慮した形となっているのが日本らしいですね。日本人独自の「みんなで頑張ろう」という意思の表れかなと感じます。
個人的には、小さな個人事務所も含めていかにデジタル的な仕事の進め方に変えることができるかが、今後のBIM推進の分かれ道だと思います。BIMの裾野を広げること、理解の底上げを行うことが極めて重要です。

「BIM=技術」から始まる建築の未来。日本が取るべき進化の形とは
ーBIM元年から現在15年以上が経過し、BIMでやるべきこと・そうでないことが見えてきた部分もあると思います。BIMという言葉は曖昧で、人によって定義が異なる印象がありますが、志手教授が考えるBIMの本質とはどのようなものでしょうか。
建築におけるプロジェクトマネジメントを実行するとき、通常はそれぞれの段階に応じたツールやシステムを用いる必要があるところですが、すべてを内包しているのがBIMです。BIMをうまく使うことでプロジェクトマネジメントが効率化し、首尾よく進むようになります。
芝浦工業大学に来る留学生たちは、BIMのことを「BIMテクノロジー」と表現します。一方で、日本人の多くは「BIM=ツール」と捉えており、技術という言い方はしません。干渉チェックや図面化がまず重要だとしても、様々なデータが蓄積できるのがBIMだという共通理解を持ち、そのデータをいかに幅広い業務で有意義に使うかという視点で考えると、「BIMは技術である」と捉えるのが本質的だと思います。
ーこれまで様々なシステムが混在していた日本だからこそ必要な考え方ですよね。海外ではBIMを起点としたツールが多くある中で、日本はどうしても既存のものを翻訳するしかないのが特有の課題なのではと感じます。
日本人は基盤技術をゼロから開発するよりは、それらが出た後の応用に優れた人種です。従来の専門分野、例えば鉄骨や設備などに適したBIM的ソフトウェアが数多くあるのは、そういう人種だからこそだと思います。そんな日本の強みをうまく発揮できればいいですね。
ー日本ならではのやり方、日本の得意なところをしっかり見定めて、今あるBIMテクノロジーにプラスして何かを作っていくのが非常に重要ですね。
近年の傾向として、先進国の発注方式が日本の建設業化している点は注目すべきです。施工者を設計にいかに取り込んでいくかであったり、ゼネコンに設計責任も負わせようという姿勢なども日本流に寄ってきている印象です。
この現象を紐解くと、BIMなどの技術があって「本来はこうすべきだ」というものが、よく見るとBIMを導入した改革の過程が日本のやり方に近いという流れになっています。これはそもそも日本がやってきたことが良かったとも言えますから、BIMを活用しつつも従来の建設業の良い部分を守っていくことが大切です。
ー海外では「できていなかったものを実現するためのBIM」という位置づけですが、一方で日本の場合は「できていることを守り抜くためのBIM」という違いがあるのですね。
ただし、これからの日本の建設業は、BIMの助けを借りなければ今までできていたことが維持できなくなる可能性があります。今後は建設技能労働者が明らかに不足する未来が目に見えています。施工管理の外注化も問題を孕んでいます。人手不足の中でいかに質を担保するか、また建設技能や施工管理のノウハウを現場で受け継ぐためにどうやって人材を育成するかという点は、諸外国とはまた違った課題です。それらを解決に導くためにも、BIMは重要な鍵を握るでしょう。
日本のBIMが向かう未来は?トップダウンとボトムアップの融合が鍵
ー諸外国ではBIMがトップダウン的なアプローチで進められてきましたが、日本の場合は諸外国の目指す姿がすでにできていて、それをベースにBIMがどう活用できるかというボトムアップ要素が非常に強いと感じます。これからは既存の技術とBIMをどう合わせるかが課題になると思いますが、志手教授はどのようにお考えですか。
そうですね、いかに融合させていくかが今後の重要なポイントです。加えて、アジアの中での日本の立ち位置にも着目すべきです。これまでは日本が先頭に立つ「ルックイースト」や「雁行型」でしたが、今後は日本も諸外国を見て追随する一員になるでしょう。
アジア諸国ではヨーロッパの文化をもとに建設産業が出来上がっている国が多く、ISO19650の考え方が自然と受け入れられています。日本がその流れに取り残されないためには、どう進むべきかも戦略的に考えなければなりません。

ーISO19650ではない日本独自のガラパゴス化が進めば、アジアで日本が取り残されてしまう可能性もありますね。今後は国内の建設産業従事者がどんどん減る中で、外国人が入ることや日本のプロジェクトを海外の建設会社に支援してもらうこともあり得ます。その際に日本の独自性とグローバルをうまく掛け算する必要性がありそうです。
一つの方向性として、業界団体にアカデミックを交えた変革の進め方があります。その一つとして現在進めている建築BIM推進会議がありますが、産官学で力を合わせて日本のBIMの今後を議論することが重要です。
現在の建築BIM推進会議には、審査タスクフォースと標準化タスクフォースを管轄する戦略ワーキンググループがあります。このワーキンググループでもう少し俯瞰的にBIMについて議論できるようになるのが理想ですので、そこは今後期待したい部分ですね。
まとめ – BuildApp 編集部感想 –
BIMという言葉が建築業界に浸透して15年以上。志手教授のお話からは、単なるツールではなく、建築における「技術」としてのBIMの本質が浮かび上がってきました。
「できていることを守るためのBIM」と「できていなかったことを実現するBIM」。日本と海外で異なる立ち位置がある中で、国内では従来技術とBIMをどう掛け合わせていくのか。志手教授の示す観点からは、日本の建設業が歩んできた歴史と、これからの進化への可能性を感じました。
グローバル標準との接続、産官学の連携、そして人材育成。どれも一朝一夕では成し得ない課題ですが、建築BIM推進会議をはじめとする取り組みが、その未来を着実に形にしていくものとなることを願ってやみません。