【2025年度版】BIM/CIMとは?違いやメリットをわかりやすく解説|国交省ロードマップや義務化の状況は?
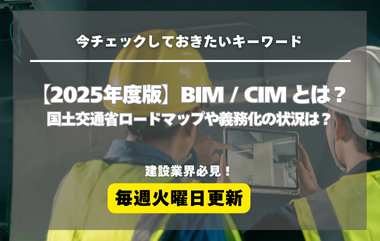
BIM/CIMは建設(建築・土木)業務を効率化できるプロセスです。また、複数のソフトウェアが提供されていますが、現在どれくらい普及しているのでしょうか。
この記事では、BIM/CIMの概要について解説したのち、2025年時点での普及状況や、活用するメリット、課題、事例について説明します。
目次
BIM/CIMとは
BIM/CIMは、建設業界のデジタル技術を活用し、3次元データに属性情報(数値や条件)を与えることで、図面を利用した検討・作成を効率化できるプロセスです。読み方は「ビム/シム」であり、正式名称は次のとおりとなります。
- BIM(Building Information Modeling)
- CIM(Construction Information Modeling)
3D次元モデルをベースとした情報管理が可能となり、計画・調査・設計・施工・維持管理という工事業務の一連の流れをすべて効率化できます。
例えば、調査時に取得した地形の点群データをBIM/CIMに読み込むことで、その後のフェーズである設計・施工でもデータの活用が可能です。また設計時に作成した属性情報をもつ3Dモデル(BIMモデル)を、施工フェーズで重機の配置などの施工計画に利用できるほか、維持管理の情報を入力する基盤データとして活用できます。
BIMとCIMの違い
BIM/CIMはどちらも同じプロセスで利用できるデジタル技術ですが、対象となる分野が異なります。
| BIM | CIM | |
| 対象分野 | 建築(住宅・ビルなど) | 土木(インフラ施設など) |
| ソフトの目的 | 建築物の設計・施工・管理 | インフラの設計・施工・管理 |
なお近年では、2つのプロセスが同じであることから、名称を統一しようという流れができつつあります。そのため、現在は建築・土木関係なく「BIM/CIM」と呼ぶようになっており、今後は海外に合わせて「BIM」という名称で統一する流れです。
【2025年最新】BIM/CIMの国土交通省ロードマップ
出典:国土交通省「BIM/CIMの進め方について」
2025年現在、BIM/CIMに関するロードマップは、国土交通省が公開している「BIM/CIMの進め方について」の資料が最新となります。
例えば、今後の方向性として、BIM/CIMを中心とした次のような取り組みが掲載されています。
| フェーズ | これまで | 今後の方向性 |
| 調査・測量・設計 | 形状の可視化 | 設計による意思疎通の効率化 |
| 地元説明・関係者間協議 | 合意形成の円滑化 | 同左 |
| 工事費の積算 | - | BIMモデルをベースとした積算作業の自動化・簡素化 |
| 施工 | BIMデータの施工・製造への活用 | 自動化・自律化施工へのデータ活用 |
| 監督・検査 | ヒートマップを利用した出来形確認 | ペーパーレス化 |
| 維持管理 | - | BIMデータを活用した維持管理の効率化 |
以上より、各フェーズで徐々にBIM/CIMの活用シーンを増やす流れができつつあります。
なお現在はBIM/CIMを利用しているものの、まだすべての業務に反映できていない状況です。そのため、今後はより密接にBIM/CIMとのかかわりが増えるよう、自動化やペーパーレス化などが推進されていく計画になります。
土木業界における義務化や導入状況
元々は「2025年度の原則活用」という目標だったBIM/CIMですが、2020年に「2年前倒し」の2023年度の義務化が発表されました。その背景には、新型コロナウイルスの流行により、リモートの重要性が高まったことなどが関係しています。実際に感染症対策のためにテレワークを導入した企業が増え、デジタル化が一気に加速しました。
では実際に、BIM/CIMは国内に浸透しているのでしょうか。参考として、国土交通省が令和4年12月に調査したBIM(建築分野)の普及状況を整理しました。
出典:国土交通省「建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査 確定値(令和4年12月調査)」
結論として、BIM単体の普及について言えば、約半数近くの企業が導入し活用している状況です。調査から2年経過する2025年ですが、コスト面の問題などもあり、全企業での原則活用の達成はまだ難しいでしょう。
ただし、徐々にBIM/CIM関連の事業が増えているのも事実です。建築分野では2026年から建築確認にBIM図面を利用することが決定しているなど、今後更なる普及が見込まれます。
BIM/CIM導入によるメリット
以下より、BIM/CIMを導入することで生まれるメリットやその効果を整理しました。
BIM/CIM導入のメリット①業務の一連の流れを効率化できる
BIM/CIMを導入することにより、次のような大幅な業務効率化を期待できます。
- 点群などから取得した現況地形のデータを活用することで、設計段階で詳細な施工費用を算出できる
- パラメトリックモデルの活用により、一部の修正をする際に図面・数量などすべての情報が自動で書き換えられる
またBIM/CIMを用いることであらゆる情報を一元化できることから、複数の工程を同時進行することも可能になりました。その結果、各フェーズごとの効率化だけではなく、工事全体のプロジェクトの日程短縮にもつながります。
BIM/CIM導入のメリット②スピーディーな情報共有ができる
BIM/CIMで作成するモデルデータは視覚的に理解しやすい情報であることから、従来利用されてきた2次元図面と比べて、知識がないユーザーでも内容を理解しやすくなります。
まず、2次元図面は空間把握能力や経験がなければ、内容を理解できません。特に建設(建築・土木)との関わりが薄い地域住民や自治体職員などに情報を共有する場合には、細かく説明をしなければ理解してもらえませんでした。
一方でBIM/CIMで作成したモデルは、立体構造のイメージしやすいデザインです。実物をイメージしやすいことから、スムーズな情報共有を実現しやすくなります。
BIM/CIM導入のメリット③人手不足の負担を削減できる
BIM/CIMで作業効率化を実現できれば、少ない人材でも多くの業務に対応できるようになります。
特に現在は人手不足に悩む建設企業が多い状況です。新しく人材を確保する余裕がない、採用活動を実施しても人が集まらないと悩む企業もあることから、BIM/CIMは人手不足の課題解決を目指している企業におすすめのプロセスだと言えます。
BIM/CIMの課題と解決策
令和4年12月に実施された国土交通省の調査によると、日本ではBIMを「導入している」が48.4%、「導入していない」が50.4%とおよそ半々の結果でした。まだBIM/CIMが普及していない理由として、以下2つの要因が考えられます。
BIM/CIMの課題①専門人材が必要
BIM/CIMは、3次元モデルの作成や属性情報の付与など、広く普及している2D・3DのCAD等と比べると、操作のための専門人材が必要です。また、BIMモデルの構築だけではなく、シミューレションや数量作成などの手順が従来の流れから変わることも含め、専門知識がないという理由で、導入を踏みとどまる企業もいます。
そういったなか専門人材を確保できないなら、セミナー講習に参加することが重要です。ソフトウェアの使い方を解説しているセミナー講習も見つかるので、BIM/CIMを導入して活用するために専門知識を習得しましょう。
BIM/CIMの課題②導入コスト・ランニングコストががかる
BIM/CIMのソフトウェアは従来のCADソフトと比べて高額です。なかには導入コスト・ランニングコストで年間数十万~数百万円かかる場合もあることから、企業にとって負担が大きくなる点に注意しなければなりません。
とはいえ、BIM/CIMを活用した事業が増えているため、いずれは導入が必要です。もし予算を確保できないとお悩みなら、補助金制度を活用できないかチェックしましょう。建設業界向けの補助金も複数見つかるため、コストを抑えたい人は使える補助金がないか探してみてください。
BIM/CIMの活用に資格は必要?
現時点でBIM/CIMのオペレーターになるための必要資格はありません。誰でも業務に活用できます。
ただし、専門知識がなければうまく操作できない点に注意してください。もし知識を身につけるために資格取得を目指したいなら、次のような資格勉強をスタートしてみましょう。
- Archicad 認定試験
- Revit Architecture ユーザー試験
- BIM プロジェクトインフォメーション資格
- BIMアセットインフォメーション資格
- BIM利用技術者試験
- BIM/CIM技術者資格認定試験
各資格は難易度が異なります。資格ページをチェックしたうえで、自身に必要な資格を選定してみてください。
BIM/CIMの活用事例
国土交通省では、令和元年より「建築BIM推進会議」を開催しています。そのなかで公募も行われている「BIMモデル事業」の具体事例をご紹介します。
BIM活用事例①東京オペラシティ(維持管理)
東京オペラシティビル㈱とプロパティデータバンク㈱によるBIM導入プロジェクトです。
クラウド化した不動産管理システムとBIMを導入し、維持管理段階におけるBIMの活用方策について検証を行いました。この取り組みを通して、施設維持管理の高度化・生産性向上・施設全体の長寿命化を図ることを目的としています。
BIM活用事例②竹中工務店(設計施工)
株式会社 竹中工務店によるプロジェクトです。
RC造、S造の建築物におけるBIM活用の効果検証・課題分析を行っています。BIMを活用した設計施工一貫方式による生産性向上の検証に加え、高精度・高品質なものづくりの実現や、施設管理・運用・LCCに至る発注者の課題を共に解決することを目指します。
主な実施概要は、BIM活用による製作、施工計画・管理、施工、工事監理の生産性向上効果の検証や、設計BIM、施工BIM、維持管理BIMにおける適正なデータ連携のための課題分析です。
まとめ
BIMの原則活用である2025年(正式には2年前倒しの2023年)を迎えましたが、まだBIMを導入している企業が少ないことが分かりました。
しかしBIM/CIMを使えば、これまでの設計、施工といった業務が大幅に効率化できます。デジタル化により、働き手不足といった問題の解決にもつながるので、自社の課題を解決できるソフトウェアがないか探してみてはいかがでしょうか。
導入コストや習得の難しさという課題はあるものの、建設のDX化には欠かせないツールです。ぜひ導入を検討してみてください。


