【2025年版】建設業許可の取得条件を解説|500万円未満でも取れる?個人・一人会社の裏ワザ・必要書類・最短取得方法
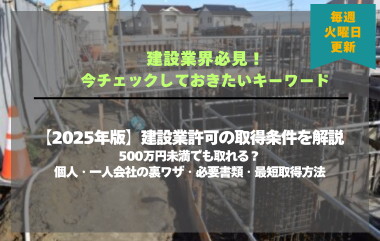
建設業界で仕事が増え始め、「そろそろ建設業許可を取得したい」と考えていませんか?
建設業許可は、原則500万円以上の工事を請け負う場合に必要になる制度ですが、2025年現在、多くの事業者が「条件が厳しい」「資格がないと取れない」「個人事業主は無理」と誤解しています。
そこでこの記事では、国土交通省の一次情報をもとに、建設業許可の取得条件・必要書類・注意点・審査で落ちやすいポイントまで、実務に即した形でわかりやすく解説します。
目次
建設業許可の取得条件とは?
建設業許可とは、建設業法にもとづき、国や都道府県から正式に建設業者として認められる制度です。
(出典:国土交通省「建設業の許可とは」)
許可を取得すると、公共工事の入札参加や500万円以上の工事請負が可能になるだけでなく、信用力・取引先開拓・融資審査において大きなメリットがあります。
なお、建設業許可には「一般許可」と「特定許可」の2種類があり、多くの事業者はまず一般許可から取得します。
- 一般建設業許可
下請への支払い総額が4,000万円未満の工事向け - 特定建設業許可
元請として4,000万円以上を外注する工事向け(ハードル高)
建設業許可は「資格」のように難関試験がある制度ではないため、条件をそろえ、証明書類を揃えて提出すれば取得が可能です。
建設業許可の概要や一般・特定許可の違いなどから詳しくチェックしたい方は、以下の記事もおすすめです▼
まず確認|建設業許可が必要になるケース・不要なケース
建設業許可が必要かどうかは、請け負う工事金額・工事内容・契約形態によって判断しなければなりません。ここを誤解したまま工事を受注すると、建設業法違反となり罰則(営業停止・罰金)を受けるリスクがあります。
(参考:国土交通省「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(令和5年3月改正)」)
結論として、建設業許可が必要になるのは、「請負金額500万円以上(材料費・消費税込)」の建設工事を受注する場合です。加えて、次のような場合にも許可が必要になります。
- 契約金額が500万円以上(税込)
- 1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の新築(建築一式工事の場合)
- 元請として下請を使う場合、支払総額が上記基準を超える場合
- 公共工事・入札に参加する場合(※金額に関係なく必須)
ただし例外や誤解しやすいパターンも多いため、正しい理解が重要です。
500万円以下でも許可が必要になる例(材料費・税込含む)
実は、500万円以下の契約においても、建設業許可が必要になるケースがあります。
そこに影響してくるのが、工事価格の算定です。工事価格は、「請負金額」=材料費・機器代・人工費・消費税を含む総額で判断します。そのため「工賃だけなら500万円以下」「施主支給だから対象外」という認識は誤りです。
以下の目安をもとに、契約したい業務の条件と見比べてみてください。(あくまで目安です)
| ケース | 結果 | 理由 |
| 人工費300万円+材料費250万円 | →許可必要 | 合計550万円のため |
| 施主が材料購入・人工のみ施工500万円 | →不要 | 合計500万円以下 |
| 人工費450万円+消費税45万円 | →必要 | 税込495万円→税込で判定 |
建設業許可の取得条件【6つの必須要件】
建設業許可を取得するためには、建設業法にもとづいた6つの法定要件をすべて満たす必要があります。
(参考:e-Gov法令検索「建設業法」)
- 経営業務の管理責任者が在籍している
- 専任技術者が事業所に常勤している
- 自己資本500万円以上などの財務基盤がある
- 申請者が法律等に違反していない「誠実な事業者」である
- 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)へ加入している
- 申請者が「欠格要件」に該当しない
【条件1】経営業務の管理責任者(経管)
建設業許可を取得するためには、まず経営業務の管理責任者(経管)が在籍していることが必須条件です。
※経管とは、建設業の経営経験をもち、会社運営が適切に行える責任者のことです。
一般許可では原則5年以上の経験が求められますが、国の要件緩和により役員経験や個人事業主の実績で代替できる場合があります。証明には登記簿・工事台帳・請負契約書などが必要です。
【条件2】専任技術者|資格一覧・実務経験で代替可能
許可を取得するためには、専任技術者が事業所に常勤していることが条件となります。
※専任技術者は施工内容に対する技術力を証明する役割を担い、施工管理技士や建築士などの資格が代表例です。
ただし、資格がなくても8〜10年程度の実務経験で代替可能なため、現場経験が豊富な会社であれば取得のハードルは下がります。特定建設業では資格要件がより厳しくなります。
【条件3】財産的基礎|自己資本500万円ない場合の回避策(融資・残高証明)
建設業許可を受けるためには、自己資本500万円以上などの財務基盤があることが条件です。
これは継続的に事業を行える資金力があるかを示すための基準です。
ただし、必ずしも口座に500万円を置いておく必要はなく、金融機関の融資可能証明書や残高証明で対応できる場合があります。創業間もない企業や資金繰り中の経営者が活用する実務的な方法です。
【条件4】誠実性|落ちる人の特徴
建設業許可を取得するためには、申請者が以下の条件にあてはまらない「誠実な事業者」であることが条件となります。
- 建設業法違反
- 税金滞納
- 虚偽申請
- 行政処分歴
実務では、「工事実績や経歴証明の内容に不自然な点がある」「書類が曖昧」という理由で追加調査が入ることが多く、書類の整合性や過去の法令対応姿勢が審査のポイントになります。
【条件5】社会保険加入|一人会社の場合どうなる?
建設業許可では、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)へ加入していることが条件となります。
従業員がいる企業では必須ですが、一人会社の場合も法人である以上加入を求められるケースが増えています。
ただし、加入義務の判断は事業形態や雇用状況によって例外扱いされることがあるため、自治体や専門家に事前確認することがスムーズな申請につながります。
【条件6】欠格要件|該当する人の例(実際に多い落選理由)
建設業許可を取得するには、申請者が次のような「欠格要件」に該当しないことが最低条件です。
- 暴力団関係者
- 禁固刑歴
- 破産手続き未復権者
- 名義貸し
現場で多いのは「書類上代表者が条件に触れてしまう」ケースや「実態が申告内容と異なる名義借り疑い」です。審査では透明性と説明責任が重視されるため、曖昧な状態のまま申請は避けましょう。
まだ条件が揃ってない人向け|取得までの3つの裏ワザ
建設業許可は、要件がひとつ欠けているだけで申請できない仕組みですが、実務では代替手段や補完方法を使ってクリアできるケースが多く存在します。
特に「資格がない」「資金500万円がない」「経営業務経験が証明できない」と悩む事業者は非常に多いですが、ポイントを押さえれば取得は十分可能です。以下では、実際に多く活用されている3つの方法を解説します。
【裏ワザ1】役員追加(家族・経験者・技術者)の活用
「経管」や「専任技術者」が不足している場合、条件を満たす人物を役員として追加することで許可要件をクリアできることがあります。
この方法は、家族や経験者を法人役員として登記し、役員経験や資格を活用する仕組みで、小規模事業者や創業段階の会社が多く利用しています。
形式だけの「名義貸し」は禁止ですが、実務参加が確認できれば合法的な手段として認められています。
【裏ワザ2】建設キャリアアップシステム(CCUS)による経験証明
経歴証明が不足している場合、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録情報が実務経験の証明として活用できるケースがあります。
工事写真や契約書が揃わない場合でも、CCUSの履歴が客観的な証拠として扱われ、行政審査での説得力が高まります。
特に、個人事業主・下請け中心の職人歴が長い人や、紙資料が残りにくい事業者にとって、許可取得の現実的なサポート手段となっています。
(参考:建設キャリアアップシステム「CCUSについて」)
なお、CCUSの概要は以下の記事で解説しています▼
【裏ワザ3】実務経験証明を集める|工事台帳・写真・発注書で代替できるケース
資格がなくても、一定期間の実務経験が証明できれば専任技術者として認められる可能性があります。
この証明は施工管理技士などの国家資格で代替可能ですが、代替できない場合は「工事台帳」「現場写真」「注文書・請求書」「元請事業者の証明書」など複数資料を組み合わせて証明する方法が一般的です。
曖昧な情報のまま提出せず、可能な限り裏付け書類を揃えることが重要です。
個人事業主・一人会社でも建設業許可は取れるのか?
個人事業主・一人会社でも建設業許可の取得は可能です。
建設業許可は法人だけの制度ではなく、建設業法では「法人または個人」が対象とされています。ただし、許可要件に対して「代表者1人で複数の役割を兼務するケース」が多く、証明書類や社会保険加入、経営経験の整理が必要になるため、法人より提出資料が増える傾向があります。
また、許可取得において重要なのが、「規模」ではなく要件を満たし、証拠資料を揃えられるかどうかです。特に個人事業主の場合、実務経験の証明方法・社会保険・経営経験の証拠が不十分になりやすく、申請の際に行政とのすり合わせが必要になることが多い点に注意しましょう。
よくある失敗・審査落ちパターンと回避策
建設業許可の申請では、「要件を満たしているのに通らない」「書類不備で差し戻された」というケースが少なくありません。理由の多くは、要件不足ではなく以下のような「証明方法」の誤りや資料の不整合が原因です。
| 失敗例・停止理由 | よくある状況 | 回避策 |
| 経験証明が曖昧 | 工事台帳や契約書が不足・証明に一貫性なし | 現場写真・注文書・請求書・元請証明を組み合わせて補強 |
| 経管・専任技術者の要件不足 | 「役職経験はあるが証明できない」など | 役員追加・CCUS登録情報など代替証明を検討 |
| 社会保険未加入で指摘 | 1人法人や職人中心企業で多い | 申請前の加入または加入予定届の提出で対応 |
| 財務要件未達 | 500万円基準を誤解、資料不足 | 融資証明書や残高証明で代替可能 |
| 名義貸し疑いによる調査 | 書類上の矛盾・実態不一致 | 登記・役割・稼働状況を一致させる |
行政は「形式より証拠・説明可能性」を重視します。そのため、完全な書類がなくても、複数証拠の組み合わせ・代替手段でクリアできる場合があります。
建設業許可の取得条件に関するよくある質問【FAQ】
一人会社でも建設業許可は取得できますか?
可能です。ただし「法人だから」「人が少ないから」という理由で優遇はされず、一般許可の要件(専任技術者・経営業務管理責任者・財産的基礎・誠実性・社会保険加入等)をすべて満たす必要があります。代表自身が経営経験と技術資格を兼ねられる場合が多く、事前に担当行政庁や専門家へ確認することでスムーズに申請できます。
建設業許可なしで500万円以上工事を請け負うとどうなる?
許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、「建設業法違反」となり罰則の対象になります。罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。さらに自治体入札や元請からの取引停止など、信用面の損失が大きく、後から許可取得する際にも不利になるケースがあるため注意が必要です。
資格なしでも建設業許可は取れる?
資格がなくても取得は可能ですが、専任技術者の要件を満たす必要があります。国家資格がない場合は「10年以上の実務経験」で代替できます。ただし実務証明には工事契約書・請求書・写真など証拠の提出が求められるため、証明資料が不足している場合は資格取得または経験証明の整理が必要です。
建設業許可は何年あれば取れる?
最低でも「経営経験5年以上」が必要とされます。ただし専任技術者の条件は経歴に応じて異なり、資格保持者なら即申請可、資格がなければ10年以上の実務経験が必要です。法人設立直後でも、代表者が過去の職務経験で要件を満たしていれば申請可能なため、年数よりも証明できる実績の有無が重要になります。
まとめ
建設業許可は、500万円以上の工事や入札案件を扱ううえで欠かせない資格です。
取得するためには「経営業務の管理経験」「専任技術者」「財務基準」「社会保険加入」など複数の条件が求められ、必要書類も多いため、申請準備には時間がかかります。
しかし、許可を取得することで、受注できる工事の幅が広がる・元請や行政案件に参加できる・取引先や金融機関からの信用が向上するなど大きなメリットがあります。これから許可取得を目指す場合は、まず自社の体制が条件を満たしているかを確認し、不足している項目があれば計画的に整備していきましょう。


