【2025年版】特定(特殊)建築物定期調査とは?対象・費用・資格までプロが徹底解説
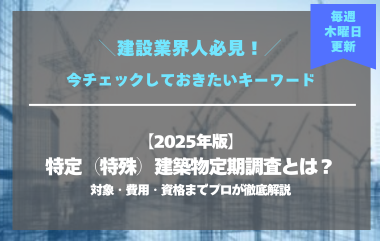
建物を安全に保つには、定期的な点検と法的な管理が不可欠です。特に「特定(特殊)建築物」と呼ばれる建物は、多くの人が利用する施設であり、倒壊や火災のリスクを最小限に抑えるために、特定建築物定期調査の実施が義務付けられています。
この記事では、2025年時点での最新情報をもとに「特定建築物定期調査」の基本概要や、対象建築物、調査の頻度、費用相場、必要な資格まで、専門家の視点でわかりやすく解説します。
目次
特定建築物定期調査とは?
特定建築物定期調査は、建物の安全性を定期的に確認するために設けられた制度のひとつです。
建築基準法に基づいて実施する法定点検であり、不特定多数の人が出入りする建物や高層・特殊な用途をもつ建物などを対象に、安全性能を確認する重要な調査となります。なお、この調査の制度については、自治体や一般財団法人などで様式などがまとめられています。
参考1:東京都市整備局「定期報告(定期調査・検査報告制度)」
参考2:愛知県建築住宅センター「特定建築物等定期報告」
参考3:福岡市「特定建築物等の定期報告制度について」
また、建築基準法といった法律関連の情報を知りたい方は、以下の記事もおすすめです▼
建築基準法第12条の定め
特定建築物定期調査は「建築基準法第12条」にもとづいて定められた法定義務です。
たとえば、第12条の第1項・第3項では、特定の建築物や設備について、所有者や管理者が定期的に専門調査を行い、結果を自治体へ報告することが義務付けられています。
また、この調査の目的は、外壁の劣化、避難設備の不備、構造上の安全性など、目視や触診で確認可能な範囲の劣化や不具合を早期に発見することであり、建物所有者の義務となります。
特定建築物と特殊建築物の違い
特定建築物定期調査と特殊建築物定期調査は、どちらも建築物の安全性確保を目的とした定期報告制度のことであり、意味や目的に違いはありません。
なお2016年の建築基準法改正に伴い、現在は特定建築物定期調査という名称に統一されています。
調査の対象建築物(マンション・病院・学校など)
特殊建築物定期調査の対象となる建築物は、次のように不特定多数の人が出入りする施設や、災害時に影響が大きい建物が中心です。
| 建築物の種類 | 主な用途・例 | 調査対象となる理由 |
| 集合住宅 (マンション) | 地上3階建以上・延床1,000㎡以上など | 居住者の避難経路や耐震性確保のため |
| 病院・診療所 | 入院施設を持つ医療機関 | 要配慮者が多く、避難困難性が高いため |
| 学校・保育所 | 幼稚園・小中高校・大学など | 子どもを含む多人数が長時間滞在するため |
| 劇場・映画館 | 劇場、映画館、ホール等 | 観客が集中するため避難計画が重要であるため |
| 百貨店・商業施設 | ショッピングモール、大型スーパーなど | 来店者数が多く、構造劣化による事故リスクがあるため |
| 宿泊施設 | ホテル、旅館、簡易宿泊所 | 夜間利用や外国人客などが多く情報伝達が困難であるため |
| 飲食施設 | キャパシティの大きい飲食店など | 火気使用・混雑時の避難安全性に懸念があるため |
| 公共施設 | 図書館、役所、福祉会館など | 地域インフラとして継続利用が必要であるため |
なお、自分の所有する建築物が調査対象かどうかを判断するためには、以下の基準をチェックするのがおすすめです。
- 建築確認時の用途区分(用途変更していないか)
- 階数・延床面積・避難経路の構造
- 地方自治体の運用基準(東京都/大阪市/横浜市/福岡などは独自基準あり)
なかでも、自治体の定期報告制度情報を確認するのが確実です。
調査は何年ごと?3年に1回の根拠
特殊建築物定期調査は、原則として3年に1回の頻度で実施することが義務付けられています。
3年という期間は、各自治体の公式サイトにも記載されており、現実的な劣化進行のスピードと管理コストのバランスを考慮して決められた期間です。
一部の自治体では、建物の用途や築年数によって調査周期が2年・5年などに変更されるケースもありますが、ほとんどの地域で「3年に1回」が基本ルールです。
特定建築物定期調査の費用相場【建物所有者向け】
特定建築物定期調査の費用は、建物の用途や延床面積、調査範囲、提出代行の有無などによって変動します。以下に、業界事例をもとにした目安表をまとめました。
| 延床面積 | 共同住宅等 | 事務所・病院等 | ホテル・店舗等 |
| ~500㎡ | 4万円前後 | 5万〜6.5万円 | 6万〜8万円 |
| ~1,000㎡ | 約5万円 | 約6.5万円 | 約7.5万円 |
| ~2,000㎡ | 約6.5万円 | 約7.5万円 | 約8.5万円 |
| ~3,000㎡ | 約7.5万円 | 約8.5万円 | 約10万円 |
| ~5,000㎡ | 約8.5万円〜11万円 | 約12万〜13.5万円 | 約13.5万〜15万円 |
| 5,000㎡超 | 別途見積もり | 別途見積もり | 別途見積もり |
※調査・点検会社の情報の平均的な金額を掲載
見積もりを依頼する際は、面積・用途・交通費等の条件を具体的に伝えることで、比較しやすい見積が得られます。また、報告書作成や提出代行が含まれるかどうか、ドローンや外壁打診調査などオプションがある場合は、その費用も明確に確認しておくと安心です。
特定建築物定期調査に必要な資格とは?
特殊建築物定期調査を実施できるのは、所定の資格・講習を修了した技術者に限られます。
建物の安全性を評価する専門的な業務であるため、誰でも自由に実施できるわけではありません。
誰が調査できるのか?調査資格者の要件
特殊建築物定期調査を実施できるのは、建築基準法で定められている、以下のいずれかに該当する有資格者だけです。
| 資格・講習の種類 | 要件・概要 | 補足事項 |
| 一級建築士・二級建築士 | 建築士法に基づく国家資格 | 実務経験と登録が必要 |
| 特殊建築物等調査資格者 | 国土交通大臣登録講習を修了 | 建築士資格+専用講習修了が必要 |
| 建築設備検査資格者 (参考) | 設備に特化。別の報告制度に対応 | 設備のみで建築本体は不可 |
なお、特殊建築物等調査資格者になるためには、次の手順を踏む必要があります。
- 建築士資格(一級または二級)を取得していること
- 国土交通大臣登録の講習機関で「特殊建築物等調査資格者講習(特定建築物調査員講習)」を修了すること
- 所定の実務経験(例:2年以上)があること(※講習機関により異なる)
建築士という比較的難易度の高い資格を取得することが欠かせない資格です。
建築士の資格取得について興味がある方は、以下の記事もチェックしてみてください。
調査から報告書提出までの流れ
特殊建築物定期調査は、調査を終えたのち、正確な報告書の作成と自治体への提出が必要です。
以下に、標準的な調査~報告書提出までの流れを表形式で整理しました。
| 手順 | 内容 | 注意点・ポイント |
| ① 対象建築物の確認 | 用途・延床面積・階数などをチェックする | 自治体基準に照らして調査義務の有無を確認 |
| ② 有資格者の選定・契約 | 調査会社や建築士へ依頼する | 調査資格の有無を要確認 |
| ③ 現地調査の実施 | 外壁・避難経路・構造の劣化確認する | 写真・記録を精密に取得 |
| ④ 報告書の作成 | 調査結果を報告書へ反映する | フォーマットに沿って記載。図面添付も必要 |
| ⑤ 自治体への提出 | 所轄の建築主事へ提出する | 原則書面+データ(PDF)提出。期日厳守 |
ちなみに、調査結果は正確に報告書にまとめ、期日までに提出が必要です。調査会社任せにせず、報告期限と内容を管理者側でも把握しておくようにしましょう。
未実施時の罰則や行政指導
特殊建築物定期調査は、建築基準法で義務付けられている調査報告制度であるため、調査を怠った場合や、報告書の提出をしないまま放置すると、法的な罰則や行政指導の対象となる可能性があります。
たとえば、特殊建築物定期調査を実施せず、報告もしなかった場合は、建築基準法第103条に基づく是正命令や過料(最大50万円)が科されるかもしれません。
(参考:報告書もしくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書もしくは添付書類の提出をした者が対象)
定期調査の報告漏れや未実施を防ぐためにも、以下のような対応を検討しましょう。
- 調査対象物件の一覧と報告スケジュールを台帳化する
- 調査資格者との契約管理を行い、実施履歴を明示する
- 管理会社と情報共有し、責任の所在を明確にする
また、万一過去に報告漏れがあった場合でも、速やかに調査を実施して報告することで、過料や公表の回避につながる可能性もあります。迷った場合は、早めに専門家や自治体へ相談しましょう。
まとめ
特殊建築物定期調査は、単なる点検ではなく、法的に義務付けられた建物の健康診断です。
調査の対象となる建築物は、マンション・病院・学校など、日々多くの人が利用する施設が中心であり、3年に1回の頻度で実施し、自治体へ報告書を提出しなければなりません。義務違反をすると、罰則・過料を科されることもあるため、十分に注意して定期点検を実施してください。


