「令和7年版国土交通白書」をDXとグリーンインフラという独自の視点から読み解いてみる
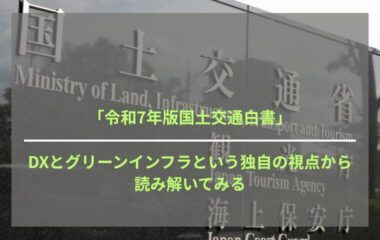
2025年6月24日、国土交通省が公開した「令和7年版国土交通白書」は、日本のインフラと社会の未来を考える上で重要な示唆に満ちている。とくに、DXとグリーンインフラに関する施策は、たんなるテクノロジーやトレンドを超え、社会や環境、インフラの持続可能性を支えるための切り札として注目度が増しているように思われる。本記事は、DXとグリーンインフラという独自の視点から、白書を読み解こうとするものだ。
目次
DX:インフラの「頭脳」をアップデートする
建設業と運輸業のDX:労働力不足への挑戦
白書では、建設業や運輸業における労働力不足が深刻化していると指摘されている。背景には、就業者の高齢化と若年層の入職減少がある。特に建設業では、2025年時点で約110万人の技能労働者が不足するとの試算も存在する。この危機に対し、DXは労働生産性の向上と新たな働き方の創出を約束する。
たとえば、建設現場でのBIMの活用は、設計から施工、維持管理までをデジタルで一元化し、効率化を図る。白書によれば、2024年度までに国土交通省が推進する「i-Construction」プロジェクトにより、3Dデータ活用による生産性向上が全国の約7割の公共工事で実践されている。さらに、ドローンやAIを活用した点検システムは、人手不足を補いながら、老朽化したインフラの安全性を確保する。実際、橋梁点検におけるドローン活用は、従来の目視点検に比べ、作業時間を約30%削減する事例も報告されている。
建設現場における自動施工とロボット活用による革新
これに加え、自動施工技術やロボット活用が建設現場の革新を加速している。白書は、自動化重機の導入により、土木工事の作業効率が最大50%向上した事例を紹介。特に、トンネル工事では、AI制御の掘削ロボットが24時間稼働し、従来の工期を20%短縮したケースが報告されている。ロボット技術は、危険な高所作業や夜間作業を代替し、労働者の安全性を向上させる一方、熟練技能者のノウハウをデジタル化することで、若手技術者の育成にも寄与する。たとえば、コンクリート打設ロボットは、センサーとAIを活用して最適な施工条件を自動調整し、品質のバラつきを抑える。2025年時点で、こうしたロボットの導入率は大規模工事の約30%に達し、2028年までに50%以上を目指す計画だ。
さらに、自動施工とロボット活用は、地方の建設現場での課題解決にも光明をもたらす。白書によれば、過疎地域では熟練労働者の確保が難しく、工期遅延が頻発していたが、遠隔操作型の建設ロボットがこの問題を軽減している。たとえば、島根県の橋梁工事では、都市部のオペレーターが5Gネットワーク経由でロボットを操作し、現場作業員の負担を大幅に削減。これにより、地方のインフラ整備が加速し、地域経済の活性化にも繋がっている。今後は、6G通信の普及やAIのさらなる進化により、リアルタイムでの遠隔施工精度が向上し、2029年までに全国の公共工事の半数以上で自動施工が標準化される見込みだ。
運輸業では、自動運転技術やMaaS(Mobility as a Service)の進展が顕著だ。白書は、レベル4の自動運転バスが地方都市で実証実験を重ね、2027年までに全国50地域での本格運用を目指すと記す。MaaSは、公共交通とライドシェアを統合したプラットフォームを通じて、地方の交通空白地帯を解消する可能性を秘める。これにより、高齢者の移動手段が確保され、過疎地域の生活基盤が強化される。
データ駆動型社会への転換
DXのもう一つの柱は、データ活用だ。白書は「スマートシティ」の実現に向けた取り組みを強調する。都市全体のデータをリアルタイムで収集・分析し、交通渋滞の緩和やエネルギー効率の最適化を図る。たとえば、横浜市では、IoTセンサーとAIを活用した交通管理システムが2024年に導入され、渋滞時間が約15%減少した。こうした事例は、データが都市の「頭脳」として機能する未来を示唆する。
しかし、課題も多い。データの標準化やプライバシー保護、サイバーセキュリティの強化は、DX推進の前提条件だ。白書は、2026年までに公共データのオープンデータ化を90%以上にする目標を掲げるが、民間企業との連携や法制度の整備が追いついていない実態も浮き彫りにしている。
今後の展望:人間中心のDXへ
DXの未来は、単なる効率化を超え、人間中心の価値創造にある。たとえば、AIによるインフラ管理は、単にコスト削減を目指すのではなく、地域住民のニーズに合わせた柔軟なサービス設計を可能にする。白書は、住民参加型のスマートシティ構想として、福岡市での「市民共創プラットフォーム」を紹介。2025年中に市民が直接アプリでインフラの課題を報告し、行政と共同で解決策を模索する仕組みが本格稼働する予定だ。自動施工やロボット活用においても、人間中心のアプローチが求められる。白書は、建設ロボットの操作インターフェースを直感的で使いやすいものに改良し、デジタルリテラシーの低い労働者でも扱えるようにする取り組みを強調。2027年までに、全国の建設現場で「ロボットオペレーター養成プログラム」を展開し、若年層や女性の新規参入を促進する計画だ。これにより、建設業の多様な人材活用が進み、業界全体の魅力向上につながる。
一方、DXの進展は新たな格差を生むリスクも孕む。デジタルリテラシーの低い高齢者や、インフラ投資が少ない地方での「デジタルディバイド」が問題視される。今後は、インクルーシブなDX、つまり誰もが恩恵を受けられる仕組み作りが求められる。白書は具体策として、2028年までに全国の自治体でデジタル教育プログラムを展開する計画を提示しているが、その実効性は予算と人材確保にかかっている。自動施工やロボット技術の普及においても、地方中小企業への技術移転や導入コストの低減が課題となる。政府は、2026年までにロボットレンタル制度や補助金を拡充し、中小規模の建設業者でも自動化技術を導入しやすくする方針を示している。
グリーンインフラ:自然と共生する社会基盤
グリーンインフラの現状:脱炭素と防災の両立
白書は、グリーンインフラを「自然の機能を活用した持続可能な社会基盤」と定義し、脱炭素と防災の両立を強調する。背景には、気候変動による豪雨や熱波の頻発がある。2024年の全国の豪雨被害額は約2兆円に上り、従来のコンクリート依存型インフラ政策、いわゆるグレーインフラ政策はすでに限界に達している。
グリーンインフラの代表例として、都市部での緑地拡大や河川の自然再生が挙げられる。東京都では、2024年から始まった「東京グリーンビズ」プロジェクトが注目を集める。既存の緑地を保全しながら、オフィス街などに緑地帯を新たに整備し、ビルや住宅などへの雨庭の整備普及を支援することなどを通じて、「自然と調和した持続可能な都市」を目指している。
地方では、農地や森林を活用した防災インフラの整備が進む。宮城県では、津波対策として沿岸部の湿地を復元するプロジェクトが進行中。湿地は津波のエネルギーを吸収し、従来の防波堤に比べ建設コストを約40%削減する。さらに、生物多様性の保全にも寄与し、地域の観光資源としての価値も生み出している。
再生可能エネルギーとの連携
グリーンインフラは、エネルギー転換とも密接に関連する。白書は、洋上風力発電の拡大を国の重点施策として掲げる。2025年時点で、日本の洋上風力発電容量は約1.5GWだが、2030年までに10GW、2040年までに45GWを目指す。この目標達成には、港湾インフラの整備や送電網の強化が不可欠だ。特に、北海道や東北地方の洋上風力ポテンシャルは大きく、地域経済の活性化にもつながる。
洋上風力は、安定した風速と広大な設置面積を活かし、再生可能エネルギーの主力として期待される。たとえば、秋田県沖では、2024年に商用運転を開始したプロジェクトが年間約30万世帯分の電力を供給。これにより、CO2排出量を年間約40万トン削減する効果が見込まれる。
また、浮体式洋上風力発電の技術開発も進んでおり、2027年までに深海域での実用化を目指す。浮体式は、従来の固定式に比べ設置可能な海域が広く、日本の急峻な海底地形に適している。政府は、2035年までに浮体式のコストを1kWhあたり10円以下に抑える目標を掲げ、民間企業との共同研究を加速している。
一方、再生可能エネルギーの導入には地域住民の理解が欠かせない。白書は、風力発電の騒音問題や景観への影響を軽減するための技術開発を加速するとしている。2026年までに、低騒音型風車の導入率を50%以上に引き上げる目標だ。
さらに、洋上風力の開発においては、漁業との共存が課題となる。白書は、漁業補償や海域利用の調整を進めるため、2025年度中に全国の沿岸自治体で「洋上風力共生協議会」を設立する計画を明記。青森県では、漁業者と事業者が共同で海底環境のモニタリングを行い、漁場への影響を最小限に抑える取り組みがモデルケースとして進んでいる。これらの努力は、洋上風力が地域の新たな産業基盤として根付くための基盤を築く。
今後の展望:循環型社会へのシフト
グリーンインフラやクリーンエネルギーの導入は、循環型社会の構築という文脈上にある。白書は、建設資材のリサイクル率を2030年までに98%に引き上げる目標を掲げる。すでに、コンクリート廃材を再利用した「リサイクルアスファルト」の採用が全国の道路工事で広がっている。さらに、バイオマスを活用したエネルギー供給や、廃棄物を原料とした新素材の開発も進む。
しかし、グリーンインフラの普及には資金面の課題が横たわる。白書は、民間投資の呼び込みやグリーンボンドの活用を提案するが、投資回収期間の長さが障壁となっている。今後は、官民連携によるリスク分担や、環境価値を経済価値に変換する仕組み(例:カーボンクレジット)がカギを握る。
また、グローバルな視点も重要だ。日本は、グリーンインフラの技術輸出を強化し、アジア太平洋地域でのインフラ整備をリードする可能性がある。白書は、インドとの技術交流(2022年の日印道路会議など)を例に、国際協力を通じた市場拡大を視野に入れる。洋上風力分野では、台湾やベトナムとの共同プロジェクトが進行中であり、日本の技術力が国際競争力を発揮する機会が増えている。2028年までに、アジア市場での洋上風力関連の受注額を現在の3倍に引き上げる目標も掲げられている。
社会全体で支える「活力あふれる社会」とは?
白書のテーマである「みんなで支え合う活力あふれる社会」は、DXとグリーンインフラといった施策群が、たんなるテクノロジーの追求や世界的なトレンドへの便乗にとどまらず、社会全体の協働を促すことを示唆する。
たとえば、地域住民がインフラの維持管理に参加する「シビックテック」の動きが広がっている。白書は、熊本県での「地域管理型インフラ」としての流域治水関連の取り組みに言及。住民がIoTセンサーで河川の水位を監視し、自治体と連携して洪水対策を行う仕組みは、行政の負担軽減と地域のレジリエンス向上を両立するものだ。
一方で、こうした取り組みは、地域間の格差を浮き彫りにする。財政力の弱い自治体では、DXやグリーンインフラの導入が進みにくい。白書は、国の補助金制度や技術支援の拡充を約束するが、地方の自立性をどう確保するかは未解決の課題だ。
インフラを通じたテクノロジーと人間の共生社会へ
「令和7年版国土交通白書」は、DXとグリーンインフラを通じて、日本のインフラが新たなフェーズに入ったことを示している。しかし、テクノロジーの進展は、同時に社会のあり方を問う。効率化や持続可能性を追求する一方で、誰のためのインフラなのか、誰が取り残されるのかを常に考える必要がある。
今後10年、DXはデータ駆動型の意思決定を加速し、グリーンインフラは自然と調和した社会を築く基盤となるだろう。だが、その成功は、技術の導入スピードだけでなく、住民一人ひとりの参画と理解にかかっている。白書が描く「活力あふれる社会」は、テクノロジーと人間が共生する社会でもある。その実現に向け、私たちは何をすべきか。答えは、データや緑の中だけでなく、私たち自身の行動の中にあるのかもしれない。


