【2025年】土木CIMとは?BIMとの違い・導入メリット・活用事例をわかりやすく解説
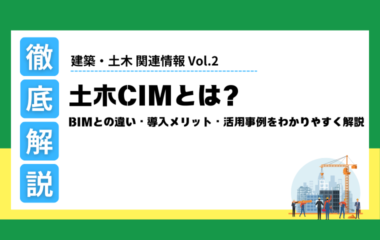
デジタル技術の進展により、土木分野でも「三次元モデル」を活用した施工や設計が急速に普及しています。そのなかでも注目されているのが「CIM(Construction Information Modeling)」です。
そこで本記事では「CIMとは何か」という基本的な概念、BIMやCADとの違い、導入によるメリットや事例を解説したのち、2025年現在の国の最新方針についてわかりやすく紹介します。
目次
CIMとは?基本概念と目的
CIM(Construction Information Modeling)とは、3次元モデル(3Dモデル)を中心に設計・施工・維持管理にかかる情報を一元管理する仕組みのことです。国の情報では次のように説明されています。
コンピュータ上に作成した3次元の形状情報(3次元モデル)に加え、構造物及び構造物を構成する部材等の名称、形状、寸法、物性及び物性値(強度等)、数量、そのほか付与が可能な情報(属性情報)とそれらを補足する資料(参照資料)を併せ持つ構造物に関連する情報モデル(BIM/CIMモデル)を構築すること
引用:国土交通省「BIM/CIM 活用ガイドライン(案)」
またCIMの読み方は「シム」であり、Construction(工事)という名称がつくことから、主に土木業界で活用されています。またCIMは、単なる3D図面ではなく、属性情報(材質・コスト・施工時期など)をデジタルモデルに組み込み、数量算出や構造計算といった手間のかかる作業を効率化できるのが魅力です。
BIMとCIMの違い【比較表付き】
CIMとよく比較されるのが「BIM(Building Information Modeling)」です。以下に2つの違いをまとめました。
| 項目 | CIM(土木) | BIM(建築) |
| 対象分野 | インフラ (道路・橋・ダム・トンネルなど) | 建築物 (ビル・住宅・工場など) |
| モデル構成 | 地形・構造物・付帯施設など | 建築物の構造・仕上げ・空調設備など |
| 関係者 | 発注者・設計コンサル・施工会社 | 建築士・設計者・施工業者 |
| 主な活用目的 | 設計協議、施工段取り、維持管理 | 意匠設計、設備管理、施工検証 |
| 国の対応方針 | 国交省「BIM/CIM活用ガイドライン」 | 国交省「BIM推進会議」 |
BIMは建築分野、CIMは土木分野に対応する技術という点が最も大きな違いです。なお、現在はBIMとCIMをまとめようという動きができており、2025年現在はBIM/CIMという名称で呼ばれることがほとんどです。また今後はBIMという名称に統一される予定となっています。
なおBIMやCIMについて詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
CADとの違い【比較表付き】
CIMは従来の「2D・3DCAD設計」とは異なり、空間認識や情報の自動化処理が可能です。以下に比較表をまとめました。
| 項目 | 2D・3DCAD | CIM(3D + 属性情報) |
| 表現 | 2次元 (平面図・断面図) | 3次元モデル (形状・構造の立体化) |
| 情報連携 | 図面を印刷・PDF共有 | クラウド共有や属性付きモデル連携 |
| 施工への反映 | 現場での再解釈が必要 | そのまま施工計画や工程に活用可能 |
| 修正の反映 | 図面ごとに個別修正が必要 | モデルを修正すれば連動して各資料に反映 |
特に大きな違いは「クラウド化」と「属性情報」の有無です。CIMはCADと比べて手動での作業を必要最小限に抑えられます。
なぜ土木業界でCIMが注目されているのか?
現在土木業界では、CIMを活用した設計スタイルへと移行する流れができています。このように注目が集まる理由は、土木業界が抱えている次の課題を解決できるためです。
- 少子高齢化による技術者不足
- 維持管理コストの増大
- 災害対応・復旧の迅速化
また、国土交通省が掲げる「i-Construction」「建設業DX」を実現することにもつながり、設計・施工・維持管理のプロセスを根本から変える技術として注目されています。
土木分野におけるCIMの導入メリット
土木業界でCIMを導入することで得られるメリットは、以下の4つです。
| メリット | 内容 |
| 情報共有の効率化 | 3Dモデルで関係者が同じ情報を共有し、認識ズレ・手戻りを削減 |
| 設計・施工の精度向上 | 干渉チェックや完成形の可視化でミス防止・設計の質向上 |
| 維持管理の効率化 | 点検・補修履歴をモデル上で管理し、ライフサイクルコストを削減 |
| 工期短縮・コスト削減 | 資材配置や工程計画の最適化し、工期短縮・費用削減に貢献 |
なお、国土交通省が公開した資料によると、ほとんどの導入企業が効率化を実感できたと回答しています。
出典:国土交通省「建築分野におけるBIMの活用・普及状況の実態調査(令和4年12月調べ)」
対して、効果を実感できなかったと感じる企業は7%程度にとどまり、多くの企業が効率化を実現できていることがわかっています。
またCIMのメリットや導入ステップを詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
土木業界に多いCIM導入の課題と解決策
土木に携わる企業が新たにCIMを導入するとき、人材や金銭などさまざまな課題に直面します。参考として以下に、よく起こる課題とその解決策をまとめました。
| 課題カテゴリ | 解決策の方向性 |
| 技術・人材の不足 | ・社内研修・外部講習を使ってスキルアップ・eラーニング・CIM技術者講習の活用 |
| 初期投資の負担 | ・小規模プロジェクトから段階的に導入・国や自治体の補助金・支援制度を活用 |
| 業務フローとのミスマッチ | ・紙文化を残しつつ一部業務からデジタル移行・モデル活用の「部分導入」から開始 |
| 発注者と受注者のギャップ | ・発注仕様書の内容確認・提案型対応・ガイドラインや事例集の共有で理解促進 |
| 成果物の扱いが不明確 | ・国交省のBIM/CIM活用要領や成果物例を参照・社内テンプレート化で対応統一 |
入念な対策を取れば、初めてCIMを導入する企業でもスムーズなスタートを切れます。自社が抱える課題と比べつつ、何を実施すべきか検討してみてください。
【2025年】国土交通省の土木CIMの最新動向
近年では、CIMの活用方針が毎年見直されており、2025年現在では「原則活用」「標準化」「ガイドライン整備」といった段階に進んでいます。ここでは、国が定める最新の方針と、義務化の動向についてわかりやすくまとめました。
| 年度 | 施策・段階 |
| 2012 | CIM試行プロジェクトの開始 |
| 2020 | BIM/CIM活用ガイドラインの初版発行 |
| 2023 | 一部公共事業でBIM/CIMの活用義務化 |
| 2025 | 適用範囲の拡大・原則CIM義務化の方向性 |
BIM/CIM活用要領やガイドライン更新内容
国土交通省はこれまでに、CIM導入の具体的な手引きとして「BIM/CIM活用ガイドライン」「CIM事業における成果品作成の手引き」「設計照査シートの運用ガイドライン」などの各種基準を整備してきました。
2025年現在、上記の内容は「BIM/CIM関連基準要領等(令和6年3月)」に詳しくまとめられています。CIMを導入した土木企業は、新たにチェックする基準要領として資料を取得しておくのがおすすめです。
公共事業での義務化対象・今後の拡大予定
CIMの活用は、すでに一部の公共工事で「原則適用」が義務づけられつつあります。
出典:国土交通省「令和5年度BIM/CIM原則適用について」
特に国主体の業務や設計費1億円以上、または工事費10億円以上の案件を中心に「3次元モデルによる納品」が求められる段階に入っており、今後2026年以降は自治体レベルでもCIMの原則適用可が進んでいくと予想されます。
まとめ
土木業界が抱える慢性的な課題を解決し、業務効率化として大きな効果を生み出すCIMは、今後土木関連企業にとって欠かせないデジタルツールとして定着していくでしょう。
なお現在進行形で基準や指針といったルールが調整されている点に注意が必要です。CIM導入を検討している担当者は、常に最新の情報を収集することを意識しましょう。


