【2025年】測量法とは?法律の概要・改正のポイント・測量の基礎知識をわかりやすく解説
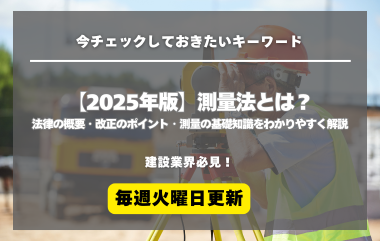
地形の状況や物体の配置などを計測する測量は、測量法という法律に準拠して実施しなければなりません。では、測量法にはいったいどのようなルールがまとめられているのでしょうか。
この記事では、測量法の概要や最新の改正内容を説明したのち、法律内に定められているルールや、測量を実施する際の基礎知識についてわかりやすく解説します。
目次
測量法とは
測量法とは、日本における測量の基準や手続き、測量成果の管理・公開について定められた法律です。
主に、土地の形状や位置関係を把握する場合や、地図の作成、都市計画、建設工事などさまざまな分野で活用します。
なお、測量は日本全国で実施する業務であることから、統一されたルールにしたがって測量をしなければ、座標や位置がズレてしまいます。そのため、測量法では、利用する測地系(座標の位置)や正しい精度で測量を実施するための機器、また求められる使い方や国家資格などが制定されました。
ちなみに測量法は1949年からある法律です。測量技術の発展とともに法律が改正されていき、現在はIT技術を駆使したドローンやレーザーなどの測量に関するルールも追加で定められています。
2025年に測量法の請求手数料が改正
測量法の最新の改正年は、令和6年(2024年)6月12日です。
当改正では、主に、測量法に基づく請求手数料の改正等が予定されています。3次元モデルによる測量成果の利用を促進すること、そしてデジタル化に伴う管理コストの適正化のために見直しが実施された背景があり、測量成果の取得および手数料に関わる次の変更が加わる見込みです。
- 測量成果を電子提供できるようになる
- 電子提供された測量成果の料金体系が整備される
- 紙媒体における測量成果交付費用を電子提供とのバランスを見て見直す
電子媒体の測量成果を利用できるようになったほか、国土地理院、自治体に対し、紙媒体・電子媒体の両方で申込みできるようになったのが特徴です。ほかにも、測量士等の登録や試験に関する規定が廃止されるなど、細かな調整も加えられています。
なお改正された測量法は令和7年(2025年)4月1日に施行される予定となります。
測量法で定められている内容
そもそも測量法にはどのようなルールが定められているのでしょうか。以下に、基本的なルールを整理しました。
| 項目 | 概要 |
| 測量の基本基準 | 測量の実施方法や精度基準を統一するための規定(座標や使い方など) |
| 測量士の資格と業務範囲 | 測量士および測量士補の資格要件や、実施可能な業務内容(2025年の改正で一部省略) |
| 測量成果の管理と公開 | 国や地方公共団体による測量成果の保管・公開に関する規定 |
| 測量の実施手続き | 基本測量、公共測量、民間測量の手続きについて |
誰がどのように測量できるのかをまとめているのが、測量法の基本です。特に測量事業者は「測量の実施手続き」に準じて業務を進行しなければなりません。
また、以下に測量法のなかでも特に重要となる既定のポイントを2つ整理しました。
測量の実施に必要な権限
測量をするためには、あらかじめ土地所有者や関係者の協力を得なければなりません。そのため測量法には、適正な方法で測量を実施するための、測量士が持つべき権限について規定されています。以下に主な権限を整理しました。
- 測量の目的で他人の土地に立ち入るための「立入権」(事前通知や承諾が必要)
- 道路や敷地などに測量の基準点を設置するための「測量標設置の権限」
- 公的測量における測量成果の提出・管理に関する「測量成果の提供義務」
許可を取得すれば、従来だと立ち入りができない場所に進入できるほか、公共の場所に基準点(杭や鋲など)を設置できる権利を所有できます。
測量成果の公開およびその利用
測量法では、測量成果を一般公開し、国民や企業が地理情報を活用できるルールが定められています。以下に、よく利用されているオープンソースの測量データの提供元をまとめました。
- 国土地理院
- 東京都 オープンデータ カタログサイト
- G空間情報センター
なお、各自治体でも地積測量図の入手(有料)等が可能です。また上記のサービスから取得したデータ等は、ただ測量図として利用するのではなく、GIS(地理情報システム)として、建物の配置や埋設管の位置などを地図上に表示するなど、多様な目的でデータを利活用できます。
測量法に関係する測量の種類
測量法のなかで定められている測量の種類を以下に整理しました。
一筆地測量
土地の筆界(境界)を明確にする目的で実施する測量です。
土地の売買や登記の際に実施し、測量士が現地で境界を確認しつつ隣接地の所有者と合意を取ったうえで、測量図を作成していきます。主に、不動産取引の安全性を確保するために欠かせない測量です。
復元測量
過去の測量記録をもとに、失われた境界や基準点を復元する測量です。
例えば、土地の境界杭が長年の間に紛失した場合、その正確な位置を再現しなければなりません。そのため過去の測量図や登記情報を洗い出し、測量機器を用いて再度現場の境界を特定します。
地形測量
土地の起伏や形状を詳細に記録するための測量です。
主に工事関連業務の初期段階〜施工の間に実施する測量であり、都市開発やインフラ整備に不可欠です。
測量士が後述する専用の測量機器を用い、高低差や地表を計測して地図を作成します。また近年では、ドローンや3Dレーザースキャナーといった新技術を活用し、短時間で広範囲を高精度に測量できる方法が登場しています。
高低測量
土地の標高や傾斜を測定し、造成工事や排水計画などに活用する測量です。
特に河川や道路の設計では、水の流れを検討するために正確な標高データの利用が欠かせません。一般的にはレベル測量機やトータルステーションを利用し、mm単位の精度で工事範囲の測定を実施します。
真北測量
主に建築物や構造物の正確な方位を決定するための測量です。
特に風力発電施設の設計や、太陽光発電パネルの設置など、方角によって効果が変動しやすい機器の設置検討で利用します。天文観測や磁気方位の知識が必要になるほか、正確な北方向を決定する経験とスキルが必要です。
測量に用いる機器の種類
前述した測量を実施するためには専用の機器を準備しなければなりません。複数の測量機器が利用されているため、それぞれの特徴や用途を整理しました。
レベル
地形の高低差を測定する機器であり、水準測量に利用します。
基本的に目視で高さ情報を測定する必要があり、建築現場や土地造成、正確な水平基準を明確にするために用います。
トータルステーション
レベルよりも高度な測量が必要な場合に利用するのが、トータルステーションです。
角度と距離を同時に測定できる電子測量機であり、測量士がプリズム(反射鏡のようなもの)を計測位置に設置し、トータルステーションからレーザーを照射することにより、精密な測量データを瞬時に取得できます。
基本的なやり方はレベルと同じであり、境界測量や地形測量に幅広く使用します。
GNSS測量機
GPSなどの衛星測位システムを利用した測量機器です。
衛星軌道上を漂っている人工衛星から地上座標の情報を取得し、mm単位での正確な位置を入手できます。移動しながらでも測量が可能であり、山間部や都市部などさまざまな環境で利用できるのが特徴です。
3Dレーザースキャナー
地形や建築物などの物体をスキャンし、自動で3Dデータ(点群)を作成できる機器です。
レベル・トータルステーションと同じように据え付けて使用し、短時間で広範囲を高精度に測量できるため、土木設計や遺跡調査などに利用されます。
UAV(ドローン)
UAV(ドローン)を活用した空中測量技術です。
前述した3Dレーザーを搭載したUAVを用いる場合と、高精度カメラを搭載した写真測量に対応できるUAVを用いる場合の2種類があります。また広範囲の測量を短時間で行えることから、災害時の被害状況把握や、森林調査などにも用いられています。
まとめ
測量業務は、測量法で定められているルールに準じて実施しなければならず、違反すると営業停止処分を受けることも少なくありません。
定期的に改正が加えられているなか、新たに2025年4月1日から改正された測量法が施行されます。測量事業者は手続き等のトラブルを避けるためにも、ぜひ最新の測量法を理解したうえで、業務を実施するようにしましょう。


