道路法の一部改正が閣議決定!令和7年に変わるポイントや過去の改正履歴を紹介
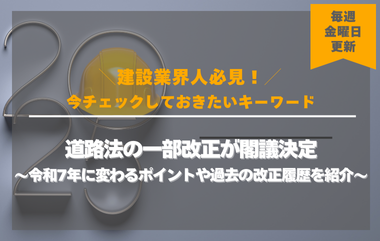
道路の設置や維持管理に関わるルールが定められた「道路法」が、令和7年に一部改正案が閣議決定されました。では、どのようなポイントが改正されることになるのでしょうか。
この記事では、道路法の概要を説明したのち、改正されるポイントや過去の改正履歴についてわかりやすく解説します。
目次
道路法とは簡単に言うと何?
道路法とは、日本国内における道路の設置や維持管理について基本的なルールを定めた法律です。人々の生活や経済活動を支える道路は、日本全体で総延長128万3,726kmあると言われており、ほとんどが社会生活のために利用されています。
参考として以下に、道路法の主な目的を整理しました。
- 道路の整備・維持管理の基準を定める
- 道路の安全性や利便性を確保する
- 道路に関する公的な権限や義務を規定する
なお、道路を円滑に維持管理するためには、設置するエリア・交通条件をもとに、明確なルールを定めなければなりません。そのような動きもあり、道路法は1952年(昭和27年)に制定され、現在も改正を加えながら法律が運用されています。
道路法と道路交通法の違い
道路法と似た言葉に「道路交通法」があります。参考として以下に、2つのキーワードの違いを整理しました。
| 道路法 | 道路交通法 | |
| 主な目的 | 道路の設置/維持管理に関する規定を定める | 道路を通行する人/車両のルールを定める |
| 管理者 | 国土交通省、都道府県、市町村など | 警察庁、都道府県警察 |
| 適用範囲 | 道路そのもの (国道/都道府県道/市町村道など) | 道路を利用する歩行者/車両/自転車など |
| 法律に定められていること | ・道路の種類と管理者の定義 ・道路の占用許可や制限 ・道路の維持管理・改築など | ・交通ルール (信号、標識、通行方法など) ・違反行為の罰則 (速度超過、飲酒運転など) |
2つの法律は、対象が道路なのか、道路を利用する人や自動車なのかという違いがあります。道路法は「道路そのものの管理に関する法律」、道路交通法は「道路の使い方を示す法律」だと覚えておきましょう。
令和7年に道路法等の一部を改正する法律案が閣議決定
令和7年2月7日、政府によって道路法をはじめとする関連法律の一部改正が閣議決定されました。
今回の改正では、社会情勢の変化や技術の進展を踏まえ、より安全で効率的な道路管理を実現する目的で改正が加えられています。参考として以下に、改正のポイントをまとめました。
- 災害時の対応について
- 管理者の人口減少における制度について
- 道路工事の脱炭素化について
- 道路網整備の基本理念について
改正の多くは、日本で頻発化している災害に対する内容です。現代ならではの課題解決を意識した道路の設置・維持管理のために複数のポイントが改正されています。
改正案が閣議決定された背景
道路法は直近だと令和6年4月1日に部分改正が実施されています。そういったなか、その1年後である令和7年に改正が閣議決定されたことには、次のような背景があります。
- インフラの老朽化への対応
- 防災・減災の強化
- 新技術の導入と道路管理の効率化
- 環境対策とカーボンニュートラルへの対応
例えば、日本の道路インフラは、高度経済成長期に整備されたものが多く、老朽化が進んでいることから、優先順位を決めた適切な補修や更新が求められています。また頻発している台風や豪雨、地震などの自然災害が道路機能維持の大きな課題となっている状況です。そのため、老朽化による道路の損壊を回避することはもちろん、道路の耐災害性向上や、緊急時の道路啓開の迅速化を目的として道路法が一部改正されています。
また建設DXの推進に伴い、センサー技術やAI、IoTを活用した道路管理の効率化が進められていること、持続可能な社会の実現に向けて、CO2排出量削減の観点からも道路のあり方が見直されていることも背景にあります。現状の課題だけではなく、今後推進していくべき要素を加えて、複数のポイントが改正されています。
令和7年の道路法改正で変更するポイント
令和7年の道路法改正のポイントを項目に分けて紹介します。どのような項目が加えられたのか、詳しく見ていきましょう。
道路の維持管理の高度化
時間の経過とともに劣化してしまう道路を長く利用していくために、令和7年の改正では、道路の点検や修繕等を、ほかの自治体が代行できる制度(連携協力道路制度)を創設しました。
今まで、道路管理は各エリアを管轄している自治体のみが対応している状況でした。しかし現在は、人口減少によって管理者側に人手不足が起きています。そういった状況下において、近隣エリアの管理者の手が空いている場合に管理業務を代行できれば、人手不足の穴を埋めることが可能です。
災害対策の強化
日本ならではの課題である自然災害が起きた場合、道路は人々の避難路としての役割があります。そこで令和7年の改正では、道路啓開計画(早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な段差修正等により救援ルートを開けること)を法定化しました。
また、被災地で不足しがちなトイレなどを各都道府県が配備できるように、占用許可基準の緩和や、設置に対して無利子貸付制度を創設するなど、被災時のソフト対策に関する項目が追加されました。
道路の脱炭素化の推進
2050年目標で推進されているカーボンニュートラルの取り組みを加速するため、道路法では、次のような脱炭素化の項目が追加されました。
- 道路管理者が道路脱炭素化推進計画を策定する枠組みを導入
- 脱炭素化に資する施設等の占用許可基準を緩和
以前までの道路管理では難しかった、脱炭素に関わる新技術の提案をしやすくなることはもちろん、脱炭素のために設置される施設の占用許可を取りやすくなるのが主な変化です。
環境のことを考えた道路管理ができるようになることから、土木業界としてもカーボンニュートラルを目指しやすくなるのが改正の魅力です。
令和7年以前の道路法改正履歴
道路法は、これまでに何度も改正が加えられて現在のルールができあがっています。参考として、過去の改正履歴を一覧に整理しました。
| 改正時期 | 主な改正内容 |
| 昭和27年(1952年) | 道路法の制定 |
| 平成13年(2001年) | 道路整備特別措置法の改正(民間資金の活用促進) |
| 平成25年(2013年) | 道路管理の効率化(道路メンテナンスの強化) |
| 令和3年(2021年) | スマートインフラ推進(ICT技術の導入) |
上記の改正は、道路法全体が大きく変わった内容について整理しています。
なお令和7年の改正は、あくまで「一部改正」です。新たに項目が付け加えられたものの、基本的な内容は、令和3年(2021年)から大きく変わっていません。
ただし、道路工事関連の業務において脱炭素や災害対策といった取り組みが加えられたため、設計業務・工事業務における提案や、発注者となる自治体の動きが変わります。管理方法や業務進行の内容が変更になる場合もあるため、まずは詳しい改正ポイントをチェックしてみてください。
まとめ
令和7年2月7日に、道路法の一部改正案が閣議決定されました。主に災害や道路メンテナンス、環境対策に関わるポイントの改正であり、今後の道路管理方法や設計・施工の提案の幅が広がる可能性があります。
なお道路法の改正に伴い、道路構造令などにも変更が加えられることがあります。この機会に、今回の閣議決定で、設計業務・工事業務に変更が起きないかチェックしておきましょう。


