建設会社は「全部DXしない」が正解。スーパーゼネコン5社から学ぶ必要最小限のデジタル化
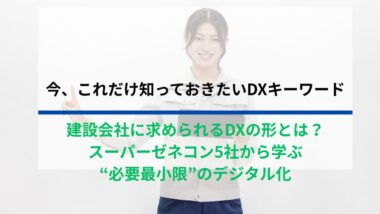
建設業界ではここ数年、「建設DX」や「現場DX」という言葉を耳にしない日はないほどです。しかし、中堅・中小の建設会社や協力会社の現場感覚としては、そこまで手を広げる余裕はなく、ITに強い人材もおらず、目の前の現場を予定通りに仕上げることで精一杯、という状況も少なくありません。
しかし、元請や発注者とのBtoB取引では、一定レベルのデジタル対応が求められつつあります。そこで、この記事では、スーパーゼネコン5社の取り組みにふれつつ、、中堅・中小の建設会社が押さえるべき「必要最小限DX」のポイントに絞ってみていきましょう。
目次
スーパーゼネコン5社も「全部一気にDXしている」わけではない

ここでは、代表的な大手建設会社、いわゆるスーパーゼネコン5社のDXについてみていきましょう。
- 鹿島建設
鹿島建設は「鹿島スマート生産」を旗印に、空間データプラットフォームと連携したデジタルツイン基盤「鹿島ミラードコンストラクション(KMC)」を全社で整備しています。KMCの上にBIMやロボット、遠隔施工システムなどを載せることで、「作業の半分はロボットと・管理の半分は遠隔で・すべてのプロセスをデジタルに」という生産ビジョンを、対象工種や現場を絞り込みながら段階的に具現化しているのが特徴です。 - 清水建設
清水建設は、建築・土木それぞれで「Shimz Smart Site」シリーズを核とした生産プラットフォームを展開しています。建築ではロボットや搬送システムを束ねる「シミズ・スマート・サイト」、土木ではAI・IoTを組み込んだ「Shimz Smart-Site Analyzer」や「Shimz Smart-Site Civil」を用いて、ダンプ運行や造成進捗を一元管理する仕組みを構築しています。これらを現場ごとに組み合わせることで、工程・安全・出来高の管理をデジタル上で回す運用へと少しずつシフトさせています。 - 大林組
大林組は、BIMを中核にした統合設計・生産環境を「BIM生産基盤」として位置づける一方で、運用フェーズ向けにはスマートビルプラットフォーム「WELCS place」を展開しています。設計・施工側ではBIMやシミュレーションを連携させた社内の統合基盤上でデータを回し、竣工後のビルではWELCS placeが各種設備・IoTデバイスをつなぐ器として機能する形で、“設計~施工~運用”をプラットフォームで貫く思想をとっています。 - 大成建設
大成建設は、施工ロボット群「T-iROBO」など現場側のDXに加えて、「Taisei-DaaS(Taisei-Data as a Service)」という全社統合データプラットフォームを構築しています。Taisei-DaaS上に、企画・設計・施工・リニューアルの各工程で発生するデータを集約し、経営ダッシュボードや作業所ダッシュボードと連携させることで、現場の実績と経営判断をつなぐ土台にしているのがポイントです。そのうえで、個別のDXソリューションやT-iROBOシリーズを、この基盤の「利用アプリ」として位置づけています。 - 竹中工務店
竹中工務店は、「建設デジタルプラットフォーム」と呼ぶ自社の統合基盤を持ち、営業・設計・見積・施工管理から人事・経理まで、事業に関わるデータをこのプラットフォームに集約しています。データレイクとIoT・BI・AIを一体で運用する構成になっており、建設DXソリューション群は原則としてこの上で稼働させる設計です。協力会社との資材搬入・据付データをBIMと連携させるなど、施工デジタルツインの実現にもこのプラットフォームを活用しているのが大きな特徴です。
共通して言えるのは、「全部を一気にDXしている会社はない」という点です。テーマを決め、対象工種・対象現場を絞って試し、うまくいったパターンを水平展開しています。
そのため、中堅・中小が「全部DXしなきゃ」と身構える必要はありません。
中堅・中小建設会社が真似すべきなのは、まずは「考え方」だけ
スーパーゼネコンと同じシステム構成や投資額を、そのまま中堅・中小の建設会社がまねる必要はありません。建設会社が本当に参考にすべきなのは、最先端のDXツールそのものではなく、「どの順番で、どこからデジタル化しているのか」という考え方です。
具体的には、次のようなDXの進め方が共通しています。
- 現場のボトルネックを絞り込んでから、手段(DXツール)を選ぶ
- 一部の工種や一部のプロセスだけで試し、成果が出たら範囲を広げていく
- 人員を増やす前に、段取りと情報の流れを見直して、省力化できる部分から変える
考え方を自社の規模・体制に合わせて小さく実践していくと、「最低限ここだけデジタル化できていれば、建設会社として十分戦える」というラインが見えてくるでしょう。
建設会社が押さえたい「必要最小限のDX」は「情報をバラバラにしない」こと
建設会社にとっての必要最小限DXを一言でまとめると、「情報をバラバラにしない仕組みをつくること」です。特に、次の3種類の情報だけでも一元管理できていれば、ムリな投資をしなくても業務効率と収益性は変わります。
- 見積・契約・受発注の条件を、案件ごとのフォルダやクラウドでまとめて管理し、「いくらで・どこまで請けているか」をすぐ確認できるようにする
- 現場写真と検査記録を、紙やアルバムではなく、現場別フォルダやシンプルなツールで残し、「いつ・どこで・何を確認したか」を後から追えるようにする
- 工事別の売上・原価・粗利と、実際にかかった手間(工数)を月1回は整理し、「どの仕事が割に合うか/合わないか」を数字で見えるようにする
3つの情報がそれぞれバラバラではなく、「探さなくてもすぐ出てくる状態」になっていれば、取引先から見ても「任せやすい建設会社」として評価されやすくなります。
失敗しない進め方として「1現場×1テーマ×3か月」を意識する
建設会社のDX導入が失敗する理由の多くは、「やり方が大きすぎる」点です。「来月から全現場で新システムを使う」「分厚いマニュアルだけ配って現場任せにする」といった進め方では、現場が混乱し、「DXは面倒だ」という印象だけが残ってしまいます。
そのため、例として「1現場×1テーマ×3か月」でスモールスタートする方法を検討してみましょう。これは、建設会社におけるDXをいきなり全社で進めるのではなく、まずは1つの現場だけで、やることを1つに絞り、3か月だけ試してみる進め方です。失敗しても被害が小さく、うまくいけば横展開しやすいのが大きなメリットです。
- 協力的な所長・職長がいる現場を1つ選び、「モデル現場」にする
- 「写真だけクラウドに保存する」「見積・注文・請書のフォーマットだけ統一する」など、DXのテーマを1つに絞る
- まず3か月間だけ運用してみる
- 3か月後に、「何が楽になったか」「どこが余計に手間だったか」「協力会社・元請の反応はどうだったか」を現場からヒアリングする
- 続ける/やめる/別のやり方に変える、のどれにするかを決め、良かった部分だけを他現場にも展開する
「小さく試して、必ず振り返る」サイクルを繰り返すことで、建設会社として本当に効果のあるDXだけが自然と残っていきます。
まとめ
鹿島建設、清水建設、大林組、大成建設、竹中工務店といったスーパーゼネコンは高度なDXに取り組んでいます。しかし、その本質は最先端技術ではなく、現場のボトルネックを見極めて小さく試し、うまくいったやり方だけを広げていく積み上げにあります。
中堅・中小の建設会社が目指すべきなのは、同じシステムや投資規模ではなく、自社に合った「必要最小限のDX」を見極めることです。
具体的には、見積・契約・受発注の情報をバラバラにしないこと、現場写真と検査記録だけは紙から卒業すること、工事別の粗利と手間を毎月きちんと把握できるようにすることが、最低限押さえたいラインになります。
DXという言葉に振り回されるのではなく、「この仕組みを入れたら明日の現場が少し楽になるか」を基準に、一歩ずつ現場目線のデジタル化を進めていきましょう。


