【2025年版】軽量コンクリートとは?1種・2種の違いからALC比較まで徹底解説
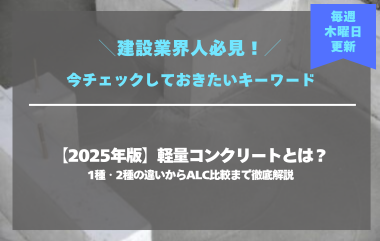
建物の軽量化や断熱性の向上、施工負担の軽減を目的に、近年多くの現場で採用が増えているのが「軽量コンクリート」です。一般的な普通コンクリートよりも比重(単位容積質量)が小さく、1種・2種・ALC(軽量気泡コンクリート)など複数のタイプが存在し、用途に応じて使い分けられます。
そこでこの記事では、軽量コンクリートの種類・特徴・比重・強度・配合・用途をわかりやすく解説します。
軽量コンクリートとは?
軽量コンクリートとは、普通コンクリートよりも比重(単位容積質量)が小さく、構造物の自重を大幅に軽減できるコンクリートの総称です。JIS A 5308(レディーミクストコンクリート)では「軽量コンクリート」として位置づけられ、1種・2種の規定や配合条件が明確に示されています。
(参考:全国生コンクリート工業組合連合会「JIS A 5308 レディーミクストコンクリート
たとえば、コンクリートを軽量化することにより「建物の荷重を減らす」「高層建築や改修で有利になる」「断熱性・遮音性が高い」といった利点を生み出せます。
一方で、軽量骨材は内部に空隙が多く吸水率が高いため、配合や水量調整には注意が必要です。
普通コンクリートや軽量気泡コンクリート(ALC)との違い
軽量コンクリートを理解するうえで重要なのが、「普通コンクリート」「軽量気泡コンクリート(ALC)」との違いです。以下にそれぞれの違いを整理しました。
| 項目 | 普通コンクリート | 軽量コンクリート 1種 | 軽量コンクリート 2種 | ALC(軽量気泡コンクリート) |
| 比重(単位容積質量) | 約 2.3〜2.4 t/m³ | 約 1.8〜2.1 t/m³ | 約 1.4〜1.8 t/m³ | 約 0.5〜0.7 t/m³ |
| 主な骨材 | 砕石・砂 | 粗骨材のみ人工軽量骨材 | 粗骨材+細骨材も軽量骨材 | 石灰質・けい酸質原料+気泡 |
| 構造区分 | RC造の主要構造部材 | RC造構造部材 | RC造構造部材(より軽量) | S造の非構造部材(外壁・屋根) |
| 圧縮強度 | 高い(~40N/mm²) | 普通とほぼ同等 | やや低め | 構造耐力なし(非構造材) |
| ヤング係数 | 高い | 普通より低い | さらに低い | かなり低い |
| 断熱性 | 低い | 普通 | 普通〜やや高い | 非常に高い(気泡が多い) |
| 遮音性 | 普通 | 高い(多孔構造) | 高い | 高いが厚みに依存 |
| 耐火性 | 普通 | 普通 | 普通 | 非常に高い(ALCの特徴) |
| 主な用途 | 梁・柱・スラブ | 高層建築/屋根押え | 改修・荷重制限現場 | 外壁材・屋根材・間仕切り・カーテンウォール |
参考:国土交通省「公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和 3 年 3 月 25 日 国営建技第 19 号|第6章 コンクリート工事」などを参照
たとえば、普通コンクリートは梁や柱といった主要構造部に用いられるのが特徴です。これに対し軽量コンクリート(1種・2種)は荷重制限などがある構造体に使えます。主にRC造向けとして適用可能です。一方でALCは、外壁パネル・屋根材などの二次製品(非構造材)に使われます。
比較表に登場した項目・数値情報については、以下より詳しく解説していきます。
また、モルタルやセメントとの違いをチェックしたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
軽量コンクリートの基礎知識(用途・種類・強度など)
ここでは、軽量コンクリートの基礎知識として、以下の情報を整理しました。
- 用途
- 種類
- 比重(単位容積質量)
- 強度(圧縮・引張・曲げ・付着)
- 経済性
軽量コンクリートの用途|構造体・非構造材で異なる使い方
軽量コンクリートは、建物の荷重を減らしたい場面や断熱・耐火性を高めたい部位で使われます。
たとえば次のように、構造体として扱える軽量骨材コンクリートと、外壁材などに使うALCでは用途が大きく異なるのが特徴です。
- 構造体:梁・床・スラブ・屋根押え(1種・2種)
- 非構造材:外壁パネル・屋根材・間仕切り(ALC)
- 改修現場:床の増し打ち・荷重制限対応
RC造の軽量化、高層建築の荷重調整、外壁の断熱性向上など、現場条件に応じて最適な種類を選定することが重要です。
軽量コンクリートの種類|1種・2種の違いとALCの位置づけ
軽量コンクリートは大きく「軽量骨材コンクリート(1種・2種)」と「軽量気泡コンクリート(ALC)」に分類され、それぞれ規格や用途が異なります。
| 種類 | 特徴 | 主な用途 |
| 1種 | 粗骨材のみ軽量 | RC造の構造部材 |
| 2種 | 粗+細骨材も軽量 | より軽量化が必要な構造部位 |
| ALC | 気泡入り二次製品 | 外壁・屋根・間仕切り |
1種・2種は主に生コンとして構造体に使われ、ALCは外壁用の軽量パネルとして施工されます。
またALCの概要を詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
軽量コンクリートの比重(単位容積質量)
軽量コンクリートの最大の特徴は「軽さ」であり、比重(単位容積質量)が普通コンクリートより大幅に小さくなっています。
| 種類 | 比重(t/m³) |
| 普通コンクリート | 約2.3〜2.4 |
| 軽量1種 | 約1.8〜2.1 |
| 軽量2種 | 約1.4〜1.8 |
| ALC | 約0.5〜0.7 |
重量低減により、構造スリム化・改修工事の荷重調整・高層建築の負担軽減に寄与できるのが軽量コンクリートの強みです。
軽量コンクリートの強度(圧縮・引張・曲げ・付着)
軽量コンクリートの強度は、普通コンクリートとほぼ同等の圧縮強度を確保できますが、ヤング係数・曲げ・引張はやや低い傾向があります。
圧縮強度:普通と同等(1種)
引張強度:普通の約1/9〜1/15
曲げ強度:普通の約1/6〜1/10
付着強度:普通と同程度
(参考:人工軽量骨材協会「技術情報・建築編」)
軽量骨材は吸水性が高いことで空隙が多く、変形性能が異なるため、構造設計時はヤング率を考慮しなければなりません。
軽量コンクリートの経済性
軽量コンクリートは材料単価こそ高いものの、自重が軽くなることで鉄筋量・鉄骨量・基礎規模が縮小できるため、構造全体としてのコストを下げやすいのが特徴です。
| 項目 | 普通コンクリート | 軽量コンクリート(1種) | 結果 |
| 材料単価 (呼び強度18想定) | 15,300円/m³ | 24,800円/m³ | 高い |
| 建物総重量 | 基準 | 約5〜10%軽減 | 軽量 |
| 鉄骨量 | 基準 | 約4〜5%削減 | 減少 |
| 基礎寸法 | 基準 | 小規模化可能 | 減少 |
| 総工事費 | 100% | 約94〜95% | 約4,600万円の削減例あり |
参考1:新潟生コンクリート協同組合「生コンクリート標準価格表」
参考2:人工軽量骨材協会「技術情報・建築編|軽量コンクリートの経済性」)
軽量コンクリートの作り方|現場・工場での製造プロセス
軽量コンクリートは、現場出荷される軽量骨材コンクリート(生コン) と、工場で製造されるALC(軽量気泡コンクリート) の2系統で、それぞれ作り方が異なります。
軽量骨材コンクリート(1種・2種)の製造手順
- 軽量骨材の含水調整(プレウェッティング)
- 配合設計(水セメント比・単位水量の調整)
- セメント・骨材・混和剤の計量
- ミキサーで練り混ぜ(混練時間を長めに設定)
- スランプ・空気量・比重の品質確認
- 現場へ出荷
人工軽量骨材(膨張スラグ・焼成シェルなど)を使用する生コンであり、普通コンクリートと同様に生コン工場で製造されます。骨材の吸水率が高いため事前吸水処理や水量調整が重要です。
ALC(軽量気泡コンクリート)の製造手順
- 発泡(スラリー中でアルミ粉が反応し気泡を発生)
- 整形(型枠内で膨張し、ブロック状に成形)
- 蒸気養生(高温・高圧のオートクレーブで強度発現)
- 切断(規格寸法としてパネルやブロックに切断)
工場で完全に成形される二次製品で、軽量・断熱・耐火の性能が安定しています。内部に微細な気泡をつくるため、コンクリートとは異なる専用プロセスで製造されます。
軽量コンクリートのメリット・デメリット
軽量コンクリートは、その名の通り「軽さ」を武器にした材料であり、構造計画・耐震計画・コスト最適化の観点で大きな利点を持ちます。一方で、吸水性や強度など、普通コンクリートとは異なる注意点もあるため、種類(軽量骨材・ALC)に応じた使い分けと施工管理が欠かせません。
ここでは、軽量コンクリートのメリット・デメリットを種類ごとに紹介します。
軽量骨材コンクリート(1種・2種)のメリット・デメリット
軽量骨材コンクリートは、構造体にも使用できる唯一の軽量材料です。
自重が減ることで構造計画の自由度が上がり、躯体コスト削減にも寄与します。一方で、吸水性が高く品質管理の難度が上がる点は注意が必要です。
| メリット | デメリット |
| 構造体の軽量化で地震力を低減 | 吸水率が高く品質管理が難しい |
| 鉄骨量・基礎規模の縮小でコスト減 | 圧送性が低くポンパビリティに注意 |
| 高層建築で効果大 | ヤング係数が低く変形が大きい |
| スラブのたわみ抑制に有利(1種) | 材料単価は普通コンクリートより高い |
軽量気泡コンクリート(ALC)のメリット・デメリット
ALCは、軽量・断熱・耐火性に優れた「外壁材」として普及しています。
パネル化されているため施工も早く、均一な品質が得られますが、構造材としては使用できず、防水や仕上げで注意が必要です。
| メリット | デメリット |
| 圧倒的な軽さ(比重0.5〜0.7) | 防水処理を怠ると吸水しやすい |
| 高い断熱性・耐火性 | 仕上げの経年劣化に注意 |
| 工場製品で品質が安定 | 構造体としては使えない |
| 施工が早く工期短縮につながる | 固定金物設計に配慮が必要 |
軽量コンクリートについてよくある質問【FAQ】
普通コンクリートとの強度差は?
軽量コンクリートは、圧縮強度そのものは普通コンクリートと大きな差がありません(JIS基準)。ただし、引張・曲げ・ヤング係数は低めで、変形がやや大きい点は設計で配慮が必要です。
軽量生コンとは何?
軽量生コンとは、人工軽量骨材や天然軽量骨材を使用し、比重を下げた生コンクリートのことです。構造物の自重を軽くできるため、高層建築の床スラブや改修工事で採用されます。普通生コンより吸水率が高く、配合設計と施工管理が重要です。
軽量コンクリートの比重は?
軽量コンクリートの比重(単位容積質量)は、1種で約1.8〜2.1t/㎥、2種で約1.4〜1.8t/㎥が一般的です。普通コンクリート(約2.3〜2.4t/㎥)より10〜40%軽く、ALCはさらに軽い0.5〜0.7t/㎥です。用途に応じて種類を使い分けます。
まとめ
軽量コンクリートは、1種・2種・ALCで性能も用途も大きく異なる材料です。
構造体の軽量化によるコストメリット、断熱・耐火性能、非構造材としての施工のしやすさなど、多くの利点があります。一方で、吸水性・強度・施工管理には種類ごとの注意点があるため、現場条件に合わせた最適な選択が欠かせません。
種類で用途が異なるため、設計条件に合わせて材料を選定しましょう。


