【2025年版】建築基準法第22条区域とは?指定区域や調べ方・メリット・デメリットまで解説
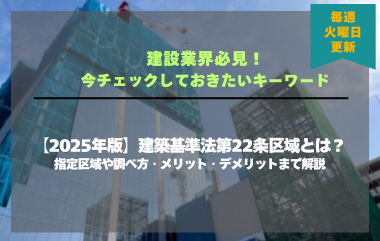
建築物を建てる際、火災に対して制限が設けられる防火地域・準防火地域以外にも「火災対策上の制限」がかかる場所があることをご存じでしょうか。それが「建築基準法第22条区域(法22条区域)」です。
この区域は、屋根の不燃化を義務づけることで火災の延焼を防ぎ、木造住宅地の延焼防止と安全確保を目的に設けられています。
そこでこの記事では、建築基準法第22条区域の意味や指定内容、調べ方、メリット・デメリットまで、現場で役立つ情報をわかりやすく解説します。
目次
建築基準法第22条区域とは?屋根の不燃化が義務づけられた地域
建築基準法第22条区域(以下「22条区域」)とは、防火地域・準防火地域以外の市街地で、屋根に不燃材を使用することを義務づけたエリアです。
(出典:e-Gov法令検索「建築基準法|第二十二条(屋根)」)
火の粉による延焼を防ぐために指定され、「屋根不燃化区域」とも呼ばれます。
またこの制度は、火災が起きた際に屋根材からの延焼を最小限に抑え、都市全体の防火性能を高めることが目的です。都市計画法上、防火地域→準防火地域→法22条区域という階層構造で定められており、木造住宅地や低層住宅地を中心に指定されるケースが多い傾向です。
また、建築基準法自体の概要を知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください▼
建築基準法第22条区域の指定内容と制限【屋根と外壁に関する制限】
建築基準法第22条区域は、屋根に関する構造制限が設けられています。
なお法22条区域は「屋根の不燃化」を基本としますが、場合によっては外壁にも制限が及ぶことがあります。特に「延焼のおそれのある部分」では法23条区域との関係性を理解することが重要です。
ここでは、屋根と外壁それぞれに関する構造基準をわかりやすく解説します。
屋根の制限(不燃材の使用が義務)
法22条区域にある建物は、屋根のすべてに不燃材料を使用することが義務付けられています。以下に不燃材の例をまとめました。
| 材料種別 | 例 | 特徴 |
| コンクリート系 | スレート瓦・コンクリート瓦 | 耐火・耐久性に優れる |
| 金属系 | ガルバリウム鋼板・銅板 | 軽量で加工しやすい |
| 瓦系 | 陶器瓦 | 伝統的だが高い耐火性能 |
たとえば、法22条区域に指定された地域は、建物が密集しているケースが多いため、火災時に屋根が燃えると火の粉が飛散し、隣家への延焼を招くおそれがあります。
そのため建築基準法第22条では「屋根は不燃材料で葺き、国土交通大臣が定める技術基準に適合する構造」とするよう定められているのです。なお、次のような小規模建築物の場合には、条例により例外的に不燃材を使用しなくても問題ありません。
- 延床面積10㎡以下の物置・あずまや・車庫
- 仮設的なプレハブ建築物
なお、後にリフォーム・増築して10㎡を超えた場合は、再度申請が必要になる点にご注意ください。
外壁の制限(法23条区域との関係)
法22条区域の建物でも、「隣地や道路に面して延焼のおそれのある部分(以下参照)」は、屋根だけでなく外壁に準防火性能が求められることがあります。
- 隣地境界線から3m以内の外壁部分
- 道路中心線から5m以内の部分
- 隣家との距離が極めて近い住宅密集地
参考として、建築基準法第23条は、「法22条区域のうち特に延焼リスクが高い場所」に外壁や軒裏の防火性能を義務づけています。つまり、法22条区域と法23条区域は重なり合う場合があり、屋根+外壁の両方に制限がかかるケースも存在します。
(出典:e-Gov法令検索「建築基準法|第二十三条(外壁)」)
なお、延焼のおそれのある部分に設けられる準防火構造は、20分間の火熱を遮り、延焼を防ぐ性能(いわゆる、20分遮熱)をもつ以下の構造が求められます。
| 構造種別 | 材料例 | 防火性能 |
| モルタル下地サイディング | ラスモル+防火ボード | 準防火構造 |
| 土塗壁 | 土+竹小舞+漆喰仕上げ | 延焼防止性能あり |
| ALC(軽量気泡コンクリート) | パワーボード等 | 高遮熱性・耐久性 |
| 金属サイディング+ロックウール | 軽量・断熱性良好 | 準防火対応多数 |
以上より、法22条区域は「屋根の不燃化」が中心ですが、外壁も条件によっては制限を受けるため、建築確認申請の際には必ず区域図と建築士の確認をセットで行うことが重要です。
法第22・23条区域に該当する場合は第24条~第27条もチェック
もし法22条区域・第23条区域に該当する場合は、以下の条項にも目を向けることが大切です。
| 条文 | 主な内容 | 適用対象 | 主な制限・義務 |
| 第24条 | 区域をまたぐ建築物の扱い | 建築物が22条区域内外にまたがる場合 | 敷地全体に22条の制限を適用 |
| 第25条 | 大規模木造建築物の外壁・屋根 | 延床1,000㎡超の木造建築 | 外壁を防火構造、屋根を不燃構造 |
| 第26条 | 防火壁・防火床の設置 | 延床1,000㎡超の建築物 | 区画ごとに防火壁・防火床で区切る |
| 第27条 | 特殊建築物の耐火義務 | 劇場・病院・学校・倉庫など | 特定構造部を耐火または準耐火に |
同一敷地で区域をまたぐ場合(第24条)や、大規模・特殊用途(第25〜27条)の建物は、さらに厳しい防火基準が適用されます。建物の位置や条件によって、対策内容や求められる性能が変化するため、見逃しがないように気を付けてください。
法22条区域・法23条区域・準防火地域の違い早見表
建築基準法では、防火規制を「防火地域」「準防火地域」「第22条区域」「第23条区域」のように段階的に分けています。
| 区域名 | 主な制限内容 | 指定目的 | 建築コスト | 調査手段・確認先 |
| 防火地域 | 壁・柱・屋根すべてを耐火構造に | 中心市街地の延焼防止 | 高 | 都市計画図/建築指導課 |
| 準防火地域 | 屋根・外壁とも準耐火構造に | 周辺住宅地の延焼拡大防止 | 中 | 都市計画図/建築指導課 |
| 法22条区域 | 屋根の不燃化義務 | 木造住宅地の屋根火災対策 | 低 | 自治体HP/都市計画課 |
| 法23条区域 | 外壁・軒裏の準防火構造 | 延焼リスクが高い部分への対策 | 中 | 都市計画課/条例資料 |
たとえば、法22条区域・法23条区域・準防火地域は、「火災リスクの段階に応じて建築構造を分ける」という思想のもとで設定されています。
あくまで目安ですが、設定されている区域によって、次のように建築コストや火災保険料の傾向が変化しやすい点にご注意ください。
| 区域 | 構造義務 | 建築コスト(目安) | 火災保険料の傾向 |
| 防火地域 | 耐火構造必須 | 通常の1.3〜1.5倍 | 割引率大(耐火建物) |
| 準防火地域 | 準耐火構造 | 通常の1.15〜1.25倍 | やや割引あり |
| 法22条区域 | 不燃屋根のみ | 通常の1.05倍程度 | 割引は小 |
| 法23条区域 | 外壁準防火構造 | 通常の1.1倍程度 | 割引中程度 |
また、あくまで傾向ですが、各区域・地域は次のように選ばれる場合があります。
- 住宅地の屋根制限 → 第22条区域
- 幹線道路沿いの商業地 → 第23条区域
- 駅前や繁華街 → 準防火地域
- 中心市街地・ターミナル周辺 → 防火地域
また、準防火地域に関する基礎知識や条文の内容、制限を知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建築基準法第22条区域のメリット・デメリット(建築費・デザイン・防火性)
建築基準法第22条区域(以下、法22条区域)は、「屋根の不燃化」を条件とする緩やかな防火規制地域です。
準防火地域よりも制限が軽く、木造住宅の自由度を確保しながらも一定の防火性能を持たせることができます。ただし、建築費やデザイン、素材選びには注意点もあります。
| 観点 | メリット | デメリット |
| 建築コスト | 安価(準防火地域より低コスト) | 不燃屋根材分の初期費増 |
| デザイン自由度 | 木造・自由設計が可能 | 屋根材の色・形に制限あり |
| 防火性能 | 火の粉による延焼を防ぐ | 外壁火災には影響なし |
| 申請手続き | 比較的簡易 | 不燃材証明が必要 |
| 保険・維持費 | 火災保険料が下がる傾向 | メンテナンスコストが発生 |
ここでは、法22条区域に建てる際の主なメリットとデメリットを比較しながら詳しく見ていきましょう。
メリット(コスト・設計自由度・保険面)
法22条区域の最大のメリットは、「防火性能を確保しつつ、建築コストを抑えられる」点にあります。
| 主なメリット | 内容 |
| 建築費が抑えられる | 防火地域のような耐火構造不要 |
| 木造住宅の自由度が高い | 屋根以外は自由設計が可能 |
| 火災保険料が下がる | 不燃屋根が評価対象 |
| 建築確認が比較的スムーズ | 準防火地域より申請項目が少ない |
| 外観デザインの選択幅が広い | 不燃瓦・金属屋根など素材多様 |
屋根のみ不燃化すれば良いため、防火地域・準防火地域のように外壁や開口部まで厳しい制限を受けません。そのため、木造建築の設計自由度を維持しながらも、一定の安全性を確保できます。
デメリット(素材コスト・デザイン制約・申請面)
一方で、法22条区域には「不燃材コストやデザイン制約」といったデメリットも存在します。
| デメリット | 内容 |
| 屋根材のコスト増 | 不燃材(瓦・金属)に限定 |
| デザイン制約 | 木製屋根や茅葺風は不可 |
| 熱伝導の影響 | 金属屋根は夏季の温度上昇が大きい |
| 建築確認項目が増える | 使用材料・性能証明が必要 |
| メンテナンス費が変動 | 塗装・防錆対応が必要な素材も |
たとえば、屋根に不燃材料を使用する必要があるため、第22条区域外の建物よりも素材費や施工費が通常よりも高くなる傾向があります。また、外観の自由度が完全ではなく、木質屋根や自然素材を多用したデザインが制限されるケースもあります。
建築基準法第22条区域の調べ方【自治体サイト・都市計画図・Google検索で確認】
建築基準法第22条区域は、各自治体(市区町村)によって指定されている区域です。
ここでは、最も確実で簡単な3つの確認方法を紹介します。
| 方法 | 信頼性 | 難易度 | スマホ対応 | コメント |
| 自治体都市計画図 | ★★★★★ | 中 | ◯ | 公式資料であるため最も正確 |
| 重説・契約書 | ★★★★☆ | 低 | ◯ | 既存物件向けであり契約時に確認可能 |
| Google検索 | ★★★☆☆ | 低 | ◎ | 目安レベル。自治体で要確認 |
【調べ方1】自治体ホームページから都市計画図を見る
最も確実な方法は、対象の自治体が公開している「都市計画図」や「建築基準法による制限図」を確認することです。以下に調べ方の手順をまとめました。
- Googleで「〇〇市 都市計画図」と検索
- 「建築基準法による制限」や「防火地域・準防火地域・法22条区域」を選択
- 住所または地番を検索して該当エリアをクリック
- 画面上に「法第22条区域」などの文字が表示されれば該当
ほとんどの自治体では、次のようなページから無料で確認できます。なかにはスマホで確認できる自治体ホームページもあります。
【調べ方2】重説・不動産契約書で確認する
建物や土地を購入済みの方は、不動産の重要事項説明書や売買契約書にも記載があります。
宅地建物取引士が交付する書類には、次のような項目が含まれていることが一般的です。
| 書類名 | 記載箇所 | 確認できる内容 |
| 重要事項説明書 | 「法令上の制限」欄 | 法22条区域・準防火地域などの指定有無 |
| 売買契約書 | 「土地の権利・用途地域」欄 | 建ぺい率・容積率・防火地域など |
| 公図・登記簿謄本 | 「地番」「地目」欄 | 住所一致を確認して法区域を特定 |
【調べ方3】Google検索+地図ツールを活用(簡易確認)
自治体サイトが見づらい場合、Google検索+地図情報の併用も便利です。
たとえば、以下のようなキーワードでWeb検索をすれば概略での確認が可能です。
- 「〇〇市 法22条区域 map」
- 「〇〇市 防火地域 準防火地域 図」
- 「〇〇市 建築基準法22条」
ただし、正式な建築確認には自治体発行の地図が必要なので、あくまで目安と考えましょう。
建ぺい率・増築・カーポートなど建築時の注意点
建築基準法第22条区域に指定されている土地では、屋根などの防火制限に加えて、建ぺい率・増築・外構(カーポート・物置など)の取り扱いにも注意が必要です。
ここでは、実務上トラブルが起きやすい「建ぺい率・容積率」「増築」「カーポート設置」の3つの注意点を解説します。
建ぺい率・容積率への影響
法22条区域の指定そのものは建ぺい率や容積率には直接影響しません。ただし、防火地域・準防火地域と重なる場合には上位制限が優先される点に注意が必要です。
まずは、対象の建物が防火地域や準防火地域に含まれるのかをチェックしましょう。
カーポート・サンルーム・物置を設置する場合
法22条区域では、屋根に不燃材を使用することが原則です。
そのため、カーポート・サンルーム・物置などの設置時には、アルミやポリカーボネート製屋根が防火構造として認められるかを確認する必要があります。カーポートやサンルームも「屋根付きの工作物」とみなされるため、建築物扱いとなるケースが多い点に注意してください。
あわせて、カーポート建築に関する基礎知識や建ぺい率のルールを知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建築基準法第22条区域についてよくある質問【FAQ】
建築基準法第22条区域とは何ですか?
建築基準法第22条区域とは、火災の延焼を防ぐために屋根を不燃材または準不燃材で施工することを義務付けた地域です。主に市街地や住宅密集地で指定され、建物の屋根材や構造に一定の防火性能が求められます。
建築基準法22条区域と23条区域の違いは何ですか?
23条区域は22条区域よりも防火性能が高い地域です。22条区域は屋根の防火性能を求める区域で、主に屋根材が対象です。一方23条区域はさらに厳しく、屋根だけでなく外壁や軒裏も準防火構造が必要になります。
カーポートは建築基準法22条区域に設置できますか?
可能です。ただし屋根材は不燃または準不燃材(アルミ・ポリカーボネート厚板など)を使用する必要が出てくるかもしれません。また、延焼防止のため母屋から1m以上離すなど、防火性能や設置位置の基準を守ることが重要です。
建築基準法22条区域の調べ方は?
確実なのは、各自治体の「都市計画情報提供サービス」で地図を確認する方法です。「〇〇市 都市計画図 法22条区域」で検索すれば、自治体の公式サイトが表示されるため、該当エリアを地図上で確認可能です。なお、重説(重要事項説明書)や不動産契約書にも記載がある場合があります。
まとめ
建築基準法22条区域は、火災の延焼を防ぐために屋根の不燃化を義務づける地域指定です。
一見すると単純な制限に見えますが、実際には防火地域や準防火地域との重なり・屋根材の選定・増築やカーポート設置時の防火性能確認など、実務面で注意すべきポイントが多く存在します。
今後、法22条区域を調べる必要がある際には、ぜひ上記の情報を参考にしてみてください。


