【2025年版】建築学部とは?何を学ぶ?理系・文系の違い・偏差値・大学ランキングまで徹底解説
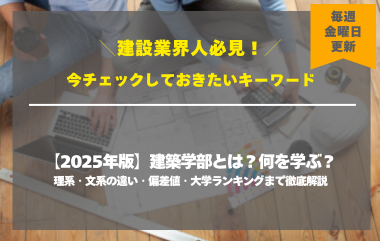
建築学部は「デザイン」「工学」「まちづくり」を総合的に学べる、理系と文系の要素を兼ね備えた学問です。しかし「建築学部では何を学ぶの?」「理系でないと難しい?」といった疑問をもつ方も多いでしょう。
そこでこの記事では、建築学部で学べることや、2025年最新版の大学ランキング・偏差値・カリキュラム内容・資格・就職先までをわかりやすく解説します。
目次
建築学部とは?学べる内容をわかりやすく解説
建築学部とは、建物を「デザイン・構造・環境・社会」の観点から総合的に学ぶ学部です。
単に建物を「設計する」だけでなく、人が快適に暮らすための空間づくり、街並み・景観・環境との調和、耐震性・省エネ性などを含めた総合的な建築教育を行います。
また、文部科学省は建築学部を工学分野に分類しているのが特徴です。
大学によっては「工学部建築学科」「建築デザイン学部」「環境建築学部」など名称が異なりますが、学ぶ内容の根幹は共通しています。
(出典:文部科学省「学科系統分類表 1 大学(学部) 工学」)
建築学科と建築学部の違い
建築学科と建築学部は一見似ているものの、「学部」と「学科」には次のような明確な違いがあります。
| 項目 | 学部 | 学科 |
| 役割 | 大学における教育・研究の基本的な組織単位 | 学部の中で特定の専門分野をより深く学ぶ組織 |
| 規模 | より大きく包括的な単位 | 学部よりも細かく限定的な単位 |
| 例 | 建築学部・工学部・理学部・芸術学部 | 建築学科・建築デザイン学科・環境建築学科 |
| 教育内容 | 学問分野全体を幅広く学ぶ | 特定の専門領域(構造・意匠・環境など)を深める |
| 将来の進路 | 総合的に建築分野へ | 分野ごとに建築士・設備士・都市計画などへ特化 |
つまり、学部=広く建築の全体像を学ぶ場、学科=特定の専門分野を深掘りする場という違いがあります。
建築学部で何を学ぶ?カリキュラムと身につくスキル
建築学部では、建築物の企画・設計・施工・管理・維持までを総合的に学ぶカリキュラムが組まれています。
大学によって名称や比重は異なりますが、基本的には以下の3分野が中心です。
- 構造・材料分野:建物の強さや安全性を科学的に学ぶ
- 計画・意匠分野:デザインや街づくりなど人間中心の建築を学ぶ
- 環境・設備分野:快適で持続可能な空間をつくる技術を学ぶ
さらに、これらの知識を統合して実際に設計・模型製作を行う実習授業も特徴です。以下より、何を学ぶのか気になっている人向けに、4年間を通じて提供されるカリキュラムや身につくスキルをまとめました。
構造・材料分野|建物を支える力学と工学
構造・材料分野では「建物の安全と強度を科学的に理解し、形にする力」を学びます。
建物は見た目のデザインだけでなく、耐震性・耐風性・荷重バランスなど、構造的な安全性が重要であるため、次の科目をもとに安全な建物のつくり方を学んでいきます。
- 構造力学
- 鉄筋コンクリート構造
- 木構造・鉄骨構造
- 建築材料学
- 構造解析(応力・変形・振動)
なお、これらの科目は、力がどのように建物に伝わるのか(力学)を理解するのが主な目的です。実際に模型実験やコンピュータシミュレーション(BIM・構造解析ソフトなど)で検証します。
計画・意匠分野|デザイン・まちづくり・歴史を学ぶ
計画・意匠(いしょう)分野では「人と空間」「地域と建築」の関係をデザインで解決する力を学びます。
単に美しい建物をつくるだけでなく、次のような科目を学ぶことにより「人がどう感じ、どう動くか」を考え、社会や環境と調和した建築を提案するのが目的です。
- 建築計画
- 建築意匠設計
- 都市計画・地域計画
- 建築史・都市史
- 建築デザイン演習
スケッチ・模型制作・CAD・BIM・プレゼンボード作成などを通じて、「建築を表現する力」を身につけていくのが一般的です。論理的なデザインスキルはもちろん、「人の心を動かす空間づくり」としての、芸術的センスも求められます。
環境・設備分野|快適な空間を支える技術
環境・設備分野では「人が快適に過ごせる空間を、地球にも優しい方法で実現する」ことを学びます。
この分野は、建築の「見えない部分」を扱う学問であり、次のようなカリキュラムを通じて空調・照明・給排水・断熱・省エネなど、建物の内部環境を科学的にデザインするのが特徴です。
- 建築環境工学
- 建築設備計画
- 熱・光・音環境の制御
- 環境心理学
- ZEH・省エネ設計・再生可能エネルギー活用
建築に関わるのなら、頑丈な建物をつくることはもちろん、人が使いやすい・住みやすい快適な場所にすることが欠かせません。特に近年では、CO₂削減やカーボンニュートラルの流れを受け、環境配慮型の建築設計が重視されています。
実習・設計課題・模型制作の流れ
建築学部では実習や設計課題を行うケースが多く、理論を現実のかたちに変える力を養うことに力を入れています。参考として以下に、実習や課題の流れを学年ごとに整理しました。
| 学年 | 主な実習・課題内容(目安) | 目的 |
| 1年 | 製図・模型制作の基礎、デザイン演習 | 建築表現の基本を身につける |
| 2年 | 住宅設計・構造演習・CAD実習 | 構造・空間の関係を理解する |
| 3年 | 公共施設・都市計画課題・グループ設計 | 社会的課題を建築で解決する力を養う |
| 4年 | 卒業設計・研究発表 | 自分の建築観を総合的に表現する |
また、上記の実習や課題をこなすことで、次のようなスキルが身についていきます。
- 空間を構想し、図面や模型で表現する建築的思考力
- 施工性や構造を踏まえた現実的な設計力
- 他者と協働して課題に取り組むチームワーク力・発表力
これらを経験しておくことにより、建築士試験の設計製図はもちろん、就職後の設計プレゼンテーション・コンペ応募などに対応できます。
卒業設計とは?4年間の集大成
卒業設計は、建築学部の4年間で学んだ知識と技術をすべて統合し、自分の建築観を形として表現する最終プロジェクトです。
いわば、学生にとっての「卒論+実践」のような存在であり、設計・構造・環境・プレゼン力の総合力が問われます。以下に出されやすいテーマをまとめました。
- 地方再生に貢献する「地域拠点の建築」
- 子どもや高齢者の居場所づくりをテーマにした「共生型住宅」
- 災害に強い「復興コミュニティ施設」
また、卒業設計は3年生の後期からスタートすることが多いです。以下の流れで計画的に準備を進めていきましょう。
| 時期 | 内容 | 目的 |
| 3年後期〜4年前期 | テーマ設定・リサーチ・敷地選定 | 社会課題や対象地域を分析する |
| 4年前期〜中盤 | 設計コンセプト・模型制作 | 具体的な形を構想・検証する |
| 4年後期 | 図面・パース・構造・環境計画の統合 | 各分野を総合的にまとめる |
| 4年末 | 公開プレゼン・審査会・展示 | 最終発表・講評を通じて発信する |
また建築学部の学生によっては、建築新人戦というコンペに参加するケースもあります。詳しくは以下の記事をチェックしてみてください▼
建築学部は理系?文系?どっちの人に向いている?
建築学部は「理系と文系の両方をあわせもつ学問分野」です。
そのため、建物を安全に建てる構造力学や材料学などは理系的な知識が必要である一方、人の暮らし・文化・デザインを考える部分は文系的な発想が欠かせません。
つまり、建築学部は理系でも文系でもチャレンジしやすい学部だと言えます。
数学や物理が苦手でも、設計・表現・まちづくりに興味がある人なら十分に活躍できます。
建築学部に向いている人の特徴
結論から言うと、建築学部に向いているのは「論理的に考えつつ、創造的に表現することが好きな人」です。以下に、理系・文系どちらの傾向にも共通するポイントを挙げます。
| タイプ | 向いている理由 |
| 論理的思考が得意 | 構造計算・施工計画などに強い |
| デザインや表現が好き | 意匠設計・都市計画に適性がある |
| コミュニケーションが得意 | チーム設計・まちづくりに必要な能力 |
| 社会問題に関心がある | 地域課題や環境設計に貢献できる |
| ものづくりが好き | 模型制作・設計製図に没頭できる |
ベースとして学ぶことは数学や物理に関係する内容ですが、大学の授業でも基礎的な部分から学習をスタートできます。上記の項目にひとつでもあてはまる方がいるのなら、ぜひ建築学部を目指してみてください。
建築学部に強い大学ランキング【国公立・私立・地方別】
建築学部と一口にいっても、大学によって学べる内容・教育方針・就職実績には大きな違いがあります。ここでは、最新の2025年版データ(偏差値・教育内容・卒業後進路)をもとに、建築学部に強い大学をランキング形式で紹介します。
国公立大学ランキング(偏差値・特徴・代表大学)
国公立大学は、研究力と実践教育のバランスが高く、国家資格「一級建築士」受験資格を得やすいことが強みです。以下にランキングを整理しました。
| 順位 | 大学名 | 偏差値目安※ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 工学部 建築学科 | 67〜72 | 理論・設計・都市・環境を総合的に学べる日本最高峰 |
| 2位 | 京都大学 工学部 建築学科 | 65〜70 | 自由度の高い研究教育と意匠・構造両面に強み |
| 3位 | 東京工業大学 環境・社会理工学院 | 65〜70 | BIM・環境・構造の先端研究に定評あり |
| 4位 | 東北大学 工学部 建築・社会環境工学科 | 60〜67 | 構造・耐震・防災分野の研究で高評価 |
| 5位 | 名古屋大学 工学部 環境土木・建築学科 | 約67 | 学際的なカリキュラムと環境建築教育に強み |
※複数の偏差値情報サイトからのおおよその平均値
国立大学の場合、研究主導型の教育(教授との共同研究や卒研テーマの自由度が高い)に強く、学費が安いためコスパに優れる点が魅力です。(年間約53万円前後)
また専門性の高い知識を学べるため、一級建築士・修士課程進学率が高いという点にも優れています。
私立大学ランキング(就職・教育内容・特色)
私立大学は、デザイン教育・表現力・就職支援に強みがあります。特に意匠系や都市デザイン系の教育は、私立大学の多様性が際立っています。
| 順位 | 大学名 | 偏差値目安※ | 特徴 |
| 1位 | 早稲田大学 創造理工学部 建築学科 | 65〜68 | デザイン×テクノロジー教育で業界評価が高い |
| 2位 | 芝浦工業大学 建築学部 | 60〜63 | 実践型BIM教育・留学制度・建築士合格率が高い |
| 3位 | 東京理科大学 創域理工学部 建築学科 | 59〜62 | 構造・環境の理系教育に特化、研究進学率も高い |
| 4位 | 日本大学 理工学部 建築学科 | 57〜60 | 卒業生ネットワークが広く、ゼネコン・設計事務所就職に強い |
| 5位 | 武蔵野美術大学 建築学科 | 55〜58 | 建築とアートの融合教育でデザイン志向者に人気 |
※複数の偏差値情報サイトからのおおよその平均値
たとえば、意匠・デザイン教育が充実(模型・CG・パース表現に強い)しているほか、就職サポートが手厚い(設計事務所・デベロッパー・ゼネコンなど)のが強みです。
また、留学・国際建築教育も盛んに行われており、海外建築を学ぶ機会も数多くあります。
あわせて大学教授のインタビューをチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建築学部全体における難易度まとめ
建築学部の難易度は「理系型」「デザイン型」「融合型」で大きく異なります。
たとえば、理系寄りの大学では数学・物理などの基礎学力が求められ、デザインや意匠系の大学では表現力・発想力・デッサン力が評価されます。
そのため「自分がどんな建築を学びたいか」で難易度の感じ方が変わる点に注意してください。
難易度順で並べるなら「デザイン型<融合型<理系型」で難しくなるイメージです。
入試で重視されるポイント(空間把握力・論理力など)
建築学部の入試では、知識だけでなく空間を理解し、理論的に考える力が問われます。
これは、将来の建築設計・構造解析・環境設計などの基礎になるため、「計算力」+「想像力」のバランスを取れる人が高評価を得やすい傾向です。参考として以下に、入試で重視されやすい能力を整理しました。
| 能力 | 概要 | 具体的な対策例 |
| 空間把握力 | 立体構造をイメージする力 | CAD・図面練習・模型制作 |
| 論理的思考力 | 条件整理→結論導出の力 | 数学・物理の構造問題演習 |
| 表現力 | デザインを形にする力 | デッサン・パーストレーニング |
| コミュニケーション力 | 設計意図を伝える力 | 面接・グループワーク練習 |
入学後に能力を学べばよいというスタンスの大学も多いため、未経験からでもチャレンジは可能です。
建築学部で取得できる資格一覧
結論から言うと、「建築士(1級・2級・木造)」を中心に、設計・施工・環境・不動産など幅広い資格取得を目指せます。
| 資格名 | 資格区分 | 概要・特徴 |
| 2級建築士 | 国家資格 | 建築物の設計・監理業務を行える資格。多くの大学で卒業時に受験資格を取得可能。 |
| 木造建築士 | 国家資格 | 木造住宅や小規模建築物の専門家。木造住宅メーカーや工務店で重宝される。 |
| インテリアコーディネーター | 民間資格 | 建築空間の内装デザイン・照明・家具提案を行う専門資格。 |
| 建築CAD検定試験 | 民間資格 | 図面作成スキルを証明できる資格。設計職・施工管理職の基礎評価に有利。 |
| 福祉住環境コーディネーター | 公的資格 | バリアフリーや高齢者住宅の知識を持つ専門職として評価。 |
| 宅地建物取引士(宅建士) | 国家資格 | 不動産業界・建設営業職でのキャリア展開に有効。 |
建築学部で目指せる就職先一覧
建築学部の就職先は「設計・施工・不動産・公務員・メーカー」など幅広く、理系学部のなかでもキャリアの選択肢が多い分野です。
| 分野 | 主な仕事内容 | 代表的な就職先 |
| 設計・デザイン系 | 建築意匠・構造・環境設計、都市デザインなど | 日建設計、三菱地所設計、竹中工務店、久米設計、隈研吾建築都市設計事務所 |
| 施工・ゼネコン系 | 建築現場の管理・安全・工程・品質管理 | 清水建設、大成建設、鹿島建設、大林組、前田建設工業 |
| 構造・設備系 | 構造計算、空調・電気・給排水設計など | 三機工業、新菱冷熱工業、日比谷総合設備、日本設計 |
| 不動産・デベロッパー系 | 企画・用地開発・再開発・営業 | 三井不動産、住友不動産、東急不動産、野村不動産 |
| 公務員・自治体系 | 建築行政、都市計画、耐震・営繕業務 | 国土交通省、都道府県庁、市町村役場、都市整備公団 |
| メーカー・建材・住宅系 | 建材開発、住宅設計、商品開発、施工支援 | LIXIL、TOTO、YKK AP、積水ハウス、大和ハウス工業 |
| コンサル・研究職系 | 環境設計・構造解析・まちづくり研究 | 建設技術研究所、オリエンタルコンサルタンツ、大学研究室 |
上記はあくまで目安ですが、専門性が高く高収入を目指せる就職先も見つかります。建築系の業種は将来的にもなくならない分野であるため、安定性を期待できるのが魅力です。
建築学部で学べることについてよくある質問【FAQ】
建築学部で何を学ぶの?
建築学部では、建物の設計・構造・材料・環境・都市計画などを総合的に学びます。デザインだけでなく、耐震性や省エネ、法規や施工まで幅広い知識を身につけることで、建築士や技術者として社会で活躍できる力を養います。
建築は文系ですか?理系ですか?
基本的には理系分野ですが、デザインや社会計画など文系要素も含まれます。数学・物理の基礎力と同時に、芸術的発想力・論理的思考・プレゼン力なども重視されるため、理系と文系の融合型学問だと言えます。
建築学部に強い大学はどこ?
2025年時点で建築分野に強い大学は、東京大学・京都大学・東京工業大学・早稲田大学・芝浦工業大学などです。これらの大学は研究設備や著名建築家の指導環境が充実しており、建築士合格率や企業評価も高い傾向があります。
建築学部から建築士になれるの?
建築学部を卒業すれば2級建築士や木造建築士の受験資格が得られます。さらに実務経験を積むことで一級建築士を目指すことも可能です。大学によっては、建築士指定課程を修了すれば卒業と同時に受験資格を自動取得できます。
まとめ
建築学部は、建物や都市を通じて人の暮らしを豊かにする力を学べるため、創造力・論理力・問題解決力を兼ね備えた人材を目指す方に最適な進路です。
建築士・都市計画・デベロッパー・行政など多彩なキャリアの基盤となるため、「形に残る仕事をしたい」「社会を動かす仕事をしたい」人におすすめの場所だと言えます。


