【2025年版】建築計画概要書とは?検証済証・閲覧・写し交付まで徹底解説|誰でも見られる?取得の流れと注意点
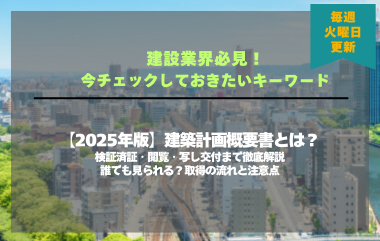
建築概要書は、その建物がどんな構造・面積・用途で建てられているかを記載した公的な資料です。不動産取引や耐震調査、違法建築チェックなど、建物の安全性や法的適合を確認するうえで欠かせない情報源となります。
しかし、どのように閲覧できるのかわからない、検証済証との違いは?写しの交付はどこで?など、取得や閲覧に関して不明点も多いのが実情です。
そこでこの記事では、2025年最新の制度・自治体運用をもとに、建築計画概要書の基本から閲覧方法・注意点までわかりやすく解説します。
目次
建築計画概要書とは?
建築計画概要書(建築概要書)は、建築基準法にもとづき建築確認申請を受けた建物の内容をまとめた公的な書類です。
(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」)
自治体の建築指導課などが管理しており、誰でも閲覧申請を行うことができ、主に次の情報がまとまっています。
- 建物の構造
- 階数
- 面積
- 用途
- 建築主
- 設計者 など
建築確認済証にもとづく主要項目が一覧で確認できるため、不動産調査や建築トラブルの解決にも役立ちます。
建築概要書と検証済証・台帳記載事項証明書の違い
建築概要書とよく間違えられやすいのが「検証済証」「台帳記載事項証明書」の2つです。以下にそれぞれの違いを整理しました。
| 書類名 | 内容 | 発行元 | 閲覧可否 | 主な用途 |
| 建築計画概要書 | 建物の構造・用途・面積などの概要情報 | 自治体 | ○(誰でも閲覧可) | 建物情報の確認 |
| 検証済証 | 建築確認が完了した証明書(確認済) | 自治体または民間検査機関 | ×(関係者のみ) | 行政審査証明 |
| 台帳記載事項証明書 | 確認済証台帳の内容を抜粋した証明 | 自治体 | ○(一部制限) | 登記・行政証明用 |
検証済証は「確認済」であることを示す証書で、閲覧は不可です。一方、建築概要書は誰でも閲覧可能な公的資料として整備されています。
なお、古い建物や民間検査機関による確認では、概要書が存在しない場合もあります。
閲覧と写し交付の違い
建築概要書は、原則として「閲覧」と「写し交付(コピー)」の2種類の方法で入手できます。
| 方法 | 内容 | 手数料の目安 | 所要時間 | 注意点 |
| 閲覧 | 役所窓口で現物を閲覧 | 200~300円程度 | 即日 | 写真撮影不可の場合あり |
| 写し交付 | コピーを受け取る | 300~500円程度 | 数日~1週間 | 本人確認が必要な自治体あり |
※手数料は自治体ごとに変動します
多くの自治体では、誰でも閲覧可能ですが、写しの交付には制限が設けられています。特にプライバシー保護の観点から、建築主情報など一部は黒塗り処理されるケースもあります。
建築計画概要書は誰でも閲覧できる?
建築概要書は、原則として誰でも閲覧できます。「建築基準法施行規則 第13条」にもとづく公開制度によって定められており、申請さえすれば手軽に情報を入手できます。
ただし、自治体によって運用が異なるため、閲覧可能な範囲や手続きが異なる点に注意が必要です。
閲覧できる人の範囲
原則、以下のような立場の人は自由に閲覧可能です。
- 一般市民(誰でも)
- 不動産業者・設計事務所
- 弁護士・行政書士などの代理人
- 研究・報道目的の関係者
なお、種類によっては例外的に、個人情報保護の観点から制限が設けられる場合もあります。事前に確認しておくことをおすすめします。
閲覧に行く前に準備しておく情報
スムーズに建築概要書を閲覧したいなら、以下の情報を事前に調べておきましょう。
- 建築物の所在地(住所・地番)
- 建築確認番号(プレートや登記で確認)
- 建築主の氏名(古い物件の場合)
申請時に迷ってしまうケースも多いため、場所などの情報はGoogleマップなどからメモしておくと安心です。
建築概要書の取得方法と「写し交付」の流れ
建築概要書の取得は、原則として自治体の建築指導課で申請します。
以下より取得と写しを交付する流れを解説します。
取得の流れ(一般的な自治体)
建築概要書は、一般的に次の流れで取得します。
- 窓口で「建築計画概要書閲覧申請書」を提出
- 手数料を納付(200〜300円程度)
- 職員立ち会いのもと閲覧
- 写し交付が可能な場合は別途申請
写し交付の申請には、申請理由や本人確認が求められることがあります。免許証やマイナンバーカードを持参しておくと安心です。
オンライン閲覧・郵送請求の可否
一部の自治体(東京都・大阪府など)では、オンライン閲覧システムや郵送請求が利用できます。ただし、全国的にはまだ普及していません。
検証済証はなぜ閲覧できない?
建築確認が完了した証明書である「検証済証(建築確認済証)」は、個人情報・設計情報を含むため、一般の閲覧対象外です。
特定の関係者(建築関係者など)以外は閲覧できない点に注意してください。
検証済証の代わりに確認できる情報
検証済証の内容は「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」で代替できます。
確認番号・構造・面積・用途など、主要な情報は概要書に反映されているため、建築に関する基本情報は建築計画概要書から取得するのがおすすめです。
建築概要書を見るときのチェックポイント
以下に建築概要書を見るときのチェックポイントをまとめました。
| チェック項目 | 確認内容 |
| 建ぺい率・容積率 | 法令範囲内かどうか |
| 用途地域 | 建築用途に合致しているか |
| 隣地境界 | セットバックの有無 |
| 階数・延床面積 | 現況と一致しているか |
たとえば、建築基準法施行令の情報と照らし合わせて問題がないかチェックするほか、現地状況と概要書に違いがないのかを判断していくイメージです。
チェック項目の数値が変わっている場合には、関係者間での調整協議などが必要になる場合もあります。
建築概要書が存在しない(ない)場合の対応
1980年以前の古い建物などは、建築概要書が未保存のケースも多くあります。特に自治体未保管の場合もあるため、次の代替方法で類似の情報を見つけることが大切です。
- 台帳記載事項証明書
- 登記事項証明書
- 行政文書開示請求
建物の構造、階数、面積、用途といった基本情報は、さまざまな資料に掲載されています。まずは自治体で保管状況を確認したうえで、代替資料の申請を検討しましょう。
建築計画概要書・検証済証の閲覧でよくある質問【FAQ】
誰でも見られるの?
建築計画概要書は、建築基準法施行規則第13条にもとづき、原則として誰でも閲覧できます。所有者や関係者でなくても申請すれば閲覧可能で、不動産購入前の調査やリフォーム計画時にも役立ちます。ただし、写し交付(コピー)は自治体によって制限があり、申請理由や本人確認が必要な場合もあります。
オンラインで閲覧できる?
数が少ないものの自治体によっては、オンライン閲覧システムを導入している場合があります。たとえば東京都や大阪府などでは、インターネット上で建築計画概要書を確認でき、建築確認番号・所在地・用途などの検索が可能です。
古い建物で概要書がない場合は?
古い建物(昭和50年代以前)では、建築概要書が保管されていないケースがあります。この場合、代替手段として「台帳記載事項証明書」や「行政文書開示請求」を活用するとよいでしょう。また、民間検査機関による建築確認物件では、自治体に資料が残っていない場合もあります。
まとめ
建築計画概要書は、建物の構造・用途・面積・確認番号などを公的に確認できる重要な書類です。不動産購入やリフォーム前の調査、違法建築リスクの確認など、幅広い場面で役立ちます。
一方で、「誰でも閲覧できる」とはいえ、自治体によって写し交付の可否や手続き方法が異なるため、事前に確認することが大切です。また、古い建物では概要書が保管されていない場合もある点に注意してください。
もし見つからない場合は、台帳記載事項証明書や行政文書開示請求から建築情報を確認するのがおすすめです。


