【いまさら聞けない】建設業労働災害防止協会とは?役割・支部活動・安全教育・最新事例まで徹底解説|2025年版
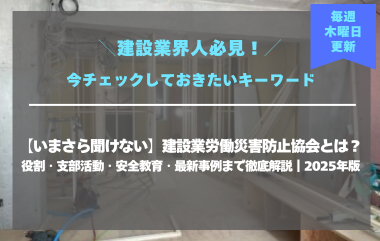
建設業界は、全業種のなかでも「労働災害の発生率」が高く、厚生労働省が発表した「労働災害発生状況(2023年|確定値最新)」によると、全産業の死傷災害のうち約3割(755名中223名)が建設業で発生しています。
(参考:厚生労働省「労働災害発生状況」)
こうした現状を踏まえ、現場の安全を守る中心的な役割を担っているのが 「建設業労働災害防止協会(建災防)」 です。
そこでこの記事では、建災防の役割や活動内容、東京支部や福岡分会など地域での取り組み、安全衛生教育・ポスター・熱中症対策といった具体的な活動事例をわかりやすく解説します。
目次
建設業労働災害防止協会とは?
建設業労働災害防止協会(通称:建災防)は、建設業に従事する労働者の安全と健康を守るために設立された公益法人です。
(出典:建設業労働災害防止協会公式サイト)
労働災害防止団体法に基づき設立された団体であり、全国に支部や分会をもち、労働災害の防止活動を推進しています。
特に墜落・転落事故や熱中症といった現場特有のリスクに対応する研修・キャンペーンを展開しており、行政や企業と連携して「労働災害ゼロ」を目指しています。
厚生労働省との関係・法的な位置づけ
建災防は、労働安全衛生法(第77条)に基づく「指定団体」 として厚生労働大臣の認可を受けて設立された法人です。
国が定める安全衛生に関する教育や普及活動を担う法的根拠が与えられており、建設業界の安全衛生活動をリードしています。
なお、厚労省は毎年「労働災害統計」を発表していますが、建災防はそのデータの重点課題を分析したのちに、次のような形で現場に落とし込んでいます。
- 安全衛生教育のカリキュラム化
- 啓発ポスターやマニュアルの発行
- 地域支部を通じた研修会の実施
単なる任意団体ではなく、行政と民間現場をつなぐ「安全衛生のハブ」 という位置づけにある団体だと言えます。
(参考:建設業労働災害防止協会「建災防の歩み」)
また、労働安全衛生法に関わる規則の一部が改正されています。興味がある方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
建設業労働災害防止協会に加入するメリット(会員制度)
建設業労働災害防止協会(建災防)には、法人や個人事業主が会員として加入する制度があります。以下に、加入するメリットを整理しました。
- 安全衛生教育を優先的に受講できる
職長教育や熱中症対策セミナーなどを会員価格で受講可能
- 最新の法改正情報やガイドラインを提供してもらえる
厚生労働省の通達や国交省のガイドラインを迅速に入手できる
- 会員名簿への掲載で信用力を高められる
建災防の公式会員名簿に掲載されることで、取引先や発注者への信頼性が高まる
- 啓発ツール・ポスターが配布される
現場で使えるポスターや資料を無償または会員価格で入手できる
- 地域支部での相談・サポートを受けられる
東京支部・福岡分会など地域単位での交流・支援を受けられる
労働災害防止に直結する情報提供・研修・相談サポートを受けられることが大きな魅力です。近年はインボイス制度や安全衛生法令改正など、建設業の経営に直結するテーマも扱っており、加入メリットが拡大しています。
建設業労働災害防止協会の主な活動内容
建設業労働災害防止協会(建災防)の役割は、現場で起きやすい労働災害を未然に防ぐための教育・啓発・支援活動 です。
ここでは、建設業労働災害防止協会の具体的な活動内容を3つ紹介します。
安全衛生教育と研修プログラム
建災防は、労働安全衛生法に基づく「特別教育」「職長教育」「新入社員研修」などを体系的に実施しています。法令上義務づけられている教育をカバーするだけでなく、現場特有の事故リスクに即した独自プログラムも含まれています。
【主な研修例】
- 職長・安全衛生責任者教育:リーダー層が現場安全を管理できる力を養成
- フルハーネス型安全帯使用作業特別教育:足場・高所作業に必須
- 新入社員研修:基礎的な安全意識の定着
教育を修了すると修了証が交付され、発注者や元請企業からの信頼にもつながります。
また、近年では安全対策として本足場の設置が義務化されています。最新の法改正情報を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
啓発ポスター・資料の配布
建災防は、現場の「目に見える安全対策」としてポスターやリーフレットを毎年発行しています。たとえば、「墜落・転落防止」と「熱中症予防」をテーマに全国キャンペーンを展開しました。
参考1:建設業労働災害防止協会「墜落・転落災害撲滅キャンペーン」
参考2:建設業労働災害防止協会「熱中症予防対策」
また、会員は公式サイトからPDF形式でポスターや資料を入手でき、必要に応じて自由に掲示できます。
地域支部・分会の取り組み
建設業労働災害防止協会(建災防)は、全国各地に支部や分会を設置し、地域ごとの課題に応じた安全対策を展開しています。
参考として、代表的な支部・分会の特徴や活動について整理しました。
建設業労働災害防止協会 東京支部
東京支部は、全国の中でも最大規模の会員数を誇り、大規模建設プロジェクトの安全対策 に注力しています。
特に、再開発地区や高層ビル建設では墜落・転落事故のリスクが高いため、以下のような活動を展開しているのが特徴です。
- 高所作業安全教育:最新の墜落制止用器具(フルハーネス型安全帯)の使用徹底
- 外国人労働者向け教育:多言語対応の安全マニュアル配布
- デジタルツール活用:VR安全体験研修による危険予知訓練(KYT)
最新の労災防止事例が共有され、企業間の安全文化の底上げに貢献しています。
建設業労働災害防止協会 福岡支部・福岡分会
福岡支部とその分会は、九州地方における建設業界の安全拠点として機能しています。福岡は夏季の高温多湿環境が厳しいため、次のように熱中症防止と重機災害防止 に特化した取り組みが特徴です。
- 熱中症対策セミナー:WBGT計を使った現場測定実習を実施
- 重機災害防止研修:バックホウやクレーン操作時の安全教育
- 地域密着型ポスターキャンペーン:「STOP!熱中症@福岡」運動
大手ゼネコンだけでなく、地場建設会社にとっても参加しやすいのが利点です。
協会利用に関する実務情報
建設業労働災害防止協会(建災防)は、安全教育や研修だけでなく、経営や実務面で役立つサービスも提供しています。
特に最近では、インボイス制度への対応や会員名簿の公開など、事務処理や対外的信用に関わる部分でのサポートが注目されています。
インボイス制度への対応
2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、建設業界でも大きな影響を及ぼしています。
建災防では、研修や講習の受講料を支払う際に、適格請求書発行事業者としてのインボイス対応を行っており、企業の経理処理に対応可能です。
(参考:建設業労働災害防止協会「インボイス対応について」)
会員サービスと名簿公開
建災防では、加入企業を対象に公式サイトや冊子で会員名簿を公開しています。
単なる会員一覧ではなく、「安全管理に積極的に取り組む企業」 であることを示す役割を果たしています。
(参考:建設業労働災害防止協会「情報公開」)
建設業労働災害防止協会の最新事例・ニュース
建設業労働災害防止協会(建災防)は、全国規模で安全衛生活動を展開しており、その取り組みは年々進化しています。
特に2024〜2025年には、デジタル技術や新しい労災防止手法を取り入れた事例が増えており、従来の講習やポスター配布にとどまらず次のような「次世代型の安全対策」が進んでいます。
| 事例 | 内容 | 特徴・取組み |
| VRを活用した危険体験型研修 | VRゴーグルを使った疑似体験教育を全国支部で導入 | ・高所作業や重機操作の危険を再現 ・現場労働者が直感的に危険性を理解 ・従来教育にデジタル技術を追加 |
| 熱中症対策キャンペーン ※厚労省と連携 | 「STOP!熱中症@建設現場」全国キャンペーンを展開 | ・WBGT値(暑さ指数)の掲示 ・1時間に1回の休憩ルール徹底 ・水分、塩分補給ポスター配布 |
| 全国安全衛生大会 | 全国各エリアで大会を開催 | ・最新の労災事例の分析を共有 ・AIによるリスクアセスメント紹介 ・ゼネコンの安全衛生活動報告 |
上記の熱中症対策キャンペーンに出てくるWBGT値(暑さ指数)については、以下の記事で詳しく解説しています▼
建設業労働災害防止協会についてよくある質問【FAQ】
建設業労働災害防止協会とは何ですか?
建設業労働災害防止協会(建災防)は、建設現場の労働災害防止を目的に設立された公益法人です。安全教育や研修、ポスター配布、熱中症対策など幅広い活動を行っています。
非会員でも研修を受講できますか?
一部の安全衛生教育や特別講習は非会員でも受講可能です。ただし、会員価格が適用されない点や資料提供の範囲が限られる場合があるため、継続受講なら会員登録がおすすめです。
インボイス制度に対応していますか?
協会は適格請求書発行事業者として登録済みで、研修受講料や教材費の領収書もインボイス対応です。電子領収書発行にも対応しており、会計処理の負担軽減が可能です。
まとめ
建設業労働災害防止協会(建災防)は、安全教育やICT活用、熱中症対策、復旧工事支援などを通じて「労働災害ゼロ」を目指す中心的な団体です。
会員制度や名簿公開は企業の信頼性向上に直結し、インボイス対応など実務面の利便性も高めています。協会の活動を活用することで、現場の安全文化を高め、持続的な建設経営に役立てられます。この機会に会員制度を利用してみるのはいかがでしょうか。


