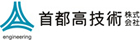「InfraDoctor®」や「トンネルやもりん®」で挑む|首都高グループが切り開くDXによるインフラメンテナンスのネクストステージ


多くの人は、高速道路の点検やメンテナンスというと、黄色いパトロールカーで道路を走りながら、人が目視で異常の有無を確認し、何かあれば人が高速道路に降り立ち、クルマに注意しながらも迅速かつ慎重に異常の排除に当たる、といった光景も思い浮かべるかもしれない。
実際、多くの高速道路ではそのような点検やメンテナンスが実行されている。しかし、首都高グループ会社である首都高技術株式会社と首都高デジタル&デザイン株式会社は、最新のデジタル技術を駆使し、インフラメンテナンスの常識を根本から変えようとしている。
その中心にあるのが、3次元点群データや画像、AIを活用した「InfraDoctor(インフラドクター)®」「InfraPatrol(インフラパトロール)®」といった技術だ。これらの技術は、単なる効率化にとどまらず、少子高齢化による労働力不足や老朽化するインフラの課題に立ち向かうための切り札、いわゆるDXの取り組みとして注目されている。本記事では、首都高グループ会社の担当者へのインタビューを通じて、都市高速DXの先駆けとも言える彼らの軌跡とネクストステージを照射する。
目次
インフラドクター MMS(モービルマッピングシステム)で首都高を健康診断する
首都高技術が開発したインフラドクターは、トンネルや橋梁などのインフラを3次元点群データや高精細な画像を使って、保守点検を効率化するシステムだ。首都高技術株式会社インフラデジタル部長の安中智氏はその成り立ちをこう振り返る。
「インフラドクターは、GIS(地理情報システム)をベースに、3次元点群データやメンテナンスの履歴を一元管理するプラットフォームとして始まりました。Googleストリートビューのように道路の映像を見られるだけでなく、構造物の3次元点群データを見ることができ、また、そのデータを引き出せる仕組みです。開発した2017年当時は、画期的なシステムとして注目されました。ただ、当時は、3次元点群データは高性能なパソコンでしか動かなかったことや、MMSによるデータの取得コストも高かったこともあり、普及には苦労しました」と振り返る。
現在では、トンネルの定期点検のデジタル化にも焦点を当てている。3Dレーザースキャナーや高解像度カメラを搭載した車両がトンネル内を走行しデータを収集する。データを解析する際は、画像処理やAI技術を活用してひび割れなどの様々な変状を検出する。このアプローチは、形状が比較的均一なトンネルに特に適している。「トンネルはデジタル技術を適用しやすいです。形状がシンプルで、データ解析もやりやすい。舗装の点検も同様に進めています」(安中氏)は語る。
インフラドクターの特徴は、単なるデータ収集にとどまらない点にある。将来は、収集した3次元点群データや画像をもとに、構造物の状態を可視化し、補修や補強の設計に直結させる。例えば、トンネルのひび割れを検出した場合、その位置や長さを正確に把握し、どの程度の補修が必要かを迅速に判断できるような仕組みにしたい。これにより、従来は熟練技術者の経験に頼っていた点検作業が、データ駆動型のアプローチで効率化される。
これにより、点検員の負担が軽減され、夜間作業の削減にもつながる。「夜間に現場で点検するのではなく、データを取ってきて昼間に点検(解析)する。技術者が最終確認を行いますが、そうやって現場の作業を劇的に減らすのが目標です」(安中氏)と強調する。
なお、先に引用した安中氏の発言には、インフラドクターは、首都高の健康診断のために開発されたものであり、実際そのために運用されているが、MMSを走らせて構造物をチェックするというシステムは、首都高だけでなく、鉄道や空港といった他のインフラメンテナンスのソリューションとなり得る、という文脈がある。
インフラパトロール 日常点検をリアルタイムでデジタル化
インフラドクターが構造物の詳細な点検を対象とする一方、日常の巡回点検のデジタル化を担うのがインフラパトロールだ。首都高の黄色いパトロールカーに搭載されたカメラやセンサーが、走行中に道路や構造物の状態をリアルタイムで記録する。
「パトロールカーには3つのカメラがついていて、ほぼ180度の視野で映像を撮影します。運転席のリモコンでボタンを押せば、異常箇所の映像が事務所に送信され、リアルタイムで確認できる」と安中氏は説明する。
このシステムは、首都高の約90台のパトロールカーに導入済みで、交通状況の監視と点検を同時に行う。現在は、ウェアラブルカメラやスマートフォンを活用した新たな展開も進んでいる。「固定カメラだと影の部分(死角)が見えないことがあります。そこで、事故現場などではウェアラブルカメラを使って詳細な映像を撮影することや、報告書を自動作成する技術を開発中です。落下物やポットホールなどの通行車両の障害となる事象を自動検知する機能の実装も目指しています」(安中氏)と話す。
インフラパトロールの強みは、リアルタイム性と柔軟性だ。従来は点検員が現地で目視し、紙の報告書にまとめる作業に多くの時間を要した。しかし、デジタル化により、データ収集から異常検知、報告までが一気通貫で行えるようになる。
首都高DXビジョン DXで目指す首都高の未来像
首都高グループにおけるDX推進の取り組みは、2023年、2024年に連続して公表された「首都高DXビジョン」と「首都高DXアクションプログラム」に集約される。首都高DXビジョンはグループが一丸となってデジタル技術の活用を更に加速・進化させ、次世代に向けた変革を目指すべく策定されたものであり、DXアクションプログラムはDXビジョンの実行施策として取り纏められた。
「首都高DXビジョンは2030年代を実現期間として、『安全・安心の追求』や『情報提供・道路サービスの進化』などの5つ大きな柱ごとに、首都高グループがDXを通じて何を目指すのかが示された指針と言えます。インフラドクターもインフラパトロールも、将来像の実現に向けたDXの取り組みとして進めてきたものです」と首都高技術株式会社取締役の寺島善宏氏は語る。
DXビジョンの背景には、インフラメンテナンスの厳しい現状がある。老朽化した構造物が増える一方で、熟練技術者は減少している。首都高の道路網は327kmに及び、約9割がトンネルや橋梁などの構造物で構成される。特に建設から50年以上経過した構造物が多く、今後10年で50年を超えるものが約半数となる。「このギャップを埋めるには、DXが不可欠です。従来のやり方では、いつかメンテナンスが追いつかなくなります」と寺島氏は危機感を口にする。
DXのカギとなるのが、AIと3次元点群データの活用だ。たとえば、トンネルの点検では、画像処理技術を有する企業と連携し、高精度なデータを取得する。しかし、現状のAIは「原始的なもの」にすぎないと寺島氏は指摘する。「今使っているAIは、特定のタスクに特化したもの。トンネルの画像解析は得意でも、他の用途には使えない。次に来るのは汎用AI型(AGI)で、複数のタスクに対応できるものです。それが実用化されれば、コストが劇的に下がるはずです」と寺島氏は指摘する。
首都高で培ったノウハウを全国のインフラへ 鉄道や空港へ
先に触れたように、インフラドクターとインフラパトロールは、首都高のニーズを満たすために開発されたが、外販プロダクトとして、他のインフラ分野でもすでにインストールされている。
首都高グループと東急株式会社との連携はその好例だ。2018年に伊豆急行線や富士山静岡空港で実証実験を行い、鉄道トンネルや滑走路の点検にインフラドクターを活用した。「鉄道や空港は、首都高とは異なるニーズがあります。たとえば、鉄道では終電後の数時間で点検を終える必要がありますが、中小の鉄道事業者はメンテナンスの予算は限られているので、インフラドクターのようなソリューションが役立と思うのです」と安中氏は説明する。
最近では、北海道エアポート株式会社にインフラパトロールが導入された。首都圏の鉄道事業者とも、夜間の保守作業の効率化に向けた技術提案をしている。「地方のインフラのニーズに合わせて技術をカスタマイズし、提供していくことも私たちの役割です。そのためにはコストをどう下げるかが最大の課題になります」と安中氏は明かす。
トンネルやもりんでインフラ建設分野に挑む首都高デジタル&デザイン
首都高グループの技術開発は、点検の自動化にとどまらない。トンネル覆工部分の狭い箇所を点検する共同開発ロボット「トンネルやもりん」は、人が目視で点検しにくいトンネル覆工での点検データ収集を可能にする。「沈埋トンネルの接合PCケーブルのジョイント部は、人が点検するのが難しい。そこにロボットを走らせ、画像を撮影して毎年点検しています」と首都高デジタル&デザイン株式会社の大場新哉氏は説明する。
日本橋区間地下化工事にも3Dモデリングで参加
3次元モデリング技術も首都高グループの重要な柱だ。特に、日本橋の地下化工事では、地下の複雑なインフラを3次元化しようとしている。「東京の地下は、電気、ガス、通信、上下水道が絡み合っていて、統合された図面はない。あっても図面通りにいかないことが多い。3次元点群データなどを使ってモデル化すれば、工事前にトラブルを予測し、作戦を立てやすくなると考えています」と安中氏は語る。
コストと品質のバランス 地方展開する上での課題
デジタル技術の普及には、コストが大きな障壁となる。特に地方自治体や中小事業者では、予算が限られるため、導入のハードルが高い。「地方では『コストが下がらなければ採用できない』というのが大前提。人がいるうちは、従来の方法でいいという考えもあります」と安中氏は指摘する。
首都高技術は既存の技術を組み合わせ、実装までの期間を短縮する戦略をとる。「コア技術の開発にはこだわらず、良いカメラやソフトがあれば現場に合わせて組み合わせる。最大でも3年以内に実用化できなければ、別の技術に乗り換えます」と安中氏は言う。この柔軟なアプローチが、技術の陳腐化をしなやかに回避する。
インフラメンテナンスの自動化と効率化を目指して
首都高技術が目指すのは、インフラメンテナンスの自動化と効率化を通じて、品質を保ちつつ人手を減らすことだ。「労働力不足への対応と働き方を変えるために、技術でカバーする必要があります。夜間作業を減らし、データを昼間に解析する仕組みが必要です」と安中氏。
同時に、人の目と経験の重要性も強調する。「AIやロボットが得意なのは単純作業。複雑な構造物の裏側や異常の微妙な兆候は、人の判断が欠かせません。機械が効率化できる部分を任せ、人が得意な領域に集中する。それが理想のバランスです」(安中氏)と続ける。
インフラメンテナンスを通じた社会貢献
首都高技術は、インフラドクターやインフラパトロールなどの技術を通じて、高速道路の管理を超えた社会貢献を目指す。「首都高速道路で培った技術を全国のさまざまな社会インフラで活用していただき、道路分野をはじめとして、空港、鉄道、港湾などの安全・安心でサスティナブルな社会インフラの実現に貢献していきたい」と寺島氏はチカラを込める。
日本橋の地下化工事で培ったノウハウが他の地域に広がり、渋谷の再開発や地方のインフラ整備に役立つ日が来るかもしれない。首都高グループの挑戦は、デジタル技術を通じてインフラの未来を切り開いていく。インフラメンテナンスが、デジタル技術によって刷新される日はそう遠くないだろう。