【2025年最新版】建設業許可の種類と29業種をわかりやすく解説!一般・特定の違いや金額・分類も
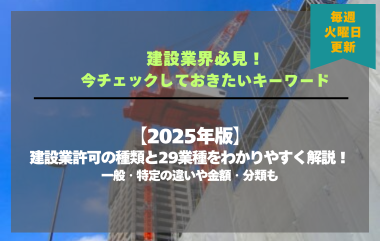
建設業を始めるには「建設業許可」の取得が必要です。しかし、その種類や業種分類、金額などが複雑でわかりにくいと感じる方も多いでしょう。
そこでこの記事では、建設業許可の取得が必要となる29業種の分類について説明したのち、一般・特定の違いや金額情報について解説します。
目次
建設業許可とは?必要な理由
建設業許可とは、一定以上の建設工事を請け負う事業者に対し、国・都道府県がその事業運営を認可する制度です。
許可がないまま請け負える工事には制限があり、「税込500万円(建築一式は1,500万円)以上」の工事を請け負うには必ず許可をとらなければなりません。なお、国土交通省の建設業法(第3条)では、以下のように明記されています。
営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
引用:e-GOV法令検索「建設業法|第3条」
また、許可を取得することで、元請・大手企業からの仕事を受注しやすくなるのもメリットです。融資や入札、公共工事への参入もスムーズになるなど、信用力の向上が期待できます。
なお、建設業許可の概要を詳しく知りたい方は、こちらの記事がおすすめです▼
許可を取らずに工事を行うとどうなる?
建設業許可が必要な工事を、無許可のまま請け負ってしまうと、建設業法違反として厳しい処分を受けるリスクがあります。以下に、起こりうる罰則・罰金等を整理しました。
- 建設業法違反による罰則(懲役・罰金)
- 取引先からの契約打ち切り
- 入札や大手案件への参入不可
- 信用情報の悪化(金融機関・自治体)
- 元請業者とのトラブル、損害賠償リスク
実際に、近年でも無許可営業による行政処分や書類送検の事例は後を絶ちません。
なお、国が主導する関西万博のアンゴラパビリオンでも無許可業者が工事に関与した疑いが出るなど、さまざまな場所で問題が起きています。
(参考:NHK「万博 アンゴラパビリオン 無許可業者が工事関与の疑い」)
建設業許可の種類は大きく2つ
建設業許可には「一般建設業」「特定建設業」の2種類があります。
どちらを取得するかは、施工体制や元請・下請の関係性、請負金額の規模によって変わります。以下より、建設会社が取得するべき許可のイメージをまとめました。
「一般」と「特定」の違い【比較表】
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
| 対象 | 中小規模の元請、下請業者 | 元請として下請へ高額発注する企業 |
| 下請契約額 | 制限なし | 1件5,000万円(建築一式8,000万円)超 |
| 財務基準 | 緩やか(債務超過NG程度) | より厳格(自己資本2,000万円以上など) |
| 技術者要件 | 専任技術者1名 | 一般と同様だが元請施工実績が必須 |
| 更新期間 | 5年ごと | 5年ごと |
どちらを選ぶべき?ポイントを解説
元請として1件あたり5,000万円(建築一式なら8,000万円)以上の下請契約を締結する可能性があるなら「特定建設業許可」が必要です。それ以外は「一般建設業許可」で十分なケースもあります。
(参考:国土交通省「建設業の許可とは」)
たとえば、公共施設の新築や大規模マンション建設で、設備・電気・防水などを下請に回す場合、その合計が5,000万円を超えるなら特定許可が必要です。一方で、住宅リフォームや内装工事がメインであれば、一般許可でも支障はないでしょう。(例外あり)
より詳しく2つの違いを知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
建設業の29業種一覧|業種分類
建設業許可は、すべての業者に一括で出されるものではなく、業種ごとに29の分類に分けられています。
ここでは、29業種の分類と特徴、また各業種でよく行われる工事のイメージをわかりやすく解説します。
建設業29業種の分類と特徴
建設業の業種は「土木」「建築」「電気設備」など、工事内容ごとに29業種に分類されており、それぞれに許可が必要です。
| 大分類 | 業種名(代表例) | 概要 |
| 土木系工事 | 土木・舗装・しゅんせつ 等 | インフラ整備、道路・橋・港湾工事 |
| 建築系工事 | 建築・屋根・内装・左官 等 | 住宅やビルの建築・リフォーム |
| 設備系工事 | 電気・管・水道施設 等 | 電気配線・給排水・冷暖房 |
| 特殊工事 | 解体・さく井・防水・塗装 等 | 専門性の高い部分施工 |
実際に行う工事に応じて、複数業種の許可を取るケースも多いため、事前に自社業務とのマッチングを明確にし、許可対象となる業種を正確に把握することが重要です。
業種分類ごとの代表工事とイメージ
29業種のなかには、聞き慣れない工事も多くありますが、実際にはよく見かける工事が大半です。以下に、代表的な工事のイメージをまとめました。
| 業種名 | よくある工事例 |
| 土木工事業 | 道路工事、擁壁、造成、上下水道敷設など |
| 建築工事業 | 木造・RC造建物の新築、増築工事 |
| 電気工事業 | 屋内配線、受変電設備、照明設置など |
| 管工事業 | 給排水設備、空調、衛生設備工事 |
| 解体工事業 | 木造・RC造・鉄骨造の建物解体 |
| とび・土工工事業 | 足場組立、基礎工事、掘削工事 |
今後許可を取得する際には、名称だけで判断せず、どのような工事を請け負うのかによって許可業種を検討しましょう。行政書士や建設業専門の相談窓口で事前に確認するのも有効です。
建設業許可の申請手続きの流れ
建設業許可の申請は、単に書類を出すだけではなく、会社の体制・技術者・財務基盤など、複数の要件をクリアしながら、所轄庁に対して適切な書類を揃えなければなりません。
以下に、一般的な建設業許可の流れをまとめました。
- 事前相談・要件確認
- 必要書類の準備(定款・決算書・資格証など)
- 専任技術者・経営業務管理責任者の要件確認
- 都道府県庁または国交省(大臣許可)へ申請書提出
- 審査(通常30〜45日) → 不備があれば修正指示
- 許可通知 → 許可証の交付 → 業者票の取得・掲示
なお、法人や新規申請の場合には、次のような書類を準備しなければなりません。
| 書類名 | 説明 |
| 許可申請書一式 | 所定の様式に記入 |
| 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 法人の設立・代表者情報 |
| 定款の写し | 会社の目的に「建設業」が含まれている必要あり |
| 決算書(直近の財務諸表) | 資本額や債務超過の確認用 |
| 専任技術者・経営業務管理責任者の資格証明 | 実務経験証明、国家資格など |
なお「書類が多くて不安…」「自社に経営業務管理責任者がいない」などの場合は、建設業専門の行政書士に無料相談するのがおすすめです。
特に、特定建設業を目指す場合は、経審との連動も視野に入れて早めの準備をスタートしましょう。
建設業許可の種類に関するよくある質問【FAQ】
建設業許可は複数業種の同時許可は可能ですか?
可能です。同一事業者が2業種以上の建設業許可を、同時に取得することは制度上認められています。たとえば「建築工事業」「内装仕上工事業」など、請け負う内容に応じて複数業種の同時申請・取得が可能です。なお、専任技術者はそれぞれの業種要件を満たす必要があります。
業種を追加したい場合はどうすればいい?
既に建設業許可を取得している場合に、別の業種を追加するなら「業種追加申請」を行います。新たな業種について、専任技術者の要件や実務経験などを証明できれば、追加での許可取得が可能です。申請方法や審査期間は新規取得とほぼ同様です。
許可の有効期限は?更新は何年ごと?
建設業許可の有効期間は「5年間」です。更新申請は有効期限満了の30日前までに手続きが必要です。期限を過ぎると許可が失効し、再取得が必要になる場合もあるため、余裕をもって更新準備を進めましょう。更新にも財務・技術者などの審査があります。
更新時期について詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
許可なしでも可能な工事はある?
あります。建設業法では「軽微な工事」は許可なしで請け負えます。具体的には、建築一式工事で1,500万円未満、その他の工事で500万円未満(いずれも税込)の請負工事です。ただし、反復的に営業として行う場合は注意が必要です。
まとめ
建設業許可は、法律上の義務であるだけでなく、取引の信頼性を高め、将来的な事業拡大や公共工事参入の土台にもなります。
「一般」「特定」といった種類の違いや、29業種の分類、許可を取らないリスク、申請手続きの流れを理解しておかなければ、許可申請で失敗する可能性が高まります。今後の申請のためにも、まずはどの種類の許可を取るべきなのかチェックしてみてください。


