人が動けば、業界が変わる。|建設DX研究所が目指す「現場ファースト」の改革
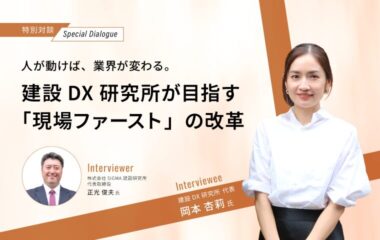
建設業界は、日本における市場規模65兆円超、およそ500万人以上が働く巨大産業です。しかし、過酷な労働環境や生産性の低下、労働人口の高齢化や減少といった多くの深刻な課題を抱えており、これらを解決に導く「建設DX」は待ったなしの状況となっています。
今回は、建設DX研究所 代表の岡本氏にインタビューを行いました。インタビュワーは、国内外の建築施工管理に豊富な知見を持つSIGMA建設研究所の正光氏です。
建設DX研究所では、情報発信・勉強会の開催・政策提言の3本柱を軸に、DX推進による労働環境改善や作業効率・生産性向上を進め、業界の課題解決を模索しています。そんな建設DX研究所の詳しい活動内容と、業界のDXの今後について語ります。
目次
プロフィール

岡本 杏莉 氏(建設DX研究所 代表/株式会社アンドパッド 上級執行役員 経営推進本部長)
日本/NY州法弁護士。西村あさひ法律事務所で国内外のM&A案件を担当後、Stanford Law Schoolに留学。株式会社メルカリで資金調達やIPOを担当。2021年に株式会社アンドパッドに入社し、2024年4月より現職。管理部門、建設DX研究所の立ち上げをはじめとする公共政策等を担当。
正光 俊夫 氏(株式会社SIGMA建設研究所 代表取締役/Founder & CEO)
ミシガン大学工学部で建設エンジニアリング&マネジメントを学ぶ。大成建設株式会社で国内・海外の建築施工管理を行った後、Autodeskのコンサルタントとしてアジア全域でBIMを推進。帰国後、PwCコンサルティング合同会社とデロイトトーマツコンサルティング合同会社での建設業界担当コンサルタントを経て、株式会社SIGMA建設研究所を設立。
建設業界の課題解決を目指して活動する「建設DX研究所」とは
ー【正光】はじめに、建設DX研究所の組織概要についてお聞かせください。
【岡本】建設DX研究所は2023年1月に任意団体として設立し、メンバー6社からスタートしました。私が所属する株式会社アンドパッドが事務局を務め、その他メンバーは主に建設DXを手掛けるスタートアップ企業です。
実はこの建設DX研究所の活動は、正式に設立する以前にアンドパッドの自主的な取り組みという位置づけで、勉強会の開催や様々な企業への声掛けを進めていました。その中で、建設業界におけるDX推進への期待が非常に高いことを実感しました。
ー具体的に建設DXスタートアップ企業からはどういった課題が挙げられたのでしょうか。
人手不足に対する突破口が見出せない企業が多い中で、DXを推進して生産性を上げることや「少ない人員でも質を落とさず、従来と同じ量の仕事をやり遂げるにはどうすべきか」といった課題への対応が迫られる状況を目の当たりにしました。
これらに対抗する手立てとして、DXをもっと盛り上げなくてはならないという業界からの期待や機運を強く感じると同時に、当社だけでなく企業の垣根を越えて様々な技術を持つスタートアップと一緒に活動する動きも必要だと考え、建設DX研究所として活動を始めました。
2025年3月には新たに5社のDXスタートアップが加入し、現在は合計11社が参加しています。
ー建設DX研究所のメンバーにはどのような企業が参加しているのか詳しく教えてください。
建設DXのソリューションを建設会社に提供するスタートアップが中心ですが、それぞれ得意な技術領域が異なり、様々なプロダクトを持っています。例えば、アンドパッドはクラウド型建築・建設プロジェクト管理サービスを提供しており、サービス提供当初は建築関連事業者の皆様を中心にご利用いただいていました。
その他の会員企業では、3Dプリンター・点群処理プラットフォームといった土木関連に強い技術を持っている会社もあります。得意領域の違う企業が複数集まることで、カバーできる部分の広がりという新たな強みを生み出せるのではと考えています。
ー建設業界は非常に広く、建築と土木という違いはもちろん、各工事の中でも様々な規模・工種がありますね。建築の中でも戸建て住宅や大規模マンション、再開発案件など多種多様ですし、土木も橋梁・ダム・トンネルなどで内容は大きく異なります。
そんな中で「土木では解決できているが、建築では未だ解決に至っていない課題」もあるでしょう。どのような課題があるか共有されていないがゆえに「わからない」で留まっていた部分を、建設DX研究所の取組みによって明らかにし、土木・建築にまたがるソリューションを生み出せる可能性があるのではと感じます。
おっしゃる通り、建設DX研究所の取り組みを通して「今までよく見えてなかった分野についてどういう課題があるのか、どのようなソリューションがあれば解決できそうか」という解像度が少しずつ上がってきている実感があります。「課題Aに対しての解決策が、課題Bにも当てはまるのでは」といった議論ができることは、私たちの取り組みにおけるメリットの一つだと感じています。
ーそのような取り組みが、建設会社側からではなくベンダー側から始まった点が非常に新しいと思います。建設業界には個別領域に特化した業界団体が数多くあり、業務も各領域でセグメントに分かれてしまい、横断的な目線で見ることが難しい状況もあります。建設業界の問題や課題が複雑化している中で、1社だけでなく複数の企業が建設DX研究所として取り組むことによって、課題をしっかりと棚卸し・共有しながら汎用的な解決策を示せる点は非常に画期的だと思います。
建設DX研究所が行う3つの活動
ー建設DX研究所の主な活動内容について教えてください。
私たちは以下3つの柱で活動しています。
①情報発信:noteやSNSを使った情報の共有・発信
②勉強会の開催(毎月):会員企業の取り組み紹介や関心の高いテーマを議論
③政策提言:中小建設事業者の声を政府に届けるための活動
情報発信では「読者に刺さる情報提供」を意識
情報発信では、建設業界の実務に携わる方にとって有益な内容を届けられるよう、ウェブメディアのnoteを活用した記事配信や、Xによる発信を定期的に行っています。noteは会員企業のインタビュー記事や最新の政策に関するレポート、テクノロジーに関する調査記事などを作成して、週に1度ほど更新しています。また、公式ウェブサイトでは、取材に関するお問い合わせ等も受け付けています。
ーnoteの記事を拝見しましたが、非常に質が高いことに加えて更新の頻度も高く、力を込めて運用していることがわかります。
インタビュー記事では、会員企業の紹介の他に、新しい技術を活用する企業のお話を聞き「こんなに面白いDX事例がある」と紹介する場合もあります。また、政策提言活動の中で気になるトピックや法改正といった大きな動きがあったときも積極的に発信しています。
ー様々な情報が掲載されていて、初めて知る会社の取り組みもあり、読者に多くの気づきをもたらしているnoteですよね。とても興味深く読んでいます。
記事を配信するうえでは様々な方に出会い、私たちも勉強の機会を得ています。建設業界に興味のあるすべての方を対象に発信していますが、今後も実務に関わる皆さんが興味を持っていただけるような内容をどんどん発信していきたいと考えています。
毎月の勉強会では会員企業間で学びをシェア
ー勉強会の参加者と、具体的な内容についてお聞かせください。

会員企業を対象に毎月1回、当社のイベントスペースでオフラインの定例部会を開催しています。この勉強会は2年以上続いており、1時間半ほどを使って建設DX研究所としての毎月の活動報告や、ディスカッションを行う内容です。
定例部会は、会員企業の皆さんに月替わりで幹事をしてもらうスタイルで運用しています。幹事が自社の最新の取り組みをシェアすることもあれば、関心のあるトピックについてゲストを呼んでお話を聞く場合もあり、テーマは各幹事が自由に決めることができます。
例えば最近では、アンドパッドのAIエンジニアをゲストに呼んで、AIを活用したプロダクトの事例紹介を行いました。参加者は全体で20名ほどなので、ただ発表を聞くだけでなく質問やディスカッションを交えつつ、ざっくばらんな意見交換や関心がある技術領域について情報共有できる会となっています。
ディスカッションでは話し切れなかった内容については、会の終わりに開催している簡単な懇親会にて、情報交換が行われています。
ー会員企業にとって、非常に貴重な情報を得る場になっているのではないでしょうか。建設業界には様々な分野がありますから、領域ごとに専門性を深めてみたり、反対に少し全体を俯瞰して見た議論をしたりと両方に対応できる可能性を秘めていると感じます。
新しい技術はもちろん、各会員企業の技術がどういった現場で使われているのかを共有できる場なので、交流を通してビジネスのつながりがより強くなるきっかけになればいいなと考えています。定例部会でどのような内容が話されたのかはnoteで配信していますので、興味がある方はぜひご覧ください。
中小建設事業者の生の声を国に届けるため政策提言を実施
ー政策提言について、具体的にどういった内容に取り組んでいるのか、また政策提言をする狙いをお聞かせください。
大手のゼネコンや規模が大きい業界団体は、政治との距離が近く様々な政策提言をしています。しかし建設DX研究所が大切だと考えるのは、中小建設事業者の声を政治に届けることです。なぜなら、建設業界のうち95%以上が中小建設事業者かつ従業員20人以下というデータがあり、中小建設事業者がDXを推進しなければ業界全体が変わることはないからです。
国土交通省をはじめとする関係省庁は、土木領域や国の直轄工事に関するDXのイメージは持っていても、中小建設事業者の実態やDXが進みにくい要因については把握することは難しいのではないかと思います。
アンドパッドをはじめとする建設DX研究所の会員企業の多くは中小建設事業者を顧客としています。現場の生の声や顧客先がDXで苦労するポイント、「ここに政策支援があればいいのに」といった要望を届けられるメンバーがそろっていますので、中小建設事業者から業界全体のDXを後押しする目的で政策提言を行っています。
ー中央省庁と中小企業が対話をする機会は多くありませんから、建設DX研究所を通して中小建設事業者の声を届けるのは非常に価値がある活動だと思います。
建設DX研究所の発足以来長く続けている活動として、政治家の先生方と一緒に行う勉強会があります。衆議院議員で建設DXを応援してくださる上野賢一郎先生が議長を務め、他にも有志の先生方にお集まりいただいています。
勉強会では、テーマにあわせて建設会社をお呼びし、生の声を発表する機会もあります。先生方からは「現場の声を聞けてよかった」という声もいただいており、今後もぜひこの取り組みを続けたいと思っています。
ー政策提言と聞くとロビー活動のイメージが強くありますが、勉強会を開催して生の声を聞いてもらう取り組みを中心としているんですね。
この活動を通して感じることは、現場の声や現場の実態が直接伝わることはもちろん、中小建設事業者が抱える「政治家や省庁にどう要望を伝えればいいのかわからない」という課題の解決にもつながるということです。
具体的に言えば、中小建設事業者側に何か訴えたいことがあったとしても「法律・規則・ガイドラインのここを変えてほしい」といった部分にまで詳細に落とし込んで考えられていない場合もあります。行政サイドに何かを訴える際には、より具体的であるほどイメージが伝わりやすいため、建設DX研究所がその橋渡し役になれればいいなと思っています。
できること・できないことを踏まえた上で、「今できる最良の方法は何だろう」と互いにディスカッションしながら答えを見つけていく活動でお役に立ちたいと考えています。
ーとても有意義な取り組みですね。建設業界の課題のうちいくつかは、国土交通省だけではなくその他省庁が管轄している場合もあり、解決には困難が伴う可能性があります。議員の先生方が参加してくださることで、省庁を越えた課題をしっかり伝えられる機会があることは解決への有効なアクションだと感じます。
省庁ごとの壁に関する課題は、様々な部分で目にします。そのうちの一つが、建設業界における行政手続きの多さです。電子化が進んでいないためにペーパーワークが多く、また国と自治体とでは手続きの中身が少しずつ違っており、多くの方が苦労している印象です。
一部は電子化されていても、システムが違うためにログインし直さなければならなかったり、システムごとに同じ内容を何度も打ち込む必要があったりします。そこを誰が主導権を持って連携を促し、引っ張っていくのか。ワンストップでいかに解決するかが重要ですが、一足飛びには進まない現状がありますね。
ーシンガポールでは2013年からBIMが段階的に義務化され、それと並行してe-Submission (現在のCORENET X)という仕組みも活用が始まりました。それまでは日本と同じように別々のところに申請や許認可の書類を出していたのを、窓口を一本化して色々な省庁が同じプラットフォーム上で情報連携できるようになっています。
例えば建物の図面やプロジェクトの情報を入れておけば、一箇所で許認可のステータスが確認できるといった形です。行政のDXを国主体で進めたのがシンガポールの特徴的な取り組みだと思います。
素晴らしいですね。一度情報を出せば、それをすべての省庁が参照して使えるのはとても便利だと思います。今は自治体別・手続き別・窓口別というように、同じ内容を何度も申請する手間が至る所で起こっています。その解決への動きが日本でも進めば、建設業界の生産性向上への効果が非常に大きいと思います。
これに似た話は建設会社の社内でも起こっていて、各社が複数のデジタルツールを使っており、それぞれがデータ連携をしていない場合も少なくありません。例えば経理などのバックオフィスが使うツールと、施工の現場監督が使うツールが違うために苦労があるという話も聞いています。アンドパッドとしては、その部分をつなぐ活動にも力を注いでいます。
当社ではアプリのマーケットプレイスに以前から取り組んでおり、経理・電子契約といった様々なツールとの連携やスムーズな移行を実現しています。また、今後は政府側のツールと民間側のツールの連携といった動きも重要になってくるでしょう。まずは建設会社の社内から電子化を進め、建設DX研究所の会員企業の力を借りながら、建設業界のDXの動きをさらに加速させる取り組みを推進していきたいと考えています。

「建設DXを広く推し進めたい」建設DX研究所の今後
ー建設DX研究所の今後の展望についてお聞かせください。
建設DX研究所の活動はまだ始まったばかりの取り組みですが、これからどんどん活動範囲を広げていきたいと考えています。日本の産業の中でも非常に大きな割合を占める建設業界に対して、DXソリューションを提供するIT企業の数はまだまだ少なく、これからますます盛り上げていく必要があります。
建設業界のDX推進のニーズは年々高まっており、中小建設事業者を含めてDXに前向きに取り組みトランスフォーメーションを実現する会社の数は少しずつ増えています。現段階では、若い経営者やITに詳しい人材が社内にいる先進的な会社がDXを進めている状況ですが、これをいかにすそ野まで広げていけるかが重要です。
ー「ITツールを使いこなして仕事をするのは当たり前」という世界になるといいですね。いまだに紙の書類や電話・FAX・Excelを使った管理が業界の主な手段である中で、業界全体がデジタル化するところまでDXを浸透させる必要はとても高いと思います。
それが実現して初めて、建設業界の課題である人手不足を乗り越えられるのではないかと考えます。その波を建設DX研究所として少しでも後押ししながら、業界全体の盛り上がりを目指して貢献していくつもりです。
建設DX研究所としては一気に100社や200社などと会員企業を増やすことは考えていませんが、信頼関係・結束感の高い仲間を徐々に増やしたいという想いはあります。建設DX領域以外のスタートアップに参加してもらったり、建設会社やアカデミア、自治体といったDXツールを使う側の立場の方々も一緒に活動するなど、建設業界内外から変革をもたらすことができればと思います。
まとめ – BuildApp 編集部感想 –
建設業界から寄せられるDXに関する課題や期待の声に向き合い、現場に寄り添いながら一歩ずつ前進する建設DX研究所。岡本さんの言葉からは、業界をより良くしていきたいという熱意が感じられました。
急激な変化よりも、志を同じくする仲間を集めて足元から少しずつ変化を促す。そんな地に足のついた取り組みが、業界全体への着実な波紋につながることでしょう。今後、どんな仲間が建設DX研究所の活動に加わり、どのように業界が変革していくのか楽しみになるお話でした。





