【2025年版】建築物の水切りとは?外壁・屋根・サッシの納まりや種類を解説
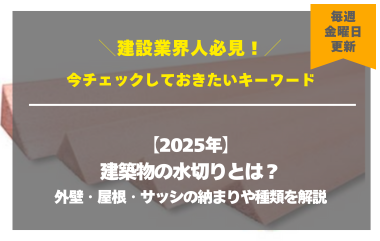
建築における「水切り」は、雨水の侵入を防ぎ、建物を長もちさせるために欠かせない部材です。特に、外壁・屋根・サッシまわりなど、雨仕舞いが重要な場所では、適切な水切りの納まりが住宅の耐久性に直結します。
そこでこの記事では、建築現場で用いられる水切りの役割を説明したのち、部位別の種類、寸法や納まりの注意点、後付け補修の対応までわかりやすく解説します。
目次
建築に用いられる「水切り」とは?
建築における水切りは、単なる板金部材ではなく「雨仕舞いの要(建物に雨水が入らないようにするための工夫や施工のこと)」となる重要な存在です。
雨水を外に逃し、建物の寿命を延ばす役割を果たす水切りは、あらゆる建築物に欠かせません。ここではその機能や設置箇所について、基本から解説します。
水切りの基本的な機能と目的
水切りとは、外壁や屋根、窓まわりなどから雨水を効率よく排出するための板金部材です。
主に「建物内部に水を入れない」ことを目的で設置し、次のような建物劣化の原因を防ぐ役割を担っています。
- 雨漏り
- 躯体腐食
- 凍害
- シロアリ被害
また、素材にはガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどの耐食性に優れた金属が使われているのが特徴です。水の流れや重力を利用したシンプルながらも非常に重要な仕組みをしています。
設置される主な場所(外壁・屋根・サッシ)
水切りは、雨水が溜まりやすい接合部や端部に設けられます。具体的には以下のような場所です。
- 外壁と基礎の境界(土台水切り)
- 外壁の出隅・入隅(形状変化部分)
- 屋根の谷部・軒先・ケラバ・棟
- 窓まわりのサッシ下
それぞれの部位に合った形状・納まりを検討しなければなりません。適切に設置しないと雨水が内部へ浸入し、雨漏りや下地材の劣化につながるため注意が必要です。
建築物に水切りがないとどうなる?
水切りを設置していない建築物は、次のような深刻なダメージを受ける可能性があります。
- 雨水が壁内部に侵入し、断熱材や木下地が腐食する
- シロアリ被害が誘発される
- 内部結露やカビが発生する
- クロスやフローリングが膨れ・剥がれる
上記のトラブルが起きると、修繕費用が高額になることもあります。
なお、国土交通省の「建設省告示第1654号」という資料では、土台に対する水切りの設置が基準化されているなど、今や建築物にとって欠かせない部材のひとつだと言えます。
水切りは後付けも可能
既存住宅でも、水切りの後付けや補修が可能です。
外壁リフォーム時や雨漏り対策として、後から水切り板金を設置する工法も一般化しており、近年では古い建物にも後付けで水切りを設置するケースがあります。
ただし、透湿防水シートとの取り合いや勾配処理には専門知識が必要です。DIYでは難易度が高いため、専門業者への依頼が推奨されます。
建築の外壁に用いる水切りの種類【部位別】
外壁部分は、もっとも雨水にさらされるエリアのひとつです。
そのため、水切りの適切な設置が、住宅の防水性能を左右します。ここでは、外壁に設置される水切りの代表的な種類、そしてそれぞれの役割や納まりのポイントを解説します。
土台水切り(基礎との接点)
出典:Joto公式サイト
土台水切りとは、外壁と基礎の間に設けられる水切りで、雨水が基礎内に侵入するのを防ぎます。通気工法ではこの部分から空気を取り込み、壁内の湿気を逃がす通気層の起点にもなります。
施工時には透湿防水シートとの重ね順が重要で、誤ると逆流や隙間からの漏水リスクが高まります。
入隅水切り・出隅水切り
出典:ソニテック公式サイト
入隅水切り・出隅水切りは、それぞれ外壁の角部(L字部)に使われる水切りです。
雨水が滞留しやすい部位を保護します。特に入隅は雨水が集中しやすく、板金加工で密閉納まりを確保することが重要です。
目地用水切り(シーリング部)
目地用水切りは、サイディングの目地部に使われる水切りです。
シーリング材の上からさらにカバーして防水性を高める目的で使用されます。定期点検時に水切り部材の変形・隙間の有無を確認することで、雨漏りを未然に防ぐことが可能です。
建築の屋根に用いる水切りの種類【部位別】
屋根はもっとも高所にあり、雨水を集中的に受け止める部位です。
そして屋根の水切りは、漏水防止と排水の役割を兼ね備えており、適切な納まりが求められます。ここでは谷樋・軒先・ケラバ・棟包みの4種類を部位別にわかりやすく解説します。
谷樋(たにどい)
谷樋は、屋根と屋根の合流点(谷部)に設ける水切りです。
集まった雨水をスムーズに流す役割を担います。雨水が集中しやすい部分のため、もっとも漏水リスクが高い部位とも言われ、施工精度が求められます。
軒先水切り
軒先水切りは、軒の先端部に取り付けられる水切り金物です。
屋根内部への雨水の回り込みを防止します。防水シート(ルーフィング)との重ね順・重ね幅が規定されており、雨仕舞いの基本となる部分です。
ケラバ水切り
ケラバ水切りは、切妻屋根の端部(ケラバ)に設け、風雨の吹き込みを防ぐための水切りです。
屋根材との取り合いや壁面との接点が複雑になるため、折り返し処理やシーリングの丁寧さが求められます。
棟包み
棟包みは、屋根の最上部(棟)を覆う水切りです。
雨の侵入を防ぐ屋根の最終防衛ラインとして機能し、棟換気部材を兼ねた水切りも多く、通気と防水のバランスが求められます。
水切りの納まりに関する注意点
水切りは単体で機能するのではなく、「壁材・下地・防水シート・コーキング」との納まり関係が正しく構成されて初めて効果を発揮します。施工する際には、特に以下の点に注意が必要です。
- 透湿防水シートとの重ね順(下から上へ)
- 水切りの勾配(最低でも2/100以上)
- 外壁材とのクリアランス(通気層確保)
- 隙間の封止(コーキング・防水テープ処理)
上記の項目を怠ると、逆流・毛細管現象・結露などが発生するかもしれません。最悪の場合、建物の劣化を早める要因になるため、DIYよりもプロに任せた方が安心です。
水切り納まりの基本比較(目安)
| 部位 | 勾配の目安 | 重ね順(上→下) | 隙間処理 |
| 土台水切り | 1/20以上 | 外壁 → 水切り → 透湿防水シート | 防水テープ+シーリング |
| 軒先水切り | 1/10以上 | 屋根材 → 水切り → ルーフィング | 水返し+水切り折返し |
| サッシ下水切り | 1/15以上 | サッシ → 水切り板金 →防水シート | コーキング処理 |
建築物の水切りについてよくある質問【FAQ】
水切りはどんな材質が使われますか?
建築の水切りには、ガルバリウム鋼板・アルミ・ステンレス・塩ビ被覆鋼板などが使われます。耐久性やコスト、施工性に応じて選定され、外観にこだわる住宅ではカラー鋼板が使われることもあります。屋根や外壁との相性も考慮が必要です。
土台水切りが浮いてきたのですが大丈夫ですか?
浮いた状態を放置すると、雨水が壁内に侵入する恐れがあります。特に通気層や透湿防水シートと密接に関係しているため、早期の点検と補修が重要です。シーリングや再固定だけでなく、部材交換が必要な場合もあります。
水切りをDIYで後付けすることは可能ですか?
簡易的な水切りであればDIYも可能ですが、納まりや防水処理が不完全だと雨漏りリスクが高まります。特に既存の外壁や下地と取り合う場合は、専門知識が必要なため、基本的には専門業者への相談がおすすめです。
まとめ
建築における水切りは、雨漏りや劣化を防ぐ「建築物の守り神」のような存在です。
正しい納まりと定期点検を心がけることで、建物の価値と寿命を守れます。後付けや補修も視野に入れ、今ある建物の状態を今一度見直してみましょう。


