【2025年版】建設業経理士とは?1級・2級の難易度・年収・活用方法までプロが解説
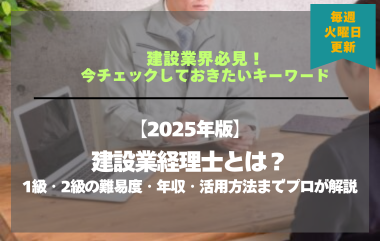
建設業界の経理として「スキルを活かしてキャリアアップしたい」「経審の加点を狙いたい」という方に注目されているのが建設業経理士です。では、一般的な簿記資格と何が違うのでしょうか?
この記事では、建設業経理士の概要をわかりやすく説明したのち、必要性や取得するメリット・デメリットについて紹介します。
目次
建設業経理士とは?
建設業経理士とは、建設業界特有の経理知識と原価管理スキルを証明できる専門資格です。
一般財団法人の建設業振興基金が提供している資格検定であり、施工管理技士といった資格と同じく、建設業にとって欠かせない資格のひとつとなります。
(参考:建設業振興基金「建設業経理検定」)
特に建設業では、「完成工事原価計算」といった、一般企業とは異なる特殊な会計処理が必要です。そのため、経理担当者がこの資格を持つことにより、経営事項審査(経審)での加点が可能となり、公共工事の入札要件を満たしやすくなるメリットがあります。
(出典:国土交通省「経営事項審査及び総合評定値の請求について」)
また建設業振興基金の概要を知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建設業経理士は国家資格?民間資格?
建設業経理士は民間資格ですが、国土交通省が管轄する建設業法に基づく「経営事項審査(経審)」の加点対象資格として公的に評価されています。
国家資格には該当しませんが、建設業法に基づく企業評価制度に直結するため、単なる民間資格以上の実務的な信用度があると覚えておきましょう。
建設業経理士が必要な人とは?【取るべき人・取らなくてもいい人】
建設業界で「キャリアアップ」「経審加点による公共工事受注拡大」を目指しているのなら、経理の担当者に建設業経理士資格を取得してもらうことが大切です。
一方で、すべての人に必要な資格ではなく、業務内容や将来のキャリアによって必要性が変化します。ここでは「取るべき人」と「取らなくてもいい人」の違いをまとめました。
【取るべき人】
- 建設業の経理担当・総務担当・現場事務員
- 建設業界で転職・昇進・昇給を目指す人
- 経審加点で公共工事の受注を増やしたい中小建設会社の社員
- 将来経理管理職を目指す人
- 建設業で独立・起業を検討している人
【取らなくてもいい人】
- 現場作業のみ担当し経理業務に全く関わらない人
- 建設業界以外への転職を考えている人
- 短期間で資格を使う予定がなく、当面活用予定がない人
建設業経理士は、建設業界でのキャリア形成や公共工事受注拡大に直結する実務的な資格です。将来のキャリアアップや社内での立場向上を目指すなら、取得を前向きに検討するのが良いでしょう。
なお転職向けに建設業経理士の資格を取得しようとしている方は、以下の記事で転職の実態をチェックするのがおすすめです▼
建設業経理士はすごい?意味ない?真実はどちら?
建設業経理士は、建設業界のなかで以下の職種を目指す方、そしてその企業にメリットがあるため、「すごい」資格だと言えます。
- 経理
- 現場事務
- 管理職
ただし、使い道がない職種・業界であれば「意味がない」と感じるケースもあり、取得目的次第で評価が変わります。
「すごい」or「意味ない」は、その人の働く環境で違うため、目的・キャリアプランに合わせて取得を検討することが大切です。
建設業経理士の1級・2級・3級の違い【試験範囲・合格率・難易度を比較】
建設業経理士の資格は1級・2級・3級と3つのランクに分かれており、それぞれ受験資格がないため好きな級から取得を目指せます。
そのため、どの級を目指すべきか悩んでいる人向けに、ランクごとの違いを整理しました。
| 項目 | 1級 | 2級 | 3級 |
| 対象 | 管理職・経理責任者向け | 実務担当・転職用 | 基礎学習・学生向け |
| 試験範囲 | 財務諸表論・財務分析など | 原価計算・会計処理 | 建設業簿記の基礎 |
| 合格率(目安) | 約20〜30% | 約40〜50% | 約60〜70% |
| 勉強時間(目安) | 200〜300時間 | 100〜150時間 | 50〜70時間 |
| 経審加点 | 高加点 | 標準加点 | なし |
| 活用範囲 | 経理管理職昇進・経審加点 | 転職・昇給・経審加点 | 基礎知識習得 |
| 受験資格 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| 難易度 | 中~高 合格率:30~35% | 中合格率:40~45% | 低合格率:60~70% |
参考:建設業振興基金「過去の実施状況」
【級選びの目安】
経審加点・転職用 → 2級がおすすめ
管理職・高度な経理力向上 → 1級を目指す
建設業経理の基礎理解 → 3級で十分(また4級もあり)
中小企業で公共工事受注を目指す場合、2級取得でも経審加点が可能です。短期間で会社の評価を高められるため、まずは2級の取得を目指してみてはいかがでしょうか。
また1級は、さらに上位加点を目指す・財務分析スキルを高めたい方に最適です。中堅〜大企業に従事している場合には、1級の取得を目指してみてください。
試験日程・スケジュール
建設業経理士の資格試験は、上期・下期の2回に分かれて実施されます。
まず上期には1〜2級の試験が実施されており、2025年では5月13日~6月12日の申し込み期間を経たのち、9月7日に試験が開催されます。
また、下期については、1〜2級、3〜4級の試験が実施されており、予定は現在準備中です。過去の実績から行くと3月に試験が開催されているため、年末当たりの申込になると予想されます。
資格取得後5年経過したらどうなる?
建設業経理士自体には有効期限はありませんが、経営事項審査(経審)の加点対象として活用する場合は5年ごとの講習受講が必要です。
登録経理試験の合格後5年を経過した者は登録経理講習を受講しなければ、経営事項審査の評価対象となりません。
引用:建設業振興基金「登録経理講習」
会社の公共工事受注力・経審評価維持のため、忘れずに講習を受け加点対象をキープしましょう。
建設業経理士の年収相場と転職市場での評価
求人サイトの情報をリサーチした結果、建設業経理士の年収相場は次のとおりであることがわかりました。
| 級数 | 年種相場(目安) |
| 1級建設業経理士 | 500万~800万円 (1,000万円の求人もあり) |
| 2級建設業経理士 | 400万~600万円 |
| 3級建設業経理士~ | 300万~400万円 |
上記の相場はあくまで目安ですが、級数を高めるごとに平均年収が高くなっていきます。本人のキャリアアップはもちろん、転職にも有利な資格であるため、資格取得を目指すこと自体に大きな魅力があると言えるでしょう。
また建設業の平均年収をチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです。
建設業経理士の実務でのメリット・デメリット
建設業経理士は実務で活かす場面が多く、特に建設業界内では役立つシーンが多い資格です。ここでは実務での具体的なメリット・デメリットを整理します。
【メリット】
- 転職・昇給・昇進時に有資格者として評価されやすい
- 資格手当(月5,000円~1万円程度)がつく企業も多い
- 経審加点で会社の公共工事受注力が向上する(企業のメリット)
- 経理実務の正確性が上がり業務効率化が可能になる
【デメリット】
- 建設業界外での活用機会は少ない
- 資格取得の勉強時間(2級で100〜150時間程度)が必要
- 経審加点維持には5年ごとの講習更新が必要
建設業に特化した経理系の資格であるため、異業種に転職した場合には、役に立ちにくいのがデメリットです。
建設業経理士は建設業界でキャリアアップを目指す人、経理実務を担当する人、公共工事受注拡大を目指す会社で働く人にとってメリットのある資格ですので、自身の今後のキャリアも踏まえて、取得の有無を検討するのが良いでしょう。
建設業経理士についてよくある質問
建設業経理士は難しいですか?
建設業経理士は級により難易度が異なり、1級は合格率30〜35%程度で難易度は高めですが、2級は40〜45%で比較的取り組みやすい資格です。建設業独自の会計知識が問われますが、過去問演習と計画的な学習で十分合格できます。
建設業経理士2級と簿記2級はどちらが難しい?
一般的に簿記2級と建設業経理士2級の難易度は同程度ですが、内容が異なります。簿記2級は企業会計全般を扱う一方で、建設業経理士は建設業特有の原価計算・工事台帳管理が中心です。建設業でのキャリア形成には建設業経理士2級が有効で、経審加点にも直結します。
まとめ
建設業経理士は建設業界で経理実務力を高め、経審加点による公共工事受注力向上や転職・昇給に役立つ実務資格です。
級ごとに難易度や活用範囲が異なり、目的に合わせて挑戦が可能ですので、キャリア形成を目指す方は、次回試験日程に向けて学習を始めることをおすすめします。


