【2025年版】建築基準法施行令とは?条文・改正履歴・建築設計でよく使うポイントをプロ視点で解説
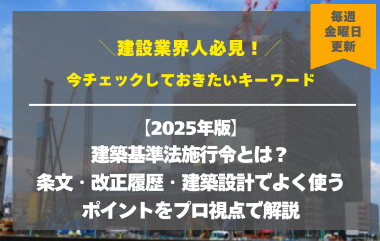
建築基準法施行令は、建築設計や施工管理、確認申請など現場での実務に直結するルールが集約された重要な政令です。しかし、建築基準法との違いや、具体的な用途がわからないとお悩みの人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、2025年最新版として、施行令の概要から、改正履歴のポイント、主要条文までわかりやすく解説します。
目次
建築基準法施行令とは?
建築基準法施行令とは、建築基準法(法律)で定められた基準を具体的に規定するために設けられた政令です。(出典:e-GOV法令検索「建築基準法施行令」)
実務では、次のような具体的な数値基準や方法が必要になる場面が多く、その詳細基準が施行令として定められています。
- 建築物の設置寸法
- 建築に利用できる部材等の上限値
- 設置できる材料や条件分けのルール
建築設計、確認申請、現場監理など、実務を遂行するためには施行令の理解が欠かせません。顧客対応や設計業務の効率化にもつながるため、建築士・施工管理技士をはじめとする建築実務者に必須の知識です。
建築基準法との違い
建築基準法と施行令は、よく混同される要素ですが、実務上の役割が次のように異なります。
建築基準法と施行令の比較表
| 項目 | 建築基準法 | 建築基準法施行令 |
| 種類 | 法律(国会で制定) | 政令(内閣で制定) |
| 役割 | 建築に関する基本的なルールを規定 | 法律の内容を具体化し詳細な基準を規定 |
| 具体性 | 抽象的(例:建築物は安全であること) | 具体的(例:耐火時間・壁厚の数値規定) |
| 位置付け | 法体系の上位 | 法律を補う下位規範 |
| 実務適用例 | 用途地域の概要、建築制限など | 階段寸法、防火構造、耐火性能などの具体基準 |
| 改正権限 | 国会 | 内閣(国土交通省が主導) |
| 参照情報 | ・e-GOV法令検索「建築基準法」・国土交通省「令和4年度改正 建築基準法について」 | ・e-GOV法令検索「建築基準法施行令」 ・国土交通省「建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年度)」 |
建築士や施工管理技士が設計・申請業務を行う際は、次の流れで活用します。
- 法律(建築基準法)で守るべき大枠の条件を把握
- 施行令で具体的な数値や技術基準を確認
たとえば、「建ぺい率・容積率・防火地域の指定は建築基準法で確認」したのちに「防火構造の詳細な仕様、階段寸法などは施行令で確認」することにより、設計の適法性と安全性を確保できます。
また、建築基準法の改正情報について知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
建築基準法施行令の改正履歴【2025年最新】
建築基準法施行令は、時代の変化に合わせて繰り返し改正されてきました。
特に、地震対策の強化、省エネ基準、バリアフリー対応など社会課題に応じて施行令の基準は更新されるため、改正履歴を把握することが設計実務に不可欠です。
ここでは過去の改正一覧と最新改正ポイントをわかりやすく整理します。
改正履歴 一覧表(年度・改正内容・概要)
以下は国土交通省・法令データ提供システムを基にした、建築基準法施行令の主要改正履歴の抜粋一覧です。
※詳細・過去すべての改正は法令データ提供システム(e-GOV法令検索)をご参照ください
| 年度 | 改正内容 | 概要(一例) |
| 1981 | 新耐震設計法 | 耐震基準を大幅改正(新耐震基準) |
| 2000 | 構造基準改正 | 木造建築物の構造規定見直し |
| 2006 | バリアフリー法対応 | 高齢者対応・段差解消義務化 |
| 2013 | 省エネ基準適合義務化 | 断熱性能・省エネ設備基準強化 |
| 2021 | 防火規制緩和・木造耐火基準改正 | 木造耐火建築物の規制緩和 |
| 2023 | 脱炭素対応断熱基準改正 | ZEH対応・断熱性能強化 |
| 2025 | 最新改正(予定含む) | 防火基準の細則見直し、避難安全基準強化、断熱等性能等級6・7への適合義務化 |
出典:e-GOV法令検索「法令改正履歴」
直近の改正ポイント
2025年の最新改正では、脱炭素社会・温暖化対策・防災力向上を目的に次のポイントが改正対象となっています。
- 断熱等性能等級6・7への適合義務化(ZEH水準・断熱性能強化)
- 避難階・避難通路の安全性基準の厳格化(煙制御・排煙基準の強化)
- 木造耐火構造の技術的基準の見直し
(出典:e-GOV法令検索「建築基準法施行令|令和7年4月1日 施行」)
そのなかでも、設計実務においては「確認申請図書で新基準に基づく断熱仕様の明示」「防火構造・避難安全検証法の適用範囲確認」「既存案件での改正適用可否の確認」などの対応が求められます。
上記のうち、木造建築物の構造基準の見直し(2025年4月施行)について知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
設計業務に関わる建築基準法施行令の主要条文
建築基準法施行令には、設計実務で日常的に参照する重要な条文があります。
ここでは建築士・施工管理技士が知っておくべき条文の要点を整理しました。
建築基準法施行令10条・10条3号の解説
10条は「建築物の建築に関する確認の特例」に関する規定です。
建築確認特例の適用条文を定めた内容であり、型式認定建築物や一戸建て住宅(用途条件あり)、その他建築物について、それぞれ適用される詳細な建築基準法および施行令の条文・構造規定・条例規定を区分ごとに整理し、確認申請時の審査簡略化の範囲を規定しています。
(出典:e-GOV法令検索「建築基準法施行令|第10条」)
建築基準法施行令80条の2の要点
80条の2は「無筋コンクリート造の構造方法に関する補則」に関する規定です。
国土交通大臣が安全上必要と認める場合、木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの特殊構造の建築物や、それ以外の構造の建築物について、大臣が定めた技術基準に従った構造方法で施工しなければならないことが定められています。
(出典:e-GOV法令検索「建築基準法施行令|第80条の2」)
建築基準法施行令112条・112条21項(防火・耐火に関する規定)
112条は「防火区画」について定めています。
そのなかでも21項は、換気・暖房・冷房の風道が準耐火構造の防火区画を貫通する場合における内容がまとめられているのが特徴です。国土交通大臣の指定を除き、大臣が定めた構造か認定品を用いた特定防火設備を設置する必要があること、そして、その設備は火災時に自動閉鎖し、遮煙性能を備えることが条件となっています。
(出典:e-GOV法令検索「建築基準法施行令|第112条21項」)
建築基準法施行令113条の要点
113条は「木造等の建築物の防火壁及び防火床」に関する規定です。
防火壁・防火床は耐火構造で火災や倒壊応力に耐える必要があるほか、延焼を防ぐ国土交通大臣指定の構造とする条件がまとめられています。また、開口部は幅・高さ2.5m以下とし特定防火設備を設置すること、加えて、管や風道の貫通時も関連規定が準用されるが、火熱遮断壁等は除外であるといった細かいルールが定められています。
(出典:e-GOV法令検索「建築基準法施行令|第113条」)
建築基準法施行令126条の2のポイント
126条の2は「屋上広場等」のうち、排煙設備の設置に関する規定です。
延べ面積500㎡超えや3階以上の一定規模の建築物には、排煙設備設置が義務付けられています。ただし、小規模区画、学校、階段部分、不燃性倉庫など火災リスクが低い場合は除外されるほか、特定の防火設備等で区画され煙やガスが避難に影響しない場合は別建物扱いとする規定がまとめられています。
(出典:e-GOV法令検索「建築基準法施行令|第126条の2」)
建築実務者が押さえるべきポイント一覧
建築基準法施行令を実務で活かすためには、改正履歴を含む最新情報の把握と、設計時の条文適用の正確さが不可欠です。
特に次の要素は、建築設計・施工・確認で問われる条件であるため、図面・仕様書で法適合を確実に担保できる準備が欠かせません。
- 接道義務
- 耐火・防火規定
- 階段や避難経路の寸法
- 排煙設備の条件 など
また、地域による条例上乗せ基準がある場合も多いため、自治体ごとの要件確認と法令データ提供システムの活用が重要です。
建築基準法施行令についてよくある質問【FAQ】
建築基準法施行令と建築基準法の違いは?
建築基準法は建築に関する基本的ルールを示す法律であり、施行令はその内容を具体化する政令です。たとえば、建築基準法で「安全であること」と示し、施行令で耐火時間や壁厚、階段寸法など具体的数値基準を定めるといったイメージです。
建築基準法施行令112条はどのような場面で必要?
施行令112条は防火地域・準防火地域での耐火・防火構造の具体的な基準が示されています。設計段階で地域の防火区分を確認し、外壁や軒裏の耐火性能、開口部の防火設備の有無などを決める際に必須となる条文であり、確認申請時の重要チェックポイントです。
建築基準法施行令の過去の条文は確認できる?
施行令の過去の条文は、e-GOV法令検索(法令データ提供システム)で履歴付きで確認可能です。改正時期ごとの条文や経過措置も掲載されており、設計変更や既存不適格建築物の扱い、改正対応の確認に役立ちます。確認申請や設計業務の法適合判断時に活用ください。
まとめ
建築基準法施行令は、設計・確認申請・施工管理における適法性と安全性確保の基盤です。
改正内容は毎年更新されるため、国土交通省や法令データ提供システムで最新情報を定期確認することが欠かせません。施行令を活用するためにも、ぜひ内容の理解に力を入れてください。


