モルタル・コンクリート・セメントの違いを徹底比較|強度・値段・用途をプロが解説【2025年版】
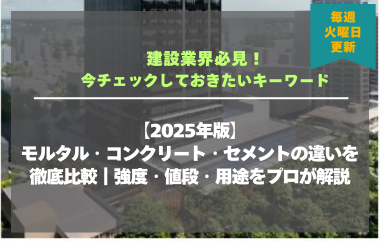
モルタル・コンクリート・セメントは、それぞれ異なる配合でつくられる建材であり、用いる場所や使い分けなどが違います。では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、モルタル・コンクリート・セメントの違いを比較表付きで徹底比較しています。DIY初心者から施工現場での活用まで実践的な選び方がわかる内容になっているので、DIYや施工判断の参考にしてみてください。
目次
モルタル・コンクリート・セメントの違い【比較表付き】
モルタル、コンクリート、セメントは似たように扱われがちですが、実は材料、配合、強度、用途に大きな違いがあります。
本項では、材料や配合、強度、見た目、値段などの違いを項目に分けて詳しく解説します。
| 比較項目 | モルタル | コンクリート | セメント |
| 主材料 | セメント・砂・水 | セメント・砂・砂利・水 | 粉体 |
| 強度 | △(低め) | ◎(高い) | – |
| 見た目 | 滑らか | 粗い | 灰色粉体 |
| 値段 | 高め | 安め | 安価 |
| 用途 | 左官仕上げ、補修 | 基礎・土間打ち | 材料の基材 |
材料・配合の違い
モルタル・コンクリート・セメントはすべて建設現場で使われる材料ですが、それぞれ配合に違いがあります。以下に、3種類の違いをまとめました。
| 材料 | モルタル | コンクリート | セメント |
| セメント | 〇 | 〇 | 〇 |
| 砂 | 〇 | 〇 | × |
| 砂利 | × | 〇 | × |
| 水 | 〇 | 〇 | × |
| 特徴 | 滑らか・密着性 | 高強度・耐久性 |
まず、モルタルは「セメント・砂・水」、コンクリートは「セメント・砂・砂利・水」でつくられており、複数の材料を組み合わせることにより材料として使用できます。
対してセメントは、これらの材料の基礎となる粉体です。料理で例えるなら、モルタルやコンクリートは料理そのものですが、セメントは材料のひとつといった認識となります。
※セメントは材料となる粉体であり、モルタル・コンクリートとは条件が異なるため、次項からは除外して説明を続けます。
見た目の違い・仕上がりの違い
モルタルとコンクリートは、見た目と仕上がりに次のような違いがあります。
| モルタル | コンクリート | |
| 表面の質感 | 滑らかで均一 | 砂利が見え粗い |
| 仕上がりの見栄え | 綺麗で美観性が高い | 凹凸があり仕上げが粗め |
| 色味 | 均一なグレー | 骨材の色が混ざる場合がある |
| 施工後の手触り | さらっとしている | ザラつきがある |
| 仕上げの自由度 | 左官で模様付けなど可能 | 表面仕上げは困難で別途仕上げ材が必要 |
社会資本システム研究室の「施工パッケージ型積算基準」のなかでは、モルタルの厚みは5〜15cm程度にするものとまとめられています。一方でコンクリートは、厚みが数メートルにもなる大きな構造物にも使われているのが特徴です。
そのため、主構造はコンクリート、その表面の仕上げはモルタルで対応するといったケースもよくあります。
強度・耐久性の違い
まず、モルタルは砂利を含まないため作業性が高く、目地埋めや仕上げ施工に適しますが、圧縮強度は10〜15N/mm²程度で、耐荷重性能はコンクリートに劣ります。
対してコンクリートは、砂利(粗骨材)が含まれるため、骨材同士が絡み合い高い圧縮強度を確保できます。国土交通省の「建築構造設計基準の資料」によると、コンクリートの一般的な圧縮強度は、軽量コンクリートで21~27N/mm²、普通コンクリートで24~36N/mm²(また18N/mm²が使われる場合もある)であると記載されています。
値段・コストの違い
モルタルとコンクリートは、次のように1.5〜2.0倍ほどの金額差があり、モルタルのほうが高額になっています。
- 普通コンクリート|19,500~25,000円/m³(粗骨材やセメントの種類で変化)
- モルタル|23,500~39,400円/m³(配合量やセメントの種類で変化)
※新潟生コンクリート協同組合が公開している「生コンクリート標準価格表 令和6年度(2024年度)」参考
これは、安価で大量に用いる砂利があるか・ないかで、内容量にかかるコストに大きな差が出るためです。(砂利が多いほど安くなる)
なお、材料費は時期的なものや経済情勢などによって、常に変動している点に注意してください。
モルタルやコンクリートの作り方
モルタルとコンクリートは、一定の品質を出すための材料比に大きな違いがあります。
たとえば、モルタルとコンクリートは、以下が基本の配合比であり、適切な練り混ぜと施工タイミングが重要です。
| 項目 | モルタル | コンクリート |
| 配合比 | セメント:砂:水 = 1:3:0.5 | セメント:砂:砂利:水 = 1:2:4:0.5 |
| 用途 | 仕上げ・補修 | 基礎・土間 |
| 注意点 | 粘度調整で作業性確保 | バイブレーターで締固め |
なお、夏場は水分の蒸発が早いため打設後の養生(散水・シート養生)が欠かせません。
また、冬場は凍結防止のため温度管理と早期養生、さらに使用する水は水道水程度の清潔な水を使用すること(泥水はNG)など、いくつかの条件に注意しながらつくる必要があります。
モルタル・コンクリートの用途・使い分け【プロ視点で解説】
モルタルとコンクリートは、似た材料でつくられている一方で、強度などに違いがあるため、使われる場面や目的が違います。
ここでは、主な用途と、具体的な使い分けについてわかりやすくまとめました。
主な用途
コンクリートは基礎・土間・駐車場など広範囲かつ高強度が必要な箇所、モルタルは外壁仕上げ・補修・目地埋めなど仕上がり美観が求められる箇所に使います。
まずコンクリートは、骨材を含むため高強度・耐久性を確保でき、大面積施工にも対応可能で施工効率が高いのが特徴です。一方でモルタルは、滑らかで均一な仕上がりが可能なため、左官仕上げ・細部補修・外壁の仕上げに向いています。
以上より「高強度・耐久性重視ならコンクリート」「仕上がり・補修重視ならモルタル」として用途を分けることが大切です。
なおコンクリートは鉄筋と組み合わせることで高い強度を発揮できます。詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください▼
どっちを使うべきか判断基準
2つの材料の判断に迷ったときは、使用箇所の広さ・荷重・目的(仕上げor耐久性)を基準に選ぶのがおすすめです。以下に、判断基準を整理しました。
| モルタルがおすすめのケース | コンクリートがおすすめのケース | |
| 判断基準 | ・外壁仕上げ、補修・小面積の段差・目地補修・見た目・美観を重視する施工 | ・駐車場、基礎、土間など・耐荷重が必要な施工・広範囲施工でコストを抑えたい場合 |
一例として、駐車場での施工は車両荷重に耐える必要があるため、強度が高いコンクリートが向いています。反対に、玄関ステップの段差補修や外壁のクラック補修ではモルタルの方が施工性と仕上がりが良くなります。
上記のうち、土間に使う土間コンクリートに興味をおもちなら、以下の記事をチェックしてみてください▼
モルタル・コンクリートについてよくある質問【FAQ】
モルタルとコンクリートどっちが強い?
コンクリートのほうが強度と耐久性が高いです。骨材(砂利)を含むため圧縮強度は18〜36N/mm²程度で、基礎や駐車場の施工に使われます。一方で、モルタルは砂利を含まず10〜15N/mm²程度で補修・仕上げ向きです。耐荷重の必要性で使い分けましょう。
モルタルとコンクリートどっちが安い?
一般的に、コンクリートの方が安価です。コンクリートは骨材(砂利)が入るためセメント量が抑えられコストが低く、広範囲施工にも適します。対してモルタルは、セメント比率が高く左官作業が必要なため材料費・施工費が高くなりやすく、小面積補修向きです。
モルタルとコンクリートは見た目でどう違う?
モルタルは、滑らかで均一な見た目で仕上がりが綺麗です。反対に、コンクリートは骨材(砂利)が含まれており、施工後の表面に骨材が見えてザラつきが残ります。美観を重視する外壁や補修はモルタル、耐久性を求める基礎・土間にはコンクリートが適します。
インスタントセメントとモルタルの違いは?
インスタントセメントは水を加えるだけで使える簡易材料で、小規模なひび割れ補修などに使われます。モルタルはセメント・砂・水を混ぜて作り、外壁仕上げやブロック目地補修に適します。規模感で言えば「インスタントセメント < モルタル」となります。
コンクリートの上にモルタル仕上げは可能ですか?
可能ですが、施工時の下地処理が重要です。コンクリート表面を清掃・目荒らしし、接着性を高めるプライマーを使用することでモルタルが密着します。駐車場の勾配調整やステップ仕上げで行われることが多く、DIYでも対応可能です。
DIY初心者にはモルタルとコンクリートのどちらが向いていますか?
DIYの施工範囲で選びましょう。小面積補修・仕上げならモルタルが扱いやすくおすすめです。対して、広範囲で強度が必要な駐車場や土間施工はコンクリートが適しています。使い分けることで施工コスト削減と失敗防止につながります。
まとめ
モルタルとコンクリートの違いを正しく理解し、使い分けることは、DIYでも外構施工でも失敗を防ぎ、仕上がりと耐久性を高める重要なポイントです。
コンクリートは骨材を含むため高強度で広範囲の基礎や土間施工に適し、コストも抑えられます。一方モルタルは滑らかで綺麗な仕上がりが特徴で、小面積の外壁補修やブロック目地施工に向きます。この条件や国・研究機関・自治体のマニュアルや示方書などを参考に、材料の選定を検討してみてはいかがでしょうか。


