【2025年版】準耐火建築物を木造で建てるには?仕様・階数・法規制・改正内容をわかりやすく解説
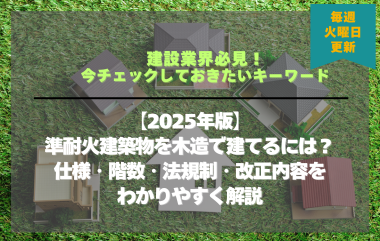
火災による延焼に耐えられる準耐火建築物は、木造でも建てることが可能です。しかし、2025年に建築基準法が改正されるなど、準耐火建築物の考えにも少しずつ変化が起きています。
そこでこの記事では、準耐火建築物の概要や建築基準法の2025年改正内容を説明したのち、設計事例や建築物の条件についてわかりやすく解説します。
目次
準耐火建築物とは?
準耐火建築物とは、火災が発生した際に一定時間、構造が崩壊しないように設計された建築物のことです。(参考:日本木造住宅産業協会「耐火・準耐火構造」)
特に木造建築では、建築基準法といった法律上の条件を満たすことにより、準耐火仕様とすることが可能となります。そこでまずは、準耐火建築物の分類や、耐火建築物との違いについて整理しました。
準耐火構造の分類(イ準耐1・イ準耐2・ロ準耐1・ロ準耐2)
準耐火構造は、以下に示す4種類があり、それぞれに使用可能な材料や構造要件が定められています。
- イ準耐1(主要構造部を通常の火災時の過熱に1時間以上耐える)
- イ準耐2(主要構造部を通常の火災時の過熱に45分以上耐える)
※階段は30分以上 - ロ準耐1(延焼の恐れのある構造が、加熱開始後20分影響を及ぼさない)
- ロ準耐2(耐火被覆しない鉄骨造など)
参考:日本木造住宅産業協会「耐火・準耐火構造」
この分類は、建築基準法第2条に示されている以下の文言を詳細化したものです。
出典:e-GOV法令検索「建築基準法第2条」
木造で準耐火建築物を建てる際には、上記の条件にもとづき、建物の階数や用途、構造材に応じて適切な準耐火構造区分を選定する必要があります。
準耐火建築物と耐火建築物との違い
準耐火建築物と耐火建築物の違いは、主要構造部に要求される耐火性能の高さと持続時間にあります。参考として以下に、2種類の違いを整理しました。
| 準耐火建築物 | 耐火建築物 | |
| 耐火構造 | 45~60分の耐火性能が必要 | 60~120以上の耐火性能が必要 |
| 用いられる構造 | 主に木造や一部鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造や鉄骨造 |
| 主な建築物 | 木造3階建て共同住宅、福祉施設など | 病院、大型商業施設、高層マンション |
準耐火建築物は比較的柔軟な設計が可能で木造対応も可能です。一方で耐火建築物は法的制限が厳しく、材料や構造選定の自由度が低くなります。
そのため設計段階で、用途・立地・コスト・施工方法を総合的に考慮して、どちらの耐火建築物にするのかを検討しなければなりません。
また建物で発生する火災の理由を知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
2025年4月の建築基準法改正で準耐火建築物はどう変わる?
2025年に施行される建築基準法の改正では、木造を含む準耐火建築物の「設計の自由度」が広がることとなっています。
ここでは、準耐火建築物に関係する改正ポイントと、木造建築への影響についてわかりやすくまとめました。
(参考:国土交通省「建築基準法・建築物省エネ法 改正法制度説明資料(令和6年9月)」)
主な改正ポイント|75分・90分耐火・燃えしろ設計とは?
2025年の建築基準法改正では「75分・90分準耐火構造」「燃えしろ設計」の導入が拡大され、木造でも中規模建築物に対応できる道が開かれます。
- 75分準耐火構造:一部の小規模商業施設(平屋・延床500㎡以下)で適用
- 90分準耐火構造:準工業地域などでの福祉施設や教育施設で採用増加
- 燃えしろ設計:断面欠損を考慮し厚さ90mm以上の柱を使用、せっこうボード不要
従来、準耐火構造は「45分・60分」の性能が基準となっていましたが、今回の法改正により「75分・90分の耐火区分」が新たに認定されました。これまではおおむね小規模な住宅建築でしか適用できなかった木造を、用途地域や延べ面積の条件によっては中規模非住宅建築も木造で実現できるようになります。
また「燃えしろ設計」は、木材が燃えても内部が耐火性能を維持できるよう厚みを確保した構造のことです。これも改正によって準耐火構造として明確に位置付けられました。
改正で拡大する木造建築の可能性
2025年の建築基準法改正により、準耐火建築物の要件が緩和・多様化したことで、木造建築の適用範囲が住宅だけでなく、非住宅・中規模施設にも拡大しつつあります。
まず、これまでは木造で中規模建築を建てる際には、防火規制の壁によりRC造や鉄骨造が前提とされていました。しかし、今回の法改正で、次のような技術的・制度的な変更が加わろうとしています。
- CLT(直交集成板)活用の明文化
- 地域材活用への補助制度との連動
(参考:林野庁「地域材利活用促進支援対策」) - 木造のZEB Ready基準対応が可能に
法改正によって、準耐火建築物のバリエーションが従来よりも多くなりました。構造設計の自由度が大幅に向上したほか、特に木造による非住宅建築の可能性が広がっているため、鉄筋コンクリートや鉄骨造以外での設計の選択肢が増えています。
また木造以外の改正内容をチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです。
木造2階建て・3階建てでも準耐火建築物にできる?
結論として、木造2階建て・3階建てでも準耐火建築物として建築することが可能です。
設定されている用途・規模・立地に応じて建築基準法の要件を満たせば、木造でも防火・耐火性能を確保した中層建築を実現できます。参考として以下に、合法的に準耐火建築物とみなされる要件をまとめました。
| 階数・用途 | 適用要件 | 適合する構造例 |
| 木造2階建て (戸建て住宅) | 地域により準耐火不要 | 通常の在来工法も可 |
| 木造2階建て (店舗付き住宅など) | 階数+用途により準耐火義務あり | ロ-2構造+石膏ボード被覆 |
| 木造3階建て共同住宅 | 原則「準耐火建築物」が必要 | イ-2構造、ロ-2構造対応が必須 |
たとえば、木造3階建ての共同住宅では、延床面積500㎡超で準防火地域内に位置する場合には「イ-2構造」(45分準耐火)や「ロ-2構造」での設計が求められます。そのため、主要構造部に石膏ボードの二重貼りや認定準耐火被覆材を使うことにより、建築確認をクリアできるイメージです。
用途地域や規模によっては、木造3階建てでも法的に問題なく準耐火建築物にできる時代ですので、設計時の選択肢が広がっている点に注意しましょう。
木造準耐火建築物の設計・施工事例
国内ではすでに、準耐火建築物を木材でつくる事例が数多く登場しています。
そのなかでも国や自治体が公表している最新の事例を2つ整理しました。
【事例1】LVLを用いた木造2階建て学校
出典:全国LVL協会「LVLを用いた木造準耐火建築物の設計事例」
全国LVL協会が発表した「LVLを用いた木造準耐火建築物の設計事例」によると、都市中心部の準防火地域に設置できる木造の学校を想定し、LVLの2階建て学校が設計されました。
木材を薄くスライスして接着した「単板積層材」を用いた学校であり、窓ガラスを除く外壁や柱、屋根まで、そのほとんどが木材で構築されています。
【事例2】
出典:日本木造住宅産業協会「木造軸組工法による耐火建築物実例集(2020年3月)」
茨城県の事例として、特別養護老人ホームが準耐火建築物として設計されました。
主に管理棟、デイサービス棟が準耐火建築物としてつくられており、燃えしろ設計を用いて設置された巨大な木材がそのまま老人ホームのあらわし(露出させる建築の仕上げ方法)として用いられています。
また設計のみならず、木材なども建築基準法の改正に合わせて改良が加えられています。詳しい情報を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください。
まとめ
火災の延焼に長時間耐える「準耐火建築物」は、木造でも建てることが可能です。
また、2025年の法改正によって、新たに75分・90分準耐火や燃えしろ設計の活用が広がり、住宅のみならず、非住宅でも木造を選べる時代がやってこようとしています。現段階でまだ事例はほとんど登場していませんが、今後、中規模建築物にも木造が活用されていくと予想されます。


