【2025年最新】全国の土木遺産を徹底ガイド|有名スポットからカード収集まで詳しく解説
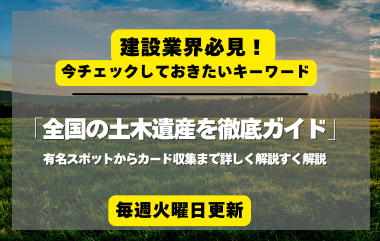
土木遺産は、平成12年に土木学会より設立された選奨土木遺産委員会から選出されている「保存に資するべき土木構造物」です。では、どのような土木遺産が登録されているのでしょうか。
この記事では、全国にある土木遺産と有名スポットについて解説したのち、コレクション要素のある土木遺産カードについて紹介します。
目次
土木遺産とは?わかりやすく解説
出典:土木学会「選奨土木遺産」
土木遺産とは、次のような人々の暮らしを支えてきた構造物(社会インフラ)のうち、歴史的・技術的に価値が高いと評価されたもののことです。
| 対象の土木構造物 | 主な種類 |
| 交通 | 道路、鉄道、港湾、河川、航空、灯標 |
| 防災 | 治水、防潮、防風 |
| 農林水産業 | 灌漑、干拓、排水、営林、漁港 |
| エネルギー | 発電、炭田、鉱山 |
| 衛生 | 上下水道 |
| 産業 | 工業用水、造船 |
| 軍事 | - |
現代の土木技術の礎(いしずえ)となった構造物は、文化遺産と同じように後世へと受け継がれるべき存在だと言えます。
そのため日本では、土木技術・事業の発展を目的に活動する「土木学会」が中心となり、優れた土木構造物を平成12年から「選奨土木遺産」として選定をスタートしました。1年ごとに地域に根差した価値や当時の革新的な技術を伝える貴重な構造物をピックアップし、専用ホームページにて選出結果が公開されています。
土木遺産の選定基準と認定プロセス
土木遺産の認定基準は明確にルール化されていませんが、主に以下のような評価で土木遺産が選出されています。
- 社会アピール(現在も持続している or 歴史的な社会的意義・文化的価値がある)
- 土木技術アピール(先輩技術者の尽力・先見性・使命感に対する理解などがある)
- まちづくりへの活用(地域の自然や歴史・文化の一部となる地域資産である)
参考:土木学会「土木学会選奨土木遺産の趣意と内容」
なお選定は、専門家の調査・評価を経て、秋頃に発表されます。毎年20種類ほど選出され、認定された構造物には記念銘板が設置されて、公式サイトを通じて広く周知されるのが特徴です。
選奨土木遺産と近代土木遺産の違い
「選奨土木遺産」は土木学会によって2000年(平成12年)から毎年開催されている制度であり、地域に埋もれがちな構造物にスポットライトを当てることが目的です。
一方で「近代土木遺産」は建築学会や文化庁などによる近代化遺産の一環として位置づけられており、文化財登録を意識した分類となっています。
つまり、選奨土木遺産は「技術・構造」をメインとした実務者主体の認定であり、近代土木遺産は「文化財」をメインとした公的支援のある枠組みであることのが主な違いです。それぞれ主催が違うほか、目的が異なる遺産だと覚えておきましょう。
全国の土木遺産一覧【有名スポット】
ここでは、全国の代表的な土木遺産を地域ごとに紹介します。旅行や観光をするときに、土木に触れる参考にしてみてください。
北海道|旭橋
出典:土木学会「北海道の選奨土木遺産」
旭橋は昭和7年に建設された「大型のバランスト型のタイドアーチ橋」です。竣工した当時の建築技術を今に伝える歴史的にも貴重な資料として、土木遺産に登録されました。
| 登録年 | 平成14年度 |
| 住所・アクセス | 北海道旭川市常盤通3丁目 |
東北|尻屋埼灯台
出典:土木学会「東北地方の選奨土木遺産」
尻屋埼灯台は明治9年にR.H.ブラントンによって建設された「近代灯台建設の始まりを伝える貴重な施設」です。現存の煉瓦造灯塔のなかでも国内最大級であり、巨大建造物として登録されています。
| 登録年 | 平成18年度 |
| 住所・アクセス | 青森県下北郡東通村尻屋字尻屋崎1番1 |
関東|黒川発電所膳棚水路橋
出典:土木学会「関東地方の選奨土木遺産」
黒川発電所膳棚水路橋は大正10年に建設された「X字型に筋交いの入った3本橋脚の水路協」です。大正期のRCラーメンは希少であることから土木遺産として登録されました。
| 登録年 | 平成20年度 |
| 住所・アクセス | 栃木県那須郡那須町稲沢1046 |
中部|鬼ヶ城歩道トンネル
出典:土木学会「中部地方の選奨土木遺産」
鬼ヶ城歩道トンネルは大正14年につくられた「尾鷲地方にある煉瓦トンネル群」のひとつです。整えられたデザインの抗門を備えており、大正期最長の道路用煉瓦トンネルとして、土木遺産に登録されました。
| 登録年 | 平成15年度 |
| 住所・アクセス | 三重県熊野市木本町1660 |
関西|梅小路機関車庫
出典:土木学会「関西地方の選奨土木遺産」
梅小路機関車庫は大正3年に設置された「蒸気機関車の回転車庫」です。日本の近代化と復興・成長を支えた蒸気機関車の歴史を伝えたほか、動態保存された世界最大級の蒸気機関庫として、土木遺産に登録されました。
| 登録年 | 平成16年度 |
| 住所・アクセス | 京都府京都市下京区歓喜寺町3番地 |
中国・四国|火ノ山砲台
出典:土木学会「中国地方の選奨土木遺産」
火ノ山砲台は明治24年に「関門海峡防備のために明治期に築造された要塞」です。戦争の歴史を残す構造物であり、現在でもその姿を留めている貴重な土木遺産として、土木遺産に登録されました。
| 登録年 | 平成28年度 |
| 住所・アクセス | 山口県下関市みもすそ川町7-14 |
西部(九州・沖縄)|筑後川デ・レーケ堤
出典:土木学会「西部地方の選奨土木遺産」
筑後川デ・レーケ堤は、明治23年に有明海のガタ土堆積を防ぎ「航路確保を行うためにつくられた導流堤」です。完成から100年以上経った現在もその役割を果たしている壮大な石導として、土木遺産に登録されました。
| 登録年 | 平成20年度 |
| 住所・アクセス | 福岡県大川市小保 |
日本・世界の土木遺産の共通点&相違点
日本と世界にある土木遺産は、それぞれ共通点と相違点があります。以下に2つの要素の違いをまとめました。
| 日本の土木遺産 | 世界の土木遺産 | |
| 構造物の種類 | 水路・橋梁・ダム・港湾・隧道などが中心 | 運河・巨大橋梁・鉄道・工業施設・港湾など大規模が多い |
| 特徴 | 地形や自然に合わせた緻密な施工、美しさと機能の融合 | 大胆でスケールの大きい設計、産業革命期の技術革新の象徴 |
| 目的・背景 | 農業用水・交通・災害対策など生活密着型 | 経済発展・軍事・交易など国際的・戦略的な要素が強い |
| 保存体制 | 土木学会などの専門団体が選定・保存活動を実施 | ユネスコや各国政府による世界遺産・文化財指定が多い |
| 価値評価 | 地域社会との関わりや歴史的経緯を重視 | 技術革新の歴史・人類への影響度を重視 |
参考:土木学会「世界遺産の中の土木遺産」
日本の土木遺産は、地域性や自然条件に適応した技術が特徴であり、水に関する構造物(水路、橋、ダムなど)が多い傾向にあります。一方で、ロンドンのタワーブリッジ、パナマ運河などの世界の土木遺産は、工業化といった要素をもつ大規模かつ機能美を備えた構造物が中心です。
それぞれ「人々の暮らしを支えた技術的成果」という共通点を持つことに対し「地域性と技術背景」という相違点をもっています。
土木遺産カードの入手方法と配布エリア
出典:国土交通省 九州地方整備局「九州インフラカード」
最近では、ダムカードに続く形で「土木遺産カード」というコレクション要素のあるアイテムなどが配布されています。主に観光案内所や管理団体で無料で配られており、観光などの一環で収集を楽しむことが可能です。
例えば、北海道では土木学会北海道支部が主導のもと、シビルネット北海道カードというものを提供しています。また九州では九州インフラカードという名称でカードが配布されているなど、地域によって異なるデザインのカードを楽しめるのが魅力です。
まとめ
土木遺産は、単なる「古い構造物」ではなく、社会の発展と人々の暮らしを支えた重要な記録です。地域の技術、歴史、文化を体感できる貴重な資源として、観光・教育の面でも注目が集まっています。
本記事で紹介した土木遺産一覧のみならずほかにも数多くのインフラ構造物があるので、ぜひ公式サイトの情報などもチェックしてみてください。


