建設業における長寿命化とは?コンクリートの耐用年数を延ばす補修方法やメリットを解説
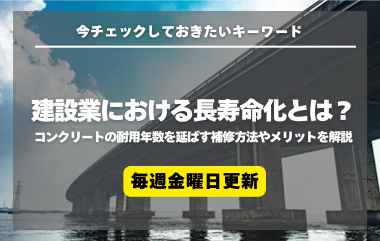
日本中で利用されているインフラ施設を長持ちさせるためには、長寿命化の対策を講じることが欠かせません。では、日本全体を見てどれくらいのインフラ施設に長寿命化対策を講じる必要があるのでしょうか。
そこでこの記事では、日本全体におけるインフラ施設の老朽化の状況を解説したのち、長寿命化のためにできることや実施するメリットについて紹介します。
目次
建設業が実施するインフラ施設の長寿命化とは?
建設業で実施されている長寿命化とは、インフラ施設が壊れて使えなくなるまでの時間を延ばし、安全に利用し続けられるよう「効率的な修繕・更新を計画する施策」のことです。
なお長寿命化はただ構造物等を補修・補強するのではなく、優先順位決めをして無駄のない計画を立てることも含まれています。
インフラ施設を管轄している都道府県および市町村ごとに長寿命化計画を立てる必要があり、建設企業はその計画に合わせて点検や補修・補強業務を実施しなければなりません。また建設企業が委託を受け、長寿命化計画を実施する場合もあります。
2025年におけるインフラ長寿命化計画の状況
長寿命化計画はすでに日本全国で取り組まれています。
例えば、平成25年に公開された「インフラ長寿命化基本計画(ロードマップ)」にもとづいて動いている自治体がほとんどであり、すでに補修・補強するインフラ施設の優先順位決めを完了し、何巡目かの工事を進めている地域も少なくありません。
出典:国土交通省「インフラ長寿命化基本計画(ロードマップ)」
なかには、計画の策定のみならず、新技術の導入等に進んでいる企業もあります。具体的な取り組みを後述しているので、ぜひチェックしてみてください。
個別施設計画と長寿命化計画の違い
長寿命化計画を知るうえで違いを理解しておきたいのが「個別施設計画」です。基本的に2つの要素は同じものだと取り上げられることも多いのですが、実際には次のような違いがあります。
- インフラ長寿命化計画は施設全体を対象として動き方を決める
- 個別施設計画は施設ごとの点検・修繕・更新の計画を立てる
具体的に言うと、個別施設計画は各施設に求められる必要な機能を維持するために中長期にわたって整備の内容や時期、費用等を詳しく計画するのが特徴です。A施設は2025年に「100万円をかけて補修する」、B施設は2030年に「500万円をかけて補強する」というように、個別の計画を立てていきます。
インフラ施設の老朽化の現状
国土交通省が公開している「社会資本の老朽化の現状と将来」によると、2023年3月時点の調査で建設後50年を超える施設が、次の割合になっていることが判明しています。
| インフラ施設の種類 | 日本全体における総数 | 建設後50年超えの割合 |
| 道路橋 | 約73万橋 | 37%程度 |
| トンネル | 約1万2,000本 | 25%程度 |
| 河川管理施設 | 約2万8,000施設 | 22%程度 |
| 水道管路 | 約74万km | 9%程度 |
| 下水道管渠 | 約49万km | 7%程度 |
| 港湾施設 | 約6万2,000施設 | 27%程度 |
なかでも老朽化の割合が大きいのが、河川上に交差するように設置されている道路橋です。現時点で4割近い道路橋が耐用年数を迎えているほか、2040年には75%まで数値が上昇すると危惧されています。
出典:国土交通省「建設後50年以上経過する社会資本の割合」
また、ほかの施設についても徐々に老朽化する割合が増加する予定です。このことから建設業界では、早急な長寿命化対策が必要であることがわかります。
インフラ施設の長寿命化の対策
インフラ施設の長寿命化のために実施する対策は「修繕」「更新」の2つです。それぞれの特徴を以下で解説します。
修繕
長寿命化のために実施する修繕は、劣化・損傷が起きている箇所を補修して老朽化の進行を防ぐ対策です。コンクリートの場合で言えば、次のような補修を実施します。
- ひびわれ補修
- 断面修復工
- 防水対策
これまで実施されていた「壊れかけてから補修をする事後保全型」の対策ではなく、損傷が発生したら「早い段階で対策をする予防保全型」として補修を実施します。
出典:国土交通省「予防保全によるメンテナンスへの転換について」
小さな範囲の補修だけで劣化の進行を抑制できるため、トータルコストを抑えられるのが特徴です。
更新
更新とは、各施設に用いられている部材ごとの寿命を決め、寿命を迎えた段階で取り替えなどを実施する対策のことです。
例えば、道路橋に設けられているガードレールに15年という寿命が設けられている場合には、5年ごとに塗り替え等の予防保全を実施したのち、15年経過したら既存のガードレールを取り除き、新たなガードレールを設置するといった対策を実施します。
どんなに長寿命化対策を実施しても、いずれは状態が悪くなっていくため、部材ごとに寿命を決めたうえで更新のタイミングを計画していかなければなりません。
インフラ施設の長寿命化を図るメリット
インフラ施設の長寿命化計画を立てると、どのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは全国の自治体(都道府県・市町村)および委託企業が取り組むメリットを解説します。
修繕や建て替えの費用を削減できる
長寿命化計画は、損傷を見つけたときに補修をするような行き当たりばったりの動き方と違い、計画的に修繕や更新を実施できるのが特徴です。
例えば壊れてしまってから補修をした場合、壊れた部分だけではなく、そこから波及して生まれた損傷など、広範囲の修繕が必要になります。一方で計画的に補修内容を決めておけば、小規模な修繕だけで済むため、壊れてから補修するよりも少ない費用でインフラ施設を維持できるのが魅力です。
ひとつの施設当たりの費用負担を削減できることから、自治体が管轄している施設管理にゆとりを生み出せるようになります。
各自治体の事業予算を無駄なく使える
長寿命化計画を実施して無駄な支出を抑えられるようになれば、施設ごとに優先順位を決めて、その順番で維持管理業務を進行できるのが魅力です。
例えば、あまり使われていない施設が老朽化しているせいで、そちらにばかり修繕費用がかかっている自治体も少なくありません。一方で長寿命化計画で「交通量が多い地域」「生活者ネットワークが密な地域」などルールを決めてしまえば、どの施設を優先して対策すべきかを明確化できます。
少子高齢化によって過疎化が進んでいる自治体なども多いことから、必要なこと・無駄なことを具体的に計画し、効果のある維持管理を実施できるようになるのが魅力です。
限られた資源を無駄にせずに済む
インフラ施設の長寿命化を図り、施設を長持ちさせることができれば、その分だけ取り壊しの必要が減り、資源を無駄にせずに済むのもメリットです。
コンクリートなどは産業廃棄物として処理しなくてはならず、すべての材料を再利用できるわけではありません。またコンクリートに使われる材料などは有限であることから、材料を無駄にしない対策としても効果を発揮します。
環境対策にもつながるため、2050年目標のカーボンニュートラルを目指す日本において、長寿命化計画は重要な取り組みだと言えるでしょう。
まとめ
老朽化しているインフラ施設が多い日本では、限られた予算のなかで無駄のない維持管理を実施しなければなりません。その際に役立つのが長寿命化計画であり、無駄のない維持管理の計画を立てられます。
現在進行形で実施されていることから、今後の老朽化問題の改善から目が離せません。


