電子商取引とは?建設業でCI-NETを利用するメリット・デメリットをわかりやすく解説
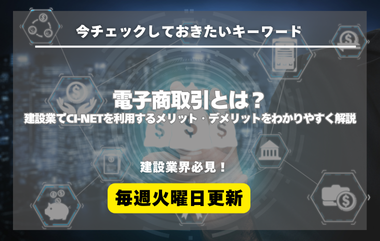
建設業における業務の見積もりや請求等の作業では、手続きの効率化を図るために電子商取引という取引手法が利用されています。そのなかでも、建設企業でよく利用されているのが建設業振興基金より提供されている「CI-NET」と呼ばれるシステムです。
そこでこの記事では、電子商取引に利用するCI-NETの概要について解説したのち、企業が利用するメリット・デメリットをわかりやすく紹介します。
目次
電子商取引ができるCI-NETとは
出典:建設業振興基金「CI-NETの仕組み」
CI-NETは、建設業界全体の生産性を高める取り組みとして開発された、電子商取引のシステムです。正式名称を「Construction Industry NETwork」と言い、次のような作業をすべてシステム内で完結できます。
- 見積依頼(商談)
- 注文
- 請求
- 決済
従来の建設業界では、上記の作業をすべて人力で対応しており、受発注者間で書類の郵送をし合う、営業担当者が直接持参するなど、手間のかかる作業が何度も発生していました。一方でCI-NETを使って電子商取引をすれば、すべてのやり取りを電子化できます。
CI-NETの利用にかかる費用
CI-NETは、有料で提供されているシステムであり、以下に示すように、企業識別コードの取得や電子証明書のため3年ごとの支払いが必要です。
| 1年目(税込) | 2年目(税込) | 3年目(税込) | 4年目(税込) | |
| 企業識別コード (資本金1億円以下の企業) | 17,600円 | 0円 | 0円 | 22,000円 |
| 企業識別コード (資本金1億円超えの企業) | 35,200円 | 0円 | 0円 | 44,000円 |
| 電子証明書 | 9,350円 | 0円 | 0円 | 9,350円 |
なお、初回の発行費用よりも、3年後に発生する更新費用のほうが若干高額になります。
CI-NETを導入する建設企業の傾向
建設業振興基金が2020年に実施した調査によると、CI-NETは約97%が受注者としての立場で利用しています。
出典:建設業振興基金「CI-NET 利用状況調査 実施状況報告(案)」
また、CI-NETを利用してから、電子商取引で業務受注をする割合について、4割程度の企業が増えていると回答をしています。
出典:建設業振興基金「CI-NET 利用状況調査 実施状況報告(案)」
さらには以下のように、注文請けや出来高報告・請求、購買見積もりの回答など、営業活動で発生する業務の対応として利用されている傾向が強いです。
出典:建設業振興基金「CI-NET 利用状況調査 実施状況報告(案)」
上記のようなポイントについて、現在アナログな手法で動いているという場合には、業務効率化や生産性向上のためにも、CI-NETを利用した電子商取引へシフトチェンジすることが望ましいと言えるでしょう。
電子商取引に関わる法律とCI-NETの位置付け
まずCI-NETは、国に定められた以下の基準にもとづいて開発された電子商取引のシステムです。
なかでも、建設産業で平成3年12月に公示された「建設業における電子計算機の連携利用に関する指針」は、建設業界における電子商取引の利用についてまとめられている取引指針です。
CI-NETは上記のような国の基準にもとづいたシステムであることから、国や自治体などの発注者からも利用が認められています。法令遵守にも寄与していることから、談合などの事例が起きる恐れのある建設業界の取引に、透明性をもたらしてくれます。
CI-NETで電子商取引をするメリット
建設業界に属する企業が、CI-NETを利用して電子商取引をするメリットを3つまとめました。
建設業務の生産性向上
CI-NETを利用して電子商取引を実施すれば、今まで手間のかかっていた次のような費用・労力的なコストを削減しやすくなります。
- 電話やFAXで書類を送付したと連絡する手間
- 書類の印刷費や郵送費
見積もりや請求等の手続きをすべて電子上で対応できることから、ペーパーレス化を実現できます。また、そこに発生する人件費や維持費(紙や封筒)などを削減できるため、手続きに関するコストダウンを目指せるのが魅力です。
さらにはCI-NETを利用することにより、共有するデータの書式が統一されます。他社の情報も含めて、どこに何が書いてあるのか見やすい書類を作成できるのもメリットです。
印紙税負担の軽減
CI-NETの電子商取引へシフトチェンジすれば、いままでに注文請求のために支払わなければならなかった印紙代を節約できます。
| 契約金額 | 印紙代 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上10万円以下 | 200円 |
| 10万円超え50万円以下 | 400円 |
| 50万円超え100万円以下 | 1,000円 |
| 100万円超え500万円以下 | 2,000円 |
| 100万円超え1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超え5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超え1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超え5億円以下 | 10万円 |
一部引用:国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
なお電子商取引の場合には、印紙代がかかりません。建設業では、注文請求の金額によっては高額な印紙代が発生することから、費用負担の削減につながります。
データドリブンの実現
CI-NET上で作成した電子データは、ログインすればいつでも自由に閲覧が可能です。過去のデータのチェックにも対応しており、傾向を分析しやすいのがメリットとなります。
例えば調達資金の抑制などは、複数のデータを比較するからこそ判断が可能です。すべて紙の書類で管理している場合、なかなか傾向を掴めず、営業担当者の勘頼りになってしまうことから、CI-NETによる電子商取引がデータドリブンの実現に役立つのです。
CI-NETで電子商取引をするデメリット
複数のメリットをもつCI-NETですが、電子商取引をする際に2つのデメリットが発生することに注意しなければなりません。
CI-NETの運営状況に依存する
CI-NETを使った電子商取引は、CI-NETのデータベース等に依存するため、もしエラーなどが起きた場合には、データ閲覧や作成に対応できません。
もちろん、高いセキュリティ対策が施されていますが、いつサイバー攻撃を受けてしまうのか予期できない点に注意が必要です。
CI-NETに対応していない企業とはやり取りができない
CI-NETを使った電子商取引は、CI-NETを導入している企業同士でしかできません。そのため、CI-NETを導入していない企業とは、効率的なやり取りができない点に注意が必要です。
またはじめてCI-NETを導入するとき、社内にIT関連の知識がある人材がいなければ、うまく使いこなせない点にも注意しなければなりません。登録や操作は簡単ですが、慣れるまでに時間がかかる点に気を付けてください。
まとめ
電子商取引は、企業間で発生する「見積依頼(商談)」「注文」「請求」などの作業をすべて電子化できる便利な取引の手法です。なかでも建設業界ではCI-NETというシステムが利用されており、導入企業数が非常に多いため、すぐに関係企業等と手続きを開始できます。
業務の生産性向上はもちろん、手間や維持費といったコストの削減にも役立つため、この機会に電子商取引ができるCI-NETに登録してみるのはいかがでしょうか。


