【令和7年最新】労務単価表まとめ!過去からの推移や令和8年の予測を解説
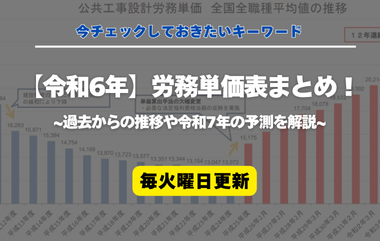
国土交通省が毎年公開している労務単価は、建設従事者の賃金に関わる重要な指標です。そして令和7年3月、新たに労務単価が更新・適用されます。では、令和6年の労務単価からどのような変化があったのでしょうか。
この記事では、令和7年度における労務単価や、過去からの推移を解説したのち、令和8年度以降の単価予測について紹介します。
目次
労務単価とは
まず労務単価とは、正式名称を「公共工事設計労務単価」と言い、建設従事者の賃金の指標を示す単価です。
例えば、ひとり当たり8時間の労務と設定したうえで、1日の単価を「円」で示します。各都道府県ごとに労務単価が設定されているため、業種に合わせて単価をチェックしなければなりません。
毎年10月に国土交通省(農林水産省)が労務単価の状況を調査し、その結果をもとに翌年の3月に最新の労務単価を公表するのが一連の流れです。全51職種分の単価情報がまとめられていることから、建設従事者は、労務単価に基づいて見積もり等を作成します。
労務単価を使った見積もりの計算方法
労務単価は、単純にひとり当たりの手間賃を示す指標であることから、そのままの金額では使えません。なお建設業界では「土木工事標準歩掛」という書籍に照らし合わせながら、費用を算出します。
例えば「集水井内足場設置・撤去」の歩掛は次のとおりであり、後述する労務単価と数量をかけ合わせて見積額を算出します。
出典:国土交通省「令和6年度土木工事標準歩掛 改定概要」
普通作業員の労務単価が23,000円だった場合には、0.51倍にした費用で算出します。そのままの単価では使えない点に注意してください。
令和7年度時点の労務単価
以下に、国土交通省が公開している「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の資料をもとに、令和7年時点における最新の労務単価を整理しました。
なお労務単価として掲載しているのは、多くの工事作業に関わる主要業種と、主要都市エリアに限定しています。
| 主な業種 | 北海道 | 東京都 | 愛知県 | 大阪府 | 福岡県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊作業員 | 25,300円 | 29,900円 | 29,200円 | 27,400円 | 26,700円 |
| 普通作業員 | 20,900円 | 26,800円 | 24,800円 | 23,300円 | 23,100円 |
| 軽作業員 | 18,900円 | 18,500円 | 19,100円 | 16,300円 | 16,100円 |
| とび工 | 28,600円 | 32,900円 | 31,900円 | 29,400円 | 28,500円 |
| 鉄筋工 | 29,600円 | 32,600円 | 30,400円 | 28,800円 | 27,600円 |
| 運転手(特殊) | 25,900円 | 30,500円 | 29,500円 | 27,300円 | 25,900円 |
| 運転手(一般) | 21,500円 | 25,400円 | 26,700円 | 23,700円 | 23,500円 |
| 型わく工 | 27,200円 | 31,700円 | 32,200円 | 31,500円 | 27,200円 |
| 大工 | - (令和6年28,100円) | 30,400円 | 33,400円 | 29,100円 | 28,300円 |
| 左官 | 30,200円 | 33,000円 | 29,200円 | 28,500円 | 28,100円 |
| 交通誘導警備員A | 17,500円 | 20,200円 | 20,900円 | 17,400円 | 16,600円 |
| 交通誘導警備員B | 14,600円 | 17,600円 | 17,200円 | 15,000円 | 14,900円 |
全体的な傾向をみると、東京都のように人口が集中しており、かつ物価の高いエリアなどでは単価が高く設定される傾向があります。対して、主要都市のなかでも地方に位置する北海道や福岡県は、ほかのエリアよりも単価が低めに設定されている状況です。
過去からの労務単価の推移【グラフ掲載】
出典:国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」
現在の日本における建設業の労務単価は、平成25年を皮切りに上昇傾向が続いています。13年連続での上昇であることから、今後も大きく労務単価が伸びていく見込みです。
なお、労務単価が最低だった平成24年時点と比べると、令和7年の労務単価は比率+85.8%と、1.9倍以上の金額増になりました。また、昨年度の令和6年における労務単価(平均23,600円)と比べても、令和7年度は比率+6.0%(平均24,852円)となり、大きな伸びをみせています。
ほかにも、主要業種のなかでも高い伸びをみせているのが「軽作業員(前年比+6.8%)」「左官(前年比+6.8%)」です。少子高齢化による熟練作業員の引退、また2025年問題により人手不足が深刻化している職種ということもあり、単価を上昇させて人材確保に力を入れていることがうかがえます。
令和6年度からの労務単価の変化
毎年更新される労務単価ですが、令和7年度は令和6年度からどれくらいの変化が起きているのでしょうか。参考として以下に、各職種ごとにおける単価の変化を整理しました。
| 職種 | 令和6年度の労務単価 (全国平均) | 令和7年度の労務単価 (全国平均) | 前年度からの比率 |
| 特殊作業員 | 25,598円 | 27,035円 | +5.6% |
| 普通作業員 | 21,818円 | 22,938円 | +5.3% |
| 軽作業員 | 16,929円 | 18,137円 | +6.8% |
| とび工 | 28,461円 | 29,748円 | +4.8% |
| 鉄筋工 | 28,352円 | 30,071円 | +5.9% |
| 運転手(特殊) | 26,856円 | 28,092円 | +5.0% |
| 運転手(一般) | 23,454円 | 24,605円 | +5.4% |
| 型枠工 | 28,891円 | 30,214円 | +5.1% |
| 大工 | 27,721円 | 29,019円 | +6.3% |
| 左官 | 27,414円 | 29,351円 | +6.8% |
| 交通誘導員A | 16,961円 | 17,931円 | +5.7% |
| 交通誘導員B | 14,909円 | 15,752円 | +5.7% |
上表からわかるように、1日当たりの労務単価が1,000〜2,000円ほど上昇しています。上昇率に差はあるものの、すべての職種の労務単価が上昇傾向です。
労務単価が変化する理由
毎年のように変化している労務単価ですが、いったい何が影響して単価の変動が起きているのでしょうか。ここでは、日本の労務単価に影響する重要ポイントを2つまとめました。
建設業界の人手不足
令和7年まで継続的に単価の上昇が続いているのは、建設業界で人手不足が加速しているためです。
例えば国土交通省が令和6年12月に実施した「建設労働需給調査結果」によると、建設業における6職種においては平均0.6%(全職種でマイナス)の人手不足が起きていることがわかりました。
出典:国土交通省「建設労働需給調査結果」
特に地方部における人手不足が加速しており、平成24年以降は継続的に不足の状態が続いています。
出典:国土交通省「建設労働需給調査結果」
なお、少子高齢化などの影響も重なり、今後も人手不足問題は加速していくものだと予想されます。
以上より、労務単価は人手不足の場合は単価を高く、人材が多い場合には単価を低くする傾向が強いです。特に現在は人手不足が続いているため、毎年のように増加が続いているのだとうかがえます。
円安の加速
現在の日本では、世界との貿易の関係で円安の状況が続いています。
例えば、円/ドルを比較した場合、2021年当たりから急激な円安が進んでおり、現在では150円/ドルを超えるなど、輸入に依存している日本では、業界を問わず物価高が続いている状況です。
出典:財務省『2024年 主要通貨為替見通し〜「強い円」は今度こそ戻ってくるのか?~』
建設業界で言えば、建築資材などを海外から輸入します。また、建設工事に利用する重機や工具の材料なども海外からの輸入が主です。そういった状況下で建設業をうまく立ち回らせるためには、単価を上げて円安に対応できる状況をつくることが欠かせません。
以上より、日本は円安の場合に労務単価が上がり、円高になると労務単価が下がる傾向が強いです。特に現在は円安が加速していることから、今後とも労務単価の上昇が続いていくと予想されます。
【ドナルド・トランプ氏のアメリカ大統領就任で更なる物価上昇も】
2025年1月20日、ドナルド・トランプ氏がアメリカ大統領に就任しました。そういったなか現在政策を進めていくなかで「関税」についての議論が交わされており、もしかすると土木業界にも関税の影響が出てしまうのではないかと危険視されています。関税によって建設資材等の価格が高騰すると、工事業務の費用が増加するかもしれません。その結果、今後さらなる労務単価の上昇が起きる可能性もぬぐい切れません。
令和8年度の労務単価予測
13年連続で上昇を続けている労務単価ですが、翌年の令和8年は、どのような金額の変化が起きるのでしょうか。
結論として、令和8年度の労務単価は令和7年度と同様に、全体的な金額の上昇が起きると予想されます。主な理由を以下にまとめました。
- 人手不足が続いている
- 少子高齢化問題を解決できていない
- 円安が止まらない
また過去の傾向をみると、特に直近の労務単価の伸び率は約5〜6%です。
よって、令和8年度も同様に5~6%程度の伸びがあると想定して計算をした場合、令和7年度の全職種の平均が24,852円であることに対し、令和8年度はそこから比率+5〜6%を加えた「26,095〜26,343円」になると予想できます。
なおこの値は、労務単価が最も低かった平成24年の13,072円の2倍に当たります。ここからわかるように、土木業界の金銭まわりの待遇は継続的に良くなっていることがうかがえます。
まとめ
労務単価は建設従事者の賃金を決める重要な指標であり、毎年の情勢を検討しつつ国土交通省が単価を公表します。
令和7年時点で過年度から上昇が続いていることにあわせ、令和8年度においても人手不足や円安の問題を受けて、更なる上昇が起きると予想できるでしょう。特に企業発注者の場合は「労務単価の上昇=発注額の増加」、また自治体発注者の場合は「労務単価の上昇=発注額の増加=増税」につながる恐れがあるため、今後の動向から目が離せません。
国土交通省が毎年公開している労務単価は、建設従事者の賃金に関わる重要な指標です。では、令和6年時点でどれくらいの単価が設定されているのでしょうか。
そこでこの記事では、令和6年度における労務単価や、過去からの推移を解説したのち、令和7年に公開予定である最新の労務単価表の予測について紹介します。


