【2025年版】建築の「スタッド」とは?2つの用途・サイズ・規格・LGSとの違いまで完全解説
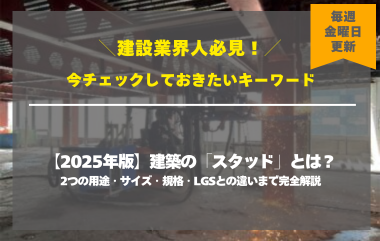
建築用語として使われる「スタッド」は、壁や天井の軽量鉄骨下地を支える部材として一般的に使われています。しかし、構造設計や鋼構造分野では「頭付きスタッド(シアコネクタ)」として鉄骨とコンクリートを一体化させる補強部材を指すこともあり、用途によって意味が大きく異なります。
そこでこの記事では、初心者が混乱しやすい「スタッドの種類」「規格」「施工上の注意点」「LGSとの違い」まで、わかりやすく解説します。
目次
建築工事における「スタッド」とは?意味と2種類の用途
建築工事における「スタッド」とは、主に内装工事で使われる軽量鉄骨下地材(間柱)を指す言葉です。石膏ボードなどの仕上げ材を固定するとき、スタッドを等間隔に配置することで壁の強度・施工品質・寸法精度を確保します。
一方で、構造躯体に使われる「頭付きスタッド(スタッド溶接金物)」は、鉄骨梁とコンクリートスラブを一体化させるシアコネクタとして使用されます。合成梁や耐震補強に欠かせない重要素材として活用されているのが特徴です。
- 「内装下地材」としてのスタッド
- 「構造部材」としてのスタッド
このように「スタッド」という言葉は、用途により意味が異なります。以下より、2種類のスタッドの意味を、用途別に解説していきます。
内装下地材としてのスタッド(軽量鉄骨)
建築現場では、内装仕上げの前に軽量鉄骨下地(LGS)を組み、壁や天井の骨組みをつくります。その際に使われる縦の部材がスタッド(間柱)です。
スタッドは、石膏ボード・防音パネル・断熱材・配線ルートの確保など、多機能な下地として重要な役割を果たします。構造材とは異なり建物の自重を支える素材ではありませんが、施工精度・耐久性・防火性能・遮音性能に影響するため、設計寸法やピッチ、規格に沿った施工が求められます。
以下より、内装下地材としてのスタッドについて解説します。
スタッドの役割
スタッドの役割は、壁や天井の仕上げ材を支えるフレームを形成することです。特に次のような建物では、内装材として石膏ボードや吸音パネルを施工するための固定点として欠かせません。
- オフィス
- 商業施設
- マンション
さらに、電気配線・空調配管・LAN配線を通す際にもスタッドがルート形成の基準となり、施工の計画性を支えます。
角型スタッドとC型スタッドの違い
スタッドには主に「C型スタッド」と「角型スタッド」の2種類が存在します。
| 種類 | 特徴 | 用途 |
| C型スタッド | JIS規格対応。寸法安定性が高い | 公共工事・設計管理が厳しい現場 |
| 角型スタッド | 高い施工性・コスト効率であり、電気配線が通しやすい | マンション・リフォーム・民間工事 |
特に、C型スタッドは精度が求められる現場に向いており、角型スタッドは施工性・コストメリットを重視する現場に採用される傾向があります。
スタッドのサイズと規格
スタッドは、目的に応じて複数の寸法が用意されています。次の呼び寸法(サイズ)が一般的であり、用途・壁厚・配線量に応じて選定しなければなりません。
| 呼び寸法 | 用途例 |
| C-50形 / 0.5〜1.0mm厚 | 軽天・間仕切り・一般壁 |
| C-65形 | 遮音壁・設備機械室 |
| C-75形 | 配管量の多い壁 |
| C-100形 | 設備干渉・商業施設・高遮音仕様 |
参考:チヨダメタルスタッド関西株式会社「JIS壁下地材」
※規格についてはメーカー公式サイトなどを参照
特に板厚(t値)は、0.5mmから1.0mmに変えるだけで強度・たわみ量が大きく変わります。設計や施工の際には管理指示書に従うことが重要です。
ランナーとの違い
スタッドは「縦材」、ランナーは床・天井側の「水平材」であり、この2つはセットとして使用します。以下にそれぞれの役割を整理しました。
- ランナー=ガイド(受け)
- スタッド=立ち材(間柱)
施工手順としては、先にランナーを固定し、そこへスタッドを差し込み立て込む方法が一般的です。
LGS(軽量鉄骨)との違い
よく「スタッド=LGS」と認識されることが多いですが、厳密にはそれぞれの位置づけが次のように違います。
- LGS:工法の総称(軽量鉄骨造の内装下地)
- スタッド:LGS工法に使う部材のひとつ
つまり、スタッド(部材)はLGS(工法)の一部です。ランナー・振れ止め・補強プレートなど複数部材の中の1種類という位置づけになります。
またLGSについて詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください▼
構造部材としてのスタッド(頭付きスタッド)
建築構造における「スタッド」は、内装材ではなく頭付きスタッド(スタッド溶接金物)を指すケースがあります。これは、鉄骨梁とコンクリートスラブを一体化させるためのシアコネクタとして使用される部材です。
鉄骨造や合成構造において、引抜き抵抗やせん断力に対して重要な役割を担います。
ここでは構造部材としてのスタッドについて紹介します。
規格・サイズ・引抜強度
頭付きスタッドの寸法は、一般的に以下の呼び径が多く採用されています。
| 呼び径(参考) | 用途例 |
| φ13 | 中小規模の合成床 |
| φ16 | 標準階・梁補強 |
| φ19 | 高荷重・耐震壁・杭頭部 |
| φ22 | 特殊補強・橋梁配合 |
参考:ダイヘンスタッド「標準寸法表」
※規格についてはメーカー公式サイトなどを参照
特に梁とスラブが一体化する「合成梁」の場合、頭付きスタッドの配置ピッチや本数が耐力計算に影響します。場合によっては設計条件で、溶接後の曲げ試験や外観検査が義務付けられるケースもあります。
溶接方法
頭付きスタッドは、スタッド溶接機を用いて鉄骨に自動的に溶接されます。一般的な施工フローは次の通りです。
- 施工前試験(WPS)確認
- 母材清掃(スケール・錆・塗膜除去)
- 溶接(1本数秒)
- 外観検査(焼付き・傾き)
- 曲げ試験(90°曲げで亀裂がないか確認)
先端にフラックスを含むため、電流が流れると瞬間的にアークが発生し、母材とスタッドが融合します。なお、施工品質は溶接条件(電流・時間・母材厚さ)の影響を大きく受けるので、施工管理者・溶接技能者によるチェック体制が重要です。
(参考:日本スタッド工業株式会社「スタッド溶接の施工と管理」)
スタッド施工でよくある失敗と対策
2つの用途のスタッドは、それぞれ施工で寸法誤差・配線干渉・強度不足・検査不備などのトラブルが起きやすい傾向があります。
ここでは、内装スタッドと頭付きスタッドで発生しやすい失敗例と防止策を整理しました。
内装スタッドの失敗例
内装スタッド工事では、以下のトラブルが多く報告されています。
| よくある失敗 | 原因 | 対策例 |
| スタッドピッチが違う | 墨出し不足・施工指示の誤認 | 基準表を事前に掲示する |
| 建具位置がズレる | ランナー・振れ止め不足 | 補強下地、事前寸法を合わせる |
| 配線・配管が通らない | 設計調整不足 | 事前設備協議・C75以上を採用する |
| ボード仕上げが波打つ | スタッド固定不足・曲がり | 板厚を変更する or プレートを補強する |
特に、遮音壁・耐火区画・入居後の壁掛け想定がある場合は、設計段階で「荷重受け下地」「スタッド補強」「スタッド厚み変更」を確定しないと、後戻りが困難になります。
頭付きスタッドの失敗例
構造スタッドの施工不良は、仕上げ品質だけでなく構造耐力や安全性に直結します。代表的な不具合は以下です。
| 不良例 | 影響 | 原因 |
| 冷接(融合不足) | 引抜耐力低下・破断リスク | 母材清掃不足・電流不足 |
| 傾斜・位置ズレ | 梁スラブの付着不均等 | 治具不良・施工精度不足 |
| 高さ不良(埋没・露出) | スラブ厚不足・コンクリ剥離 | 施工後管理不足・配筋干渉 |
溶接品質が確認できない場合は是正処置が必要とされるため、的確な溶接施工が求められます。
建築のスタッドに関するよくある質問(FAQ)
建築工事でスタッドとは?
建築でいう「スタッド」は、主に壁や天井の下地材として使われる軽量鉄骨の縦材(間柱)のことです。石膏ボードや断熱材を取り付ける際の支持材になり、配線ルート確保や施工精度にも影響します。一方、構造分野では鉄骨とコンクリートを一体化させる「頭付きスタッド」を指す場合もあります。
頭付きスタッドはどこで使う?
頭付きスタッドは、鉄骨梁とコンクリートスラブを一体化させる「合成梁」や耐震補強、杭頭部の連結など構造用途で使用されます。主に引抜抵抗を高め、せん断力を伝達する役割があり、設計・施工の際には配置本数・ピッチ・曲げ試験が求められています。
まとめ
建築で使われる「スタッド」は、使用される分野によって意味が異なります。
内装工事では軽量鉄骨下地材(間柱)として使われ、壁の強度や施工精度、防音・防火性能に影響します。一方、構造用途では頭付きスタッド(シアコネクタ)として、鉄骨梁とコンクリートを一体化させる役割があります。
用途によって寸法・規格・施工方法・検査内容が大きく変わるため、設計段階の判断ミスや施工方法の誤解がトラブルにつながりやすい部材です。迷ったら、仕様書・基準・現場条件を確認しながら、適切なスタッド選定を行いましょう。


