【2025年版】建築の「まぐさ」とは?意味・役割・寸法やツーバイフォー・在来工法での扱いの違いも解説
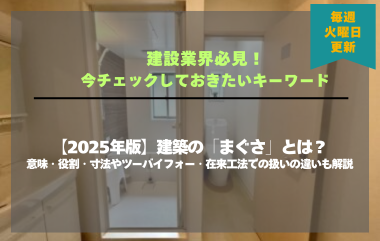
「まぐさ(まぐさ材)」という言葉は、建築現場や施工管理、設計図面などで頻繁に登場する基本用語のひとつです。しかし、「窓台との違いは?」「鴨居とは別物?」「在来工法とツーバイフォーで役割が違う?」など、建築初心者にとっては混乱しやすい要素でもあります。
そこでこの記事では、まぐさの意味・役割・寸法・工法別の違い・混同しやすい部材との比較まで体系的に解説します。
目次
建築の「まぐさ」とは?用途・機能をわかりやすく解説
まぐさは、次のような開口部の上に水平に取り付けられる横架材です。
- 窓
- ドア
- シャッター
【横架材とは?】
主に軸組構法に用いられる水平方向に架け渡される部材のこと
上部の壁や屋根荷重を両側の柱へ伝え、開口部がたわまないよう補強する役割を持ちます。日本ツーバイフォー建築協会では、「90㎝以上の開口部には、必ず上部に補強材としてまぐさ(壁の開口部を補強するための横架材)を取り付ける必要があります。」と説明されています。
(引用:日本ツーバイフォー建築協会「Vol.1 ツーバイフォーこそ、リフォームしやすい」)
ここでは、建築に用いられるまぐさの役割や、言葉の由来を紹介します。
まぐさの役割|開口部にかかる荷重を柱へ伝える構造材
まぐさの役割は「開口上部の荷重を安全に逃がす梁の補助材」です。
もしまぐさが無い場合、開口部周辺に荷重が集中し、以下の問題が発生する可能性があります。
| 想定される問題 | 内容 |
| 開口部上部のたわみ | サッシ・建具の動作不良 |
| 外壁のクラック | 仕上げ材・タイル・サイディングの破損 |
| 耐震強度の低下 | 地震時に変形・破損のリスク上昇 |
特にツーバイフォー工法では構造強度の一部として扱われ、耐力壁の性能に直結します。安全性を確保するためにも、建物の規模や形状に合わせて、まぐさのサイズ・材料の選定が不可欠です。
まぐさの漢字・由来
まぐさは本来、「楣」または「目草」と書きます。しかし、建築資格試験や現場指示書、図面上では漢字が読みづらいことから、現在は「ひらがな表記」が一般的です。
なお、まぐさの語源については複数説がありますが有力なものは以下です。
- 柱間の目(寸法)を草(材料)で塞ぐ=目草
- 古建築で「梁に添える材」として呼ばれた歴史的呼称
※確定した研究資料が少ないため、語源は文献によって諸説ある
他の部材との違い|混同しやすい建築用語比較
建築用語のなかでも、まぐさは特に「窓台(まどだい)」や「鴨居(かもい)」と混同されやすい部材です。
名称が似ているだけでなく、取り付け位置や用途が近いため、現場初心者が迷うポイントでもあります。ここでは、それぞれの違いを解説します。
| 項目 | まぐさ | 窓台 | 鴨居 |
| 位置 | 開口部上部 | 開口部下部 | 引き戸上部 |
| 構造材か | 〇(特に2×4) | △(支持材) | ✕(非構造材) |
| 耐震性への影響 | 大 | 小 | なし |
| 使用場所 | 窓・玄関・開口部 | 窓・扉 | 和室 |
まぐさと窓台の違い(位置と役割)
結論として、まぐさは「開口部の上部の補強材」である一方、窓台は「開口部の下部支持材」です。
| 項目 | まぐさ | 窓台 |
| 設置位置 | 開口部の「上」 | 開口部の「下」 |
| 主な役割 | 上からの荷重を柱に逃がす構造材 | サッシ・建具・荷重を安定支持 |
| 耐震性能への影響 | 大(特にツーバイフォー) | 小(主に仕上げと施工品質に関与) |
| 材料例 | 木材・集成材・鋼材 | 木材・下地材・サッシ枠一体可 |
特に大きな違いは設置場所が開口部の上なのか、下なのかというポイントです。どちらも窓や扉の開口部に関わる部材ですが、役割・構造上の意味合いは大きく異なる点に注意してください。
まぐさと鴨居の違い(用途・構造・住宅文化)
「鴨居」は和室文化がある日本特有の建築用語であり、引き戸や障子・襖(ふすま)を走らせる溝が彫られた木材を指します。一方で、まぐさはサッシや開口部に用いる完全な構造材であり、建具機能を担う鴨居とは本質的に異なります。
| 比較項目 | まぐさ | 鴨居 |
| 主用途 | 開口部上部の耐力補強 | 建具のガイドレール |
| 荷重設計 | 荷重を受ける(構造材) | 荷重を受けない(非構造材) |
| 使用場所 | 洋間・窓・玄関・シャッター | 和室・襖・障子・引戸 |
| 施工精度 | ±3mm誤差で性能影響大 | 建具動作で±1mm精度重要 |
| 建築文化 | グローバル共通 | 日本文化特有 |
鴨居については、荷重を受けない非構造材という扱いです。障子やふすまを取り付けるために利用するのが一般的です。
工法別の「まぐさ」の設計と考え方
まぐさは、どの建築でも同じ役割を持つわけではありません。特に「在来工法」と「ツーバイフォー工法(2×4)」では、まぐさの重要度・設計ルール・寸法基準が大きく異なります。
ここでは工法別に、まぐさの設計の考え方を紹介します。
在来工法(荷重は梁・胴差しで受ける・まぐさへの負荷は小さめ)
木造軸組工法といった在来工法では、梁(はり)や胴差しが開口部上の荷重を受ける構造となっているため、まぐさそのものは補助材として扱われるケースが多いです。
荷重への負担は小さく、構造材というよりも寸法調整用に用いられます。
ツーバイフォー工法(弱点補強の核心部材・まぐさ受けが必要)
ツーバイフォー工法では、壁=構造体として荷重を受ける「モノコック構造」が採用されています。そのため、窓やドアなどの開口部は構造的弱点となり、まぐさが耐震構造上の重要要素となります。
大きな荷重を受けることから、まぐさの寸法・材料が耐震等級に直結します。施工ミスや設計値の誤りがあると、サッシのゆがみや壁倍率の低下、さらには耐震性能不足に陥るケースがあるため、入念な設計検討が欠かせません。
まぐさの寸法と設計基準
まぐさの寸法は「どのくらいの窓幅(開口寸法)を設けるか」によって変化します。
特に木造住宅では、工法・荷重条件・耐震等級・設計仕様によってまぐさの高さ・厚み・材料の種類が変わるため、決まった寸法ではなく、条件に応じた算定が必要です。
日本ツーバイフォー建築協会の「枠組壁工法建築物構造計算指針」などでも、開口補強の考え方が示されており、寸法算定は経験ではなく基準に基づく設計が必須とされています。
素材別の種類|どんな材料が使われる?
まぐさに使用される材料は、以下に示す条件によって異なります。
- 構造方式
- 耐震基準
- 開口サイズ
- コスト
- 施工方法
以下では、工法別・設計思想に合わせた代表的な素材を整理します。
木造(一般材・集成材)
木造住宅におけるまぐさは、一般材(無垢材)と集成材(エンジニアリングウッド)が主流です。どちらも木材ですが、強度・安定性・コスト・長期性能が異なります。
まず一般材(無垢材)は比較的扱いやすく、在来工法では現在も使用されています。ただし耐震基準が高い住宅(耐震3・長期優良住宅)では、湿度変化による反り・割れが懸念点となり、採用割合は減少傾向です。
続いて集成材は、無垢材よりも強度に優れ、反りや割れが少ないため、寸法安定性を高めやすいのが強みです。近年では、高耐震住宅や大型開口部などでの使用例も増えています。
また集成材のひとつであるCLT工法について詳しく知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
鉄骨造(形鋼・LGSなど)
鉄骨造では、まぐさは木材ではなく鋼材で形成されます。開口幅・構造計算結果・防火区画区分で、次の材料から選定されるのが特徴です。
- 形鋼(H鋼・C型鋼・アングル材)
- LGS(軽量鉄骨材)
たとえば鉄骨造のまぐさは、構造壁一体として扱われるため、梁に近い強度を担うケースもあります。また、まぐさ単体で使用するのではなく、構造材+LGS補助の組み合わせで設置するのが一般的です。
またLGS建築について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください▼
建築のまぐさについて新人が疑問に思う質問【FAQ】
柱のまぐさとは?
柱のまぐさとは、開口部(窓や扉)の上に設置され、両側の柱へ荷重を逃がす横架材のことです。柱に固定されることで、上部の壁や屋根荷重を支え、サッシや建具が歪まず使用できる状態を保ちます。特にツーバイフォーでは耐震部材として扱われ、設計基準に沿った寸法・材種選定が求められます。
まぐさはどの工法で必要?不要?
まぐさは在来工法でも使用されますが、耐震的に必須なのがツーバイフォー工法です。在来工法では梁や胴差しが荷重を受けるため、まぐさの負担は比較的小さく補助材扱いです。一方、ツーバイフォーでは壁が構造体となるため、開口部は弱点となり、まぐさとまぐさ受けをセットで設計する必要があります。
まぐさ構造とは?
まぐさ構造とは、開口補強のためにまぐさ・まぐさ受け・柱・面材構造を一体化し、耐震性能や荷重支持性能を確保する設計を指します。特にツーバイフォー工法では「まぐさ=構造の一部」であり、釘ピッチ・断面寸法・補強スタッド位置などが住宅性能表示基準や国交省仕様書に基づき決められています。
まとめ
まぐさは、開口部の上部に設置され、荷重を柱へ逃がす重要な構造材です。
工法によって役割が変化し、在来工法では補助的役割ですが、ツーバイフォー工法では耐震性能に直結する核心部材となります。
ほかにも、素材・寸法・施工方法が開口幅や設計条件で変わります。開口計画や補強の判断に迷う場合は、プロに相談することで施工品質と安全性を高められます。


