新規建設の手順が変わる?2025年からの法改正で影響を受ける許可・契約・施工要領の最新動向
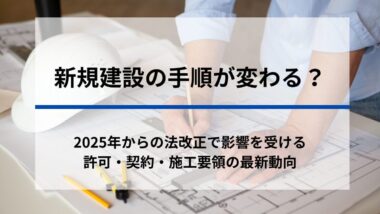
2025年以降、新規建設プロジェクトを進める際に留意すべき制度的な変化が、これまで以上に複雑かつ重要となっています。小規模工事から大規模案件まで、発注者・受注者双方に影響を及ぼす改正が、建設業法・公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)で進んでいるといえるでしょう。
本記事では「新規建設のルール」という視点からその変化を整理するとともに、実務上確認すべきポイントを解説します。
目次
2025年における建設業の制度変化

建設業における担い手不足や資材高騰、長時間労働といった構造的課題は長年指摘されてきました。国は建設業における課題を是正するため、令和6年6月14日に「建設業法および公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)」を改正しました。
改正の柱は、以下の3つです。
- 技能者の処遇改善
- 資材高騰時における労務費転嫁の円滑化
- 生産性向上と働き方改革
単なる制度変更ではなく、施工現場のマネジメントや契約実務に直結する内容です。
また、2025年から2026年にかけて段階的に施行されるため、各事業者は自社の契約区分・現場規模に応じた準備を進める必要があります。
新規建設の小規模〜大規模工事における主要な改定ポイント
2025年から2026年にかけて施行される改定内容の主な要点は次のとおりです。
・労働者の処遇確保の努力義務化(賃金・勤務条件の適正化)
・資材費・労務費の著しい低価格契約の禁止
・監理技術者や施工体制台帳の配置・提出要件の見直し
・ICT・DXの活用を前提とした生産性向上の推進
すべての工事に共通して影響する項目です。特に、下請契約金額や請負金額の基準が見直され、「特定建設業の許可」が必要となる範囲が広がります。
加えて、発注者・受注者間の契約内容にも新たな配慮義務が導入されました。たとえば「材料費や労務費を著しく下回る金額で契約してはならない」と明文化されており、原価割れ契約の防止を目的としています。そのため、低価格競争に依存した契約慣行は通用しにくくなるといえるでしょう。
たとえば、2026年には以下のような変更点が予想されています。
・下請法が「中小受託取引適正化法(取適法)」へ改称予定
従業員数を基準に適用範囲が拡大し、契約書面の交付・支払期日・価格交渉ルールの明文化が義務化される
・労務単価のさらなる引き上げと工期管理ガイドラインの強化
資材高騰・人件費上昇への対応として、国が定める基準単価と工程管理指針の改訂がある
・安全衛生管理の義務範囲拡大
労働者50人未満の事業所にもメンタルヘルス対策や化学物質管理の義務が段階的に適用される
中〜大規模新規建設で強まる要件と手順
2025年の法改正により、特に中〜大規模建設工事では、現場運営と契約実務の両面で新たな基準が導入されます。監理技術者の専任義務や施工体制台帳の作成に加え、工期の適正化とICT施工管理の導入が「義務的要素」として位置づけられました。
そのため、従来の人的依存型管理から、デジタルと法令遵守を軸にした統合的な施工体制への転換が迫られています。ここでは、改正の具体的内容と、中〜大規模現場で求められる新たな要件・対応手順をみていきましょう。
監理技術者・施工体制強化・工期管理について
2025年の改正では、中〜大規模工事を中心に、監理技術者の専任配置および施工体制台帳の提出義務が強化されます。
まず、請負契約金額の基準が見直され、専任義務の対象範囲が拡大することで、より多くの工事現場に監理技術者の常駐が必要です。監理技術者の配置計画・兼務体制・現場間移動の運用方法など、企業側の体制整備が急務となったといえるでしょう。
また、今回の改正では「著しく短い工期での契約締結を禁止する」条文が明文化されました。過度な工期短縮は、労働環境の悪化や品質低下につながるため、工期管理が契約上の遵守項目として位置づけられます。
発注者・元請・下請のいずれも、契約段階で現実的な工期を設定し、設計変更や追加発注時の「工期延長協議の手順」を明示することが求められます。
国土交通省が公表している「適正な工期設定のためのガイドライン(令和6年度改訂)」にも連動しており、公共工事のみならず民間工事にも波及しています。今後は、工期の適正性が契約監査の対象となる可能性もあり、現場管理者の責任範囲は拡大すると予想されます。
ICT/DX活用と現場管理の効率化
改正建設業法の特徴の1つが、ICTや建設DXを活用した施工体制の効率化です。特に注目すべきは、軽微工事における専任義務の緩和措置として「ICTによる遠隔監理制度」が導入される点です。
クラウド施工管理システムやウェアラブルカメラ、電子黒板を用いた遠隔立会が可能となり、監理技術者が複数現場を効率的に管理できる仕組みが制度的に整備されます。
BIM/CIM)の導入も拡大しており、設計・施工・維持管理データを一元化することで、品質・安全・コストを同時に管理することが可能になっています。国土交通省が推進する取り組みでは、BIM/CIM、電子契約、遠隔臨場を「新しい標準」と位置づけており、今後はこれらを活用していない事業者は入札・契約の競争力で不利になると考えられます。
発注者側でも、「ICT活用体制の有無」を入札要件や評価項目として明示する動きが広がっています。特に、総合評価落札方式を採用する自治体では、クラウド施工管理やデジタル写真管理の導入状況が評価対象となるケースも増加傾向です。
新規建設プロジェクトを進める際のチェックリスト
2025年の建設業法・入契法改正によって、契約金額の基準や技術者配置、工期設定、ICT施工管理の各分野で新たな基準が適用されます。中〜大規模工事では、発注者・受注者の双方に明確な確認義務が発生します。
ここでは、改正後の現場運営に対応するための主要チェック項目についてみていきましょう。
発注者が確認すべき事項は以下のとおりです。
| 確認項目 | 内容 | 対応のポイント |
| 契約予定金額と監理技術者配置基準 | 改正後は専任義務の適用範囲が拡大。金額に応じて監理技術者の配置が必要 | 契約前に資格証明・専任誓約書を確認する |
| 契約書への価格根拠・禁止条項 | 「材料費・労務費の根拠提示」や「原価割れ契約の禁止」を明示 | 見積根拠と再協議条項を契約書に明文化する |
| 工期設定の適正化 | 入契法改正により短縮工期の防止が義務化 | 工期ガイドラインに沿って工程表と積算の根拠を保存する |
| ICT施工管理体制の条件化 | DX推進により、発注段階でICT導入の有無を条件化 | 電子黒板・遠隔臨場・クラウド施工管理の導入を求める |
受注者が確認すべき事項は以下のとおりです。
| 確認項目 | 内容 | 対応のポイント |
| 許可区分・技術者配置の適合 | 金額基準の改定により、配置要件が変化 | 自社の許可種別と現場規模の整合性を再点検する |
| 見積内訳の明確化 | 改正法により原価の説明責任が強化 | 材料費・労務費・直接経費を明示して原価割れを防ぐ |
| 契約変更条項の整備 | 設計変更・追加工事の発生時に対応 | 再協議の手順を契約書に明文化し、紛争を防止する |
| 施工管理・記録のデジタル化 | ICT施工管理や遠隔臨場への対応が必須化 | クラウド施工管理システムで工程・品質・安全を一元管理する |
まとめ
2025年以降の建設業は、制度対応とデジタル活用を両立させることが不可欠になります。監理技術者の配置基準や工期設定、価格契約の在り方までが再定義され、事業者には透明性と説明責任が求められます。
とくに中〜大規模工事では、施工体制台帳とICT施工管理が実務の中心的役割を担うようになるでしょう。法令対応を単なる義務と捉えず、生産性と品質の両立を図る経営基盤の強化として取り組みましょう。


