建築家とはなにか?
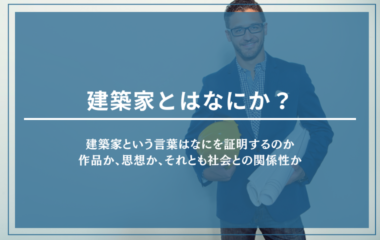
本記事の問いは至ってシンプルだ。「建築家とはなにか?」だ。しかし答えは、驚くほど複雑だ。とくに日本においては…。
日本の建築業界を眺めると、ただ一級建築士を持つだけの者が、「建築家」という称号を軽々しく名乗ることは一般的ではない。しかし、法的には、資格の有無を問わず、誰でも建築家を名乗っても問題ない。資格は技術を保証するが、建築家という言葉はなにを証明するのか。作品か、思想か、それとも社会との関係性か。
アメリカでは「建築家(Architect)」を名乗るには州法で定められた試験に合格し、登録を受けなければならない。イギリスでは7年以上の教育と実務を経て、ようやく登録が許される。ドイツでは各州の建築家会議所に登録された者だけが、法的に「建築家(Architekt)」を名乗れる。フランスの建築法は「建築は文化の一表現である」と高らかに謳い、建築家を芸術家として位置づける。
欧米とは対照的に、日本では、建築家という呼称は、建築士という技術資格制度と文化・芸術のあいだで漂っている。
建築家とはなにか──。この問いは、職業の定義を超えて、日本の近代化そのものを問うている。失われた統合性。分断された技術と芸術。制度化できなかった身体知。そして今、一部の建築家たちが取り戻そうとしている。
資格と称号、技術と芸術、制度と文化──。これらの狭間で揺れ動く「建築家」という存在を、日本と欧米の対比、歴史的変遷、そして現代的意味から読み解く。
目次
アーキテクトの語源が示す原理
ギリシャ語の「アルキテクトーン」──「アーキ(最初に存在する者)」と「テクトーン(建てる人)」の合成語──。それは単なる技術者ではなく、職人たちを統率し、技術を統合し、構想を実現に導く者を意味していた。建築の語源には、すでに思想性が埋め込まれている。
西洋では15世紀ルネサンス期、ブルネレスキがフィレンツェ大聖堂に世界最大のドーム屋根を足場なしで完成させ、アルベルティが「建築論」で建築学を学問として体系化したとき、職人と建築家の境界線が引かれた。彼らは高い教養と科学的知識を持つ存在として、芸術家的な地位を獲得した。以降、建築家は技術者であると同時に、思想家でありデザイナーとなった。
失われた統合者──日本の棟梁という存在
明治以前の日本には、まさにこの「アルキテクトーン」の原義を体現する存在がいた。それが大工の棟梁だった。
古代律令制下の「木工大工(こだくみのおおいたくみ)」に起源を持つこの称号は、建物の最も重要な構造である「棟」と「梁」から名付けられた。15世紀中頃から棟札に名が記されるようになった棟梁は、設計から施工まで一貫して統括する、まさに統合的な建築の責任者だった。
明治以前の棟梁は、建築士であり、現場監督であり、積算者であり、渉外者であり、職人であり、大工を束ねる経営者でもあった。彼らは図面を引き、構造を考え、材料を選定し、職人たちを指揮し、施主と交渉した。つまり、西洋のアーキテクトが15世紀に獲得した役割を、日本の棟梁は独自の形で担っていたのだ。
しかし、両者には決定的な違いがあった。西洋のアーキテクトが芸術家として理論化され、職能として確立されていったのに対し、日本の棟梁は職人の延長線上にあり、体系的な理論や教育制度を持たなかった。 技術は徒弟制度を通じて口伝され、7~8年の年季奉公と1年のお礼奉公を経て一人前となる。知識は身体に宿り、言語化されることなく継承された。
明治維新がもたらした断絶
1868年、明治維新という劇的な転換点が訪れる。開国とともに西洋の技術が怒涛のように流入し、「文明開化」の掛け声のもと、日本は性急な近代化を迫られた。ここで、設計と施工の分離が始まる。
政府は百数十名の外国人技師を招聘し、鉄道、港湾、官公庁の建設を指導させた。イギリス人建築家ジョサイア・コンドルが工部大学校(後の東京大学工学部)で建築学を教え、日本初の「建築家」たちが養成された。辰野金吾、妻木頼黄といった工部大学校の卒業生たちは、西洋建築様式を学び、石造やレンガ造の技術を習得した。
一方、伝統の木造建築技術を持つ棟梁たちは、突如として未知の世界に放り込まれた。地方の学校や役所、病院など新しい機能を持つ施設が求められたが、石造建築は彼らにとって全くの未知の領域だった。錦絵や実物の見聞を頼りに、見よう見まねで洋風建築を建てる。これが「擬洋風建築」と呼ばれる、独特の様式を生み出した。
松本市の旧開智学校、山形市の旧済生館本館──これらの擬洋風建築は、日本の伝統的な和小屋組の構造に西洋風の外観を纏わせた、文化的ハイブリッドだ。柱にはフルーディング(溝彫り)を模しながら、天井には波に千鳥や松竹梅といった日本の題材が描かれる。階段は急で、二階建ての経験が乏しい大工たちの苦心が偲ばれる。
清水建設の二代目、清水喜助が手がけた「三大擬洋風建築」に代表されるように、棟梁たちは創意工夫で未知の様式に挑んだ。しかしこの試みは、明治10年代後半には「様式的正確さを欠いた恥ずかしいもの」として断罪されることになる。工部大学校を卒業した日本人建築家たちが、西洋建築を「正しく」直写した建築を建て始めたからだ。
ここに、日本における建築家と職人の分断が決定的となった。設計は建築家の領域となり、施工は職人の仕事となった。棟梁が持っていた統合的な役割は分解され、建築家は図面を引き、大工は図面通りに作る──この分業体制が確立した。
日本における奇妙な二項対立
一級建築士は国土交通大臣の認定を受けた国家資格であり、試験を突破する必要がある。しかし、「建築家」という呼称には明確な定義がなく、国家資格の有無にかかわらず誰でも名乗ることができる。
ここに逆説が生じる。法的には「建築士」が保護された国家資格であるのに対し、「建築家」は誰でも自称できる曖昧な呼称だ。にもかかわらず、建築家とは自分の思い描く建物を設計していくアーティストを指し、一級建築士と比較して、建築家はその人のプランニング自体に価値を持たせられる人と定義される傾向がある。
つまり、資格を持つ者が必ずしも建築家ではなく、建築家と呼ばれるには資格を超えた何かが必要とされる。それは作品性であり、思想性であり、社会的意義だと言える。
欧米の厳格な法的保護──「建築家(Architect)」という権威
この日本の曖昧さは、欧米諸国の制度と対比すると、その特異性が際立つ。
アメリカでは、「建築家(Architect)」という称号は州法によって厳格に保護されている。 全米建築家登録委員会協議会(NCARB)が統括する建築家登録試験(ARE)に合格し、州の登録を受けた者だけが「建築家(Architect)」を名乗ることができる。無資格者がこの称号を使用すれば、法的処罰の対象となる。試験は9科目、延べ33.5時間に及び、全科目合格まで平均2年半を要する。さらに多くの州では1~2年ごとの資格更新が義務づけられ、継続教育が求められる。
イギリスも同様に、1931年建築家登録法以来、「建築家(Architect)」の称号を法的に保護してきた。建築家登録評議会(ARB)への登録なしに建築家を名乗ることは違法だ。資格取得までの道のりは長い──3年間の大学教育(パートⅠ)、1年間の実務訓練、2年間の大学院教育(パートⅡ)、さらに1年間の実務訓練を経て、最後に専門実務試験(パートⅢ)に合格する必要がある。このサンドイッチ制度と呼ばれる教育システムは、理論と実践の往復を通じて建築家を育成する。
ドイツでは各州の建築家法が「建築家(Architekt)」の称号使用を禁止している。州ごとに設置された建築家会議所(Architektenkammer)に登録された者だけが、この称号を名乗れる。登録には通常、4年以上の建築教育課程修了と2年以上の実務経験が必要だ。さらに興味深いのは、建築家以外に「内装建築家(Innenarchitekt)」「景観建築家(Landschaftsarchitekt)」「都市計画家(Stadtplaner)」といった専門分野別の称号も法的に保護されている点だ。
フランスでは1977年の建築法が、称号の独占と業務の独占を同時に定めた。国立建築学校などで政府認定学位(DPLG)を取得し、建築家協会に登録した者だけが「建築家(Architecte)」を名乗り、設計業務を行うことができる。特徴的なのは、建築家協会への登録に第三者性が求められる点だ。建設会社などに所属する建築設計士は、利益相反の可能性があるため登録できない。建築法第1条が「建築は文化の一表現である」と高らかに謳うフランスでは、建築家は技術者ではなく、文化の担い手として位置づけられている。
これらの国々では、「建築家(Architect)」という称号は単なる職業名ではなく、法的に保護された社会的、文化的エスタブリッシュメントの証なのだ。
制度が映し出す文化的相違
では、なぜ日本だけが、こうした法的保護を持たないのか。
一つの仮説は、日本の「建築士」が欧米の「建築家(Architect)」と「建築技術者(Building Engineer)」の両方の性格を併せ持つことに起因する。欧米では建築家と建築技術者は、教育体系、資格制度、職能団体すべてにおいて明確に区別される。建築家は芸術家であり、技術者とは決して呼ばれない。
一方、日本の建築士は、意匠設計だけでなく、構造設計、設備設計、さらには施工監理まで広範な領域をカバーする。一級建築士の資格は、あらゆる建物の設計・工事監理を可能にする技術資格であり、その意味で極めて実務的だ。しかし、それゆえに「作家性」や「思想性」といった芸術的側面が、資格要件として明示されにくい。
この包括性は、実は明治以前の棟梁の役割を受け継いだものだ。 棟梁が設計から施工まで一貫して担っていたように、建築士も広範な業務をカバーする。しかし明治維新による設計と施工の分離は、皮肉にも完全には達成されなかった。建築士という資格に、両方の要素が折り重なる形で残されたのだ。
もうひとつの要因は、日本における建築の文化的位置づけだろう。フランスが建築を「文化の一表現」と法律で定義するのに対し、日本の建築基準法は「技術的な最低限の基準」の遵守を目的とする。この対比が示すのは、建築を芸術として捉えるか、安全を確保する技術として捉えるかという根本的な視座の違いだ。
そしてこれは、棟梁から建築士への移行過程で失われたものを物語っている。 棟梁は理論化されなかったが、確かに建築を総合的な営為として捉えていた。木の性質を知り、構造を理解し、意匠を考え、職人たちと協働して空間を創り出す──それは技術であると同時に、一種の芸術でもあった。
しかし明治以降、建築は急速に「科学」として再構築された。西洋の構造力学、材料工学、設備工学が導入され、建築は計算可能な技術体系となった。棟梁が持っていた身体化された知──木の癖を読む眼、空間のバランスを感じる感覚──などは、数値化できないがゆえに、近代的な教育制度からこぼれ落ちていった。
EU諸国では1985年のEC理事会指令により、加盟国間で建築家資格の相互承認が進められた。これは、建築家の役割がヨーロッパ全体で共通の価値と基準を持つことを前提としている。一方、日本の一級建築士は、国際的な相互承認の枠組みに直接対応していない。APECアーキテクト・プロジェクトでは一級建築士がその要件とされたが、これは例外的な試みだ。
興味深いことに、北欧の一部の国(フィンランド、ノルウェー、スウェーデン)には建築家の試験制度や登録制度が存在しない。建築設計に従事するのに免許は不要であり、適格性の判断は地方自治体に委ねられている。しかしこれは日本の曖昧さとは異なる。教育機関が授与する学位そのものが、専門性の証明として機能しているのだ。
資格と作家性の狭間で
「アーキテクト」の語源であるギリシア語には「ものごとの原理や根本的な知識を備えた上で、職人たちを指導し、技術を統合して、制作を企画しうる能力を持つ者」という意味が込められている。この定義は示唆に富む。建築家には技術的能力だけでなく、構想力と統合力が求められることを含意しているからだ。
日本建築家協会は建築家の職能原則として「建築家は依頼者及び社会の期待に応え、人と人を結ぶ美しい快適な環境づくりをめざし、建築の精神によって絶えず新たなる創造へ向かい、人間の幸せに寄与する」と宣言している。ここには単なる設計業務を超えた、社会的使命が謳われている。
プリツカー賞を受賞した伊東豊雄は「建築家に一番必要なことは社会の中にもっと深く入り込んでいくことだ」と語る。建築家とは、物理的な建造物を作るだけでなく、その場を使う人の活力や成長、笑顔を作ることを意味するのだという。
アーキテクチャとしての建築
ある建築家は、現代において、社会構造を「アーキテクチャ」と呼称し、建築家を表層ではなく、それを下部から支える社会構造こそ設計すべきだと主張する。ここに至って、建築家の役割は物理的な建物の枠を超える。都市計画、環境設計、コミュニティ形成──建築家はシステムそのものの設計者となる。
安藤忠雄が独学で建築を学び世界的評価を得たこと、坂茂が紙管を用いた災害支援建築で社会貢献したこと。これらの事例が示すのは、建築家を定義するのは資格ではなく、建築を通じて何を実現するかという姿勢だということだ。
職能としての建築家が抱えるジレンマ
ここに、なぜ一級建築士の資格を持つ者が軽々しく建築家を名乗れないのか、という問いに対する答えが用意されている。それは建築家という言葉が、単なる職業名を超えた「作家」としてのアイデンティティを要求するからだ、ということだ。
多くの「建築家」と呼ばれる人たちは一級建築士の免許を持っているが、一級建築士の免許を持っていても、たとえば設計業務を行わない人も少なくない。資格は必要条件だが、十分条件ではない。建築家と呼ばれるには、独自の建築思想、一貫した美学、社会との対話──これらを作品として体現する必要がある。
この日本特有の曖昧さは、逆説的に建築家という言葉を重層的なものにした。アメリカやイギリスでは「建築家(Architect)」が法定資格であり、試験に合格すれば誰もが名乗れる明確な称号だ。しかし日本では、この曖昧さゆえに、建築家という言葉はむしろ重みを増した。誰でも名乗れるからこそ、名乗るには覚悟がいる、という状況を創出している。
法的保護がないということは、建築家という呼称が純粋に社会的承認によってのみ成立することを意味する。欧米では制度が建築家の地位を保証するが、日本では作品と実績が建築家としての承認を勝ち取る。この違いは、プロフェッショナルをどう定義するかという、より深い文化的差異を反映している。
欧米、特にフランスやドイツでは、建築家は医師や法律家と同様のエスタブリッシュメントとして確立されている。職能とは単なる職業ではなく、高度な専門知識と倫理的責任を伴う社会的使命を持つ役割を指す。1671年にフランスが設立した王立建築アカデミーは、建築家を芸術家として制度的に位置づけた最初の試みだった。
日本にはこうした職能概念の伝統が薄い。建築士は技術者であり、官公庁や企業に所属する者も多い。建築設計は独立したエスタブリッシュメントというより、より大きな建設産業の一部として認識されてきた。だからこそ、「建築家」という言葉が、制度の外側で、より文化的・芸術的なニュアンスを帯びることになったのだ。
ここには、失われた棟梁の記憶が影を落としている。かつて棟梁は、施主と直接対話し、土地を読み、材料を選び、空間を構想し、職人たちと協働して建築を実現させた。それは単なる技術の適用ではなく、総合的な判断と創造の行為だった。
ここで新たな問いが生まれる。現代において「建築家」を自称する者の多くは、実はこの棟梁的な統合性を取り戻そうとしているのではないか。設計士の下請けとして図面通りに作るのではなく、自らが施主と向き合い、プランを考え、空間の質に責任を持つ──一部の伝統工法を守る棟梁たちが今も実践しているように。
「建築家」という言葉の曖昧さは、制度の不備というより、むしろ近代化の過程で分断されたものを再統合しようとする、無意識の抵抗なのかもしれない。
建築家という生き方
建築家とは、結局のところ、それは資格でも肩書でもなく、建築を通じて世界と対峙する態度そのものと言えるかもしれない。
日本建築家協会は「地域の誇りをつくる建築家」「生きている歓びをつくる建築家」「子どもたちの好奇心をつくる建築家」が存在すると謳う。物理的な建造物を作ることだけが仕事ではない。その場を使う人の活力、地域のシビックプライド、持続可能な未来──これらをデザインすることが建築家の仕事なのだ。
一級建築士という資格は、建築という営為に参加するための通行手形だ。しかし建築家という呼称は、自ら獲得するものであり、作品によって証明されるものだ。資格があるから名乗れるのではなく、建築を通じて何を実現したかによって、初めて建築家と呼ばれる資格を得る。
このパラドックスこそが、建築家という役割の本質を物語っている。法的な保護がないからこそ、建築家という言葉は純粋に職能の質と思想の深度によって定義される。資格を持つ者が名乗ることを躊躇し、無資格でも名乗れる──この奇妙な状況が、逆説的に建築家という存在の真摯さを担保しているのだ。
つまり、建築家とは、資格ではなく、建築という行為を通じて社会と対話し続ける者の名ではないだろうか。


