【2025年最新版】建築スリットとは?構造スリットの役割・施工方法・標準図・写真付きで徹底解説
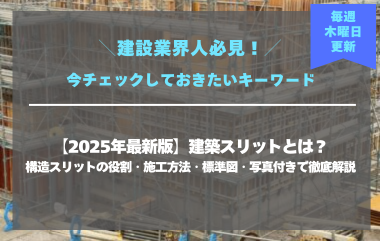
スリットは、鉄筋コンクリート造の建物を地震から守るために欠かせない仕組みです。しかし現場では「目地と何が違うの?」「施工でミスしたらどうなる?」といった疑問や不安の声も少なくありません。
そこでこの記事では、スリットの基本・役割・種類・施工方法・標準図・施工ミス事例までわかりやすく解説します。
目次
建築における「スリット」とは?
スリットとは、柱や梁と壁の間に意図的に設ける細い隙間のことです。
この切れ目を入れることで、地震時に建物の一部に力が集中せず、構造全体に揺れを分散させることができます。特に鉄筋コンクリート造(RC造)の建物では重要な要素で、「構造スリット」「耐震スリット」と呼ばれることもあります。
耐震性を左右する重要なスペースであるため、計画段階での確認が欠かせません。
目地との違い(混同しやすいポイント)
スリットと目地は見た目が似ていますが、役割が次のように異なります。
- スリット
→ 構造を切り離すための隙間であり、耐震性を高めるために設置する
- 目地
→ コンクリートやタイルの表面に入れる溝であり、ひび割れ誘発や仕上げ材の調整のために設ける
つまり、スリットは「建物を守る仕組み」、目地は「仕上げを守る工夫」という点が主な違いです。
建築基準法とスリットの関係
スリットは、1981年に「新耐震基準」が導入されて以降、柱や梁と雑壁を切り離すための設計が求められるようになりました。
(出典:国土交通省「住宅・建築物の耐震化について」)
実際、1995年の阪神淡路大震災では、スリットがない建物で柱や梁の破損が多発しました。その教訓から、スリットの設置が安全確保のうえで不可欠であると再認識されたのです。
このような背景もあり、建築基準法の第20条では「建築物は地震など外力に対して安全であること」が定められています。設計者はスリットを含めた耐震計画を行う義務があるため、「法律で裏付けされた安全対策」として必要なスペースだと覚えておきましょう。
(出典:e-Gov法令検索「建築基準法」)
また建築基準法関連の概要を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
構造スリット(耐震スリット)の役割と必要性
建物などに用いられるスリットは、正式名称を構造スリット(別名、耐震スリット)と言い、柱や梁といった主要構造部に過度な応力が集中するのを防ぎ、建物の倒壊リスクを下げて次の効果をもたらします。
- 地震時のエネルギーを分散できる
- 建物全体の変形能力(靭性)を確保できる
- 壁や柱の破壊を防ぎ、修繕コストを抑えられる
たとえば、柱と雑壁が一体化したままだと、大きな地震の揺れで壁が柱に強くぶつかり「せん断破壊」を起こす危険があります。対して構造スリットは「切り離す」ことで安全性を高めるのが特徴です。
建築スリットの種類と特徴
建築におけるスリットには、以下の示す4種類があり、それぞれ設置される位置や役割が異なります。
- 垂直スリット
- 水平スリット
- スリット壁
- 完全スリット・部分スリット
ここでは各スリットの特徴をわかりやすく解説します。
垂直スリット(柱と壁の分離)
垂直スリットは、柱と壁を切り離すために鉛直方向に設けられる隙間です。
目的は、地震時に壁が柱へ強く当たって破損させないことであり、柱内寸法の1/100程度の幅を確保します。
- メリット
柱の破壊を防いで、建物全体の耐震性を高める - 注意点
施工時にコンクリート側圧でずれやすいため、固定金具を使用する
垂直スリットは「見えない地震対策」のひとつです。施工ミスを起こさないためにも、設計段階でのチェックが欠かせません。
水平スリット(梁と壁の分離)
水平スリットは、梁と壁を切り離すために水平に設けられる隙間です。一般的に20〜30mm程度の幅を取ります。
- メリット
梁と壁が一体化せず、梁の変形を吸収できる - 注意点
止水処理を適切に行わないと漏水のリスクが高まる
特に屋外に面した妻壁やバルコニー部分では、スリットに防水材や止水ゴムを組み合わせることが推奨されています。
スリット壁(雑壁の影響を防ぐ仕組み)
スリット壁とは、雑壁(構造的に不要な壁)を主要構造から切り離して設置する壁のことです。
- メリット
雑壁による応力集中を避けられる - 注意点
振れ止め筋を入れて、壁がふらつかないよう補強する必要がある
雑壁は柱や梁に直接つながると、地震時に構造体に悪影響を与えることがあります。そのためスリットを入れて「力を逃がす」工夫が必要です。
完全スリットと部分スリットの違い
ここまで紹介した各スリットには、完全スリットと部分スリットの2種類があります。以下にそれぞれの違いを整理しました。
| 種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 完全スリット | 壁と柱・梁を完全に切り離す | 応力伝達を防ぎ耐震性が高い | 壁の安定性を確保する補強が必要 |
| 部分スリット | 一部鉄筋で柱・梁と接続 | 壁の安定性を確保しやすい | 応力が一部伝達し耐震効果が低下する可能性 |
たとえば、マンションの耐震壁や公共施設のように「耐震性を最優先」したい場面では完全スリットを選びます。
一方で、学校やオフィスのように「ある程度の耐震性を確保しながらも、壁を揺れにくく保ちたい」場面など、壁の安定感や施工性も考慮したいときには、部分スリットを採用するケースが多いです。
構造スリットの施工方法と注意点
構造スリットの施工は、新築工事と補強工事(リフォーム・耐震改修)で方法が少し異なります。重要なポイントを以下に整理しました。
【新築の場合】
- 設計図・標準図に従い、型枠施工の段階でスリット材を設置する
- コンクリート打設の際にスリット材がずれないよう、固定金具で固定する
- 打設後に型枠を外し、所定の幅(垂直1/100、水平20〜30mm程度)が確保されているか確認する
【補強工事等の場合】
- 既存の壁をグラインダーで切断し、柱や梁と分離する
- RCレーダー探査で鉄筋位置を把握し、誤って鉄筋を切らないよう注意する
- 切り離した隙間に、発泡ポリエチレン材やロックウールを充填する
- 最後に止水用のシーリング・耐火材を施工する
ただし、どちらの場合でも「適切な位置に設ける」「隙間に緩衝材を充填する」「止水・耐火処理を行う」という基本は共通です。
施工ミスの事例と対策
スリット施工では、ちょっとした不注意が建物の安全性に大きな影響を及ぼします。以下に代表的な施工ミスと、その対策を紹介します。
- スリット材のずれ
コンクリート打設時に圧力でスリット材が動いてしまい、隙間が確保できない
- 止水処理の不足
バルコニーや外壁部で防水処理が甘く、雨漏りの原因になる
- 幅(スペース)不足
垂直スリットの幅が壁高さの1/100以下だと、地震時に壁が柱にぶつかって破壊する
- 鉄筋の誤切断
既存建物の補強工事で、鉄筋を誤って切ってしまう
各施工ミスを対策するためには、打設前にスリット材を固定金具で保持し、ずれを防ぐほか、雨掛かり部にブチルゴム付き製品や段差スリットを採用するといった方法があります。
また、設計通りの幅をスケールで確認し、施工管理者がチェックする、補強工事では必ずRCレーダー探査を実施して鉄筋位置を把握するなど、ルールを決めて対策をすることで手戻りを防止しやすくなります。
建築スリットについてよくある質問【FAQ】
スリットとは建設業で何を指しますか?
スリットとは、柱や梁といった主要構造部材と壁をわざと切り離すために設ける隙間のことです。地震時に壁から構造体へ不要な力が伝わるのを防ぎ、建物全体の耐震性を高める役割があります。伸縮や防水にも関わる重要な設計要素です。
スリット構造とは何ですか?
スリット構造とは、建物の柱・梁と雑壁を完全または部分的に分離して設計する構造形式です。これにより地震の揺れで雑壁が壊れたり、柱や梁が破損するリスクを減らせます。阪神淡路大震災以降、建築基準法でも導入が広がった安全性重視の構造設計です。
スリット部とは建築における何を指しますか?
スリット部とは、設計図上で「スリットを設ける部分」を指し、柱と壁・梁と壁の境界に位置します。ここには緩衝材や止水処理材が充填され、耐震・防火・防水の性能を維持する工夫が求められます。施工精度が不足すると漏水や耐震性低下の原因になります。
建築スリットにはどんな種類がありますか?
建築スリットには、柱と壁を切り離す「垂直スリット」、梁と壁を分離する「水平スリット」、雑壁を構造体から切り離す「スリット壁」の3種類があり、「完全スリット」と「部分スリット」に分けて設計検討を実施します。
まとめ
建築における「スリット」は、特に構造スリット(耐震スリット)は地震時に建物を守る重要な仕組みです。垂直スリット・水平スリット・スリット壁など、用途に応じた種類があり、完全スリットと部分スリットの使い分けによって構造性能が変わります。
一方で、施工精度や止水処理に不備があると耐震性や耐久性に悪影響を及ぼすため、施工時の注意点や標準図の確認が欠かせません。
特に阪神淡路大震災以降は建築基準法改正によりスリットの重要性が明確化され、現在ではほぼ必須の設計要素となっているため、建築設計に関わる人なら、誰もが理解しておきたいキーワードです。と」です。施工後のメンテナンスまで意識して比較すれば、コストを抑えつつ美観を10年以上維持することも可能です。


