【2025年最新版】建築士の受験資格を徹底解説!一級・二級・木造ごとの要件と実務経験の最新ルールとは?
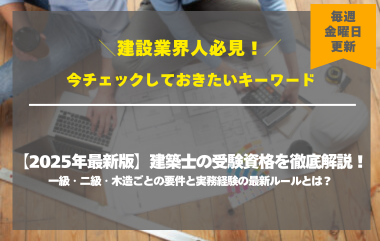
この記事では、日本の三大・五大建築家をはじめ、海外の巨匠、現代を代表するデザイナー、さらに若手や女性建築家まで幅広く紹介します。
建築士の受験資格は、2020年の建築士法改正以降、受験時点で実務経験が不要になり、大学・専門学校・高校などで指定科目を修了していれば受験資格を得られるようになりました。ただし、免許登録には学歴に応じた実務経験が必須である点には注意が必要です。
(出典:建築技術教育普及センター「建築士試験の受験資格が変わります!」)
そこでこの記事では、一級・二級・木造建築士それぞれの受験資格の違いや、実務経験が必要になるタイミングについて、これから受験を検討している方に向けてわかりやすく解説します。
目次
建築士の受験資格はどう変わった?【最新制度】
建築士の受験資格は、2020年の建築士法改正で大きく変わりました。
従来は「受験前に一定の実務経験が必須」とされていましたが、現在は学歴要件を満たせばすぐに受験が可能になっています。その一方で、免許登録の段階で学歴に応じた実務経験が必要と整理された点が主な違いです。
つまり、試験に合格しても、実務経験がなければ免許を登録できない点に注意が必要です。合格後に登録できないというトラブルを避けるためにも、実務経験に認められる業務内容(設計・工事監理・施工管理など)を早めに確認しておきましょう。
※合格後すぐに実務経験がなくとも、実務経験が揃ってからの登録が可能です。
また建築士法の概要もチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです▼
一級建築士の受験資格
一級建築士は、建築士のなかでも最も高いレベルの国家資格です。
超高層ビルや大規模施設の設計・工事監理を行えるため、受験資格は法律で厳格に定められています。
ここでは最新の制度に沿って、受験資格の条件と注意点を整理します。
(出典:建築技術教育普及センター「一級建築士|受験資格」)
受験資格(学歴・資格による要件)
一級建築士の受験資格は、以下のいずれかを満たすことが条件です。
- 大学・短大・高等専門学校・専修学校等で指定科目を修めて卒業した者
- 二級建築士の取得者
- 建築設備士の取得者
- その他、国土交通大臣が特に認める者
(例:外国大学の建築学科卒業者など)
ここで重要なのは、「入学年度による違い」です。
たとえば、平成21年度以降に入学した人は、国土交通大臣が指定する「建築に関する指定科目」を修めて卒業する必要があります。一方で、平成20年度以前に入学した人だと、従来の所定課程を修めて卒業していれば受験資格が認められます。
さらに、外国の大学で建築を学んだ場合は、建築士法第14条第三号の審査を受け、国土交通大臣から「国内の学歴と同等以上」と認定される必要がある点に注意してください。
(参考:e-Gov法令検索「建築士法」)
免許登録に必要な実務経験年数(学歴別一覧表)
2020年(令和2年)の制度改正以降、一級建築士試験を受験する時点では実務経験は不要になりました。しかし、試験合格後に免許登録を行う際には、学歴に応じた実務経験が必要です。以下はそのチェックポイントです。
- 実務経験の有無は「受験資格」ではなく「登録資格」で審査される
- 設計事務所、施工会社、行政機関などでの設計・工事監理・施工管理業務が対象
- アルバイトや一般事務は含まれない
なお免許登録時には、大学建築系卒業者は2年以上、短大・専門学校卒業者は3〜4年以上の実務経験が必要です。
二級建築士の受験資格
二級建築士は、一般住宅や中規模建築物の設計・工事監理を担える資格です。
建築士法第15条で受験資格が規定されており、学歴や資格に応じて必要な実務経験年数が異なります。
特に「入学年度」と「実務経験を積んだ時期」によって条件が分かれる点に注意が必要です。
(出典:建築技術教育普及センター「二級建築士|受験資格」)
学歴による条件
二級建築士試験は、次のように学歴に応じた受験資格が定められています。
- 大学・短大・高専・高校・専修学校・職業訓練校で指定科目を修めて卒業した者
→ 実務経験0年で受験可能 - 建築設備士の資格を持つ者
→ 実務経験0年で受験可能 - 外国大学等を卒業した者
→ 都道府県知事の審査を受けて「国内と同等以上」と認定されれば受験可能 - 建築に関する学歴がない者
→ 7年以上の実務経験が必要
また、一級建築士と同じように、平成20年度以前・21年度以降の入学年によって学歴要件が変わる点も重要です。
実務経験の扱い
二級建築士の実務経験要件は、制度改正により大きく変わりました。
- 令和2年3月1日以降の建築実務
→ 「受験資格」において実務経験は不要
→ 学歴要件を満たせば卒業後すぐに受験可能 - 平成20年11月28日〜令和2年2月29日までの建築実務
→ 改正前の要件に従って判定される - 平成20年11月27日以前の建築実務
→ 旧制度に基づき、学歴がない場合でも「有効と認められる実務」を7年以上積むことで受験資格を得られた。
つまり現在は、「学歴がある人は実務経験ゼロで受験可能」「学歴がない人は7年以上必要」という整理になっています。
よくある勘違い「二級建築士には受験資格がない?」の真相
ネット上では「二級建築士には受験資格がない」という誤解を見かけます。結論から言えば、学歴や資格があれば卒業後すぐに受験できるため、受験資格のハードルが低いという意味合いで使われているケースが多いです。
ただし実際には、次の条件があります。
- 高校建築科や専門学校建築系の卒業者は即受験可能
- 大学卒業者も同様に即受験可能
- 学歴がない場合だけ「7年以上の実務経験」が必要
「受験資格がない=誰でも受けられる」わけではないと覚えておきましょう。
木造建築士の受験資格
木造建築士は、木造2階建て以下・延床300㎡以下の住宅や建築物を設計・監理できる資格です。
受験資格は二級建築士と学歴+実務経験要件の考え方が類似しており、次のような「学歴要件」と「実務経験要件」の組み合わせで決まります。
| 学歴・資格 | 必要な実務経験年数(試験時) |
| 大学・短大・高専・高校・専修学校・職業訓練校で指定科目を修了し卒業 | 0年 (学歴があれば卒業後すぐ受験可能) |
| 建築設備士 | 0年 |
| 外国大学卒(都道府県知事の認定が必要) | 所定の年数以上 |
| 建築に関する学歴なし | 7年以上 |
つまり、建築系の学歴や建築設備士資格をもつ人は実務経験ゼロで受験可能です。一方で学歴がない人は7年以上の実務経験が必要となります。
(出典:建築技術教育普及センター「木造建築士|受験資格」)
また、建築系の仕事では、建築士以外の国家資格を目指すルートもあります。詳しくは以下の記事をチェックしてみてください▼
実務経験として認められる業務内容
建築士試験における「実務経験」は、単なる会社勤務年数ではなく、次のような建築に関する一定の業務に従事した経験を指します。
| 区分 | 業務内容 | 実務経験としての扱い |
| 設計業務 | 意匠設計、構造設計、設備設計、図面作成の補助 | 認められる |
| 工事監理業務 | 設計図通りに工事が行われているか確認する業務 | 認められる |
| 施工管理業務 | 工程管理・安全管理・品質管理など、現場での管理業務 | 認められる |
| 行政・公的機関での業務 | 建築確認申請の審査、建築行政関連の実務 | 認められる |
| 調査・評価業務 | 耐震診断、劣化調査、省エネ性能評価など | 認められる |
| 事務作業・営業活動 | 書類作成や営業活動など、建築士業務に直接関わらない作業 | 原則認められない |
| CADオペレーターのみの補助作業 | 建築士の指示に従って単純に図面を描くだけの業務 | 原則認められない |
なお、免許登録時には、勤務先の上司や建築士の署名が入った「実務経験証明書」の提出が求められます。以下は記入するポイントです。
- 経験内容は「建築士業務との関連性」が明確であること
- 勤務期間が客観的に証明できること(雇用契約書・在職証明書など)
- 複数の勤務先で積み上げた経験も合算可能
これらを正しく準備しておくことで、登録審査をスムーズに通過できます。
最短ルートで建築士を目指す方法
結論から言うと、学歴と実務経験の組み合わせ次第で最短ルートは変わります。
ここでは、高校卒業後すぐに進学する場合と、社会人や大学生から転身する場合における学習の最短ルートを紹介します。
高校生からのルート
高校を卒業した時点で建築分野に進む場合、建築系の大学や専門学校に進学するのが最短ルートです。
特に大学進学ルートは、実務経験が「免許登録時」に求められる形に改正されたため、卒業直後から受験できるメリットがあります。早ければ22歳で二級建築士、25〜26歳で一級建築士の合格を狙えます。(個人差あり)
はじめて建築の学習を始める方は、以下の建築用語から覚えていくのがおすすめです▼
社会人・大学生からのルート
社会人や大学で別分野を学んでいる人が建築士を目指す場合には、次のルートがおすすめです。
- 文系大学や他分野卒
→ 建築系の専門学校・通信教育に通い、必要な指定科目を履修することで受験資格を獲得可能 - 社会人経験者
→ 建築関連の職場で実務経験を積みながら、夜間・通信の建築課程で学び資格取得を目指す - 二級建築士から一級建築士へ
→ 実務を積みながらキャリアアップを図るのが現実的かつ王道ルート
最近では、社会人向けの通信教育課程や夜間課程が増加しています。仕事と両立しながら資格取得を目指す人も多いため、受講を検討してみてはいかがでしょうか。
通信や社会人向け学習で受験資格を得る方法
建築士を目指したいけれど、すでに社会人として働いていたり、大学で別の分野を専攻していたという方は「通信教育」や「夜間課程」を活用するのがおすすめです。以下にメリットをまとめました。
- 働きながら学習できる
- 卒業後に二級建築士・木造建築士の受験資格を取得できる
- 独学では難しい「建築構造・設備・法規」なども体系的に学べる
たとえば、建築士法にもとづいて国土交通大臣が指定した通信制専門学校や短大であれば、卒業時点で受験資格を満たせます。
なお、通信・夜間課程だけではなく、実務経験を積むことも同時に必須です。建築会社や設計事務所で働きながら通信課程で学ぶことで、最短で受験資格を得られます。
建築士の受験資格についてよくある質問【FAQ】
二級建築士の受験資格は本当にないの?
二級建築士の受験資格は「誰でも受けられる」という意味ではありません。建築に関する学歴や資格があれば最短0年で受験可能ですが、学歴がない場合は7年以上の実務経験が必要です。
建築士受験資格に「大学卒業」は必須?
大学卒業は必須ではありません。専門学校や高等学校の指定学科でも条件を満たせば受験可能です。学歴がない場合でも、所定の実務経験を積めば資格を得る道が開かれています。
実務経験はいつ必要になる?
二級建築士や木造建築士の場合、学歴によっては実務経験が不要なケースもあります。一級建築士は令和2年以降、試験合格後の登録時に実務経験の確認が必要となり、学歴と実務の両方を満たす必要があります。
社会人でも建築士を目指せる?
社会人からでも十分に目指せます。通信課程や夜間の建築学科で学歴要件を満たし、実務経験を積めば受験資格を取得可能です。仕事を続けながら学べる制度が充実しているため、キャリアチェンジにも対応できます。
通信教育だけで資格は取れる?
通信教育で指定科目を履修し卒業すれば学歴要件を満たせますが、建築士免許取得には試験合格が必要です。さらに登録には実務経験も求められるため、通信教育「だけ」で完結するわけではなく、学習+実務の両立が不可欠です。
まとめ
建築士試験の受験資格は、一級・二級・木造によって条件が異なります。また、学歴や入学年度によっても細かく変わります。
そして、受験する際のポイントとなるのが、学歴で満たせない部分を実務経験で補えること、そして一級建築士では試験合格後に登録時の実務経験審査が必須になっている点です。
社会人や未経験からでも、夜間・通信課程を利用すれば受験資格を満たすことは十分可能ですので、学歴と実務経験のバランスを計画的に整えつつ、受験を目指してみてはいかがでしょうか。


