【2025年最新】建設物価指数とは?推移・建築費指数との違いと国交省データの見方を徹底解説
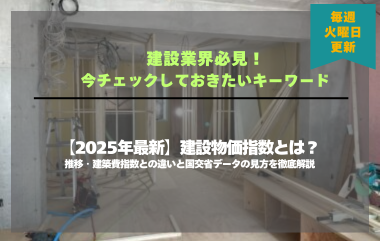
建設業界では、資材価格や労務費の変動が工事費に直結します。その動きを客観的に把握するために使われるのが「建設物価指数」です。
そこでこの記事では、国土交通省や一般財団法人建設物価調査会が公表している、建設物価指数の情報についてわかりやすく解説します。また、2025年最新の情報や過去からの推移、実務での使い方も紹介します。
目次
建設物価指数とは?基本の仕組みと役割
建設物価指数とは、建設工事に必要な「資材価格」「労務費」などの変動を数値化した指標です。
物価の推移を定点観測して、工事費の動向やコスト管理の基準として利用されています。また、基準となる指数を出された後は、公共工事の積算や建設業界全体の経済分析に活用されるのが特徴です。
建設物価指数は建築費指数・建設資材物価指数に分かれる
建設物価指数は大きく分けて「建築費指数」 と 「建設資材物価指数」の2種類が存在します。以下に2つの指標の概要を整理しました。
- 建築費指数
建築費指数は、建築物の工事価格の動きを建物ごとに示す指数です。集合住宅、事務所、工場、木造住宅などの建物タイプ別に算出されており、建物単位の工事費の変動を比較するのに適しています。 - 建設資材物価指数
工事に直接使用される資材価格の動向を明らかにする指標です。燃料や機械使用料は含まず、資材そのものの価格変動に特化しています。
両方を組み合わせて見ることで、資材価格の上昇が建物全体の工事費にどの程度影響しているかを把握できます。
建設工事費デフレーターとの違い
建設工事費デフレーターは、国全体の経済統計の一部として算出し、マクロな視点で建設投資額を分析する仕組みです。対して、建設物価指数はより現場寄りで、資材・労務ごとの詳細な価格変動を把握します。
つまり「国全体の建設投資動向をみるならデフレーター」「工事費の具体的な積算や契約調整なら建設物価指数」と役割が分かれています。
建設物価指数の調査主体と情報源(国土交通省や建設物価調査会)
建設物価指数は、主に以下の2機関が調査・発表しています。
- 国土交通省
「建設工事費デフレーター」などを通じ、GDP統計の一部として利用 - 建設物価調査会
「建設物価指数」「建築費指数」などを独自に調査し毎月公表
両者は対象や計算方法が異なりますが、どちらも業界関係者にとっては欠かせない一次情報源です。たとえば、建設物価調査会が毎月10日前後に発表する「建築費指数月報(詳しくは後述)」は、実務でよく参照します。
出典:建設物価調査会公式サイト / 建設工事費デフレーター(国土交通省)
建設物価指数の推移(最新データと長期比較)
建設物価指数は年ごとの資材価格や労務費の変動を反映しているため、短期的な動向と長期的なトレンドを両方確認することが重要です。
ここでは最新の速報値と過去10年の推移を整理します。
2025年最新の建築費指数の月報(速報値)
一般財団法人 建設物価調査会が発表した2025年8月の建築費指数(2015年=100)によると、東京の代表的な建物の工事原価は以下のとおりです。
| 建物種類 | 構造 | 指数 | 前月比 | 備考 |
| 集合住宅 | RC造 | 139.2 | +0.1% | 小幅に上昇 |
| 事務所 | S造 | 137.8 | ±0.0% | 横ばい |
| 工場 | S造 | 136.4 | -0.0% | わずかに下落 |
| 住宅 | 木造 | 143.2 | ±0.0% | 高水準を維持 |
たとえば、集合住宅(RC造) が微増しており、都市部での資材価格や施工コスト上昇を反映しているのがわかります。また、事務所(S造) は横ばいで推移し、安定傾向。さらに工場(S造) は小幅に下落し、産業系建物ではコスト調整が進む兆しです。
なお、木造住宅は前月比横ばいながら高い水準を維持し、木材価格や労務費の影響が続いています。
このように、建築費指数は建物用途ごとに価格変動を把握できるのが特徴です。公共・民間を問わず、予算策定や融資判断、設計見直しの際に参照されます。
(出典:建設物価調査会「建築費指数【2025年8月分】」)
2025年最新の建設資材物価指数の月報(速報値)
一般財団法人 建設物価調査会が公表した2025年8月の建築費指数月報によると、東京における総合指数(2015年=100)は 143.2でした。
- 前月比:+0.1%
- 前年同月比:+3.2%
| 部門 | 指数 (2015年=100) | 前月比 | 前年同月比 |
| 総合 | 143.2 | +0.1% | +3.2% |
| 建築部門 | 141.9 | +0.1% | +2.6% |
| 土木部門 | 147.7 | +0.3% | +4.3% |
| 建築補修 | 139.8 | ±0.0% | +3.5% |
特に 土木部門の上昇率が+4.3% と大きく、公共工事を中心にコスト増加が続いている点が注目されます。一方で「建築補修」は前月比横ばいで推移しており、改修工事における資材価格は安定傾向にあります。
(出典:建設物価調査会「建設資材物価指数【2025年8月分】」)
建設物価指数の実務での使い方
建設物価指数は単なる統計データではなく、実際の現場や経営判断に直結する指標です。積算や契約調整、資金計画など、次のようにさまざまなシーンで活用されています。
- 積算や見積もりの基準として
- 契約・価格調整の交渉材料に
- 資金調達や事業計画の判断材料に
例として、建設会社や設計事務所は、建設物価指数を見積書や積算根拠の裏付けとして利用します。また、資材価格が大きく変動する局面では、建設物価指数が発注者と施工者の交渉材料となります。
加えて、金融機関やデベロッパーも、建設物価指数を投資判断や融資審査の参考指標としています。
建設物価指数についてよくある質問【FAQ】
建物物価指数とは何ですか?
建物物価指数は、建築物を完成形の「建物単位」で捉え、工事費の変動を示す指数です。建設資材の価格や労務費を組み合わせ、集合住宅・事務所・工場・住宅など用途ごとに算出されます。公共工事の積算や、民間建築におけるコスト比較の基準としても用いられ、建築計画の妥当性を判断する指標になります。
建設資材物価指数の2025年最新情報は?
2025年8月に公表された建設資材物価指数(2015年=100、東京)は総合で143.2、前年同月比+3.2%と高止まりの傾向が続いています。建築部門は141.9(+2.6%)、土木部門は147.7(+4.3%)、建築補修は139.8(+3.5%)と分野別に差が見られます。
木造・RC造・S造の住宅の建設物価指数は?
2025年8月の建築費指数によると、東京では木造住宅が143.2で高水準を維持し、鉄筋コンクリート造(RC造)の集合住宅は139.2と前月比+0.1%の小幅上昇でした。一方、鉄骨造(S造)の事務所は137.8で横ばい、工場は136.4でわずかに下落しました。
まとめ
建設物価指数は、資材価格や労務費の変動を数値化し、積算・契約・資金計画の判断に欠かせない指標です。建築費指数・建設資材物価指数を組み合わせて確認することで、建設コストの全体像を正しく把握できます。
なお、2025年も依然として高水準が続いている状況です。月報なども公開されているため、今後の工事計画や予算策定では常に最新データの活用することを意識しましょう。


