【2025年最新】建設業法施行令をわかりやすく解説|令和7年改正内容・条文別ポイント・施行規則との違い
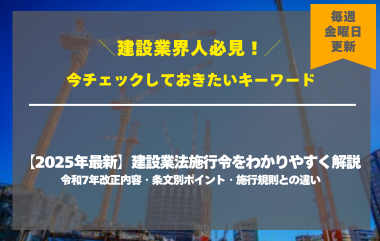
建設業に関わる方にとって「建設業法」は必ず守らなければならない基本ルールです。しかし実務で重要なのが、法律そのものよりも、より細かく基準を定めた「建設業法施行令」になります。
そこでこの記事では、建設業法施行令の概要から、実務に直結する主要な条文についてわかりやすく解説します。また、令和7年度の最新改正情報も紹介しているので、ルールを読み解く参考にしてみてください。
建設業法施行令とは?
建設業法施行令とは、建設業法を実際に運用するために内閣が制定する「政令」です。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令」)
建設業法は法律として理念や方向性を示していますが、抽象的でそのままでは現場に当てはめにくい部分が多いです。そこで、施行令によって次のようなルールが明文化されます。
- 許可が必要となる工事金額の下限
- 主任技術者や監理技術者を配置しなければならない基準
- 「軽微な工事」として許可不要になる範囲
「何をやれば法令違反になるのか(ならないのか)」を判断するうえで欠かせない指針です。建設業法施行令は数年ごとに改正が入り、基準が変わるため、常に最新版を押さえておきましょう。
建設業法・施行令・施行規則の違い
建設業にかかわる3つのルール(法律・政令・省令)は、それぞれ役割が異なります。比較表を整理しました。
| 区分 | 制定機関 | 内容のレベル感 |
| 建設業法 (法律) | 国会 | 大枠・理念 |
| 建設業法施行令 (政令) | 内閣 | 数値基準や条件 |
| 建設業法施行規則 (省令) | 国交省 | 実務手順・様式 |
建設業法が「骨格」、施行令が「肉付けされたルール」、施行規則が「運用マニュアル」に近い立ち位置です。
また、建設業法や施行規則の概要を知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建設業法施行令や施行規則・ガイドラインの違い
建設業界では「ガイドライン」もよく登場しますが、ここにも次のような違いがあります。
- 施行令・施行規則
法的拘束力あり。違反すれば行政処分の対象。 - ガイドライン
国交省が示す指針。努力義務に近く、法的強制力はない。
(ただし実務上は遵守が推奨され、許可審査や監査で参照されやすい)
現場感覚で言えば、「やらなくても罰則はないが、やらないと不利になる可能性が高い」のがガイドラインです。なお監査の際には、ガイドラインを基準に指摘を受けるケースが多いため、無視せず参考にしておく必要があります。
建設業法施行令の主要条文解説
建設業法施行令には、現場の実務に直結する条文が数多く存在します。ここでは、特に重要度が高く、許可や技術者配置に影響する主要条文を整理して解説します。
- 第3条|使用人
- 第6条|主任技術者・監理技術者の配置
- 第7条の2|許可不要となる軽微な工事の範囲
- 第7条の4|工期短縮禁止と発注者の責務
- 第27条|下請契約に関する規定
- 第28条|監理技術者の兼任要件
- 第34条|主任技術者配置の特例
第3条|使用人
第3条は、建設業法における「使用人」の範囲を規定しています。
支配人や営業所の代表者を使用人とみなすと定めており、許可申請や欠格要件の判断基準に直結するため重要です。営業所の代表者が違反行為を行った場合でも、会社全体の責任が問われる仕組みとなっています。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令|第3条」)
第6条|見積期間・軽微工事・一括下請負の規制
第6条から第6条の4では、次のルールが定められています。
- 建設工事の見積期間や保証人が不要となる軽微工事の範囲
- 一括下請負を禁止する重要工事(共同住宅新築)
- 一括下請負の承諾手続を電子的に行う方法
工期短縮や責任逃れを防ぎ、品質確保と適正な契約を目的とする条文です。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令|第6条」)
第7条の2|下請代金支払期日と資本金要件
第7条の2では、建設業法の第24条の6第1項(下請代金支払期日と資本金要件)に関連する金額を「4,000万円」と定めています。
特定の許可や技術者配置の基準となる金額であり、工事規模の線引きに活用されます。金額基準は改正で見直される場合があるため、常に最新の数値を確認しておくことが重要です。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令|第7条の2」)
(出典:e-Gov法令検索「建設業法|第24条の6 第1項」)
第7条の4|施工体制台帳・体系図作成義務と金額基準
施行令第7条の4では、建設業法第24条の8第1項に定められている「施工体制台帳の作成・施工体系図の掲示の金額」として、次の基準を示しています。
- 請負金額5,000万円以上の工事
- 建築一式工事の場合:請負金額8,000万円以上の工事
施工体制台帳には、下請業者の名称・工事内容・工期などを記載し、現場ごとに備え置く必要があります。さらに施工体系図を作成し、現場の見やすい場所に掲示することも義務です。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令|第7条の4」)
(出典:e-Gov法令検索「建設業法|第24条の8」)
第27条|専任の主任技術者・監理技術者が必要な工事
第27条では、特定の大規模・重要工事について、専任の主任技術者または監理技術者の配置を義務づけています。
- 金額基準
4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上) - 対象工事
国・自治体発注の施設、公共性の高い建築物(学校・病院・図書館など)、社会インフラ施設(市場・工場・放送設備・熱供給施設など)
公共性が高く影響範囲の大きい工事では、現場に専任技術者を置き、品質や安全を確実に確保する体制が求められます。また、同一場所で密接に関連する複数工事を同一業者が行う場合には、1人の専任技術者がまとめて管理できる特例も認められています。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令|第27条」)
第28条|監理技術者・主任技術者の専任要件と金額基準
第28条では、主任技術者・監理技術者の配置に関する金額基準を示しています。
原則として、工事1件あたりの請負代金が1億円以上の場合(建築一式工事は2億円以上)、専任の配置が求められます。さらに、公共性が高い施設や多くの人が利用する施設の工事では、専任義務が強化されます。
ただし、工事金額が政令で定める基準未満である場合などには、専任要件が緩和される特例も認められています。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令|第28条」)
(出典:e-Gov法令検索「建設業法|第26条の3 イ」)
【令和7年改正】建設業法施行令の変更点まとめ
令和6年12月6日、国土交通省が「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました(施行日は令和7年2月1日)。以下が主な変更点です。
| 項目 | 改正前 | 改正後 |
| 特定建設業許可が必要となる下請契約金額の下限 | ・建築一式工事以外:4,500万円以上 ・建築一式工事:7,000万円以上 | ・建築一式工事以外:5,000万円以上 ・建築一式工事:8,000万円以上 |
| 施工体制台帳作成義務の下請金額の下限 | 同上:4,500万円/7,000万円 | 同上:5,000万円/8,000万円 |
| 主任技術者・監理技術者の専任が必要な金額下限 | 同上:4,000万円以上/8,000万円以上 | 同上:4,500万円以上/9,000万円以上 |
| 監理技術者等の専任義務(ICT合理化) | 工事ごとに専任配置 | ICT活用等の条件を満たせば請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)で2現場まで兼務可 |
| 特定専門工事の下請金額上限 | 4,000万円未満 | 4,500万円未満 |
| 営業所技術者の兼任要件(ICT合理化) | 原則兼任不可 | ICT活用条件を満たせば請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)の工事で1現場兼務可 |
| 技術検定の受験手数料 | 現行額 | 引き上げ(詳細は省令規定) |
今回の改正は「金額基準の底上げ」と「ICT活用による専任義務の合理化」が大きな柱です。特に中堅・中小建設業者は、許可要件や施工体制台帳作成義務の範囲が広がる一方で、ICT条件を満たせば人材負担が軽減されます。
建設業法施行令についてよくある質問【FAQ】
2025年度の建設業法改正で何が変わる?
2025年(令和7年)改正では、主に「金額要件の引上げ」と「監理技術者・営業所技術者の専任義務の合理化(ICT活用)」が行われました。特定建設業許可、施工体制台帳作成義務、主任技術者・監理技術者専任義務などの基準金額が従来より高くなり、一定規模未満の工事では負担が軽減されました。
建設業法で500万円以下の工事はどう扱われる?
建設業法施行令では「軽微な工事」として定義され、原則として許可不要の扱いとなります。たとえば、請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満)や、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事などが該当します。ただし、反復継続的に請け負う場合や、特定の条件を満たすと許可が必要となるケースもあるため注意が必要です。
建設業法施行令改正(令和7年)はいつから?
令和7年(2025年)2月1日から施行されています。なお、一部の規定(監理技術者の専任合理化など)は令和6年12月13日から先行施行されており、段階的な運用開始となっています。
宅建業法施行令とは何が違う?
建設業法施行令は「建設工事を請け負う業者」に関する詳細ルールを定めた政令です。一方、宅建業法施行令は「不動産取引(宅地・建物取引業者)」に適用される政令で、免許基準や業務運営上の細則を規定しています。いずれも法律を補完する政令ですが、対象となる業種(建設 vs 不動産取引)が異なります。
(出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法施行令」)
まとめ
建設業法施行令は、建設業法を現場で具体的に運用するために欠かせない政令です。
営業所や許可要件の定義から、主任技術者・監理技術者の専任義務、下請契約の金額基準まで、施工体制や契約実務に直結する細かなルールを規定しています。
なお、当施行令を理解するためには「最新の金額基準や専任要件を正しく把握しておくこと」が重要です。判断を誤ると違反や許可取り消しのリスクがあるため、常に最新の法改正情報を確認しましょう。


