【2025年最新】建設業法施行規則をわかりやすく解説|改正内容・第14条の2・様式まとめ
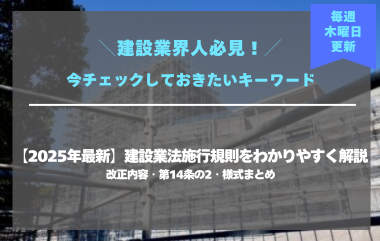
建設業界に関わる方であれば「建設業法」というキーワードを耳にしたことがあるはずです。では、その法律を現場で具体的にどう運用するか定めている「建設業法施行規則」については、どこまで理解できているでしょうか。
この記事では、建設業法施行規則の概要から主要な条文、第14条の2・14条の4の具体的な内容、財務諸表様式や施工体制台帳の書き方、押印廃止の改正ポイントまでわかりやすく解説します。
目次
建設業法施行規則とは?
建設業法施行規則とは、建設業法を具体的に運用するために制定された国土交通省令です。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行規則」)
まず「建設業法」には建設業に関する「法律」がまとめられており、基本的な枠組みを示しています。しかし、許可申請書の様式や施工体制台帳の記載方法、経営事項審査に用いる財務諸表の形式といった実務的な細部までは本文で定められていません。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法」)
そこで登場するのが「施行規則」です。次のような実務に関わる細目を規定しています。
- 許可申請や変更届に使用する「別記様式」
- 施工体制台帳や作業員名簿の記載方法
- 技術検定の実施要領
- 財務諸表の様式や注記のルール
つまり建設業法施行規則は、「建設業法を現場でどう運用するかを示すマニュアル」と言える存在です。建設業に携わる経営者、監理技術者、事務担当者など、必ず理解しておくべき規定となっています。
また建設業法の概要や2025年の改正情報を知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建設業法施行令と施行規則の違い
建設業法に関連するものとして、もうひとつ「建設業法施行令」があります。
(出典:e-Gov法令検索「建設業法施行令」)
施行規則と似た印象をもたれがちですが、次のような役割の違いがあります。
| 建設業法施行令 (政令) | 建設業法施行規則 (省令) | |
| 制定主体 | 内閣(政令) | 国土交通省(省令) |
| 役割 | 法律を実施するための基本的な枠組みを定める | 施行令をさらに具体化し、実務運用に必要な細部を規定 |
| 実務への影響 | 建設業許可が必要かどうかの判断に直結 | 許可申請や施工体制台帳の整備、財務諸表作成など日常業務に直結 |
簡単に説明すると、施行令が「法律の大枠」、施行規則が「現場実務のルール」というイメージです。この関係を知っておくと、建設業許可や契約書作成において「どの文書を参照すべきか」がわかりやすくなります。
また、建設業許可について詳しく知りたい方は、以下の記事もおすすめです▼
建設業法施行規則の主要な条文・規定
建設業法施行規則のなかでも、実務に直結する条文の概要を整理しました。
現場管理や建設業許可の維持に欠かせないため、各項目をチェックしておきましょう。
第14条の2(施工体制台帳の記載事項)
第14条の2では、施工体制台帳に必ず記載すべき内容が定められています。
公共工事や一定規模以上の工事では、多数の下請業者が関わります。そのため、工事全体の責任体制を明確にし、発注者や監督官庁がチェックできるようにする必要があります。
なお、施工体制台帳には、以下の項目を記載しなければなりません。
- 元請業者の商号・名称
- 工事の名称、工事場所
- 発注者の氏名または名称
- 主任技術者・監理技術者の氏名、資格
- 下請負人の商号、工事内容、契約金額
- 外国人技能実習生や特定技能者の氏名、在留資格、従事内容
国土交通省の定める様式にもとづき、漏れなく記載することが求められます。適切に整備していない場合、監督処分や許可取消のリスクもあるため注意が必要です。
(参考:e-Gov法令検索「建設業法施行規則|第14条の2」)
第14条の3(下請負人に対する通知等)
第14条の3は、元請業者(作成建設業者)が下請負人に対して重要事項を通知することを義務付けた規定です。
通知は書面または電磁的方法で行い、現場に掲示・表示して下請業者が容易に確認できるようにする必要があります。通知すべき内容は次の通りです。
- 作成建設業者の商号または名称
- 下請負人がさらに下請に出す場合には「再下請負通知」を行う義務がある旨
- 再下請負通知の書類を提出すべき場所
さらに、この通知は単に紙で渡すだけではなく、「工事現場の見やすい場所に掲示する」「電子計算機や電磁的記録を利用して表示する」といった方法で、下請業者が閲覧できるようにする必要があります。
(参考:e-Gov法令検索「建設業法施行規則|第14条の3」)
第14条の4(再下請負通知を行うべき事項等)
第14条の4は、下請業者がさらに別の建設業者に再下請を出す際に行う「再下請負通知」の具体的な内容を定めた条文です。再下請負契約の透明性を担保することが目的です。
通知に含めるべき内容は次の通りです。
- 再下請負通知人の商号・住所・許可番号
- 請け負った工事の名称、注文者名、契約締結年月日
- さらに下請させた業者に関する情報(商号、工事内容、契約条件など)
- 契約書の写し(請負代金額の一部を除外できる場合あり)
また、通知は書面だけでなく、電子情報処理組織を使った電磁的方法でも可能とされています。承諾を得れば、パソコンを介したファイル共有や電子媒体の交付で代替できます。
(参考:e-Gov法令検索「建設業法施行規則|第14条の4」)
建設業法施行規則の様式と書類
建設業法施行規則では、建設業許可や経営事項審査に必要な「別記様式(以下参考)」が定められています。
上記は、許可の更新や公共工事の入札可否を左右する重要書類です。「古い様式を使って申請が差し戻された」「記載漏れで審査が遅れた」といった声もあるため、常に最新版を確認したうえで、様式を揃えることが欠かせません。
建設業法施行規則の改正と押印廃止(令和3年から施行)
建設業法施行規則は、実務の変化にあわせて改正が重ねられてきました。そのなかでも大きな転換点となったのが、2021年1月1日施行の「押印廃止」です。
申請書や届出書など多くの別記様式から押印欄がなくなり、自署や電子申請での提出が基本となりました。なお、押印不要となった現在の対応方法を以下に整理しました。
- 許可申請書、変更届出書などで押印不要
- 電子申請の利用が拡大
- 訂正は訂正印ではなく書き直しが原則
- 自治体によっては本人確認書類の提出が追加される場合もあり
旧様式で申請すると差し戻されてしまうため、手続き前には必ず建設業法施行規則の最新情報を確認しておきましょう。
建設業法施行規則についてよくある質問【FAQ】
施行規則とは何ですか?
建設業法施行規則とは、建設業法を現場で具体的に運用するために国土交通省が定めた「省令」です。許可申請の別記様式、施工体制台帳や作業員名簿の記載方法、財務諸表の書き方など、実務で必要な細部を規定しています。つまり「建設業法を正しく実務に落とし込むためのルールブック」です。
建設業法に該当しない工事とは?
代表的なのは「請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満または木造住宅延べ面積150㎡未満)」の工事であり、この場合は建設業許可が不要です。たとえば、小規模な修繕やリフォームが典型例ですが、公共工事や特定条件に当てはまる場合は別途規制があるため注意が必要です。
特定建設業の7業種とは?
特定建設業とは、大規模な下請契約を伴う工事を請け負う場合に必要となる許可区分です。7業種とは、土木一式工事・建築一式工事・大工工事・とび土工工事・石工事・屋根工事・電気工事を指します。これらは特に規模が大きく、多くの下請業者を抱える工種のため、経営事項審査や財務基準も厳しく設定されています。
押印廃止はいつからですか?
建設業法施行規則における押印廃止は、2021年(令和3年)1月1日から施行されました。許可申請書や届出書など多くの別記様式で押印が不要になり、署名や電子申請での対応が原則となりました。事務効率は向上しましたが「旧様式を使用して差し戻された」という事例もあるため、申請前に最新版様式を必ず確認しましょう。
まとめ
建設業法施行規則は、建設業法を現場で具体的に運用するための重要な省令であり、許可申請の様式や施工体制台帳、再下請負通知など実務に直結する内容が細かく定められています。
特に第14条の2〜第14条の4は、元請・下請の関係や再下請負契約の透明性を確保するうえで欠かせない条文です。詳しく理解できていなかったという方は、建設業法施行規則に一度目を通しておくとよいでしょう。


