ブルータリズム建築を完全ガイド|意味・語源・特徴・歴史/日本・世界の名作とWebデザイン・映画まで【2025年最新】
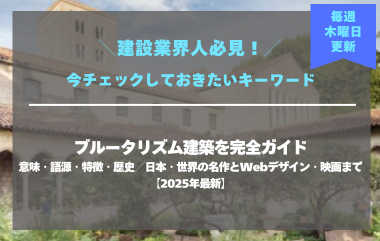
ブルータリズムは1950年代に登場した建築様式で、無骨なコンクリートをむき出しにしたデザインが特徴です。一見「冷たくて不気味」と思う人もいれば、その潔さや力強さに魅了される人もいます。
そこでこの記事では、ブルータリズムの意味や歴史、日本や世界の代表建築、デザインとの関係についてひも解いていきます。
目次
ブルータリズムとは?意味と語源

「ブルータリズム(Brutalism)」は、素材を隠さず“そのまま”見せる建築スタイルです。
特にコンクリートの打ちっぱなし仕上げが有名で、重厚で力強い印象を与えます。
また、名前から「ブルータル=残酷?」と誤解されがちですが、本来の語源はフランス語のbéton brut(ベトン・ブリュット=生のコンクリート)です。言葉の意味として「荒々しさ」ではなく「素材のありのまま」のことを指しています。
モダニズム建築との違い
ブルータリズムは「モダニズム建築」から派生した建築デザインのことであり、両者には大きな違いがあります。
| モダニズム建築 | ブルータリズム建築 | |
| デザインの印象 | 白く清潔、軽やかで普遍的 | 無骨で重厚、圧倒的な存在感 |
| 仕上げ | 壁や柱を塗装・パネルで覆う | コンクリートや素材をむき出し |
| 感じ方 | スッキリ・洗練 | 荒々しい・力強い |
つまり、モダニズムが「均整のとれた美」を追求したのに対し、ブルータリズムは「素材の生々しさや重量感」を表現した様式です。街歩きで見分ける際は、「白く滑らかか?灰色で無骨か?」を基準にするとわかりやすいでしょう。
また、建築様式とは別に、最新の建築技術を知りたい方は以下の記事もおすすめです▼
ブルータリズムの特徴
ブルータリズム建築は「素材そのものを隠さず見せる」ことで独特の迫力と存在感を放ちます。
ここでは、その特徴を4つの視点から解説します。
素材感を強調したデザイン(打ち放しコンクリートなど)
ブルータリズムの最大の特徴は、打ち放しコンクリートをそのまま見せる設計です。
戦後の建設ブームでは、安価で大量生産できるコンクリートが主流となります。そしてブルータリズムをもつ建築家たちは、コンクリートを覆い隠すのではなく「正直に見せる」ことに価値を見出しました。
装飾を排したミニマルな美学
ブルータリズム建築には、ほとんど装飾がありません。
なぜなら、目的は「機能そのものを見せる」だからです。余計な飾りを省き、構造や導線に直結したデザインとしました。「無駄を削ぎ落とす」ことで、建物の本質的な力強さが前に出てくる、それこそがブルータリズム建築の魅力です。
力強く重厚なフォルムと存在感
ブルータリズムは「そのままのフォルム」だからこその圧倒的な存在感があります。
第二次世界大戦といった戦後の復興期、公共建築や集合住宅に求められたのは「安心感」と「耐久性」でした。自然と町にブルータリズムの建物が増えていったのはもちろん、徐々にランドマークになる建物も増加していったのです。
建築以外への広がり(Webデザインなど)
ブルータリズムは今、建築だけでなくWebやグラフィックデザインにも応用されています。
なぜなら、その「無骨さ」「素材感を隠さない潔さ」が、デジタルデザインにも新鮮に映るからです。特に活用頻度の高いデザインを整理しました。
- 白黒や強いコントラストの色使い
- 等幅フォントやシンプルなタイポグラフィ
- 非対称レイアウトや要素の詰め込み
- シンプルすぎるナビゲーション
「つくり込まれすぎたWebデザイン」と対照的で、逆に個性や存在感を強調する手法として人気です。
(参考:文化庁「建築文化に関する検討会議(第3回)」)
ブルータリズムの歴史と背景
ブルータリズムは1950年代のイギリスで誕生しました。
第二次世界大戦後、各都市は空襲で荒廃し、安価で耐久性のある建材が求められていました。そこで「仕上げを施さないコンクリート建築」が合理的かつ象徴的な選択肢となったのです。
その後、ブルータリズムはヨーロッパから世界中へと広がりました。これは、大量生産可能なコンクリート建築が、復興期の住宅・公共建築に最適だったためです。
しかし、復興とともに1970年代以降、ブルータリズムは「醜い建築」と批判され衰退しました。灰色の外観や巨大なスケール感が「冷たい」「圧迫感がある」と感じられるようになり、現代では徐々に数を減らし続けている建築様式となっています。
日本におけるブルータリズム建築
日本でも1950年代〜70年代にかけて、ブルータリズム建築が数多く建設されました。
戦後の高度経済成長期において「公共性・耐久性・コスト効率」を兼ね備えたコンクリート建築は大いに重宝され、大学キャンパス、役所、集合住宅、文化施設などに広がりました。
なお日本では安藤忠雄の初期作品群(住吉の長屋ほか)が「打ち放しの素材感」を強く提示し、国内事例が多く参照されています。東京では代々木競技場のほか、区立図書館や大学キャンパスにもブルータリズム的意匠が点在します。
東京で見られるブルータリズム建築

「ブルータリズムを実際に見てみたい」という方に向け、東京を中心とした代表的な事例を紹介します。
| 建物名 | 所在地 | 設計者 | 特徴 |
| 国立代々木競技場(1964年) | 渋谷区 | 丹下健三 | 有機的曲線と大胆なコンクリート構造の融合。東京五輪の象徴。 |
| 東京都庁舎旧庁舎(1957年竣工、解体済み) | 千代田区 | 前川國男 | コンクリート打放しの庁舎建築。日本におけるブルータリズムの初期例。 |
| 国立国会図書館 国際子ども図書館(旧帝国図書館)改修部 | 台東区 | 前川國男 | 歴史的建築にブルータリズム的要素を融合。 |
| 東京カテドラル聖マリア大聖堂(1964年) | 文京区 | 丹下健三 | 巨大なコンクリートの翼を広げたような造形。宗教建築とブルータリズムの融合。 |
これらの建築は「無骨さ」と「公共性」の両方を兼ね備え、今もなお日本の都市にランドマークとして存在しています。
特に高度経済成長期の東京では、コンクリートを多用したスケール感のある建物が「時代の先端」として受け入れられました。
またブルータリズム建築以外にも、日本の名建築をチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです▼
世界の代表的ブルータリズム建築

ブルータリズムは1950年代から70年代にかけて、ヨーロッパ・アメリカ・日本を中心に世界中で建設されました。
特徴的な無骨さや力強さは都市のランドマークとなり、今日でも保存や再評価が進められています。ここでは代表的な建築をまとめて紹介します。
| 建物名 | 所在地 | 設計者 | 特徴・ポイント |
| ラ・トゥーレット修道院 | フランス・エヴー | ル・コルビュジエ | 生コンクリートを駆使した修道院。厳格な幾何学と光の演出が融合。 |
| ガイゼル図書館 | 米国・UCサンディエゴ | ウィリアム・L・ペレイラ | 宙に浮かぶランタンのような形。未来的デザインの象徴。 |
| ナショナル・シアター | 英国・ロンドン | デニス・ラスダン | 段状に重なるコンクリートの塊。批判と再評価を繰り返す代表作。 |
| トーレ・ブランカス | スペイン・マドリード | F.J.サエンス・デ・オイサ | 「成長する木」をテーマにした集合住宅。UFO的フォルムが話題。 |
| レ・シュー・デ・クレテイユ | フランス・パリ郊外 | ジェラール・グランヴァル | 丸い集合住宅群。「キャベツ集合住宅」と呼ばれ、20世紀遺産に登録。 |
| バービカン・センター | 英国・ロンドン | チェンバレン、パウェル&ボン | 大規模文化複合施設。住宅・劇場・美術館が一体化。 |
| 旧ホイットニー美術館(現メトロポリタン美術館別館) | 米国・ニューヨーク | マルセル・ブロイヤー | 逆ピラミッド型の重厚な外観。ニューヨーク近代美術の象徴。 |
| ジェネックス・タワー | セルビア・ベオグラード | ミハイロ・ミトロヴィッチ | ツインタワーを橋で連結。都市の玄関口に立つランドマーク。 |
これらの建築に共通するのは「無骨さを隠さず、社会性や都市性を強調した点」です。
都市復興の象徴として生まれたブルータリズムは、今なお街のランドマークとして圧倒的存在感を放ち、「嫌われながら愛される建築様式」として語り継がれています。
(参考:台東区『世界遺産「ル・コルビュジエ」の建築作品』)
また、美しい建築デザインの美術館をチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです▼
ブルータリズム建築についてよくある質問【FAQ】
ブルータリズムの特徴は何ですか?
ブルータリズムは、打ち放しコンクリートなど素材をそのまま見せる設計手法が特徴です。装飾を極力省き、構造体そのものの力強さや無骨さを前面に出します。直線的・幾何学的なフォルムや重厚感が強調されるため、公共建築や集合住宅で採用されることが多く、街のランドマークとして存在感を放っています。
ブルータリズムを代表するデザイナーや建築家は誰ですか?
代表的な建築家には、ル・コルビュジエ(ラ・トゥーレット修道院)、マルセル・ブロイヤー(旧ホイットニー美術館)、デニス・ラスダン(ロンドンのナショナル・シアター)、丹下健三(代々木競技場)などがいます。評論家のレイナー・バンハムは理論化に大きく貢献し、アリソン&ピーター・スミッソン夫妻が「新ブルータリズム」を提唱したことでも知られています。
ラースロー・トートは実在の建築家ですか?
ラースロー・トートは、映画『ブルータリスト』(2024年公開)に登場する架空の建築家です。物語の中ではホロコーストを生き延びてアメリカに渡り、ブルータリズムを提唱した人物として描かれています。ただしモデルとなった実在の建築家にマルセル・ブロイヤーなどの影響が指摘されており、史実と創作を織り交ぜて構築されたキャラクターです。
映画『ブルータリスト』のモデルとなった人物は誰ですか?
映画『ブルータリスト』の主人公ラースロー・トートは架空の人物ですが、ハンガリー出身でアメリカに渡ったマルセル・ブロイヤーとの共通点が多く指摘されています。ブロイヤーは実際に戦前ドイツから亡命し、アメリカで活躍した建築家です。映画は実在の史実を直接描くのではなく、戦後建築が抱えた社会的テーマやブルータリズムの思想を寓話的に表現することを意図しています。
まとめ
ブルータリズムは、戦後の混乱期に登場した「無骨でありながら誠実な建築様式」です。打ち放しコンクリートの素材感を隠さず見せ、装飾を削ぎ落とすことで、社会の復興や公共性を象徴する存在となりました。
その一方で「醜い」「圧迫感がある」と批判されることもあり、ときおり賛否両論が起こっています。しかし近年は、映画『ブルータリスト』の公開や保存活動の広がりをきっかけに、再び注目を集めました。
日本国内にも建築物が残っているため、この機会に足を運んでみてはいかがでしょうか。誌からも新しい知識やトレンドを取り入れましょう。


