【2025年最新】建築設備士とは?仕事内容・年収・受験資格・難易度・勉強時間まで徹底解説
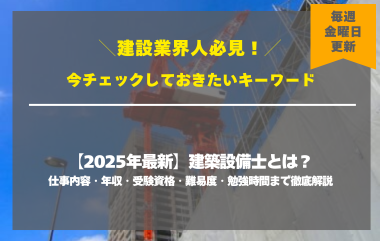
建物の安全性や快適性を支える「空調・給排水・電気設備」を総合的に理解し、建築士に助言できる唯一の国家資格が「建築設備士」です。近年は省エネ法改正や脱炭素社会の推進に伴い、建築設備士の存在がますます重要視されています。
そこでこの記事では、建築設備士の仕事内容や年収、受験資格、試験の難易度や勉強時間までを徹底解説します。
目次
建築設備士とは?国家資格としての役割
建築設備士とは、建築士法にもとづいて国土交通大臣が認める「建築設備に関する専門知識と技能を持つ有資格者」です。
特に、延べ面積2,000㎡を超える建物では、建築士が設備設計や工事監理を行う際に「建築設備士の意見を聴くよう努める」ことが法律上の努力義務とされています
(参考:e-Gov法令検索「建築士法|第18条」)
また、国土交通省や自治体では、省エネ適合義務化やZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)推進において、今まで以上に建築設備士の関与を評価しています。全国の都道府県では、確認申請書に建築設備士の記載欄が設けられています。
(参考:建築設備技術者協会『確認申請書に「建築設備士」の記載欄が充実 改正建築基準法が平成19年6月20日から施行となりました』)
また、建築設備の仕事概要からチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建築士との違い|アドバイザーとしての役割
建築士と建築設備士は、どちらも建物に関する専門資格ですが以下のように役割が異なります。
| 項目 | 建築士 | 建築設備士 |
| 主な業務 | 建物全体の設計・監理 | 建築設備に関する助言・計画 |
| 法的位置付け | 独占業務あり | 独占業務なし(助言義務あり) |
| 対象 | 構造・意匠・設備全般 | 空調・電気・給排水など設備分野 |
| 期待される役割 | 設計・工事監理の中心 | 建築士の補完、専門的アドバイス |
つまり、建築士が「建物全体の司令塔」だとすれば、建築設備士は「設備面の参謀役」と言えます。設備が複雑化する現代においては、両者の連携が高品質な建物を生み出す鍵です。
「建築設備士は意味ない?」と言われる理由と実際のニーズ
「建築設備士は意味がない」という声を耳にすることがあります。
しかし、それは建築設備士が独占業務をもたない資格だからです。建築士のように、直接「設計や工事監理を独占的に行う」ことはできず、あくまで助言者という立場にとどまります。そのため「資格を取っても活躍できないのでは?」と誤解されがちです。
一方で、建築設備士の現場でのニーズは年々強まっています。背景には以下の要素があります。
- 省エネ基準の義務化(2025年から全住宅対象)
- 脱炭素社会の推進(カーボンニュートラル政策)
- 大規模建築物の確認申請における「意見聴取」制度
上記について、建築士だけでは省エネ設計や設備の最適化に対応しきれません。実際のプロジェクトでは、建築設備士の助言がないと設計の見落としや性能不足につながることもあります。
建築設備士の年収・将来性
建築設備士は、資格をもつことで、待遇改善やキャリアアップに直結するケースが多く、今後も需要が高まる見込みです。
ここでは年収の相場と、将来性を左右する社会背景について解説します。
平均年収の相場(500~700万円)
建築設備士の平均年収は500万〜700万円が一般的です。
(参考:国税庁「民間給与実態統計調査」)
もちろん所属先や役職によって差はありますが、日本の平均年収(約461万円)と比較すると高めの水準です。
(出典:国税庁「1 平均給与」)
また、多くの企業では 資格手当(1万〜10万円/月) が支給されるため、実務経験とあわせて年収アップにつながりやすい点も特徴です。
脱炭素・省エネ法対応で需要が高まる背景
今後の建築設備士の年収や将来性を支える大きな要因は、脱炭素社会への移行と省エネ基準の義務化です。
- 住宅・非住宅の省エネ基準適合義務化(2025年4月施行予定)
- ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)やZEH住宅の普及
- カーボンニュートラルに向けた国土交通省・環境省の政策推進
これらにより、空調・換気・給排水・電気といった設備分野の専門家である建築設備士の役割はさらに重要性を増します。
建築設備士試験の受験資格と実務経験
建築設備士試験は、誰でも受験できるわけではなく、学歴・資格・実務経験のいずれか、あるいは組み合わせが必要です。
これらの条件を満たさないと受験申込ができないため、受験を目指す人は必ずチェックしておくべき重要ポイントです。
学歴要件ごとの受験資格(大卒・短大卒・高卒)
建築設備士試験は、建築・機械・電気分野の学科を修了しているかどうかで、必要な実務経験年数が変わります。
| 最終学歴 | 必要な実務経験年数 |
| 大学卒(建築・機械・電気系) | 2年以上 |
| 短大・高専卒 | 4年以上 |
| 高校卒 | 6年以上 |
| 専門学校卒(2年制・4年制) | 2~6年(修得単位数による) |
参考:建築技術教育普及センター「令和7年建築設備士試験 受験総合案内書」
大学で建築・設備系を学んだ場合は、最短2年で受験資格が得られるため効率的です。
実務経験だけで受験できるケース
学歴や他資格がなくても、9年以上の建築設備関連の実務経験があれば受験可能です。対象となる業務は以下のように幅広いです。
- 設計事務所での建築設備設計や工事監理
- 設備工事会社・建設会社での施工管理・積算
- ビル管理会社での維持管理業務(改修や保全を伴うもの)
- 大学や研究機関での設備関連研究
実務経験のみで挑む場合は、証明書類の提出が必須となるため、勤務記録や業務内容を早めに整理しておきましょう。
建築士や施工管理技士など資格保持者の特例あり
すでに他の建設系資格をもっている場合、必要な実務経験が大幅に短縮されます。
- 一級建築士・一級施工管理技士(電気・管工事)
- 空気調和・衛生工学会設備士
- 電気主任技術者(第1~3種)
資格保持者は2年以上の実務経験だけで受験資格を得られます。
建築設備士試験の概要と試験日程・スケジュール
建築設備士試験は、年1回実施される国家試験です。
試験は「第一次試験(学科)」と「第二次試験(設計製図)」の二段階に分かれており、どちらにも合格することで建築設備士資格を取得できます。
試験概要
以下の表に、試験の全体像を整理しました。
| 区分 | 内容 | 出題形式・科目 | 問題数 | 制限時間 |
| 第一次試験(学科) | 建築全般の知識を問う筆記試験 | 建築一般知識(27問)、建築法規(18問)、建築設備(60問) | 計105問 | 建築一般+法規:2時間30分建築設備:3時間30分 |
| 第二次試験(設計製図) | 設備計画と設計図作成 | 建築設備基本計画(記述)11問+建築設備設計製図(空調・換気・給排水・電気のうち選択1分野) | – | 5時間30分 |
試験日程(令和7年実施例)
2025年(令和7年)の建築設備士試験は以下のスケジュールで予定されています。
| 項目 | 日程(予定) |
| 申込受付期間 | 2月25日(火)10:00 ~ 3月14日(金)16:00 |
| 受験票発送 | 5月下旬 |
| 第一次試験(学科) | 6月中旬(日曜) |
| 一次試験合格発表 | 7月下旬 |
| 第二次試験(設計製図) | 8月中旬(日曜) |
| 二次試験合格発表 | 11月上旬 |
毎年6月〜8月に試験が集中するため、春までに基礎固めを終えるのが合格への近道です。ぜひ2026年に向けて学習をスタートしましょう。
申し込み方法・受付期間
建築設備士試験はインターネット申込のみで受け付けています。以下に申し込みの条件を整理しました。
- 必要書類:顔写真データ、卒業証明書・成績証明書または資格証明書の写し
- 受験手数料:36,300円+ネット受付事務手数料
- 受付期間:例年 2月下旬~3月中旬(令和7年は2/25~3/14)
なお2025年からは「受験資格証明書の原本郵送」が不要になり、写しをアップロードする方式へ変更されました。申込締切を逃すと翌年まで受験できないため、早めに準備しておきましょう。
建築設備士試験の合格率
建築設備士試験は、建築関連資格のなかでも難易度が高い部類に入ります。一次試験・二次試験ともに専門性が問われるため、計画的な学習が必須です。
以下に合格率の推移を整理しました。
| 年度 | 一次試験合格率 | 二次試験合格率 | 総合合格率 |
| 令和2年 | 25.7% | 41.4% | 13.5% |
| 令和3年 | 32.8% | 52.3% | 18.8% |
| 令和4年 | 31.4% | 46.4% | 16.2% |
| 令和5年 | 30.0% | 48.7% | 19.1% |
| 令和6年 | 33.3% | 53.4% | 21.5% |
| 令和7年(速報・一次のみ) | 26.1% | ― | ― |
参考:建築技術教育普及センター「建築設備士試験データ」
「合格できるのか不安」という方は、無料相談や合格体験談を参考に学習計画を立てると安心です。
建築設備士の勉強時間と勉強方法
建築設備士試験に合格するには、十分な学習時間を確保し、効率的な勉強方法を選ぶことが重要です。
特に社会人受験者が多いため、計画的に学習スケジュールを組むことが合否を左右します。参考として、「独学」と「スクール利用」の2パターンの違いをまとめました。
| 学習方法 | メリット | デメリット |
| 独学 | 費用が安い(参考書+過去問で2〜3万円程度)自分のペースで進められる | 計画管理が難しい製図試験は独学だと添削がなく不安 |
| スクール・講習会 | 講師から直接指導を受けられる製図試験の添削が受けられる仲間と学習できモチベ維持 | 費用が高い(10〜30万円程度)通学・通信のスケジュールに合わせる必要あり |
一次試験などは、試験サイトで公開されている過去問などを用いて対策しておけば、合格点を目指せます。
(参考:建築技術教育普及センター「建築設備士試験 試験問題等」)
ただし、二次試験(製図)は独学では難しいため、スクールや講習会の受講を検討する人が多いのが現実です。
建築設備士の難易度
結論から言うと、建築整備士の総合合格率は15〜22%前後で推移しており、建設業界のなかでも難関資格に位置付けられます。
建築設備士試験が難しいといわれるのは、次のように出題範囲の広さと試験方式の特性にあります。
- 出題範囲が広い
→ 建築一般・法規・設備(空調・換気・給排水・電気)と複数分野にまたがる
- 一次・二次の二段階突破が必要
→ 一次は暗記中心、二次は製図+記述の応用力が必須
- 学習負担が大きい
→ 合格まで500〜1,000時間が目安(特に社会人は確保が難しい)
特に二次試験の設計製図は、実務経験や製図力が不足していると合格が難しいです。そのため、スクールや添削指導を活用する人が大勢います。
他資格との比較(建築士・施工管理技士との違い)
建築設備士の難易度を、ほかの建設系資格と比較すると以下のようになります。
| 資格 | 総合合格率 | 主な特徴 |
| 一級建築士 | 約10%前後 | 法規・構造の深い知識+長期学習が必要 |
| 二級建築士 | 約20%前後 | 設計・法規中心、学習量は一級より少ない |
| 一級施工管理技士(管工事・電気工事) | 約35〜40% | 実務経験が必須、学科+実地試験 |
| 建築設備士 | 15〜22% | 設備特化の国家資格、一次+二次突破型 |
難易度は 二級建築士以上・一級建築士未満 と評価されることが多いです。特に設備分野の専門性に特化しているため、建築士よりもニッチで深い知識が求められます。
建築設備士取得のメリット一覧
建築設備士は独占業務を持たないものの、資格を取得することでキャリアや収入面で大きなメリットがあります。ここでは代表的なメリットを整理します。
| メリット | 詳細内容 |
| キャリアの幅が広がる | 設備設計のアドバイザーとして建築士やゼネコンから信頼されやすい。ダブルライセンスで専門性を強化できる。 |
| 年収・待遇アップ | 資格手当(月2万〜10万円)を支給する企業が多い。平均年収500〜700万円で、無資格者との差が出やすい。 |
| 省エネ・ZEB対応でニーズ拡大 | 2025年の建築物省エネ法改正で、建築設備士の専門性が不可欠に。ZEB推進により環境分野での役割が拡大。 |
| 就職・転職で有利 | 設備設計事務所やゼネコンの求人で「建築設備士歓迎」とされるケースが多数。官公庁・自治体求人での加点もあり。 |
今後の業界動向を踏まえると、取得によるメリットはさらに拡大していくと予測されます。
建築設備士の就職先と働き方
建築設備士は「設備の専門家」として幅広い業界で活躍できます。以下に、主な就職先と働き方の特徴を整理しました。
| 就職先 | 業務内容の特徴 |
| 設備設計事務所 | 空調・換気・給排水・電気設備の設計を担当。建築士と協働して設備計画を立案。 |
| 建築設計事務所 | 建築設計と連携し、省エネやZEB対応を含む設備面のアドバイスを提供。 |
| ゼネコン(総合建設会社) | 大規模プロジェクトで設備設計・施工監理に携わる。資格手当も充実。 |
| 設備工事会社(空調・衛生・電気) | 設計図をもとに現場で施工管理や工程調整を行う。 |
| 官公庁・自治体 | 公共施設の省エネ化計画や設備更新工事の審査・発注を担当。 |
| 不動産・ディベロッパー | 大規模開発における設備計画、維持管理・リノベーション対応。 |
ライフスタイルやキャリアプランに応じて「設計寄り」「施工寄り」「安定志向」の働き方を選択可能です。安定・専門性・収入アップのいずれも狙える資格として価値が高いため、ぜひ取得を目指してみてください。
また、建築設備関連の設計業務に携わりたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
建築設備士についてよくある質問【FAQ】
建築設備士は意味がないって本当ですか?
意味がないというのは誤解です。建築整備士には、建築士などのように独占業務はないものの、省エネ法対応やZEB推進で需要が高まっており、転職市場でも評価される資格です。
建築設備士になるにはどんな受験資格が必要ですか?
学歴(大卒・短大卒・高卒)に応じた実務経験年数や、建築士・施工管理技士など他資格による特例があります。建築技術教育普及センターの「令和7年建築設備士試験 受験総合案内書」で詳細条件をチェックできます。
勉強時間はどのくらい必要ですか?
合格までに500〜1,000時間が目安です。実務経験や基礎知識の有無によって必要時間は変わります。
建築設備士の年収はどれくらいですか?
平均500〜700万円程度だと言われています。国内の全国平均の年収461万円よりも高いのが特徴です。また資格手当として月1〜10万円を支給する企業もあり、取得により待遇アップが見込めます。
まとめ
建築設備士は、建築物に欠かせない「設備」の専門家として位置付けられる国家資格です。独占業務はないものの、省エネ法改正・ZEB推進・脱炭素社会といった時代背景のなかで需要が拡大しており、資格取得によるキャリア価値は年々高まっています。
建築設備士は「意味がない資格」ではなく、むしろ今後の建築業界で必須級の人材価値をもつ資格です。建築士や施工管理技士とのダブルライセンスを目指す人は、ぜひ取得のために試験を受けてみてください。


