【2025年最新】初心者が覚えるべき建築知識とは?基礎ノウハウや人気書籍・雑誌の魅力を徹底解説
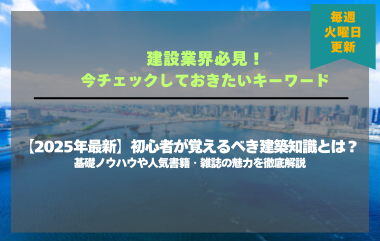
建物を設計するとき、必要になるのが「建築知識」です。建築の基礎を理解していないと、設計図を書けないほか、施工へ進むことができず工事トラブルの原因になりかねません。
そこでこの記事では、代表的な住宅工法の特徴を整理しつつ、業界人や建築学生に愛読される雑誌『建築知識』の魅力やバックナンバーを紹介します。
目次
建築の基礎知識|代表的な住宅工法をわかりやすく解説
住宅の工法は、建物の耐久性やコスト、設計自由度を左右する重要な要素です。
ここでは日本で多く採用される代表的な4種類の工法を解説します。
木造住宅(軸組工法・2×4工法)
木造住宅は、日本でもっとも普及している工法であり、次の2つの工法が用いられています。
- 軸組工法
- 2×4(ツーバイフォー)工法
軸組工法は柱と梁で骨組みをつくり、設計やリフォームの自由度が高い点が魅力です。また2×4工法は、壁パネルで支える箱型構造で、耐震性・断熱性に優れ、工期も短縮できます。ただし、軸組は施工精度を高める必要があること、2×4は設計制約があることに注意しなければなりません。
鉄骨造住宅(重量鉄骨・軽量鉄骨)
鉄骨造は高い耐震性と耐久性を誇る建物です。大空間や3階建て以上の住宅にも対応でき、以下の2種類に分かれます。
- 重量鉄骨
- 軽量鉄骨
重量鉄骨はラーメン構造により間取りの自由度が高く、軽量鉄骨は工期が短くコストを抑えやすいのが利点です。一方でサビや火に弱く、基礎工事や防錆処理にコストがかかる点には注意が必要です。
鉄筋コンクリート造(RC造)
鉄筋コンクリート造は、耐久性・耐火性・遮音性に優れた構造で、マンションや高耐久住宅に多く採用されます。
重厚感のある建物をつくれる一方、工期やコストは木造より高くなりがちです。また、地盤が弱い地域では改良工事が必要となる場合もあり、設計と施工管理の精度が重要です。
ユニット工法・プレハブ工法
ユニット工法やプレハブ工法は、工場で部材やユニットを製造し現場で組み立てる方式で、工期が短く品質が安定するのが強みです。
マニュアル化されているためコスト削減にもつながります。ただし、規格化されていることから、間取り変更やリフォームが難しく、デザインが画一的になりやすい点には注意が必要です。
また建築に関する知識は建築基準法といった法律から学ぶことも大切です。具体的な数値情報も含めて学びたい方は、以下の記事をご参考ください▼
雑誌『建築知識』とは?建築業界人に愛される専門誌
建築の知識を継続的に深めたいという方は、建築業界人に愛される専門誌『建築知識』を購入するのがおすすめです。
『建築知識』は建築の基礎から最新トレンドまで幅広く扱う専門誌です。
建築士や施工管理者、学生まで幅広い層に読まれており、実務的な技術解説と文化的な建築特集を両立しています。
(出典:エクスナレッジ「建築知識」)
建築知識の概要と歴史
1959年創刊の『建築知識』は、建築士や施工者の学習を支える定番雑誌です。
(参考:エクスナレッジ「【復刻版】建築知識 創刊号(1959年1月号)」)
基準法改正や省エネ制度など最新情報を追える一方、寺社建築や世界の街並みなど文化的な特集も人気を集めています。半世紀以上の歴史を持ち、建築業界のバイブル的存在とされています。
建築知識ビルダーズとの違い
出典:エクスナレッジ「建築知識ビルダーズ」
『建築知識』の雑誌には、姉妹誌として実務者向けに施工ノウハウを深掘りする『建築知識ビルダーズ』という本も販売されています。
現場の工務店や大工に役立つ具体的なディテール、納まりの工夫を紹介しており、設計や法規を扱う本誌とは棲み分けられています。
使い分けとして、設計者は『建築知識』、施工現場は『ビルダーズ』がおすすめです。
建築知識の入手方法
『建築知識』は書店やAmazon、出版元であるエクスナレッジストアから購入できます。
Kindleなど電子書籍でも読むことができ、バックナンバーは出版社サイトで購入可能で、定期購読サービスなら毎月最新号を自動で入手できます。
電子版の読み放題プランもあるため、学生や若手建築士でもコストを抑えて知識を深められるのが魅力です。
最新号の特集テーマ紹介
出典:エクスナレッジ・ストア「建築知識25/09」
2025年8月発売の『建築知識25/09』は「旧石器から昭和まで 長崎の建物と町並み詳説絵巻」が特集されています。
長崎は外交と交易の玄関口として多彩な文化を受け入れ、出島や大浦天主堂、軍艦島など独自の建築遺産を育みました。そして本号では建物と町並みを通じて歴史を紐解き、人物や出来事までイラストでわかりやすく解説されています。
旅をするように長崎の魅力を学べる一冊です。
| 項目 | 内容 |
| 定価 | 1,800円+税 |
| 著者名 | ― |
| ページ数 | 122ページ |
| 判型 | B5判 |
| 発行年月日 | 2025年8月20日 |
人気のバックナンバー一覧とおすすめ号
『建築知識』は最新号だけでなく、過去号も高い評価を受けています。
ここでは「法律・制度」「歴史・文化」「実務」「ユニークなテーマ」の4視点から、注目のバックナンバーを紹介します。
法律・制度を学ぶなら
| 号 | タイトル | 概要 | リンク |
| 2024/11 | 大改正 建築基準法・建築物省エネ法 | 法改正の要点や省エネ基準義務化を徹底解説。実務対応に必携の1冊。特別付録「建築知識手帳2025」付き。 | 公式サイト |
歴史・文化を楽しむなら
| 号 | タイトル | 概要 | リンク |
| 2025/01 | 神社建築大全 | 起源から構造、象徴まで神社建築を網羅。写真・図解豊富で文化理解に最適。 | 公式サイト |
| 2025/03 | 沖縄の建物と街並み歴史絵巻 | 琉球文化と建築を年表形式で紹介。街並み・気候風土と建築の関係を学べる。 | 公式サイト |
実務に役立つ特集
| 号 | タイトル | 概要 | リンク |
| 2025/02 | 建物種類ごとディテール図鑑 | 店舗・学校・工場など多用途建築の細部ディテールを収録。設計現場に必携。 | 公式サイト |
| 2025/04 | 建物種類ごと間取り図鑑 | ホストクラブから消防署まで多彩な建物の間取り事例を収録。実務・学習両用。 | 公式サイト |
面白いテーマで人気の号
| 号 | タイトル | 概要 | リンク |
| 2025/05 | 建物の壊れかた | 地震・津波・噴火・紛争による建築被害を分析。構造的弱点や防災知識も学べる。 | 公式サイト |
| 2025/08 | 本と生きる空間 | 図書館・書店・読書空間を特集。建築と文化が融合する空間デザインを紹介。 | 公式サイト |
建築知識を学ぶメリットと活用法
『建築知識』を活用するメリットは、読者の立場に応じて変化します。
たとえば、設計・施工のプロから学習者、一般読者まで幅広い層が、それぞれの目的に応じて知識を得られる点が建築知識の魅力です。以下にそれぞれのメリットをまとめました。
- 実務者向け
建築基準法や省エネ基準など最新法規をキャッチアップできる - 学生向け
図解・イラストが豊富で試験対策や研究に役立つ - 一般読者向け
歴史や文化を題材とした特集で、建築を「文化体験」として楽しめる
当雑誌は、専門誌でありながら、学ぶ目的に合わせて柔軟に活用できる「建築の総合プラットフォーム」です。
一般的な建築知識を学びつつ、息抜きや新たな知識の習得のために雑誌購入を視野に入れてみると良いかもしれません。
また学生の場合は、雑誌から学ぶ知識がコンペ「建築新人戦」に役立つケースもあります。詳しくは以下の記事をチェックしてみてください▼
建築知識についてよくある質問【FAQ】
建築知識の電子版と紙版はどちらがおすすめ?
電子版はスマホやタブレットで手軽に読め、検索や持ち運びが便利です。一方、紙版は図解や写真を大きく確認でき、製図や設計時に手元に置きやすいのが魅力です。学生や若手はコスパの良い電子版、設計者や研究用途には紙版を選ぶのがおすすめです。
学生でもバックナンバーを購入できますか?
学生でも出版社公式サイトやAmazonなどでバックナンバーを購入可能です。電子版の読み放題プランを利用すればコストを抑えられ、必要な号だけ購入することもできます。学習テーマに合わせて過去特集を選べば、研究や課題制作にも役立ちます。
建築士試験対策に使える号は?
『建築知識』は法規改正や構造解説を特集した号が試験対策に有効です。特に「2024/11 大改正 建築基準法・省エネ法」や「2025/02 建物種類ごとディテール図鑑」などは出題傾向に直結する知識をカバーします。過去問と併せて読むことで、理解の定着や実務的な応用力が養えます。
まとめ
『建築知識』は、住宅工法の基礎から歴史・文化、最新の法改正やディテール解説まで幅広く扱う建築専門誌です。建築業界での実務者はもちろん、学生や一般読者にとっても学びや発見の多い一冊と言えます。
建築を「仕事」として学ぶ人も、「趣味」として楽しむ人も、『建築知識』は知識の幅を広げ、日常に新しい視点を与えてくれるおすすめの雑誌です。基準書や法律などから建築知識を学ぶだけではなく、雑誌からも新しい知識やトレンドを取り入れましょう。


