【2025年版】建築確認申請とは?わかりやすく流れ・費用・期間・不要なケースまでプロが解説
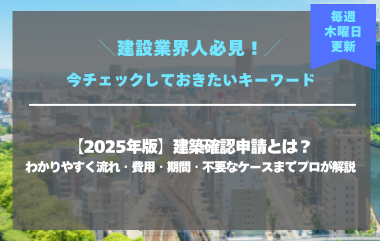
建物を新築・増改築する際には、「建築確認申請」という手続きが必要になる場合があります。このとき、申請の有無や流れ、費用、必要書類、不要なケースを理解していないと、着工が遅れたり、余計なコストが発生したりするリスクがあります。
そこでこの記事では、2025年最新の制度改正や実務での注意点をもとに「建築確認申請」の全体像をわかりやすく解説します。
目次
建築確認申請とは?基本の意味と目的
建築確認申請とは、建築物の計画が建築基準法や関連法規に適合しているかを、着工前に行政または指定確認検査機関が審査・許可する制度です。
違反建築を防ぐための制度であり、安全で適法な建物を確保するための手続きとして知られています。
特に日本では、地震や火災などの災害リスクが高く、建物の安全性を確保するために厳しい法基準が定められています。建築確認申請は、これらの基準に基づき、構造・防火・採光・換気・避難経路などが適切かを事前にチェックすることで、事故や被害を未然に防ぐ役割を果たします。
(参考:国土交通省「建築確認・検査制度の概要(PDF)」)
建築確認申請は誰がする?【申請主体と関係者の役割】
建築確認申請は、原則として建築士が申請主体となります。
特に、設計を担当する以下の建築士が、建築基準法第6条に基づき、設計図書と必要書類を揃えて申請します。(参考:e-Gov法令検索「建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)」)
- 一級建築士
- 二級建築士
- 木造建築士
このように申請主体が決められているのは、法規適合性を正確に判断できる専門知識が必要なためです。
構造計算、防火区画、避難経路、採光・換気などの基準は高度であり、誤りがあると審査で不適合となり工事が進められません。建築士が主体となることで、法令遵守と施工品質を確保できます。
なお、建築確認申請は施主単独でも可能ですが、実務上は建築士に依頼するのが一般的です。
建築確認申請が必要なケース
建築確認申請が必要かどうかは、建物の種類・規模・構造・用途によって決まります。
基準は建築基準法第6条に定められており、住宅・事務所・店舗など用途を問わず、一定規模以上の工事では申請が必須です。参考として以下に、必要なケースを2つ整理しました。
【必要ケース1】新築工事(一定規模以上)
新築工事は、規模や構造にかかわらず、ほとんどの場合で建築確認申請が必要です。
たとえば、新築の建物は、安全性・耐震性・防火性能に直接関わるため、法律上もっとも厳しい審査対象となります。構造計算、防火区画、避難経路など、法令適合性を詳細に確認する必要があります。
なお、一般的には都市計画区域内での審査が義務付けられていますが、以下の場合には、都市計画区域外でも特例を除いて申請をするのが特徴です。
- 木造|2階建て・延べ面積100㎡超
- 鉄骨造・鉄筋コンクリート造|階数にかかわらずほぼすべて
新築工事を計画する際は、敷地の用途地域や建ぺい率・容積率なども同時にチェックし、申請要否を早めに判断しましょう。
【必要ケース2】増改築や用途変更
既存建物の増築・改築・用途変更も、条件によっては建築確認申請が必要です。
特に、工事内容が構造や安全性に影響する次のような場合には、ほぼ対象となります。
- 住宅を店舗や事務所に用途変更する
- 延べ面積が10㎡を超える増築
- 主要構造部を変更する改修
小規模工事でも用途や構造に影響があれば申請対象になるため、自己判断せず建築士や自治体に相談することが安全です。
建築確認申請が不要なケース
建築確認申請は、すべての建築工事で必要になるわけではありません
建築基準法第6条で定められた「適用除外」に該当する場合や、規模が一定以下の小規模工事では申請が不要です。以下に不要なケースの例をまとめました。
- 木造平屋建てで延べ面積10㎡以下の物置
- 仮設建築物(例:工事現場の事務所)で使用期間が短いもの
- 都市計画区域外の小規模建築物(※自治体によって異なる)
- 建築基準法第6条第1項ただし書きに該当する軽微な工事
法律では、工事規模や構造が周囲の安全や都市計画に与える影響が少ない場合、事務負担を減らすために申請を免除しています。ただし「不要」と判断して工事を進め、後から申請義務があったと判明すると、是正命令や罰則の対象になる点に注意が必要です。
また、不要の条件を詳しく知りたい方は以下の記事がおすすめです▼
建築確認申請の流れと必要書類
建築確認申請は、計画段階から着工までに4つのステップを踏みます。
ここでは、実務でよく使われる4ステップと、各段階で必要となる書類・注意点を解説します。
参考1:東京都「建築物を安全に建てるために:建築確認・検査の手続(建築基準法)」
参考2:福岡市「福岡市確認申請の手引き(令和7年4月一部改正)」
【STEP1】事前相談と計画確認
まずは、申請前に自治体の建築指導課や指定確認検査機関で事前相談を行い、計画が法令に適合しているかを確認します。
次の要素などを事前に把握することで、後の設計変更や審査遅延を防げます。
- 用途地域
- 建ぺい率
- 容積率
- 高さ制限
- 防火規制
早期相談はコスト削減にも有効です。
【STEP2】申請書類の作成
建築確認申請が必要だとわかったら、建築士を中心に、以下の必要申請書類を作成します。
- 建築確認申請書
- 設計図書
- 構造計算書
- 委任状 など
ちなみに、様式や図面内容は自治体や指定確認検査機関の基準に沿う必要があります。不備があると補正や再提出の原因となるため、提出前に必ずダブルチェックを行いましょう。
【STEP3】審査期間と補正対応
申請後、審査機関が法令適合性を確認します。この期間は申請者は審査結果を待つことになります。
このとき、採光や防火仕様、構造計算などに不備があれば補正指摘(修正指摘)が届くため、期限内に修正し再提出しましょう。
補正対応が遅れると着工時期に影響するため、建築士・施工者と連携し迅速に対応することが重要です。
【STEP4】確認済証の交付と着工
審査を通過すると「確認済証」が交付され、着工が可能になります。
確認済証は、建築計画が建築基準法など法令に適合していることを証明する書類で、工事現場には掲示義務があります。着工後も法令遵守を続け、工事完了時には「完了検査」を受け、検査済証を取得する流れとなります。
建築確認申請にかかる期間と費用
建築確認申請の期間は一般的に7〜21日程度、費用は数万円〜数十万円が相場です。
ただし、建物規模や構造、自治体・審査機関によって大きく変わります。以下に目安表をまとめました。
| 建物の種類 | 期間目安 | 費用目安 |
| 木造2階建(100㎡) | 約10日 | 3〜6万円 |
| RC造3階建(300㎡) | 約14〜21日 | 10〜20万円 |
| 特殊建築物(病院・劇場など) | 約21日以上 | 20〜50万円 |
※上記は国交省・指定確認検査機関の公表データや実務事例を基にした一般的な目安です。
スムーズに建築確認申請をクリアするためにも、余裕を持ったスケジュールを設定しましょう。早めの書類準備が期間短縮とコスト抑制につながります。
建築確認申請のよくあるトラブルと対応策
建築確認申請は計画どおりに進まないこともあります。
特に審査期間の延長や再申請は、着工遅延やコスト増につながるため注意が必要です。ここでは、現場でよくある3つのトラブルと、その具体的な対応策を解説します。
【トラブル1】許可がなかなかおりない(補正・修正指摘)
審査が長引く主な原因は、補正指摘への「対応の遅れ」や「修正内容の不十分さ」です。
たとえば、補正期限を過ぎると再申請扱いになる場合があり、期間が大幅に延びます。指摘の意図を正確に理解し、必要な修正を一度で完了させることが重要です。
建築士や施工者との連携を密にし、補正指摘書を受け取ったら即日対応を開始しましょう。
【トラブル2】書類不備による再申請
必要書類の欠落や誤記は、再申請につながります。
再申請になると費用と期間が余計にかかり、工事スケジュール全体に影響する点に注意しましょう。最新の申請様式や提出条件を事前に確認することが必須です。
【トラブル3】制度改正・基準の解釈違い
制度改正や基準の解釈を誤ると、申請が通らない原因になります。
建築基準法や関連条例は定期的に改正されるため、過去の経験だけで判断すると不適合になることがあります。国交省や自治体の最新資料を定期的に確認し、必要なら専門家に判断を仰ぎましょう。
建築確認申請についてよくある質問【FAQ】
建築確認申請は自分でできる?
法律上は、施主が自ら申請することも可能です。ただし、建築基準法や都市計画法、防火規定など専門的な知識が必要で、図面や構造計算の作成も求められます。実務上は一級・二級建築士、木造建築士に依頼するのが一般的です。
建築確認申請が不要な建物の例は?
代表的な例として、木造平屋で延べ面積10㎡以下の物置、工事期間が短い仮設建築物、都市計画区域外の小規模建築物があります。ただし、地域や構造によって例外があるため、必ず自治体や指定確認検査機関に事前確認が必要です。
建築確認申請が遅れるとどうなる?
審査完了前に着工すると違法建築となり、工事中止命令や是正命令の対象になります。さらに、補正や再申請で費用と期間が増加し、契約や融資スケジュールにも影響します。着工時期から逆算して、余裕を持った申請スケジュールを組むことが重要です。
まとめ
建築確認申請は、安全で法令に適合した建物を実現するための重要な手続きです。
必要・不要の判断、流れ、期間や費用を理解し、早期の準備と関係者との連携を徹底することで、着工遅延や余計なコストを防げます。最新の法改正や自治体基準も確認し、疑問があれば専門家に相談しましょう。


