【2025年最新版】建築用語大全|よく使う・かっこいい・基礎から構造まで初心者向けに解説
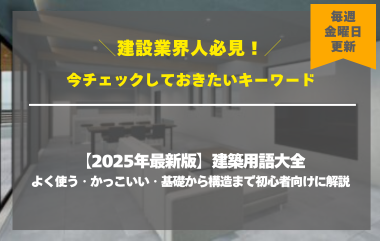
建築の世界には、現場や図面、打ち合わせのなかで頻繁に使われる専門用語が数多く存在します。しかし、初心者やこれから家づくり・リフォームを始める人のなかには「聞いたことはあるけど意味があいまい」という言葉も少なくないでしょう。
そこで本記事では、2025年最新版の建築用語大全として、「よく使う用語」から「かっこいい響きの専門語」、さらに「木造住宅」「構造別」「カタカナ用語」まで幅広く解説します。
目次
建築用語とは?初心者が知っておくべき理由
建築用語とは、建物の設計・施工・管理の各場面で使用される専門的な言葉の総称です。
建築用語を理解しておくことで、家づくりやリフォームの打ち合わせ、現場でのやり取りがスムーズになり、誤解やミスを防げます。
たとえば、図面上で「梁成(はりせい)」という表記があった場合、これが梁の高さを意味することを知らなければ、構造的な制約や空間の見え方を正しく理解できません。また、施工中に「養生シートを外します」と言われたとき、その役割を理解していれば、作業の段取りや仕上がりへの影響をイメージできます。
建築用語の理解は、発注者・施工者・設計者をつなぐ橋渡しです。建築初心者は業務の理解や建築に関わるコミュニケーション向上のためにも、基礎用語から覚えていきましょう。
建築用語の基本一覧【初心者向け】
建築分野には数百を超える専門用語がありますが、まずは現場や打ち合わせで頻出する基本用語から押さえることが大切です。
ここでは初心者が最初に覚えておくべき建築用語を、住宅・木造建築、構造部材、寸法測定の3カテゴリーに分けて一覧で紹介します。
住宅や木造建築でよく使う基礎用語一覧
木造住宅では、基礎工事から屋根仕上げまでに、次のような多くの専門用語が使われます。
- 基礎:建物を支える土台部分。布基礎やベタ基礎などの種類がある
- 土台:基礎の上に据える構造材で、柱や壁を支える
- 柱:建物を垂直に支える構造部材
- 梁(はり):床や屋根を水平に支える部材
- 軒天(のきてん):屋根の軒裏部分。雨風や日差しから外壁を守る
木造住宅の基本用語を理解していれば、現場見学や図面確認の精度が向上します。
構造や部材に関する基本用語一覧
次のような建築構造の部材名を知っていれば、施工方法や耐震性の説明をスムーズに理解でき、判断材料が増えます。
- 耐力壁:地震や風圧に耐える壁
- 筋かい:構造を補強する斜材。耐震性向上に寄与
- 胴縁(どうぶち):外壁材を固定するための下地材
- 火打ち梁:床や屋根の変形を防ぐ斜め部材
- 野地板:屋根材の下地板
構造用語は住宅の安全性を左右するため、必ず押さえておきましょう。
寸法・測定に関する用語一覧(mm・尺・間など)
寸法や測定用語は、図面の理解や現場寸法確認に必須です。
- mm(ミリメートル):国際標準の長さ単位
- 尺(しゃく):伝統的な日本の長さ単位(1尺=約303mm)
- 間(けん):柱中心間の距離であり住宅規格に多用
- スパン:構造物の支点間距離
- クリアランス:部材間の余裕寸法
寸法単位や表現を誤解すると、設計ミスや施工トラブルにつながるため、上記の用語をしっかりと理解しておきましょう。
建築用語【構造・工法別】
建築は、木造住宅で使われる言葉と、鉄筋コンクリート造や鉄骨造で使われる言葉、さらには屋根・外壁・内装といった部位ごとの言葉は、意味や役割が大きく異なります。
ここでは、構造・工法別に覚えておくべき用語を整理して紹介します。
木造建築の構造用語一覧(軸組工法・筋かい・梁など)
木造建築は、日本の住宅で最も一般的な構造であり、次のような特有の用語が複数あります。
- 軸組工法(在来工法):柱と梁で構成する日本の伝統工法であり間取りの自由度が高い
- 筋かい:地震や風圧に耐えるため、壁内に斜めに入れる補強材
- 梁(はり):床や屋根を支える水平部材
- 火打ち梁:建物の変形を防ぐ斜材
- 胴差(どうさし):柱の中間に入れる水平材で、構造を安定させる
木造は構造材や工法が耐震性・耐久性に直結するため、用語の理解が安全性と品質判断に欠かせません。
なお、木造住宅の構造は耐震性確保が重要であり、建築基準法の構造強度に関する基準が定められています。また、建築基準法関連の基礎知識を知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼
鉄筋コンクリート・鉄骨造の構造用語一覧(RC造・SRC造など)
鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨造(S造、SRC造)は、都市部や大型建築物(ビルや店舗など)で多く採用されます。
- RC造(鉄筋コンクリート造):鉄筋で補強したコンクリートで構成
- S造(鉄骨造):軽量で高強度の鋼材を使用
- SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造):鉄骨を鉄筋コンクリートで覆い、耐震性に優れる
- 耐火被覆:鋼材を高温から守る仕上げ材
- ラーメン構造:柱と梁を剛接合して強度を高める構造方式
特に構造のメインとなるRC・S・SRCの違いを押さえることで、構造選択の判断材料が増えます。
また、RC造やSRC造については、建築行政情報センター ICBAの「建築物の構造関係技術基準解説書(通称:黄色本)」で構造安全性の基準が明確化されています。
加えて、鉄筋コンクリートの概要を知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
屋根・外壁・内装など部位別の用語一覧
建築工事のなかで、次のような部位名と役割を知っていれば、修繕や改修時の見積書も理解しやすくなります。
- 棟(むね):屋根の頂部
- 谷樋(たにどい):屋根の谷部分を流れる雨水を集める樋
- サイディング:外壁材の一種で、金属・窯業系など種類がある
- クロス:内装壁紙
- 巾木(はばき):壁と床の境目に取り付ける仕上げ材
施工や修繕の打ち合わせでの誤解や伝え間違いを防止するためにも、ぜひチェックしておきましょう。
現場でよく使う建築用語
建築現場では、図面や構造の説明とは異なり、作業手順や安全管理に関する独自の用語が飛び交います。
職人同士や現場監督とのコミュニケーションを円滑にするためにも、本項で紹介する用語を理解しておきましょう。
施工・工事の工程に関する用語一覧(上棟式・養生・墨出しなど)
こちらで紹介する「工程用語」を理解しておけば、現場での進捗状況や作業内容を正確に把握できます。
- 上棟式(じょうとうしき):棟上げ完了を祝う儀式であり、工事安全祈願の意味もある
- 養生(ようじょう):資材や仕上げ面を保護する作業
- 墨出し(すみだし):施工位置を正確に示すため床や壁に基準線を描く作業
- 荒床(あらゆか):仕上げ材を貼る前の床下地
- 仕上げ工程:内外装の最終的な仕上げ作業
工程の名称は、作業段階や工事品質を示す重要な指標です。誤解があると工期や仕上がりに影響します。
安全管理や作業指示の用語一覧(足場・水平器・仮設など)
次の安全用語は、事故防止のための必須知識です。
- 足場:高所作業を行うための仮設構造物
- 水平器:構造物や部材の水平度を確認する計測器
- 仮設:工事期間中のみ設置する設備や構造物
- 親綱(おやづな):高所作業時に安全帯を取り付けるためのロープ
- 保護具:安全帯・ヘルメット・防護手袋など
現場は高所作業や重機の使用など危険が多く、正確な用語理解が安全確保に直結します。安全管理用語を押さえておけば、作業者だけでなく現場訪問者の安全確保にも役立ちます。
カタカナ・外来語の建築用語
建築業界では、海外発祥の技術やデザイン様式が数多く取り入れられており、カタカナ表記の外来語が頻繁に使われます。
本項で紹介する用語を理解すれば、設計コンセプトや仕上げの方向性を正しく把握できるのはもちろん、発注や打ち合わせでの意思疎通がスムーズになります。
デザインや建築様式に関する用語一覧(アールデコ・モダニズムなど)
建築様式の外来語は、空間の雰囲気や意匠の方向性を的確に伝えるためのキーワードです。
- アールデコ:幾何学的で装飾的なデザイン様式(1920〜30年代に流行)
- モダニズム:合理性・機能性を重視した20世紀の建築運動
- ミニマリズム:装飾を排し、シンプルさを追求するデザイン手法
- バロック:曲線や装飾を多用し、豪華さを演出する様式
- ポストモダン:歴史的要素を再解釈して取り入れる多様な様式
それぞれ、歴史的背景や文化的影響を反映しており、理解しておくことでデザイン提案や選定時の判断が的確になります。
建築図面・設計で使うカタカナ用語一覧(モジュール・スパン・プランなど)
設計図や仕様書には、寸法体系や計画を表すカタカナ用語が多数登場します。
- モジュール:設計の基準寸法単位(例:910mmモジュール)
- スパン:支点間距離
- プラン:設計図や間取り計画
- セクション:断面図のこと
- ディテール:細部の意匠や施工方法
カタカナ用語は、情報を短く簡潔に伝えるための道具であり、意味を理解して使うことが重要です。キーワードを理解すれば、図面の読み取り精度が上がり、施工との連携が取りやすくなります。
かっこいい響きの建築用語セレクション
建築用語のなかには、意味だけでなく響きの美しさや独特の語感で人を惹きつける言葉も複数あります。
ここでは、構造やデザイン分野で「かっこいい」と感じられる用語、そして建築史や海外建築に由来する印象的な用語を紹介します。
プロが選ぶ美しい響きの構造・デザイン用語一覧
構造やデザインに関する専門用語は、音の響き自体が洗練された印象を与えるものがあります。
- ピロティ:建物の1階部分を柱だけで支え、空間を開放した構造
- カーテンウォール:建物の外壁を非耐力壁としてガラスなどで構成するデザイン
- アトリウム:吹き抜け空間を指す用語で、光や開放感を演出
- コーニス:外壁上部の水平装飾帯
- オーバーハング:壁面や床面を支持点から外側へ突き出した形状
造形的イメージとリンクしており、聞くだけで空間の雰囲気を想起できるため、デザインコンセプトの訴求力が高まります。
建築史や海外建築から生まれた用語一覧
歴史的・文化的背景をもつ用語は、その由来を知ることで建築の奥深さを感じられます。
- コリント式:古代ギリシャの建築様式の一つで、柱頭にアカンサスの葉飾りをもつ
- ゴシック:尖塔やアーチを特徴とする中世ヨーロッパの建築様式
- ルネサンス:古典的様式の復興を目指した15〜16世紀の西欧建築
- バシリカ:古代ローマの公共建築形式
- アーチ:湾曲した構造形状で、構造的にも美観的にも優れる
日本国内でも、高級住宅や公共建築の設計に上記の用語が多く取り入れられています。そのため、デザイン提案や教育的解説にも活用できます。
建築業界特有のおもしろ用語
建築の現場や設計事務所では、一般的な日常会話と同じ単語でも、業界独自の意味をもつ場合があります。
さらに、職人同士でしか通じないスラングや略語も多く存在し、初めて耳にすると「?」となることも少なくありません。そこでここでは、そうした“業界あるある”の建築用語を紹介します。
日常と意味が違う建築用語
日常会話で使う言葉と、建築業界での意味が異なるケースがあります。
- 笑う:日常では「微笑む」意味だが、現場では「部材同士がかみ合わず、隙間ができる」こと
- 風邪を引く:体調不良ではなく、「建物内部に風が通り抜けてしまう施工不良」を指す
- 耳:人の耳ではなく、「部材や仕上げ材の端部の出っ張り部分」
- 腰:人体の腰ではなく、「壁や柱の中間部分」
業界用語は比喩的な表現が多いため、正しい意味を知ることが誤解防止につながります。
現場でしか通じないスラング
現場では、すばやくコミュニケーションをとるために、次のような独自の短縮語や隠語を用いるケースがあります。
- ゲンノウ:金槌の一種(玄翁)
- バカ棒:長さや水平を確認するための仮の基準棒
- タコ:型枠などを固定するための足場部材
- コバ:材料の断面や端の部分
- 埋めころす:仮設材を撤去せずにそのまま埋めてしまうこと
スラングを理解すれば、現場での指示や冗談の意味も把握でき、関係性の構築にも役立ちます。
建築用語に関するよくある質問【FAQ】
建築用語はどのくらい覚えるべきですか?
初心者はまず50〜100語程度の基礎用語から学ぶのがおすすめです。住宅・構造・施工工程に関する頻出語を押さえれば、図面理解や現場コミュニケーションが格段にスムーズになります。すべてを一度に覚える必要はなく、必要に応じて調べながら徐々に習得しましょう。
木造とRC造では使われる用語が違いますか?
違います。木造では「柱」「梁」「筋かい」などの用語が頻出し、RC造(鉄筋コンクリート造)では「梁スラブ」「型枠」「鉄筋かぶり厚」などが使われます。構造によって材料や工法が異なるため、用語も変わります。両方の特徴を理解しておくと応用が効きます。
現場用語の中で管理者が特に覚えておくべきものは?
管理者が理解しておくと便利な現場用語は「養生」「墨出し」「仮設」「足場」などです。工事の進行や品質管理に直結する言葉で、意味を理解しておくことにより、現場の説明や工程確認がスムーズになります。安全確認にも役立ちます。
建築用語を効率よく覚える方法はありますか?
おすすめは「図解+現場見学+用語カード学習」の組み合わせです。図解で視覚的に理解し、現場見学で実物と照らし合わせ、カードやアプリで繰り返し学習すれば記憶が定着しやすくなります。特に現場写真や動画を活用すると、イメージと用語が結びつきやすくなります。
まとめ
建築用語は、設計から施工、完成後のメンテナンスまで、あらゆる工程で正確な意思疎通を行うための共通言語です。
意味を理解していないと、図面の誤読や現場での勘違いが生じ、工期や品質に影響する恐れがあります。これから建築業務をスタートする人はもちろん、日常的に業務に関わるという方は、ぜひ本記事の建築用語全集を活用してみてください。


