建築士法とは?施行規則・施行令・改正・設計業務・違反事例をわかりやすく解説【2025年版】
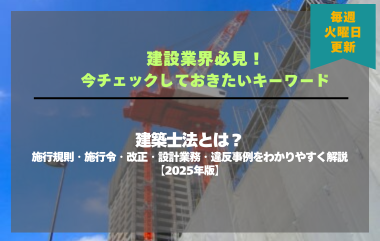
建築士法は、建築士が社会的に安心・安全な建物を設計・監理するための基盤となる法律です。そして、2025年6月の一部改正では、実務にややつながる変更が加えられました。
そこでこの記事では、2025年の改正情報を交えつつ、建築士法の概要・施行令・施行規則・主要条文・改正内容・違反事例 をわかりやすく解説します。
目次
建築士法とは?概要わかりやすく解説
建築士法は、建築士の資格制度や業務範囲、登録や監督体制、さらには違反時の罰則を定めた法律です。
- 資格制度|一級・二級・木造建築士の区分と要件
- 業務範囲|設計や監理を行える建築物の規模・用途の規定
- 登録と監督|免許登録や更新、建築士事務所の管理体制
- 罰則規定|違反行為に対する罰金や免許取消などの処分
建築物の「安全性」「耐久性」「快適性」を確保することを目的として1950年に制定され、その後も社会のニーズに合わせて何度も改正されてきました。建築士法を理解することは、設計業務従事者だけでなく、建築業界全体にとって重要なポイントです。
(参考:e-Gov法令検索「建築士法」)
対象となる資格(一級・二級・木造建築士)
建築士法で規定されている資格は「一級建築士」「二級建築士」「木造建築士」の3種類です。それぞれの資格には扱える建築物の規模や用途に明確な違いがあり、設計や監理を行える範囲が定められています。
そのなかでも、特に2025年の改正で注目されたのは、二級建築士の業務範囲拡大です。
出典:建築技術教育普及センター「建築士の種類と業務範囲」
現在は、従来よりも大きな木造住宅や地域密着型施設を設計できるようになっています。
建築士法と関連する法律(建築基準法との関係)
建築士法は、建築物の設計や監理を担う「建築士」に関する法律であり、一方の建築基準法は、建築物そのものの安全性・耐久性・防火・採光・衛生などを定めた法律です。
| 法律 | 主な内容 | 対象 |
| 建築士法 | 建築士の資格・業務範囲・登録制度・罰則 | 建築士(人) |
| 建築基準法 | 建物の安全・構造・防火・衛生・都市計画との調和 | 建築物(もの) |
実務においても、建築士は設計図を作成する際に建築基準法を確認し、法令違反のない設計を行わなければ行政確認が下りません。逆に、建築士法違反があれば設計行為自体が無効となるため、両者の遵守が不可欠です。
(参考:e-Gov法令検索「建築基準法」)
また建築基準法や施行令の概要を知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください▼
建築士法施行令・施行規則とは?
建築士法は法律本文だけではなく、詳細なルールを定める「施行令」と「施行規則」によって運用されています。それぞれの役割を以下にまとめました。
【施行令】
内閣が制定する政令で、建築士法の大枠を具体的に定めるものです。たとえば、建築士事務所の管理者要件や、業務に従事できる建築物の範囲などが記載されています。
(参考:e-Gov法令検索「建築士法施行令」)
【施行規則】
国土交通省令として定められ、より実務的な細部を規定します。例として、建築士試験の内容・合格基準、免許申請や登録手続きの詳細が挙げられます。
(参考:e-Gov法令検索「建築士法施行規則」)
建築士は、施行令や施行規則に沿って登録・更新を行い、設計監理の業務を遂行しなければなりません。違反すれば免許停止や登録抹消のリスクがあるため、実務者にとっては法律本文と同じくらい重要な規範です。
主要条文の解説(条番号別)
建築士法のなかでも、特に実務に大きな影響を与えるのが第3条の2と第20条です。
これらの条文は建築士の業務範囲や責任を具体的に定めており、設計・監理の現場で頻繁に参照されます。ここでは「第3条の2」「第20条」を中心に、それぞれの内容と実務での留意点をわかりやすく解説します。
建築士法第3条の2とは(定義と意義)
建築士法第3条の2は、一定規模以上の建築物について、一級建築士または二級建築士でなければ設計や工事監理ができないと定めた規定です。
建築物の安全性を担保するために、規模や構造に応じた専門資格を持つ建築士が関与することを義務づけています。
| 規定内容 | 適用建築物 | 必要資格 |
| 構造制限 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造・れんが造などで延べ面積30㎡超 | 一級 or 二級建築士 |
| 面積制限 | 延べ面積100㎡超(木造は300㎡超) | 一級 or 二級建築士 |
| 階数制限 | 階数が3以上の建築物 | 一級 or 二級建築士 |
| 条例による変更 | 都道府県が条例で面積要件を別途定める場合あり | 条例に従う |
参考:e-Gov法令検索「建築士法|第3条の2」
たとえば、鉄筋コンクリート造の150㎡の共同住宅や、木造3階建てのアパートは、この条文により一級または二級建築士でなければ設計・監理を行えません。
また、一級・二級建築士などがかかわる建築設計について知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建築士法第20条とは(意味と留意点)
建築士法第20条は、建築士が設計・工事監理を行った際に必ず行うべき表示や証明に関する義務を定めた規定です。以下に、主な内容を要約しました。
| 規定内容 | ポイント | 実務での注意点 |
| 設計図書への記名・表示 | 設計図書に資格名を表示し記名する義務 | 記載漏れは無資格設計と同様に扱われる可能性 |
| 構造計算証明書の交付 | 安全性を構造計算で確認した場合、証明書を建築主に交付 | 特に大規模建築物では必須 |
| 工事監理報告 | 工事監理終了時に文書で建築主に報告 | 電子報告も可能(建築主の承諾が必要) |
| 建築設備士の意見の明示 | 大規模建築物の建築設備に関与した場合は報告書に明示 | 共同責任が問われる場合あり |
参考:e-Gov法令検索「建築士法|第20条」
建築物の安全性や設計の信頼性を担保するため、設計図書や報告書に建築士の責任を明確に示すことが求められます。
たとえば、耐震構造を伴うマンションの設計で構造計算を行った場合、建築士は証明書を建築主に渡さなければなりません。これにより、建築主は設計が法規に適合していることを確認できます。
建築士法の最新の改正内容【2025年時点】
2025年6月1日(令和7年6月1日)、刑法等の一部改正に伴い、建築士法施行規則の一部も改正されました。今回の改正は、建築士の直接的な業務範囲や資格要件を変えるものではありませんが、登録手続きに必要な書式に影響を及ぼす実務的に重要な変更です。
国土交通省の案内によれば、登録申請・更新を行う際は必ず改正後の書式を使用する必要があります。旧書式で申請すると差し戻しや再提出を求められる場合があるため注意が必要です。
※改正後の書式は国土交通省公式サイトからダウンロード可能です。
(参考:熊本県建築士事務所協会「【重要】建築士法施行規則第六号書式の一部改正について(令和7年6月1日から)」)
建築士法違反と罰則一覧
建築士法に違反すると、資格の停止や取消し、罰金刑など厳しい処分が科されます。以下に、主な違反内容と罰則を整理しました。
| 違反内容 | 罰則 | 備考 |
| 無資格での建築士業務 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 建築士の名称を不正使用・無免許設計 |
| 虚偽・不正で免許取得 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 免許取消し・刑事罰対象 |
| 一級/二級/木造建築士でなければできない設計を無資格で実施 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 第3条・第3条の2・第3条の3違反 |
| 業務停止命令違反 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 行政処分中の設計・監理業務 |
| 講習事務停止命令違反 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 第10条36項関連 |
| 虚偽の構造計算証明交付 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 第20条違反 |
| 虚偽登録・不正登録 | 1年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金 | 第23条関連 |
| 虚偽申告や帳簿不備(軽微) | 30万円以下の罰金 | 第40条関連(帳簿未備付・虚偽記載) |
| 建築士事務所協会の不正使用 | 30万円以下の罰金 | 名称の不正使用(第40条17号) |
| 法人が関与した場合 | 個人の罰則+法人も罰金刑 | 第42条関連 |
| 軽微な届出違反 | 10万円以下の過料 | 第43条関連(届出漏れ・虚偽記載など) |
参考:e-Gov法令検索「建築士法|第10章 罰則」
建築士法についてよくある質問
建築士法第20条は何を定めている?
建築士法第20条は、建築士が設計や工事監理を行った際の責任表示を義務付けています。設計図書には資格種別と氏名を記載し、構造計算で安全性を確認した場合は証明書を交付する必要があります。工事監理終了時の報告や電子報告の活用も規定され、透明性確保の要となる条文です。
建築士法改正はいつから施行?
直近の大きな改正は、平成26年法律第92号に基づき、2015年(平成27年)から順次施行されました。さらに2025年6月1日には刑法改正に伴い、建築士法施行規則が改められています。特に契約の書面義務化や管理建築士の責務明確化などは最新情報の確認が重要です。
建築士法に違反するとどうなる?
建築士法に違反すると、無資格業務や虚偽申請など重大なケースでは1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科されます。軽微な届出違反や帳簿不備でも過料や30万円以下の罰金となる場合があります。違反は免許取消や業務停止など行政処分につながり、業務継続や社会的信用に深刻な影響を及ぼします。
まとめ
建築士法は、建築士の資格や業務範囲、責務、罰則を定めた法律で、建築物の安全と利用者の安心を守る重要な基盤です。
近年の改正で契約の書面義務化や管理建築士の責務強化が進み、違反には拘禁刑や罰金など厳しい処分が科されます。法令遵守を徹底するためにも、この機会に、最新動向を把握しておきましょう。


