建設リサイクル法の対象工事は何?対象資材・届出義務を解説|対象外・違反事例も【2025年版】
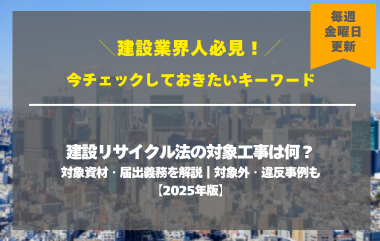
近年、建設現場では廃棄物の再利用や適正処理が強く求められています。そして、その中心となる法律が「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」です。
この記事では、建設リサイクル法の対象となる工事や資材、届出義務、対象外となるケース、違反事例と罰則まで、2025年版の最新情報をもとにわかりやすく解説します。
目次
建設リサイクル法の目的と概要
建設リサイクル法は、2002年に全面施行された建設廃棄物の適正処理と資源循環を目的とする法律です。
国土交通省が平成30年に公開した「建設副産物実態調査結果(確定値)概要」によると、年間の建設廃棄物の量は7,440万トンも発生しており、不適切処理が環境問題や不法投棄を招いてきました。これに対し建設リサイクル法が運用されたことにより、平成30年時点の最終処分量は212万トン(7,228万トンはリサイクル)という状況まで改善しました。
つまり、建設リサイクル法は、建設業界の透明性と持続可能性を高め、違反リスクを回避するための必須ルールと言えます。
建設リサイクル法の基本知識からチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建設リサイクル法の対象となる工事【早見表付き】
建設リサイクル法では、一定規模以上の工事を「対象工事」と定めており、資材の分別解体と再資源化を義務付けています。
この「対象」かどうかを誤って判断すると、届出漏れや罰則のリスクにつながるため、具体的な基準を正しく理解することが欠かせません。ここでは、建築物の解体・新築・修繕、そして土木工事の対象基準を解説します。
| 工事の種類 | 基準 | 対象となる例 |
| 建築物解体工事 | 床面積80㎡以上 | 木造住宅90㎡の解体 |
| 新築・増築工事 | 床面積500㎡以上 | 商業施設、マンション |
| 修繕・模様替え工事 | 請負金額1億円以上 | 大規模オフィス改修 |
| 土木工事 | 請負金額500万円以上 | 道路舗装、橋梁補修 |
参考:環境省「建設リサイクル法の概要」
建築物解体工事の対象要件
延べ床面積が80㎡以上の建築物を解体する工事は、建設リサイクル法の対象になります。
これは小規模な木造家屋などを除外することで、実務上負担を軽減しつつ、廃棄物の多い規模の工事を重点管理するために基準が設けられました。
一見、小規模に思える戸建ても、80㎡を超えれば対象に含まれる点に注意しましょう。
建築物の新築・増築工事の対象要件
延べ床面積が500㎡以上の新築または増築工事も、建設リサイクル法の対象となります。
この規模の工事の場合、コンクリートや木材などの使用量が膨大になり、再資源化の効果も大きいため基準が設けられました。
そのため、商業施設や大規模なマンション、ビル建設が主な対象です。500㎡を超えるか否かが重要な判断ポイントとなります。
修繕・模様替え(リフォーム)工事の対象要件
建築物の修繕・模様替え工事では、請負金額が1億円以上(税込)の場合に対象となります。
そのため、百貨店の大規模リニューアルやオフィスビルの全面改修などが該当しやすい傾向です。規模は小さくても、内装材や設備交換が多額に及ぶ場合は対象となる可能性がある点に留意してください。
土木工事の対象要件
道路・橋梁・造成などの土木工事は、請負金額が500万円以上(税込)で対象となります。
特に土木工事は、コンクリートやアスファルトの使用量が多く、再資源化による環境負荷低減効果が高いため、多くの工事が建設リサイクル法の対象です。
建築物では床面積基準、土木工事では金額基準と覚えておきましょう。
建設リサイクル法の対象外となる工事
建設リサイクル法はすべての工事に適用されるわけではありません。代表的な対象外工事を以下の表にまとめました。
| 区分 | 基準 | 注意点 |
| 小規模解体工事 | 延べ床面積80㎡未満 | 80㎡を超えると対象になるため計測必須 |
| 修繕・模様替え工事 | 請負金額1億円未満 | 高額な設備改修の場合は対象になるケースあり |
| 土木工事 | 請負金額500万円未満 | 見積もりで500万円を超える可能性がある場合は注意 |
| 特定建設資材を使用しない工事 | 法律で定められた資材を使用しない | 産業廃棄物処理法に基づく処理は必要 |
誤って対象外と判断すると、後に違反扱いとなる可能性があるため、事前確認が不可欠です。工事内容だけでなく、床面積や金額を明確に把握しましょう。
建設リサイクル法の対象となる特定建設資材【一覧表】
建設リサイクル法では、廃棄物のなかでも特に発生量が多く、再資源化の効果が高い「特定建設資材」が対象とされています。
これらの資材は、分別解体や再資源化が義務付けられており、正しく対応しなければ違反となる可能性があります。参考として以下に、対象資材の種類と具体的な再資源化方法をまとめました。
| 資材の種類 | 具体例 | 主な再資源化方法 |
| コンクリート | 鉄筋コンクリート、PC版 | 破砕して再生砕石として道路路盤材などに再利用 |
| コンクリートと鉄から成る資材 | SRC造の部材、梁・柱 | 鉄はスクラップ回収、コンクリートは再生砕石化 |
| アスファルト・コンクリート | 道路舗装材、駐車場舗装 | 再生アスファルト合材として再利用 |
| 木材 | 建物の柱・梁、合板、内装材 | 木質チップに加工し、ボード材や燃料に利用 |
参考:国土交通省「建設リサイクル基礎知識解説」
これらの特定建設資材は、工事規模の基準を満たすことで、分別解体・再資源化の対象となります。
届出義務と手続きの流れ
建設リサイクル法では、対象工事を行う際に届出が義務付けられています。
特に、工事の発注者と元請業者の役割を理解しておかないと、届出漏れや違反扱いになる可能性があります。ここでは、発注者と元請業者・下請業者の具体的な義務と、手続きの流れを整理します。
発注者の義務
対象工事を発注する場合、工事着手の7日前までに「分別解体等の計画届」を所轄の自治体へ提出しなければなりません。以下に届出の流れをまとめました。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| 1. 対象工事の判定 | 延べ床面積・金額・資材を確認し、対象かどうか判断 | 床面積80㎡以上、500㎡以上、1億円以上、土木500万円以上 |
| 2. 分別解体等計画の作成 | 特定建設資材の処理方法・搬出先を整理 | 元請業者からの情報提供が必要 |
| 3. 届出書の提出 | 工事着手の7日前までに所轄自治体へ届出 | 不提出は20万円以下の罰金リスク |
| 4. 許可確認・工事契約 | 元請業者と契約し、分別解体費用を明記 | 見積り段階で要確認 |
| 5. 工事完了後の報告受領 | 元請から処理実績報告を受け取る | 記録を一定期間保存する義務あり |
元請業者・下請業者の役割
元請業者は、発注者に再資源化計画を文書で説明し、契約書に分別解体や再資源化の費用を明記する必要があります。以下に、届出の基本フローを整理しました。
| ステップ | 内容 | ポイント |
| 1. 対象工事の確認 | 発注者と協力して対象工事かを判定 | 誤判定防止のため図面・見積を精査 |
| 2. 再資源化計画の策定 | 分別解体方法・資材処理ルートを設計 | コンクリート・木材・アスファルト等を資材別に明記 |
| 3. 発注者への説明 | 計画内容と費用を文書で説明 | 契約書に「分別解体費用」を明示 |
| 4. 分別解体の実施 | 実際に現場で解体し、資材を分別 | 下請業者に安全・適正な施工を徹底 |
| 5. 実績の報告・記録保存 | 発注者に再資源化完了を報告 | 書類は5年間保存(自治体により変動) |
建設リサイクル法の違反事例と罰則
建設リサイクル法に違反すると、行政処分や刑事罰が科される可能性があります。
特に、届出漏れや未登録業者への発注はよくある違反事例であり、過去には施工停止や罰金が課されたケースも報告されています。以下に、主な違反例をまとめました。
| 違反内容 | 想定される罰則 |
| 届出を怠った場合 | 20万円以下の罰金 |
| 未登録業者に発注 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 分別解体を怠った場合 | 行政指導、工事中止命令、処分場での受入拒否 |
| 虚偽届出 | 書類差し戻し、工事許可取り消し |
出典:e-Gov法令検索「建設リサイクル法|第7章 罰則」
違反は罰金や懲役、工事停止など重大なリスクを伴います。届出・契約・分別解体の3つを徹底することが、違反防止の基本です。
建設リサイクル法の対象工事・資材についてよくある質問【FAQ】
建設リサイクル法は、工事が複数棟に分かれる場合も合計する?
複数の建物を同一契約で解体・建設する場合は、延べ床面積や工事金額を合計して判断します。たとえば、同一敷地内で2棟を同時解体する場合に、各棟が40㎡でも合計が80㎡を超えれば対象です。国交省も合算判断を原則としていますので注意が必要です。
(参考:国土交通省「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」)
建設リサイクル法は発注者と施工者のどちらが届出する?
届出義務者は発注者です。ただし実務上は、元請業者が届出書の作成を代行し、発注者の押印をもらうケースが一般的です。届出を怠った場合は発注者が責任を負いますが、元請業者も適切な支援をしなければ契約違反や指導対象となる恐れがあります。
届出後に工事内容が変わった場合の対応方法は?
工事規模や内容に変更があった場合は、変更届を速やかに提出する必要があります。特に延べ床面積や請負金額が基準を超える変更があった場合、届出を修正しないと違反と見なされることがあります。変更届は自治体の様式に従って記載・提出してください。
届出は電子申請できる?
近年は、多くの自治体が電子申請に対応しています。横浜市や大阪市などでは、自治体の公式サイトから届出書を作成・提出可能です。ただし全自治体が対応しているわけではないため、事前に自治体窓口で確認しましょう。電子申請ができない場合は紙で提出する必要があります。
まとめ
建設リサイクル法は、建築物や土木工事に伴う廃材を分別・再資源化し、環境負荷を減らすための重要な法律です。
対象となるかは「床面積80㎡以上」「新築500㎡以上」「修繕1億円以上」「土木500万円以上」が目安となります。違反は罰金や工事停止のリスクにつながるため、対象資材や手続きの流れを理解し、確実に対応していきましょう。面積を早めに確認するほか、迷ったら自治体や専門家に相談することをおすすめします。


