高層建築物とは?|世界・日本のランキングと最新トレンド解説【2025年版】
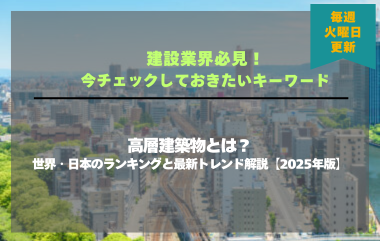
都市のシンボルとして人々を魅了し続ける「高層建築物」ですが、2025年現在、世界では高さ800メートルを超える超高層ビルが誕生し、日本でも麻布台ヒルズ森JPタワーが新たなランドマークとして注目を集めています。
そこでこの記事では、世界と日本の最新ランキングをはじめ、建築基準法や消防法で定められる定義、構造の特徴まで徹底解説します。
目次
世界の超高層建築物ランキングTOP5
| 順位 | 建築物名 | 所在地 | 高さ | 主な用途 |
| 1位 | ブルジュ・ハリファ | UAE・ドバイ | 828m | オフィス・ホテル・展望台 |
| 2位 | ムルデカ118 | マレーシア・クアラルンプール | 678m | オフィス・ホテル |
| 3位 | 上海中心 (Shanghai Tower) | 中国・上海 | 632m | オフィス・展望台 |
| 4位 | アブラージュ・アルベイト・タワーズ | サウジアラビア・メッカ | 601m | ホテル・商業施設 |
| 5位 | 平安金融センター | 中国・深圳 | 555m | オフィス・展望台 |
日本の高層建築物最新ランキングTOP5
| 順位 | 建築物名 | 所在地 | 高さ | 主な用途 |
| 1位 | 麻布台ヒルズ森JPタワー | 東京 | 330m | オフィス・ホテル |
| 2位 | あべのハルカス | 大阪 | 300m | 百貨店・ホテル・展望台 |
| 3位 | 横浜ランドマークタワー | 神奈川 | 296m | オフィス・ホテル・展望台 |
| 4位 | 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー | 東京 | 266m | オフィス・商業・ホテル |
| 5位 | ミッドタウン八重洲 | 東京 | 240m | オフィス・ホテル |
また、建設企業のランキングについて興味がある方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
建築基準法や消防法における高層建築物の定義
高層建築物を理解するためには、単に高さや外観だけでなく、法令上どのように規定されているかを押さえる必要があります。
特に、日本では「建築基準法」「消防法」によって、それぞれ明確な基準が設けられています。
建築基準法における定義
建築基準法では、一般的に高さ31mを超える建物を「高層建築物」と定義しています。
これは、避難や消防活動の安全性を確保するために設定された基準です。高さが増すほど火災時の避難や消火活動が難しくなるため、より厳格な規制が必要となり基準が設けられました。なお、高層建築物には以下の義務が課されています。
- 非常用エレベーターの設置
- 耐火性能を持つ構造材の使用
- 避難経路の確保と避難階段の複数設置
- 非常電源の確保
高層建築物は、厳格な安全基準を満たすうえで建築しなければなりません。
参考:e-Gov法令検索「建築基準法」
また建築基準法に興味をお持ちなら、以下の記事もチェックしてみてください▼
消防法における定義と注意点
消防法でも、高さ31mを超える建築物を「高層建築物」として扱っており、火災対策を強化しています。
なぜなら、建築基準法と同様に火災は高層階ほど救助が困難になるため、初期消火と煙制御の重要性が増すためです。また消防法では、人命を守るために次のような防災設備の設置を建築主に義務付けています。
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知器
- 屋内消火栓設備
- 防火区画や排煙設備
- 避難誘導灯や赤色灯
加えて、建物の管理者は定期的な避難訓練の実施や消防計画の作成を行う必要があるなど、防災システムの充実化を図らなければなりません。
「31m」という高さ基準の意味
建築基準法・消防法で共に定められている31mという高さ基準ですが、これは「はしご車」の救助可能高さが約30mが限界であることが数値の根拠です。(2025年現在は40m級のはしご車もあります)
参考:東京消防庁「30メートル級はしご車」
31mを超えると外部からの救助が事実上困難となることから、人命保護の観点から設けられた命のラインとして、数値が定められています。
高層建築物の構造と設計の特徴
高層建築物は、以下に示す要素が一体となって成立します。
- 地震や強風など外部環境に耐える強固な構造
- 都市景観に調和するデザイン
- 人命を守る安全設備
ここでは、主要な構造形式、外装・内装デザイン、安全設備と赤色灯について解説します。
主要な構造形式
高層建築物には、耐震性と耐火性を備えた構造が必須です。代表的な形式は以下のとおりです。
| 構造形式 | 特徴 | 採用例 |
| S造 | 軽量・施工が早い | 東京スカイツリー |
| SRC造 | 高耐震・高耐火 | 横浜ランドマークタワー |
| 免震・制震 | 揺れを低減 | 麻布台ヒルズ森JPタワー |
軽量かつ強度に優れ、耐震性や耐火性に優れている構造にしなければならないのはもちろん、免震・制震技術の導入により、地震時の揺れを低減させるなど、地震の多い日本での安全性を高めることも重要です。
外装・内装デザインの傾向
近年の高層建築物は、次のようなデザインが2025年現在の主流です。
- ガラスカーテンウォール:採光性と省エネ性能を両立
- 緑化デザイン:屋上庭園や壁面緑化で都市環境を改善
また、内装では快適性と機能性を重視し、オフィス・ホテル・商業施設を融合した複合用途が増加しています。
安全設備と赤色灯の役割
次のような高層建築物の防災設備は、人命を守る重要な設備です。
- 避難誘導灯・赤色灯:停電・煙発生時も視認性が高い
- スプリンクラー・火災報知器:初期消火と早期警報
- 非常用エレベーター:消防隊や高齢者・障がい者支援
- 煙制御設備:避難経路の視界を確保
特に、赤色灯は緊急時の誘導に欠かせません。みずほ情報総研株式会社の調査によると、赤色灯の設置により避難開始時間が短縮した事例も報告されています。(参考:みずほ情報総研株式会社「高齢者や障がい者に適した火災警報装置の調査研究業務」)
注目の建設中・計画中プロジェクト
2025年現在、日本各地で新たな高層建築物が計画・建設中です。
- Torch Tower(トーチタワー)
完成すれば高さ約358mで日本一に(2028年完成予定) - 横浜みなとみらいプロジェクト
観光とオフィスを融合した次世代型ビル群であり2025年度中に複合施設がオープンする予定です
建築技術の向上により、今後も更なる高層建築物が登場します。日本でも、世界のランキングを塗り替える建物が生まれるかもしれません。
高層建築物についてよくある質問【FAQ】
「高層建築物」と「超高層ビル」の違いは?
高層建築物は建築基準法上、高さ31mを超える建物を指します。一方、超高層ビルは慣用的に高さ100m以上の建物を呼ぶ場合が多いです。法的な定義は「高層建築物」にのみ存在し、「超高層ビル」は建築業界やメディアで用いられる独自の用語である点に注意しましょう。
消防法で定める高層建築物の定義は?
消防法では、高さ31mを超える建築物を高層建築物とし、火災対策を強化するため特別な設備を義務付けています。具体的には、スプリンクラーや火災報知器、屋内消火栓設備、防火区画の設置が必要であり、火災時の避難安全性と初期消火の実効性が高まります。
日本で今後一番高くなる予定の建築物は?
東京・大手町に建設予定のTorch Tower(トーチタワー)が完成すれば、高さ約385mで日本一となります。竣工は2028年頃を予定しており、完成後は麻布台ヒルズ森JPタワー(325m)を超え、オフィスや商業施設、ホテルを含む大規模複合施設として注目を集めています。
高層建築物は地震に強いの?
日本の高層建築物は、免震構造や制震ダンパーなど最新の耐震技術を取り入れて設計されています。たとえば、麻布台ヒルズ森JPタワーやあべのハルカスには、揺れを吸収・分散する仕組みが導入されており、一般的な中低層建物よりも安全性が高いとされています。
英語で「高層建築物」とはどう言う?
「高層建築物」は、英語でHigh-rise buildingと表現されます。また、特に高さが際立つものをSkyscraper(摩天楼)と呼ぶ場合もあります。国際的な建築や観光の文脈では「skyscraper」がよく使われますが、法律文書や学術的をもとにする場合は「high-rise」が適切です。
まとめ
高層建築物は、都市の象徴であると同時に、安全性・快適性・環境性能を兼ね備えた複合施設です。
世界では800mを超える建築物も登場しており、日本でも麻布台ヒルズ森JPタワーや計画中のTorch Towerが注目を集めています。
今後も地震対策や省エネ技術を取り入れた次世代ビルが続々誕生する予定であるため、建築や都市開発に関心のある方は、最新動向を定期的にチェックしてみてはいかがでしょうか。


