建築基準法の道路とは?42条・種類・2m接道要件を徹底解説【2025年版】
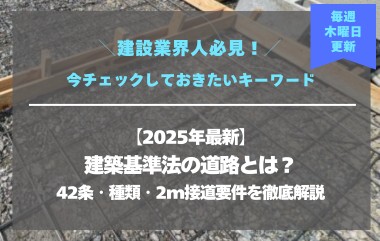
建築基準法では「道路」に接していないと建物を建てられない場合があります。では、その“道路”とはどのような道路を指すのでしょうか。
この記事では「建築基準法の道路」の定義や種類、42条道路・私道との関係、2m・4mといった接道義務のルールなどを、初心者向けにわかりやすく解説します。
建築基準法における「道路」の定義とは?
建築基準法で定める「道路」とは、「建築基準法第42条に基づく道路」のことを指します。これに該当しない道路に接している土地では、原則として建物の建築・増改築はできません。
(参考:e-GOV法令検索「建築基準法」)
また、建築基準法では、火災時や災害時の避難・緊急車両の進入を確保するため、建物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある(接道義務)と定められています。
したがって、接道している道路が「法的な道路」でなければ、その敷地は建築不可とされているのが特徴です。
また、2025年4月の建築基準法改正に関する変更点を知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
建築基準法上の道路と一般的な道路の違い
建築基準法で定める“道路”と、日常的に私たちが通っている“道路”は、必ずしも一致しません。以下に、2つの道路の違いをまとめました。
| 通常の道路例 | 建築基準法上の扱い | 理由・注意点 |
| 舗装された私道 | ×(非該当) | 所有者の許可や位置指定を得ていない |
| 幅3.5mの路地 | △(2項道路の可能性) | セットバックが必要な場合が多い |
| 車が通れる農道 | ×(非該当) | 道路法にも建築基準法にも基づいていない |
| 公園内の遊歩道 | ×(非該当) | 建築物が接しても接道義務を満たせない |
たとえば、建築基準法上の「道路」とは、単に舗装された道ではなく、「建築基準法第42条に定める6種の道路」に該当するものです。それ以外の道、たとえば舗装された私道や農道、私有地内の通路などは、道路とはみなされません。
建築予定の敷地に接する道路が「建築基準法上の道路」であるかどうかを確認するには、各市区町村の「建築指導課」「都市計画課」で確認可能です。
特に古い住宅地や再建築不可の物件を購入する際には、「道路種別証明」「接道確認書」の取得を検討しましょう。
また、建築基準法とは別に設けられている建築基準法施行令についても知りたい方は、以下の記事がおすすめです▼
建築基準法42条の道路種別【6つの種類】
建築基準法における「道路」は、すべてが同じ性質を持っているわけではありません。
際には、第42条に基づいて6つの種類に分類されており、それぞれに接道要件や建築可否のルールが異なります。以下より、建築基準法の42条で定められている条件をひとつずつ紹介します。
| 分類 | 該当条文 | 概要説明 |
| 公道 | 42条1項1号 | 一般的な国道・県道・市道など |
| 計画道路 | 42条1項2号 | 開発事業や土地区画整理により設けられる |
| 旧道 | 42条1項3号 | 昭和25年以前から存在し現在も利用される |
| 位置指定道路 | 42条1項4号 | 私道に指定が与えられた道路 |
| 準法定道路 | 42条1項5号 | 建築審査会の同意に基づき認定される道 |
| セットバック道 | 42条2項 | 現況幅員が4m未満で2項に該当する既存道 |
42条1項1号道路|道路法による道路(一般の公道)
国道・県道・市町村道など、道路法にもとづいて整備・管理されている公道です。建築基準法上の“正規の道路”であり、原則として接道要件を問題なく満たします。
42条1項2号道路|都市計画事業や土地区画整理で整備される予定の道路
都市計画法や土地区画整理法にもとづく事業で整備される予定の道路です。事業認可が下りていれば、未完成でも建築基準法上の道路として扱われます。
42条1項3号道路|旧法道路(1950年以前からある道路)
建築基準法が施行された1950年(昭和25年)以前から建物が立ち並び、現に使われている道です。幅員や状況によってはセットバックが必要な場合もあります。
42条1項4号道路|位置指定道路(私道でも指定済みならOK)
私道であっても、建築基準法上の基準を満たし、行政から「位置指定」を受けた道路です。通行権や管理体制も確認が必要で、建築行為には特に注意が求められます。
42条1項5号道路|法43条ただし書道路に準ずる
建築審査会の同意にもとづき、例外的に建築を認めるために指定された道路です。特例的な扱いで、条件によっては建築許可が下りるケースもあります。
42条2項道路|セットバックを前提とする4m未満の道路
幅員が4m未満でも、建築基準法施行時にすでに存在し、一定の建物が並んでいた道路です。建築時には中心線から2m後退(セットバック)が求められます。
接道義務とセットバックのルール
建物を建てる際、もっとも重要な要件のひとつが「接道義務」です。
敷地が法令で定める条件を満たした道路に接していないと、建築確認がおりず、建物を建てることができません。また、狭い道路に接している場合には「セットバック(後退)」の対応が必要になるケースもあります。
ここでは、建築基準法における接道義務の基本ルールと、2項道路とセットバックの実務的な関係について解説します。
接道義務の基本|幅4m以上の道路に2m以上接する
建築基準法第43条では、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に、間口2m以上接していなければならないと定められています。これを「接道義務」と呼びます。
この接道要件は、火災や災害時の避難経路・消防車の進入路確保が目的です。また、狭小地や旗竿地などの建築に対する最低限の安全基準としても機能しています。
なお土地の取得時は、以下のポイントに注意しなければなりません。
- 幅員4m以上の道路に接していない → 建築不可
- 道路幅は満たすが、接道長が1.8mしかない → 再建築不可
- 接道していても、道路が建築基準法上の道路でない → NG
なお、土地を購入する際には「道路種別証明書」「接道状況確認書」を自治体で事前取得することが大切です。なんとなくという気持ちで判断せず、「法的な接道かどうか」を確認しましょう。
2項道路とセットバック
幅員が4m未満の道路でも、建築基準法上の「2項道路」に該当する場合は、セットバック(敷地の一部後退)を条件に建築が認められます。
ここで言う「2項道路」とは、昭和25年以前から使用されていて幅員が4m未満の道で、一定の建築物が立ち並んでいる道路のことです。このような道路では、将来的な拡幅を想定して、道路中心線から2mの位置まで敷地を後退させる義務があります。
参考として以下に、セットバックのイメージをまとめました。
| 道路幅員 | セットバック必要距離 | 建物の建築可能位置 |
| 3.6m | 0.2mずつ | 中心線から2m以外 |
| 3.0m | 0.5mずつ | 中心線から2m以外 |
| 2.0m | 1.0mずつ | 中心線から2m以外 |
なお、セットバックが必要な土地では、建築面積が減少するほか、擁壁やブロック塀の移設費用も発生することがあります。購入前に現地調査や役所への確認が欠かせません。
建築基準法の道路のよくある勘違いと注意点
建築基準法の道路について「舗装されていて車が通れる=建築可能な道路」と思い込むのは危険です。法的に定義された「42条道路」に2m以上接していなければ、建築許可は下りません。
参考として以下に、よく勘違いされているポイントを整理しました。
- 舗装されている=道路と思い込む
- 古い通路だから建築OKだと思った(旧道でもセットバックが必要)
- 私道だから自由に使えると思っていた(通行権・共有者同意が必要)
- セットバックしても建築面積は変わらないと思っていた(実際は減る)
- 不動産広告に「建築可」と書いてあったのに建てられなかった
「建てられる土地」と「建ててもよい土地」は別物です。土地を取得する際には、証明やセットバックの有無などの事前確認を怠らないようにしましょう。
まとめ
建築基準法における「道路」は、見た目や舗装状態では判断できません。建築可否を左右するのは、「建築基準法第42条に該当するか」「接道義務を満たしているか」「セットバックの必要があるか」といった法的要件です。
今後、購入や建築を検討する際は、専門家への相談や自治体の確認を行い、法的に「建てられる土地」であるかを事前に把握することをおすすめします。


