【2025年】一般建設業と特定建設業の違いとは?許可取得方法・請負金額の上限を徹底解説
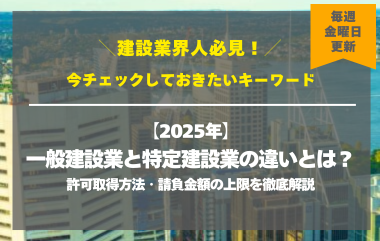
「建設業の許可を取りたいけれど、一般建設業と特定建設業の違いがわからない」「どちらを取得すべきか、いつ取得すればよいのか知りたい」とお悩みではないでしょうか。
この記事では、2025年最新情報をもとに、一般建設業と特定建設業の違い、許可取得の方法、請負金額の上限を初心者向けにわかりやすく解説します。
目次
建設業法における「一般建設業許可」「特定建設業許可」の定義
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、請負金額や下請契約の有無で取得区分が変わります。
上記の許可は、建設業法の第5〜17条等で規定されており、業者が適切な工事管理・財務体制のもとで施工することを目的として定められました。
(参考:e-GOV法令検索「第2節 一般建設業の許可(第5~14条)」「第3節 特定建設業の許可(第15~17条)」)
なお、各条には「許可申請」「申請の添付書類」「許可基準」「許可の効力」「登録手数料」「廃業時の対応」などが定められており、建設業者は条文に準じた対応が求められます。
また、建設業許可・建設業法の概要からチェックしたい方は、以下の記事がおすすめです▼
【2025年版】建設業許可制度の最新動向
2025年現在、建設業許可制度は、以下の3点が注目されています。
- 特定建設業許可の基準が引き上げられた
(税込4,500万円→5,000万円 ※建築一式工事は別) - 現場技術者の配置に関する規定が変更された
(情報通信技術・ICTの活用などを条件に、専任義務が緩和) - 労働環境改善と働き方改革に対応した
(賃金基準の明確化、長時間労働の抑制、休日取得の促進などが実施中)
建設業法および建設業許可は、定期的な変更・改良が加えられる場合があるため、常に最新情報をチェックすることが欠かせません。最新の条件がわからない場合は、専門家に相談するのもおすすめです。
一般建設業と特定建設業の違いとは?
一般建設業許可と特定建設業許可は、建設業法で定められた建設工事の規模や役割に応じて分かれており、元請・下請、請負金額の上限などに違いがあります。
ここではポイントに分けて、それぞれの違いを紹介します。
主な役割の違い
まず、一般建設業は中小規模工事、特定建設業は大規模工事の元請として、下請契約を管理する役割があります。
| 許可種別 | 主な役割 |
| 一般建設業 | 小〜中規模工事の元請・下請 |
| 特定建設業 | 大規模工事の元請(下請管理を含む) |
規模が小さい工事であれば、一般建設業の許可だけで問題ありません。
対して、公共工事や大型民間プロジェクトを元請として請け負う場合には、特定建設業許可を取得していないと受注が不可能なケースもあります。
取り扱える工事の種類の違い
一般建設業・特定建設業は、ともに取り扱える工事の種類自体は同じです。ただし、工事金額や元請・下請で扱える規模が変わる点に注意しなければなりません。
たとえば、建設業法では29業種の工事が定められており、どちらの許可でも同じ種類の工事を扱えます。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 管工事
- 電気工事 など
しかし、規模が大きい工事となる場合には、同じ工事の種類でも特定建設業の許可を受けている業者しか対応できません。2つの違いを簡単に説明すると「工事の種類は同じ」だけど「規模が違う」と覚えましょう。
下請工事の請負金額による違い
特定建設業は下請契約で4,500万円(税込)以上(建築一式は6,000万円以上)の工事を請け負えますが、一般建設業はこの金額以上の下請契約が締結できません。
| 工事種別(税込) | 許可なし | 一般建設業 | 特定建設業 |
| 下請契約1,500万円未満 (建築一式工事) 下請契約500万円未満 (建築一式工事以外) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 下請契約5,000万円未満 (建築工事業の場合は8,000万円未満) | ✕ | ◯ | ◯ |
| 下請契約5,000万円以上 (建築工事業の場合は8,000万円以上) | ✕ | ✕ | ◯ |
出典:国土交通省「建設業の許可とは」
5,000万円で基準を設けられているのは、大規模工事では資本力・施工管理能力・責任体制が必要であり、それを特定許可保有者に限定しているためです。大きな工事を継続的に受注する場合には、特定建設業の取得が不可欠となります。
許可の要件・審査基準の違い
特定建設業許可は、一般建設業許可よりも財務要件が厳格です。
| 項目 | 一般建設業 | 特定建設業 |
| 財務要件 | 純資産の額が正、資金調達能力あり | 純資産2,000万円以上、欠損の額が資本金の20%以下 |
| 経営業務管理責任者 | 必要 | 必要 |
| 専任技術者 | 必要 | 必要 |
上記の違いがあるのは、大規模工事を請負・下請管理するにあたって、支払能力・経営体制の安定性が求められるためです。特定建設業の許可を取得したい場合には、資金調達力や財務体制の準備を含めて、計画を立てる必要があります。
建設業許可の取得方法と流れ
建設業許可を取得するための流れを以下にまとめました。
- 経営業務管理責任者・専任技術者の要件を満たしているか確認する
- 事務所・営業所の所在地要件を確認する
- 純資産の額や欠損割合など財務要件を確認する
- 必要な書類(登記簿謄本・納税証明・身分証明・住民票など)を収集する
- 申請書類を作成する(業種選定、決算書添付など)
- 都道府県庁または国土交通省に申請書を提出する
- 審査期間(おおむね30〜45日)を経て許可通知を受け取る
- 許可通知後、許可証を受領し営業開始する
なお、許可後も毎事業年度終了後に決算変更届を提出しなければなりません。また、許可の有効期限は5年間であるため、定期的な更新申請が必要です。
許可取得時の費用と期間の目安
建設業許可の取得には平均で3〜4ヶ月、費用は以下の項目を考慮して約20万〜60万円程度が目安です。
- 申請料
- 書類取得費
- 専門家報酬
国土交通省や都道府県の公式情報によると、許可申請は書類準備・申請・審査・許可交付という流れで進むため、それぞれのステップで時間を必要とします。また、法人登記簿・納税証明・身分証明など、多数の書類取得費用も発生するため、予算を確保しておくことが重要です。
なお、自社だけで更新手続きができる場合には、専門家報酬をカットできます。
より詳しく建設業許可の更新について知りたい方は、以下の記事もチェックしてみてください▼
一般建設業と特定建設業の違いについてよくある質問
一般建設業許可はどのタイミングで必要?
工事1件の請負金額(税込500万円以上、建築一式工事は1,500万円以上)を受注する場合や、元請・下請を問わず建設工事を継続的に行う場合には、一般建設業許可が必要です。許可を取得せず工事を行うと、建設業法違反となり営業停止処分や罰金の対象となります。
元請でも一般建設業の許可で問題ない?
元請で工事を受注する場合でも、下請契約の金額が税込5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満)であれば一般建設業許可で対応可能です。ただし、金額を超える場合や大型公共工事を請け負う場合は特定建設業許可が必要になります。
許可の更新はいつ必要?
建設業許可は原則5年ごとの更新が必要で、有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります。許可を継続し営業を続けるためには、決算変更届や役員変更届など日々の許可管理が重要です。更新申請を忘れると無許可状態となり、受注中の工事に影響が出ます。
特定建設業へ切り替えるタイミングは?
元請として大規模工事を受注し、下請契約の金額が税込5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる見込みが出た段階が切り替えの目安です。特定建設業許可は財務要件などが一般許可より厳格なため、計画的に資本強化・要件確認を進めたうえで切り替えましょう。
建設業許可を取らずに工事をするとどうなる?(罰則・罰金)
無許可(一般建設業の許可で特定建設業の工事を受注する場合も含む)で建設工事を行うと建設業法違反となり、最大3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります(建設業法第50条)。さらに営業停止命令を受ける場合もあるため注意してください。
まとめ
建設業に従事する際には、まず一般建設業と特定建設業の違いを理解することが重要です。
特に経営者の場合、許可なしの工事だけに対応するのか、一般・特定のどちらの許可を取るべきなのかの判断を迫られるケースが少なくありません。どの許可を取るべきか不安な場合は、専門家へ相談し、最新の法改正情報も踏まえて計画的な取得・更新を進めましょう。


