【2025年版】準防火地域とは?建築制限・メリット・後悔しない家づくりまで徹底解説
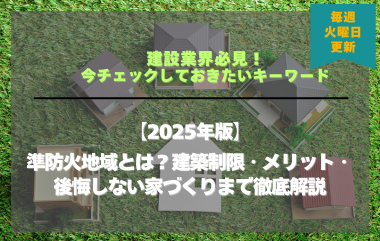
準防火地域に指定されたエリアは、建物の構造や外壁・窓に一定の制限がかかり、建物を建てる際の設計・費用に影響が出る場合があります。では、具体的に、準防火地域とはどのようなエリアのことを指し、またどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
この記事では、準防火地域の概要を説明したのち、防火地域との違い、詳しい制限のルール、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
目次
準防火地域とは?
準防火地域とは、都市部での火災の延焼を防ぐために、建築物に一定の耐火性能を求める地域のことです。
当エリアは、建築基準法に基づいて市区町村が定めており、エリア内で木造住宅などを建てる際には、構造や開口部の仕様に制限がかかるようになります。
(参考:e-GOV法令検索「建築基準法(第5節 防火地域及び準防火地域)」)
たとえば、窓ガラスには網入りや防火ガラスが求められたり、外壁や軒裏にも不燃材料が必要になったりするケースも少なくありません。住宅が密集する影響で起きる延焼を防ぐために、火災対策の一環として指定されています。
防火地域・指定なし地域との違い
準防火地域と防火地域は、どちらも火災に備えた規制エリアですが、求められる建築基準の厳しさが異なります。以下に、防火地域・準防火地域・指定なし地域の違いをまとめました。
| 区分 | 主な用途 | 建築制限 | 木造住宅の可否 |
| 防火地域 | 商業地・繁華街中心部 | 耐火建築物が原則 | 基本的に不可(例外あり) |
| 準防火地域 | 住宅地や準商業地など | 一定の耐火性能が必要 | 条件付きで可 |
| 指定なし地域 | 郊外・低密度地域 | 特に制限なし | 可 |
まず防火地域は、原則すべての建物を「耐火建築物」とする必要があるのに対し、準防火地域は「一定の耐火性能を満たせばOK」という比較的ゆるやかな規制です。
【耐火建築物とは?】
火災時に建物の主要構造部(壁、柱、床、梁、屋根、階段など)が一定の耐火性能をもち、建物の倒壊や延焼を防止する構造の建築物のことです。
また準防火地域は住宅地や準商業地が対象となることから、住民の生活に関わるエリアだと言えるでしょう。
さらに、火災に強い家を建てたいなら、準耐火建築物の確認も重要です。以下の記事で解説しているので、あわせて確認してみてください。
準防火地域に指定されるエリアの調べ方
準防火地域は、次のような方法でエリアを調べることができます。
- 都市計画図
- 建築確認申請書
また、自治体によってはホームページ上にエリア情報が公開されていることも少なくありません。参考として以下に、東京都世田谷区における準防火地域の公開マップを掲載しました。
出典:世田谷区「世田谷区都市計画図1(地域地区等)」
また、全国都市計画GISビューア(試行版)というサービスを使えば、準防火地域の情報を全国版として調べられます。
もし公開されていない場合には、役所の都市計画課に問い合わせて、対象エリアが準防火地域に含まれているのかを確認することも可能です。
準防火地域の建築制限とは?|住宅にかかる規制一覧
準防火地域に家を建てる場合、建物の構造や使う材料に一定の制限がかかります。
そのなかでも特に影響が大きいのが「外壁・軒裏・窓(開口部)」「木造2階建て住宅」です。以下より、それぞれの規制に関する基本情報をまとめました。
外壁・軒裏・開口部(窓・ドア)に求められる仕様
準防火地域では、外壁・軒裏・開口部などの外部に面する部分に「一定の耐火性能」をもたせる必要があります。
| 建築部位 | 求められる性能 | 使用例 |
| 外壁 (隣地境界1m以内) | 準耐火構造 or 不燃材料 | 金属サイディング、ALCパネル |
| 軒裏 | 準不燃材以上 | ケイカル板、不燃合板など |
| 開口部 (窓・ドア) | 防火設備 | 網入りガラス、防火サッシ、シャッター |
上記は、建築基準法施行令第136条の2〜4で定められている内容であり、隣接建物との延焼防止を目的として対策しなければなりません。(参考e-GOV法令検索「建築基準法施行令」)
なお、対策に用いる材料によっては、建築コストが増加します。予算にも影響する項目であるため、建築の際には入念な予算検討が重要です。
木造2階建ては建てられる?
準防火地域でも、一定の条件を満たせば木造2階建て住宅の建築が可能です。
ただし、防火性能に関する構造・材料・部材の仕様に適合することが条件になります。参考として以下に、準防火地域に適用できる構造の特徴をまとめました。
| 構造種別 | 特徴 | 備考 |
| 一般木造 | 規制が厳しい | 延焼ラインを越える部分に注意 |
| 省令準耐火構造 | 火災に強く保険も割安 | 設備・間仕切りの仕様指定あり |
| 準耐火構造 | RC・鉄骨に近い性能 | 建築コストはやや高め |
上記のうち、準耐火構造や、省令準耐火構造(火災保険が割安になる構造)であれば、住宅金融支援機構のフラット35の利用が可能となります。
準防火地域のメリット・デメリット
準防火地域は、よく「制限があって家を建てるのが大変そう」だというイメージをもたれがちです。確かに、防火に向けた対策が必要になるなど、それ相応の対策が欠かせません。
このとき、準防火地域に家を建てることには複数のメリットと、少しデメリットが存在します。準防火地域のメリット・デメリットを理解したうえで建築を検討したい方は、ぜひ参考にしてみてください。
メリット|火災対策・保険料割引・資産価値維持
準防火地域で実施する建築には、次のような生活の質&安全性向上のメリットがあります。
- 延焼被害のリスクが低減される
- 火災保険料が割安になる(省令準耐火構造など)
- 高耐火住宅の条件を満たせば、フラット35などの融資に有利になる
- 将来の資産価値が落ちにくいエリアとして評価されやすい
たとえば、準防火地域という規制により防火性能の高い建材が使われるため、万が一火災が起きても、被害を最小限に抑えられます。近隣の住宅で火災が起きても延焼するリスクを抑えられるため、被害に遭いにくいのもメリットです。
また、準防火地域の建物は火災保険料が安くなる「省令準耐火構造」に対応しやすくなり、住宅金融支援機構の融資制度(フラット35)でも優遇対象になることがあります。安全性の高いエリアであるため、不動産価値の安定にもつながります。
(参考:住宅金融支援機構「省令準耐火構造の住宅とは」)
デメリット|建築コスト増・デザインの制約・ガラス制限
複数のメリットをもつ準防火地域ですが、次のようなデメリットがある点に注意しなければなりません。
- 建築材料のコストが増加する
- 防火対策を優先するためデザインに制約がある
- 選べる建材に制限を受ける
たとえば、開口部に防火ガラスや防火サッシを使うと、通常より1.5〜2倍のコストがかかることがあります。
また、デザイン上採用したかった「全面ガラス張り」「木製サッシ」が使えないケースがあるなど、理想とするおしゃれな家を建てられないことがある点に注意してください。
準防火地域で家を建てるときのチェックリスト
準防火地域に家を建てるとき、設計段階での確認不足や素材の選定ミスが「思わぬコスト増」や「設計のやり直し」につながるリスクがあります。
参考として以下に、失敗を回避するために欠かせないポイントをチェックリストにまとめました。
| チェック項目 | 内容 | タイミング |
| 自分の土地が準防火地域かどうか確認する | 都市計画図・自治体Web・役所窓口で確認 | 設計前 |
| 準防火地域に対応した設計ができる建築士か確認 | 実績や対応経験を確認 | 設計依頼時 |
| 開口部(窓・ドア)に防火設備を選定しているか | 防火ガラス・防火サッシなど | 設計中 |
| 外壁・軒裏に不燃・準不燃材料を使用しているか | ALC・ケイカル板等 | 設計中 |
| 使用予定の建材が国土交通大臣認定済か | 防火認定ラベル・証明書の確認 | 設計中 |
| 火災保険の構造区分を確認・申請したか | 省令準耐火なら割引あり | 設計完了後 |
| 設計変更が必要になった際の予算余力を確保しているか | 10万~30万円程度の余力をもつ | 設計中~施工前 |
| 地元自治体の条例(独自制限)がないか確認 | 一部自治体でさらに厳しいケースあり | 設計初期 |
| 確認申請書類に準防火地域対応項目が記載されているか | 審査段階で不備を防ぐ | 設計完了時 |
| 建築後の「性能表示制度」対応の有無を確認 | フラット35や評価項目に影響 | 施工後~登記時 |
準防火地域は設計自由度が少し狭まりますが、きちんと対応すれば十分に魅力的な住宅を建てられます。一番の落とし穴は「知らずに動くこと」ですので、設計者と早期に話すことが重要です。
まとめ
準防火地域は、建築基準法に基づき火災の延焼を防ぐために設定された地域であり、住宅の構造や使用する建材に一定の防火性能が求められるのが特徴です。
そして準防火地域での建築は「知らなかった」で後悔するケースがあるため、事前の情報収集と専門家との相談が重要です。土地購入・設計の前に確認すべきポイントを押さえることで、コスト・デザインともに納得できる家づくりを実現しやすくなります。


