土木型枠工事の基本と種類|工程・材料・単価・基礎工事との違いを徹底解説
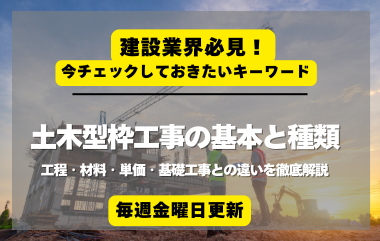
土木型枠工事は、コンクリート構造物をつくる際に欠かせない準備です。しかし、具体的にどのような作業工程を経て利用されるものなのかイメージできずにいる人も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、土木型枠工事の基本を解説したのち、一般的な工事工程の流れ、型枠工事の種類、単価についてわかりやすく解説します。
目次
土木型枠工事とは?
土木型枠工事とは、コンクリート構造物を形成するために必要な「型(かた)」を設置する作業工程です。
社会インフラの根幹を支える、次のようなコンクリート構造物の施工に欠かせない準備であり、液体状のコンクリートが固化するまで、重力の影響で外側に流れ出さないように設置する必要があります。
- 橋梁(現場打ちの橋桁、橋脚、橋梁など)
- 擁壁
- 河川構造物(堰・魚道)
- 下水道(カルバート)
- トンネル
- ダム
なお国土交通省の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改定)」の資料では「大工工事」のカテゴリに分類されています。木材、鋼材、樹脂などのさまざまな素材が使われており、構造物の規模や形状によって適切な型枠を用いるのが特徴です。
また、土木全般の基礎知識を知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
建築型枠工事との違い
土木型枠工事と似た名称の「建築型枠工事」は、土木と同様に、コンクリートを成形するための型枠工事です。しかし目的・設計・施工環境・求められる精度など、複数の点が異なります。
| 土木型枠工事 | 建築型枠工事 | |
| 主な施工対象 | インフラ構造物 | 住宅・ビル・商業施設などの建築物 |
| 環境条件 | 屋外・地形変化あり | 室内・整備された現場が多い |
| 型枠の種類 | 鋼製型枠・再利用型枠 | 木製型枠・システム型枠 |
| 要求精度 | 構造的強度とスピード重視 | 寸法精度・美観重視 |
| 使用頻度 | 大量・繰り返し使用 | 1現場ごとに使い切りが多い |
上記からわかるように、対象物の用途や施工環境で、用いられる型枠工事の手法が異なります。
基礎工事との違い
型枠工事と類似する工事業務である「基礎工事」は、コンクリート構造物を構築するうえで欠かせない工程です。ただし、それぞれの工事は実施内容が明確に違います。
- 基礎工事|基礎に使われるコンクリートを打設する
- 型枠工事|打設したコンクリート形状を維持する
以上より、型枠工事は、コンクリートを打設・養生する基礎工事でも用いられるのが特徴です。橋梁下部工の基礎の打設、擁壁の基礎コンクリート打設など、本設工事なのか、仮設の材料なのかという違いがあります。
型枠工事の基本工程と流れ
型枠工事は、コンクリート構造物の品質を維持するために、精密な調整を加えながら設置する必要があります。参考として以下に、型枠工事の開始〜終了までの流れをわかりやすくまとめました。
【ステップ1】数量の拾い出し
まずは、設計図や型枠図をもとに、必要な型枠部材の寸法や数量を算出します。
誤差があると後の工程で不具合が生じるため、重要な準備です。
【ステップ2】加工
拾い出しで算出した寸法に従い、合板や桟木などの型枠資材をあらかじめ切断・加工しておく工程です。
現場作業の効率化と精度確保につながり、過不足なく型枠を用意するために欠かせません。
【ステップ3】墨出し
現場のコンクリート構造物が正しい位置・寸法で施工されるよう、床面や壁面に基準線を描く作業です。
墨出しの精度によって型枠の建て込み品質が変化するため、mm単位で調整しなければなりません。
【ステップ4】建て込み
墨出しが完了したら、加工された型枠資材を現場で組み立て、所定の位置に設置する建て込みを実施します。
水平・垂直の精度や安定性を確保しながら支保工(コンクリートなどの圧力で型枠が移動しないように支える材料)などで固定します。
【ステップ5】締め付け
コンクリートの養生中に型枠がずれないよう、型枠同士を緊結し、コンクリート打設時に変形や漏れを防止するためにしっかりと固定します。
主にセパレーターや締め金具などを用いて締め付けを実施します。
【ステップ6】コンクリート打設
完成した型枠の中にコンクリートを流し込み、バイブレーターなどで振動を与えて空気を抜きながら成形していきます。
なお型枠は、コンクリートが固化するまで継続して設置しておかなければなりません。
【ステップ7】型枠解体
コンクリートが十分に硬化したら、型枠を安全に取り外します。
コンクリートと型枠は張り付いているため、構造物を傷つけないよう慎重に作業し、型枠材を再利用する場合は回収が必要です。
型枠の種類一覧
型枠工事は、工事の目的および構造物の形状や施工環境にあわせて、最適な型枠を使い分けることが重要です。参考として以下に、よく用いられる型枠の種類をまとめました。
| 型枠の種類 | 特徴 | 向いている施工 | 注意点 |
| 木製型枠 | ・加工しやすく安価・現場加工が柔軟 | 小規模・曲線部 | 耐久性が低く再利用困難 |
| 鋼製型枠 | ・高耐久で繰り返し使用可能 | 大型土木構造物 | 重量がありコスト高 |
| プラスチック型枠 | ・軽量で作業性が良い・清掃しやすい | 仮設・狭小地 | 変形に注意が必要 |
| システム型枠 | ・工場製造で高精度・組立が簡単 | 反復構造物 | 初期導入費が高め |
| 特殊型枠 | ・自由形状の構造物に対応可能 | 曲線・複雑形状 | 専門技術が必要 |
上記のうち、多くの土木工事現場で活用されているのが、木製型枠と鋼製型枠です。
例えば、大型構造物なら鋼製、住宅地や狭い現場なら木製が主流であり、地域を問わず安価に入手でき、多くの現場に適用できる木製型枠は、多くの土木工事で活用されています。
型枠工事に使用される資材一覧
土木工事の型枠は、単に板を組むだけでなく、支保工・締め付け・保持部材など多くの資材を組み合わせて施工しなければなりません。以下に、よく使用される資材とその特徴を整理しました。
| 資材名 | 用途・特徴 |
| 合板 (ベニヤ) | ・型枠の基本材料として活用されている・軽量で加工しやすいが耐久性はやや低めである |
| 桟木 (さんぎ) | ・型枠の補強や骨組みに使用する・断面が一定で組み立てやすい |
| セパレーター | ・両側の型枠の間隔を一定に保ち、締め付け強度を確保する |
| 型枠支保工 | ・型枠が崩れたり変形したりしないように支える仮設材である・パイプサポートなどが用いられる |
| 締め付け金具 | ・コンクリート打設時の型枠変形を防ぐために使用する・フォームタイなども含む |
各資材は、現場環境や施工条件によって使い分けられます。特に大規模工事の場合には、多くの資材を活用するのが特徴です。
型枠工事の単価
型枠工事の単価は、工法・材料・施工規模・作業環境によって大きく異なります。
例えば、国土交通省が毎年3月に発表している公共工事設計労務単価では、全国平均で30,214円と設定されています。(参考:国土交通省「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について 」)
また農林水産省が公開している「工事費一覧表( 建築工事 )(全体)」では、一例として次のような単価が挙げられています。
- 普通合板型枠|3,680円/㎡
- 一般用型枠|9,020円/㎡
- 打放合板型枠|4,970/㎡
なお、型枠工事全体にかかる費用は、上記の人件費・材料費のほかにも、運搬費などをトータルした費用として算出しなければなりません。規模や工法等によって金額が変化する点に注意が必要です。
また、型枠工以外の公共工事設計労務単価の最新情報や傾向を知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
まとめ
土木型枠工事は、コンクリート構造物を安全かつ正確に施工するための非常に重要な基盤工事です。
今後の土木施工では、BIMやICTを活用した拾い出し精度の向上や、環境負荷の少ない型枠資材の選定もポイントになってくるため、まずは型枠工事の流れを確実に理解することからスタートしましょう。


