【2025年版】土木設計とは?仕事内容・資格・向いている人・年収までわかりやすく解説
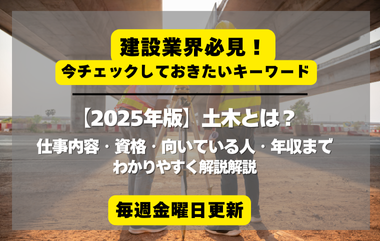
土木設計は、道路や橋梁、河川など多岐にわたる分野が関わる仕事です。しかし、具体的にどのような流れで仕事をするのかイメージできないとお悩みではないでしょうか。
そこでこの記事では、土木設計の仕事内容やきつい理由を解説したのち、取得すべき資格や年収事情について、初心者向けにわかりやすく紹介します。
目次
土木設計の仕事内容とは?
土木設計とは、インフラ整備に必要な構造物・施設の「設計」を担う仕事です。
【土木設計のイメージ】
- 道路設計
- 橋梁設計
- 上下水道設計
- 公共施設の整備
例えば、社会全体で利用されている施設(建物を除く)のほとんどが、土木業務のなかでつくられており、社会を支える重要な職種として知られています。
なお土木設計では、業務のすべてに「図面に起こす工程」が必要です。また図面の作成に伴い、数量算出、金額算出、構造計算や安全性の検討、地質条件の把握など、理系分野における専門知識が求められます。
土木分野全体の基礎知識を身につけたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
計画〜設計の流れ
土木設計では、以下に示す工程を経て、構造物等を設計していきます。
| 設計工程 | 主な内容 |
| ①計画 | ・用地条件やニーズの整理、概略プランの立案 (立地条件・コスト試算など) |
| ②調査 | ・地形測量、土質調査、交通量調査など現地の実態把握 |
| ③基本設計 | ・諸元条件に基づき構造形式やレイアウトを設計 (仮設計、ルート検討など) |
| ④詳細設計 | ・図面・数量・構造計算書など実施設計の作成 (発注用図面など) |
| ⑤成果物作成 | ・成果品提出(CAD図面・数量表・報告書類) ・設計レビューの対応 |
上記のうち、①〜②は、調査会社、測量会社などと協力しながら業務を進めていきます。なお、基本設計に入る前には、調査位置・範囲の選定などとして設計の立場から関わることも少なくありません。
また、上記の一連の流れは、国土交通省が公開している「土木設計・測量・地質調査等の業務関係共通仕様書(案)(令和7年度)」にて詳しい工程や検討情報がまとめられています。なかでも土木設計は、以下のように仕様書が細かく分けられているため、受注した業務ごとに適切な知識を身につけなければなりません。
また、設計業務では上記の仕様書だけではなく全国の自治体や組織、協会などが公開している「基準書」「手引き」「要領」などを用いて検討を行う必要があります。適用する情報については共通編の巻末に掲載されているため、最新版をチェックすることが大切です。
それぞれの段階で関係者と協議しながら進める、綿密かつ実務的なプロセスです。
設計で使用する主なソフト・技術
土木設計の業務では、以下に示す多様なソフトウェアが活用されています。
- CADソフト
- BIM/CIMソフト
- 解析ツール
- GIS技術
- 自動化ツール(RPAなど)
例えば、上記のソフトを活用することにより、土木設計で欠かせない「構造の安全性」「法令順守」「地形・地質のデータ活用」などに対応できます。特に近年では、BIM/CIM対応ソフトの導入ニーズが高まっていることから、早期の導入検討が必要です。
また土木で利用されているCIMについて詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
土木設計の仕事がきついと言われる理由とは?
土木設計に従事している人たちのなかには、この仕事は「きつい」「やめとけ」という人もいます。なぜそう言われているのか以下に理由をまとめました。
- 主に公共インフラに関わる設計であるためミスが許されない
- 行政・施工・住民など多くの関係者との調整が必要である
- 納期が限られているため残業が発生しやすい
例えば、国土交通省 東北地方整備局が公開している「建設業における働き方改革と工期の適正化について」によると、土木設計を含む建設業は、ほかの産業と比較して労働日数・時間が長いのが特徴です。
出典:国土交通省「建設業における働き方改革と工期の適正化について」
このように、土木設計はタフさを求められる仕事です。ですがその反面「やりがいを感じる人」が多い仕事でもあります。なお近年では、テレワーク導入やICT技術、BIM/CIM技術といった効率化により、上記の問題は少しずつ解消され始めています。
土木設計に向いている人
「自分が土木設計の仕事に向いているのかわからない」とお悩みの方向けに、向いている人の特徴をまとめました。
- 理系的(計算・検討・分析)な思考をもっている人
- 慎重で責任感が強い人
- 新しい知識を学ぶ意欲がある人
- チームで協力して作業ができる人
- まちづくりに興味がある人
土木設計はただ黙々と図面を作成するだけではなく、人(同じ設計者・下請け・発注者・住民)との協調を大切にしなければならない仕事です。そのため自身にあっているのかを検討することはもちろん、そのような人間になりたいのかを考えて土木設計を目指してみてください。
土木設計に必要な資格一覧
土木設計は、国家資格がなくとも仕事をスタートできます。しかし、資格を取得したほうが有利に業務受注・進行ができる点は気にしなければなりません。参考として以下に、取得すべき資格を一覧にまとめました。
| 資格名 | 主な概要と難易度 | おすすめ度 | 難易度 |
| 技術士(建設部門) | 技術力と実務経験が評価される土木設計の最高峰資格(国家資格)です。管理・設計・発注者全員が取得したい資格となります。 | ★★★★★ | 高 |
| RCCM(土木部門)または土木設計技士 | 建設コンサルタント向けの設計専門資格です。 | ★★★★☆ | 中~高 |
| 測量士・測量士補 | 測量・地形データの扱いに関する資格です。 | ★★★☆☆ | 低 |
| CAD利用技術者試験(2級/1級) | 設計ツールの操作スキルを証明できる資格です。未経験からの転職の場合は取得しておくと安心です。 | ★★★☆☆ | 低~中 |
| 一級土木施工管理技士 | 主に施工現場で役立つ資格であり、現場の流れを理解する際に役立ちます。 | ★★☆☆☆ | 高 |
最終目標として取得を目指したいのが技術士であり、30歳まで取得できない場合はRCCMを先に取得しておくと安心です。
なお、一級土木施工管理技士について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。
土木設計技士・技術士との違い
資格取得のなかでよく間違えられるのが、土木設計技士と技術士です。
まず技術士は土木設計における最高峰の国家資格であり、国主体の案件受注のほか、自身で建設コンサルタントを立ち上げる際に必要な資格となります。
対して土木設計技士の資格は、土木施系における品確法(公共工事の品質確保の促進に関する法律)にもとづき正しい設計ができることを証明できる資格です。必要性は高いものの、技術士の取得のほうを優先的に考えることをおすすめします。
土木設計で見込めるキャリアと必要な勉強
土木設計に従事した場合のキャリアの目安を以下にまとめました。
- 初級設計技術者(図面作成や数量計算などの単純作業)
- 中堅技術者(主任・担当)
- 上級技術者・プロジェクトマネージャー(管理職)
- 発注者技術職(一次請け・行政・公団)
- 建設コンサルの開業・独立技術士業務
なお、土木設計のスキルや知識を身につけるためには、書籍を用いた勉強のほか、マニュアルや基準書を読み込むことが重要です。またセミナー講習などに参加し、常に新しい知識を身につけ続けることをおすすめします。
土木設計の年収事情
厚生労働省が公開している職業情報提供サイトjob tagによると、土木設計技術者の平均年収は603.9万円だと発表されています。
当年収は、国税庁が公開している日本全体の平均年収である461万円よりも高い数値を示しています。また平均年収のピークは50〜54歳の720.9万円であり、安定した収入を期待できるのが魅力です。
まとめ
土木設計は、社会インフラを支える重要かつ専門性の高い仕事です。責任の重さから「きつい」と言われる場合もありますが、キャリアや年収、将来性の面でも非常に魅力的な職種になります。
もし、土木設計に興味をおもちの方は、本記事の情報を参考に、新たなキャリアステップを目指してみてはいかがでしょうか。


