【2025年版】土木とは?意味・工事の種類・建築との違いを初心者向けにやさしく解説
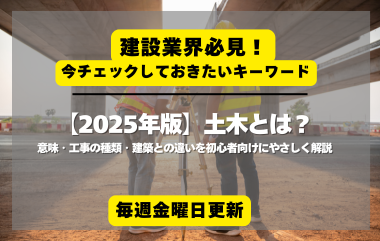
土木のことについて興味があるものの、土木の全体像をイメージできないとお悩みではないでしょうか。また、土木に携わる人たちの仕事や、就業した場合の収入面、そして仕事の将来性を気にしている人もいるはずです。
そこでこの記事では、土木の概要や意味、工事内容等を紹介したのち、土木業界に就業したい人向けのキャリアと給与についてわかりやすく解説します。
目次
土木の定義と役割
まずは初心者向けに「土木」という言葉の意味や使われ方についてわかりやすく解説します。土木という言葉に含まれている工事の範囲なども含め、詳しく見ていきましょう。
土木とは何か?わかりやすく解説
土木とは、道路、橋梁、ダム、トンネル、上下水道など、人々の生活を支える経済活動を支える「社会基盤(インフラ)」を整備・維持する技術や工事の総称です。
土木という言葉は、土やコンクリート、水など自然界からつくられている土地全体の造成や整備を実施する重要な仕事であり「日常的に利用できる道路や橋、トンネルがある」という裏側には、土木に関わる人たちによるさまざまな取り組みが隠れています。
また、地震や水害による被害を食い止めたり、時間とともに発生する経年劣化を防止したりと、長く快適に利用できるように、継続して維持し続けていくことも重要な役割のひとつです。
土木の語源と歴史的な背景
「土木」という言葉は、中国の古典『周礼』に由来していることをご存じでしょうか。
この古典書には「土をもって国を治め、木をもって家をつくる」という言葉が記載されており、日本へ古典がやってきたことに伴い、土木という言葉が生まれました。
また明治時代に西洋の「civil engineering」という言葉が入ってきたことに伴い、その訳語に「土木」が採用され、近代的な土木工事が本格化しました。
(参考:J-Stage『わが国および中国における「土木」の語義の歴史的変遷に関する研究』)
建設業界における土木の位置付け
建設業界は大きく「建築」と「土木」に分かれます。
国土交通省では広辞苑等をもとにした定義をまとめており、土木工事・建築工事と分けて工事業務が展開されています。(出典:国土交通省「建設業法等における定義」)
なお「建築」は建物の設計・施工を対象とし、対して「土木」は地盤や構造物、インフラ整備など、広い空間に対する工事が中心です。国や自治体が発注する公共事業では、道路、河川、トンネル、港湾などのプロジェクトが土木工事に該当します。
土木工事の種類と具体例
道路・橋梁・河川などのインフラ整備
土木工事は多岐にわたりますが、主に次のようなインフラ整備を目的とした工事が実施されます。
| 工事種別 | 具体例 | 内容 |
| 道路工事 | 地盤の掘削、舗装、排水の確保などを行い、安全で快適な道路を整備する(国道・県道・市道・農道など) | |
| 橋梁工事 | 構造解析や強度確保、安全基準に基づく設計・施工を実施する(河川橋・道路橋など) | |
| 河川・ダム工事 | 洪水調節、水資源の確保、発電など多目的に利用される河川やダムの建設・維持を行う(河川護岸、堰、重力式ダムなど) | |
| トンネル工事 | 山岳部や都市部での交通路確保のため、掘削や支保工などの技術を用いてトンネルを通す(道路工事と併用) |
特に道路工事は、ほかの工事とともに実施するケースが多くあります。
造成工事や下水道工事
前述したカテゴリとは別に、次のような重要な工事も土木という枠組みに含まれます。
- 造成工事|住宅地や工場などの建設を目的に土地を整備する
(盛土・切土・排水・擁壁など) - 下水道工事|都市の衛生環境を保つために実施する
(埋設配管・マンホール設置)
土木と建築の違い
建設という枠組みに含まれる「土木」「建築」には、それぞれ工事業務という類似点がある一方で、2つの相違点があります。
建設業法における定義の違い
まず建設の動き方や目的、ルールなどがまとめられている「建設業法」では、土木・建築を次のように分けて説明しています。
- 土木工事|道路・橋・ダム・トンネル・上下水道・河川といった公共インフラの整備が主な対象であり、国や自治体が発注する公共事業が多く、都市の基盤を支える役割を担う
- 建築工事|住宅・マンション・ビル・学校など、建物の新築・増改築・修繕などを対象とする工事であり、個人や民間企業からの発注も多い
つまり土木と建築には、発注者が誰なのか、対象となる「もの」が何なのかという違いがあります。
建設業法について詳しく知りたい方は、以下の記事をチェックしてみてください。
施工対象と目的の違い
土木と建築は、施工する対象と工事の目的にも違いがあります。
まず土木は「社会インフラの整備」が主目的であり、安全性・耐久性・機能性が重視された構造物等をつくり出して維持管理を行います。施工対象は地盤や構造物の基礎・屋外構造物が中心です。
続いて建築は「人が住み、使う空間」をつくることが目的で、快適性・美しさ・空間設計などの意匠性も重視しなければなりません。
どちらも近い関係にあるものの、土木については一般人が利用するよりも社会的に必要とされる施設や設備をつくることが目的となります。
また土木・建築の違いを詳しく知りたい方は、以下の記事がおすすめです。
土木職のキャリアと給与
土木という仕事は、その他の業種と比較して、技術系に特化したキャリアを進めるのが特徴です。国が公開している給与情報も含めて、土木職としての仕事の中身をまとめました。
土木系企業(作業員・設計・施工管理)の平均年収と日当相場
厚生労働省が公開している職業情報提供サイト「job tag」をもとに、土木系企業で働く人材の平均年収をまとめました。
体力的な作業を行う土木作業員よりも、技術的な知識や業務全体の管理等を担う設計・施工管理の技術者のほうが平均年収が高く設定されています。国税庁が公開している日本全体の平均年収が461万円だと言われているため、土木は比較的平均以上の収入を得やすい仕事だと言えるでしょう。
また土木設計技術者の単価などは、以下の記事で解説する情報などから算出できます。
公務員土木職の仕事内容と年収
土木工事の発注者となる「公務員土木職」の仕事の平均年収は、おおよそ400〜500万円だと言われています。(公務員系の求人サイトの平均年収より算出)
また総務省が公開している「令和5年地方公務員給与実態調査結果の状況」によると、技能労務職という職種の給与月額が約35万円であるため、年収420万円程度になる計算です。なお当計算には諸手当などを含んでいないため、全国の平均年収よりも多くもらえると予想されます。
土木に関する豆知識
土木について、より詳しい知識を身につける参考として、2つの豆知識をまとめました。
おみくじにおける土木の意味とは
土木という言葉は、神社などで購入するおみくじにも用いられています。
主に家や会社の建築や増築などの運勢を指し示す項目であり「新しく家を建てるがどうなのか」「今のタイミングでリフォームしてもいいのか」など、建築寄りの説明がまとめられているのが特徴です。
土木に関連するトレンド・流行
土木分野では今、次のようなトレンドが加速しています。
- 業務へのBIM/CIM活用(参考:とよおかBIM/CIMポータル)
- UAV測量の活用(参考:国土地理院)
- 施工管理アプリによる業務効率化
これまでアナログな管理が実施されていた土木業界ですが、近年では国土交通省による建設DXの推進により、デジタル化が著しい進歩を見せています。
多くの土木企業が導入をスタートしている分野ですので、土木の今を知る参考にしてください。
まとめ
土木はインフラ施設をつくること、そして継続して維持管理を続けることを目的とした重要な役割のある仕事です。主に国や地方公共団体から発注を請けて工事業務を提供します。
土木業界は今、デジタル化への移行なども急速に進んでいるため、今後の動向から目が離せません。


